「実家を相続したけど、住む予定がない…」 「古い家を売りたいけど、税金がどれくらいかかるか不安…」 「できるだけ税金を抑えて家を売る方法はないかな?」
こんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。実は、古い家を売却する際には、知っておくべき税制や特例がたくさんあります。これらをうまく活用すれば、支払う税金を大幅に減らすことも可能です。
この記事では、古い家を売却する際にかかる税金の基本知識から、知っておくと得をする特例や控除まで、初心者にもわかりやすく解説します。さらに、相続した家の売却に関する特別なポイントや、税金を抑えるための実践的なアドバイスもご紹介します。
最後まで読むことで古い家の売却に関する税金の仕組みを理解し、最適な売却方法を選べるようになります。それでは、古い家の売却と税金について詳しく見ていきましょう。
どの不動産会社を選べばいいかわからない場合は一括査定サイトのがおすすめです。特にズバット不動産売却は厳選な審査を通過した不動産会社が対応してくれるので安心です。
古い家の売却と税金の基礎知識

古い家とは何か?
一般的に「古い家」と言われるのは、建築から何年経過した家を指すのでしょうか。実は、明確な定義はありませんが、税金面では建物の法定耐用年数が重要な基準となります。
木造住宅の法定耐用年数は22年、鉄筋コンクリート造のマンションなどは47年と定められています。この年数を超えると、建物の価値は理論上ゼロになるとされていますが、実際の市場ではまだ価値があることも多いです。
特に税制優遇措置の中には、築年数が条件になっているものもあります。例えば「被相続人の居住用財産(空き家)の特例」は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象となります。
売却時にかかる主な税金の種類
古い家を売却すると、主に以下の税金がかかる可能性があります。
1. 譲渡所得税と住民税
家を売って利益(譲渡所得)が出た場合に課税されるのが、譲渡所得税と住民税です。合わせて「譲渡所得税」と呼ばれることも多いです。税率は所有期間によって異なります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税30.63% + 住民税9% = 約39.63%
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税15.315% + 住民税5% = 約20.315%
例えば、5年超所有した家を売って1,000万円の利益が出た場合、税金は約203万円になります。ただし、後述する特例を使えば、この税金を大幅に減らせる可能性があります。
2. 印紙税
不動産の売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税金です。売買金額によって税額が変わります。例えば、1,000万円〜5,000万円の売買契約では1万円の印紙税がかかります(2027年3月31日までの軽減税率適用時)。
3. 登録免許税
所有権移転登記をする際にかかる税金です。売買による所有権移転の場合、固定資産税評価額の2%が税率となります。
これらの税金は売却価格や状況によって変わりますので、具体的な金額は専門家に相談することをおすすめします。
譲渡所得税の計算方法

譲渡所得の算出方法
譲渡所得税を計算するためには、まず「譲渡所得」を算出する必要があります。譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
売却価格:実際に家を売った金額です。
取得費:家を購入したときの価格や、購入時にかかった諸費用(登記費用、不動産仲介手数料など)の合計です。相続した家の場合は、被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぎます。
譲渡費用:家を売却する際にかかった費用です。不動産仲介手数料、印紙税、測量費用、古い家を取り壊した場合の解体費用なども含まれます。
所有期間による税率の違い
先ほど触れたように、譲渡所得にかかる税率は所有期間によって大きく異なります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):約39.63%
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):約20.315%
この「所有期間」は、取得した日から売却した年の1月1日までの期間で計算されます。例えば、2018年6月に購入した家を2024年8月に売却した場合、所有期間は「2018年6月から2024年1月1日まで」となり、5年超となるため長期譲渡所得の税率が適用されます。
相続した家の場合、所有期間は被相続人の所有期間を含めて計算します。例えば、親が1990年に購入し、2022年に相続して2024年に売却した場合、所有期間は1990年からとなります。
取得費が不明な場合の概算取得費の使い方
古い家の場合、購入時の書類が残っておらず、取得費が不明なケースがよくあります。そのような場合には「概算取得費」という制度を利用できます。
概算取得費は、売却価格の5%を取得費とみなす制度です。例えば、取得費が不明な家を3,000万円で売却した場合、取得費は3,000万円×5%=150万円と計算できます。
ただし、実際の取得費が売却価格の5%より高いと思われる場合は、できるだけ実際の取得費を証明する資料(売買契約書、領収書、登記簿謄本など)を探し出す方が有利になることが多いです。
古い家の売却時に使える特例制度①:居住用財産の3,000万円特別控除

3,000万円特別控除の概要
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。この特例を利用すると、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がゼロになります。
例えば、譲渡所得が2,500万円の場合、3,000万円特別控除を適用すると譲渡所得はゼロになるため、税金はかかりません。譲渡所得が4,000万円の場合は、3,000万円を控除した1,000万円に対して税金がかかります。
適用条件と必要書類
この特例を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 売却する家に住んでいたこと(過去に住んでいた家も条件あり)
- 売却する年の前年・前々年に3,000万円特別控除や買換え特例などを利用していないこと
- 売却価格が1億円以下であること
過去に住んでいた家の場合は、以下の条件も満たす必要があります。
- 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
- 住まなくなった理由が、転勤や老人ホーム入居などやむを得ない事情であること
必要な書類としては、確定申告書のほか、売買契約書や登記事項証明書、住民票の写しなどがあります。詳細は税務署や税理士に確認しましょう。
具体的な税金計算例
実際に3,000万円特別控除を適用した場合の税金計算例を見てみましょう。
【事例】20年前に2,000万円で購入した家を5,000万円で売却した場合
- 譲渡所得の計算 売却価格:5,000万円 取得費:2,000万円 譲渡費用(仲介手数料等):250万円 譲渡所得 = 5,000万円 – 2,000万円 – 250万円 = 2,750万円
- 3,000万円特別控除の適用 控除後の譲渡所得 = 2,750万円 – 3,000万円 = 0円(マイナスの場合は0円)
- 納税額 長期譲渡所得税額 = 0円 × 20.315% = 0円
この例では、3,000万円特別控除を適用することで、税金がゼロになります。特例を適用しなければ、約558万円(2,750万円 × 20.315%)の税金がかかっていたところです。
古い家の売却時に使える特例制度②:相続した空き家の特例

被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除
親などから相続した空き家を売却する場合に使える特例として、「被相続人の居住用財産(空き家)の特例」があります。この特例も、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
通常の3,000万円特別控除との大きな違いは、自分が住んでいなくても適用できる点です。親が住んでいた家を相続し、自分は一度も住まずに売却しても、条件を満たせばこの特例が使えます。
適用条件(築年数・区分所有でないことなど)
この特例を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいた家であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家(旧耐震基準の家)であること
- 区分所有建物(マンションなど)でないこと
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
この特例は、古い空き家の流通促進を目的として設けられたものです。特に築古の一戸建て住宅の相続に悩む方にとって、大きなメリットとなる制度です。
適用期限と必要な手続き
この特例の適用期限は、現在のところ2025年12月31日までとなっています(期限延長の可能性あり)。
適用を受けるには、確定申告の際に必要書類を提出する必要があります。主な必要書類は以下の通りです。
- 確定申告書および譲渡所得の内訳書
- 被相続人の住民票の除票(亡くなる直前まで一人で住んでいたことを証明)
- 耐震基準に適合しないことを証明する書類または耐震改修工事をしたことを証明する書類
- 売買契約書の写し
事前に家屋の耐震診断を受けておく必要がある点に注意しましょう。
古い家の売却時に使える特例制度③:その他の控除と特例

居住用財産の買換え特例
住んでいた家を売って、新しい家を購入する場合に使える「居住用財産の買換え特例」があります。この特例を使うと、古い家の売却による譲渡所得の課税を、新しい家を売却するまで繰り延べることができます。
適用条件には、売却する家と購入する家の両方に一定期間住んでいることや、売却価格が1億円以下であることなどがあります。
低未利用土地等を譲渡した場合の特例
地方の空き家や空き地など、低未利用の土地等を売却した場合、譲渡所得から最高100万円を控除できる特例があります。これは比較的新しい制度で、都市部の空き家対策というより、地方の空き家・空き地対策に焦点を当てたものです。
適用を受けるには、市区町村から「低未利用土地等確認書」を取得する必要があります。
譲渡損失が出た場合の損益通算・繰越控除
家を売却して損失が出た場合、一定の条件を満たせば、その損失を給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できる特例があります。さらに、相殺しきれない損失は、翌年以降3年間繰り越して控除することも可能です。
この特例は主に以下の2種類があります。
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 住んでいた家を売却して損失が出た場合に適用できます。
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 住宅ローンが残っている家を売却し、ローンの残債が売却代金を上回る場合(いわゆる「オーバーローン」の状態)に適用できます。
どちらの特例も、確定申告が必要です。
特例の併用に関する注意点
これらの特例のいくつかは併用できない場合があります。例えば、以下の組み合わせは併用できません。
- 3,000万円特別控除と居住用財産の買換え特例
- 3,000万円特別控除と譲渡損失の損益通算・繰越控除
また、3,000万円特別控除は一度使うと、その後2年間は再び利用できません。つまり、3年に1回しか使えない特例です。
どの特例を使うのが最も有利になるかは、個々の状況によって異なります。不明点があれば、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
古い家の売却方法と税金の関係

そのまま売却する場合の税金
古い家をそのまま売却する場合、建物と土地の両方に価値がある状態で売ることになります。ただし、建物が古いほど建物部分の価値は低くなり、土地の価値が売却価格の大部分を占めるようになります。
税金面では、建物部分にも価値があるため、譲渡所得の計算に建物の取得費も含めることができます。これにより、譲渡所得が少なくなり、結果的に税金も少なくなる可能性があります。
取り壊して更地にして売却する場合の税金
古い家を取り壊して更地にしてから売却する場合、建物部分の価値がなくなり、土地だけの売却になります。この場合、建物の取得費は譲渡費用として計上できませんが、取り壊し費用(解体費用)は譲渡費用に含めることができます。
一般的な解体費用は、木造一戸建ての場合で150万円〜300万円程度です。この費用を譲渡費用に含めることで、譲渡所得が減り、税金も少なくなる可能性があります。
ただし、建物を取り壊してしまうと、建物部分の取得費や、リフォーム費用などが無駄になる点に注意が必要です。
リフォーム・リノベーションしてから売却する場合
古い家をリフォーム・リノベーションしてから売却する場合、リフォーム費用は以下のように扱われます。
- 資本的支出(建物の価値を高めるための支出):取得費に加算
- 修繕費(現状維持のための支出):譲渡費用に計上
例えば、キッチンの交換やバスルームの改装などは資本的支出、壁紙の張り替えや畳の表替えなどは修繕費に分類されることが多いです。
リフォーム・リノベーションにより売却価格が上がれば、税金も増える可能性がありますが、3,000万円特別控除などの特例を上手く活用すれば、税負担を抑えることができます。
どの方法が税金面で有利になるかの比較
どの売却方法が税金面で最も有利になるかは、物件の状況や市場の需要などによって異なります。一般的には以下のような傾向があります。
- 建物がまだ価値を持つ場合:そのまま売却
- 建物の価値がほとんどない場合:取り壊して更地で売却
- 需要があり、リフォーム後の価格上昇が見込める場合:リフォーム・リノベーション後に売却
最終的には、不動産会社に査定を依頼し、「そのままの状態での査定額」と「更地にした場合の査定額」を比較するのがおすすめです。また、リフォーム・リノベーションを検討する場合は、費用と売却価格の上昇分を比較して判断しましょう。
相続した古い家を売る場合の特別な注意点
相続税と譲渡所得税の関係
相続した家を売却する場合、相続税と譲渡所得税の両方について考える必要があります。
相続税は相続した時点で課税され、譲渡所得税は売却して利益が出た場合に課税されます。相続した家の価値は、相続税評価額として相続税の計算に含まれますが、この評価額と実際の市場価値には差があることが多いです。
特に注意が必要なのは、相続税評価額と売却価格の差です。例えば、相続税評価額が2,000万円の家を5,000万円で売却した場合、単純に考えると3,000万円の譲渡所得が発生しますが、実際の計算はそう単純ではありません。
取得費の算出方法(被相続人の取得費を引き継ぐ)
相続した家の取得費は、被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぎます。つまり、親が何十年も前に購入した価格が取得費になります。
例えば、親が40年前に1,000万円で購入した家を相続し、その家を5,000万円で売却した場合:
譲渡所得 = 5,000万円(売却価格)- 1,000万円(取得費)- 譲渡費用
このように計算されるため、相続した古い家を売却すると、取得費が低いことから高い譲渡所得が発生しやすくなります。そのため、3,000万円特別控除などの特例を活用することが重要です。
相続から売却までの期間による影響
相続した家を売却するタイミングも重要です。前述の「被相続人の居住用財産(空き家)の特例」を利用するには、相続開始から3年以内に売却する必要があります。
また、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)より前に売却した場合は、実際の売却価格を相続税の計算に用いることができる場合があります。これにより、相続税の負担が軽減される可能性があります。
共有名義の場合の注意点
相続した家が複数人の共有名義になっている場合、売却時には共有者全員の合意が必要です。また、税金の計算は各共有者の持分に応じて個別に行うことになります。
例えば、3人で均等に共有している家を6,000万円で売却した場合、各自の売却価格は2,000万円となります。譲渡所得や税金もそれぞれの持分に応じて計算されます。
共有者それぞれが3,000万円特別控除などの特例を適用できるため、共有の場合は税金面で有利になることがあります。
税金を抑えるための実践的なアドバイス

確定申告の正しい方法
古い家を売却して譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要です。確定申告は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに行います。
確定申告の際には、以下の書類を準備しましょう。
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)
- 売買契約書の写し
- 取得費や譲渡費用を証明する書類
- 特例適用に必要な書類(3,000万円特別控除を受ける場合など)
確定申告書や内訳書の記入方法については、税務署で相談できるほか、国税庁のホームページでも詳しい解説があります。
必要経費として計上できるもの
古い家の売却時に、以下のような費用は譲渡費用として計上できます。
- 不動産仲介手数料
- 印紙税
- 測量費用
- 解体費用(家を取り壊した場合)
- 広告宣伝費
- 契約書作成費用
また、家の取得後に行ったリフォームのうち、資本的支出に該当するものは取得費に加算できます。
これらの費用は、できるだけ領収書や契約書などの証拠書類を保管しておくことが重要です。
税理士への相談タイミング
複雑な特例を利用する場合や、高額な譲渡所得が見込まれる場合は、税理士への相談をおすすめします。特に以下のようなケースでは、専門家のアドバイスが役立ちます。
- 複数の特例のうち、どれを選択するのが有利か判断が難しい場合
- 相続した家の取得費が不明で、最適な対応を検討したい場合
- 複数の不動産を同時期に売却する場合
- 過去の確定申告に誤りがあり、修正したい場合
税理士への相談は、家の売却を検討し始めた段階、または売買契約を結ぶ前に行うと、より効果的なアドバイスが得られます。
売却前に確認すべきチェックリスト
古い家を売却する前に、以下のチェックリストを確認しておくと安心です。
- 所有期間の確認(5年以下か5年超か)
- 取得費の確認と証拠書類の収集
- 適用できる特例の検討
- 売却方法の検討(そのまま売るか、解体して売るか)
- 複数の不動産会社からの査定取得
- 譲渡所得と税額のシミュレーション
- 必要に応じて税理士への相談
特に取得費の証拠書類は、古い家ほど見つけることが難しくなります。購入時の売買契約書や領収書、登記簿謄本などがあれば、大切に保管しておきましょう。
まとめ

古い家を売却する際の税金について、基本的な知識から特例制度、実践的なアドバイスまで解説してきました。ここで重要なポイントをおさらいしましょう。
- 古い家を売却すると、譲渡所得に対して所得税と住民税がかかりますが、特例を活用することで税負担を大幅に減らせる可能性があります。
- 特に重要な特例は「居住用財産の3,000万円特別控除」と「被相続人の居住用財産(空き家)の特例」です。条件を満たせば、最大3,000万円まで譲渡所得から控除できます。
- 相続した古い家は、被相続人の取得費を引き継ぐため、譲渡所得が大きくなりやすく、税負担も重くなりがちです。特例の活用が特に重要になります。
- 売却方法(そのまま売る、解体して売る、リフォームして売る)によって税金に影響が出るため、各方法のメリット・デメリットを検討することが大切です。
- 確定申告の際には、取得費や譲渡費用を証明する書類をしっかり準備し、適用条件を満たす特例は積極的に活用しましょう。
古い家の売却は、単に「高く売る」だけでなく、「税金をどれだけ抑えられるか」という視点も重要です。この記事で紹介した知識を活用して、賢く家を売却しましょう。
よくある質問(FAQ)
「古い家を売っても税金はかからない?」
古い家を売却しても必ずしも税金がかかるわけではありません。譲渡所得(売却益)がなければ、譲渡所得税はかかりません。また、譲渡所得があっても、3,000万円特別控除などの特例を適用すれば、税金がゼロになる可能性もあります。
ただし、印紙税など取引自体にかかる税金はかかります。
「どの特例が一番お得なの?」
どの特例が最もお得かは、個々の状況によって異なります。一般的には、3,000万円特別控除が最も広く使われています。譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金がゼロになるためです。
ただし、住宅の買い替えを検討している場合は、買換え特例と住宅ローン控除を組み合わせたほうが有利になるケースもあります。最適な選択は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
「確定申告はいつまでに行えばいい?」
確定申告は、家を売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。例えば、2024年中に家を売却した場合、2025年の2月16日から3月15日までが申告期間です。
期限を過ぎると、無申告加算税などのペナルティが科される可能性があるため、期限は必期限は必ず守りましょう。
「複数の特例を同時に使うことはできる?」
多くの特例は併用できません。例えば、3,000万円特別控除と買換え特例は併用できません。また、同じ特例を短期間に何度も使うこともできない場合があります。3,000万円特別控除は、一度使うとその後2年間は再び利用できません。
ただし、長期譲渡所得の軽減税率と3,000万円特別控除は併用できます。つまり、3,000万円を超える譲渡所得に対しては、20.315%という軽減された税率が適用されます。
「マイホームを買い替える場合の特例は?」
マイホームを買い替える場合、「居住用財産の買換え特例」を利用できる可能性があります。この特例を使うと、売却による譲渡所得の課税を繰り延べることができます。
適用条件としては、売却する家と購入する家の両方に一定期間住んでいること、売却価格が1億円以下であることなどがあります。また、この特例を利用すると、新しい家の取得費が調整されるため、将来売却するときの税金計算に影響します。
ただし、住宅ローン控除との兼ね合いなど、総合的に判断する必要があります。どちらが有利かは個々の状況によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
すぐに実行できる具体的なアクション3つ
1. 取得費と譲渡費用の資料を整理する
古い家の売却を検討している方は、まず家の購入時の資料を探し出しましょう。売買契約書、領収書、登記簿謄本など、取得費を証明できる書類があれば大切に保管しておきます。
また、リフォームやメンテナンスの領収書も、資本的支出として取得費に加算できる可能性があります。これらの資料を整理しておくだけで、確定申告時に大きく役立ちます。取得費の資料がない場合は、概算取得費(売却価格の5%)を使うことになりますが、実際の取得費が高ければ、その分譲渡所得を減らせるため、できるだけ資料を見つけるよう努力しましょう。
2. 複数の不動産会社に査定を依頼する
古い家の売却価格は、不動産会社によって大きく異なることがあります。最低でも3社以上の不動産会社に査定を依頼し、「そのままの状態での査定額」と「更地にした場合の査定額」の両方を出してもらいましょう。
一括査定サイトを利用すれば、一度の申し込みで複数の不動産会社に査定を依頼できるので便利です。査定結果を比較することで、どの売却方法が最も有利か、また、いくらの譲渡所得が見込まれるかを予測できます。
3. 適用可能な特例を確認し、税理士に相談する
自分のケースでどの特例が適用できるか、また、どの特例を選択するのが最も有利かを確認しましょう。特に譲渡所得が高額になりそうな場合や、複数の特例の選択に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
売却前に相談することで、税金面で最適な売却方法や時期を選択できます。相談料はかかりますが、適切なアドバイスにより大幅な節税ができる可能性があるため、十分に元が取れるでしょう。
税理士を探す際は、不動産売却に詳しい税理士を選ぶことがポイントです。多くの税理士事務所ではホームページで得意分野を紹介していますので、それを参考にしてみてください。
これらのアクションを実行することで、古い家の売却に関する税金の負担を効果的に抑えることができるでしょう。特に特例の活用は大きな節税につながりますので、条件を満たしているか、しっかり確認することが重要です。
どの不動産会社を選べばいいかわからない場合は一括査定サイトのがおすすめです。特にズバット不動産売却は厳選な審査を通過した不動産会社が対応してくれるので安心です。

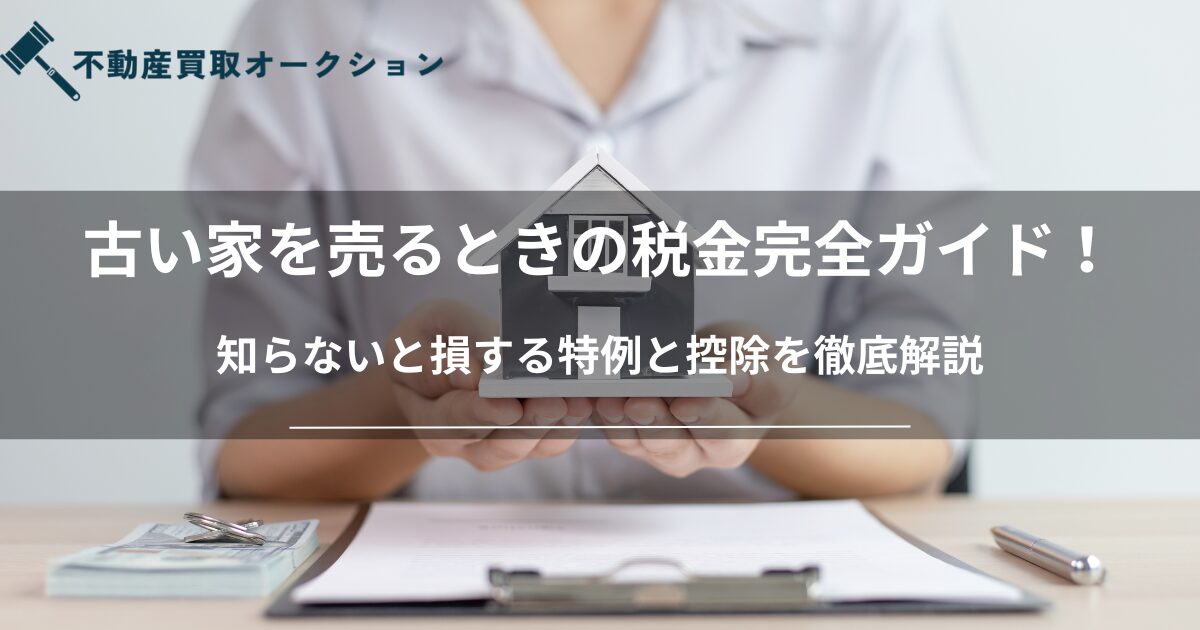

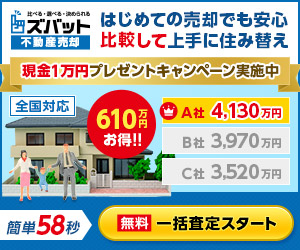

コメント