「母が認知症になって、共有名義の家を売ることができなくなりました」 「父の認知症が進み、共有名義の口座からお金を引き出せません」
このような相談は、高齢化社会の日本で年々増加しています。親世代の認知症が進行する中、共有名義の不動産や預金口座に関するトラブルは、多くの家族が直面する現実的な問題です。
実は、日本では65歳以上の高齢者のうち、約600万人が2025年には認知症を発症すると予測されています。そして、夫婦や親子間での共有名義の財産は珍しくありません。認知症と共有名義が重なると、思いもよらない困難に直面することがあるのです。
この記事では、共有名義の基本から認知症発症時の問題点、そして家族が後悔しないための具体的な対策まで、わかりやすく解説します。「うちの親はまだ元気だから大丈夫」と思っていても、いざというときに慌てないよう、今から知識を身につけておくことが大切です。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有名義とは何か?

共有名義とは、複数の人が一つの財産(不動産や預金など)の所有権を共同で持つことです。たとえば、夫婦で購入した家や、親から子へ相続する際に兄弟姉妹で共有するケースがよくあります。
よくある共有名義のパターン
家族間での共有名義には、主に次のようなパターンがあります。
まず多いのは夫婦間での共有です。共働き夫婦が住宅ローンを組む際、二人の名義で購入することが一般的になっています。また、親子間での共有も珍しくありません。親の土地に子が家を建てるケースや、将来の相続を見据えて親の不動産を子と共有名義にするケースです。そして相続が発生した後の兄弟姉妹間での共有も増えています。
共有名義の法的な意味を理解することも大切です。法律的には、共有者それぞれが持分(しょうぶん)という権利を持ち、その権利に応じて財産の処分や管理に関与できます。例えば、夫婦が50%ずつの持分を持つ家であれば、どちらか一方だけの意思で売却することはできません。両方の同意が必要になるのです。
ここで大切なのは、共有名義の財産を動かすときには原則として全員の同意が必要だということです。そして、この「全員の同意」という点が、認知症が絡むと大きな壁になるのです。
認知症と共有名義で起こりやすい問題

認知症が進行すると、判断能力が低下し、法律行為(契約など)を自分で行うことが難しくなります。これが共有名義の財産管理において、様々な問題を引き起こします。
認知症になると何が変わるのか?
認知症は進行性の病気です。初期は物忘れ程度でも、中期から後期になると財産管理や契約などの重要な判断ができなくなります。法律上、認知症が進行して判断能力が著しく低下した状態では、有効な契約ができなくなります。つまり、不動産の売買契約や銀行での重要な手続きなどができなくなるのです。
共有名義の不動産・預金で特に困ること
共有名義の財産で最も困るのは、全員の同意がないと処分できないという点です。例えば、夫婦で共有している家があり、夫が認知症になった場合、妻一人の判断で家を売却することはできません。夫の同意が必要ですが、認知症の夫は有効な同意ができないからです。
同様に、親子で共有名義にしている土地があり、親が認知症になった場合も問題です。土地を売りたい、あるいは活用したいと思っても、親の同意が得られないため行き詰まります。
銀行口座も同様の問題が発生します。共有名義の口座から大きな額のお金を引き出そうとすると、全員の同意が求められることがあります。認知症の人が共有者にいると、この同意が得られず、必要なお金を引き出せないケースもあるのです。
家族が直面する具体的な3つの壁
実際に家族が直面する壁は主に次の3つです。
1つ目は「売却・処分の壁」です。共有不動産を売却したくても、認知症の共有者の同意が得られないため、売却できません。特に介護費用のために不動産を現金化したい場合などに深刻な問題となります。
2つ目は「管理・活用の壁」です。不動産の修繕や建て替え、賃貸に出すなどの活用方法を決めるのにも、全員の同意が原則として必要です。認知症の共有者がいると、こうした判断ができずに不動産が放置される結果になることもあります。
3つ目は「費用負担の壁」です。固定資産税などの維持費や修繕費の負担割合について話し合いができなくなります。認知症の共有者がこれらの費用を理解して支払うことが難しくなるため、他の共有者に負担が集中することがあります。
こうした壁を取り除くには、早めの対策が不可欠です。次のセクションでは、認知症になる前にできる対策について具体的に見ていきましょう。
認知症になる前にできる対策

認知症になる前の対策が最も効果的です。元気なうちにできることをしておくと、将来の家族の負担が大きく軽減されます。
元気なうちに話し合っておくべきこと
まず大切なのは、家族での話し合いです。特に高齢の親と子は、今後の財産管理について率直に話し合うことが重要です。「もしも認知症になったら、財産をどうしたいか」「共有名義の不動産をどうするか」など、具体的に話し合っておきましょう。
この話し合いは決して簡単ではありません。親世代は「まだ大丈夫」と考えがちですし、子世代も親の老いや認知症について話し出しにくいものです。しかし、早めに話し合うことで選択肢が広がり、後々の混乱を防げます。
共有名義の見直し方法
共有名義を見直す方法はいくつかあります。
一つは、共有名義を解消して単独名義にする方法です。例えば、親子で共有している土地を、子の単独名義に変更するなどです。これには贈与税などの検討が必要ですが、将来のトラブルを防ぐ効果があります。
また、共有持分の調整も検討できます。例えば、認知症リスクの高い高齢者の持分を小さくし、判断能力のある共有者の持分を大きくすることで、将来の管理がしやすくなる場合があります。
いずれにしても、名義変更には税金や登記費用がかかりますので、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
任意後見制度の活用
任意後見制度は、将来の認知症に備える有効な手段の一つです。この制度は、「まだ判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときのために支援者(後見人)をあらかじめ決めておく」というものです。
例えば、「自分が認知症になったら、長男に財産管理を任せたい」と考える親は、任意後見契約を結んでおくことで、その意思を法的に保証できます。共有名義の財産についても、あらかじめ任意後見人に与える権限の範囲を決めておくことができます。
任意後見制度の利用には公証人役場での契約が必要で、費用は約5万円程度からかかります。しかし、将来の安心を買う投資と考えれば、決して高くはないでしょう。
家族信託の検討
近年注目されているのが家族信託という方法です。これは、財産の所有者(親など)が、信頼できる家族(子など)に財産管理を任せる仕組みです。
例えば、親が所有する不動産の「管理権」を子に託すことで、親が認知症になっても子が不動産を管理・処分できるようになります。共有名義の場合も、共有者全員が合意すれば家族信託を活用できます。
家族信託のメリットは、認知症になっても成年後見制度を利用せずに柔軟な財産管理ができることです。ただし、設計には専門知識が必要なので、司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
すでに認知症の症状が出ている場合の対応策

すでに認知症の症状が出ている場合は、法的な手続きが必要になることが多いです。
成年後見制度の利用方法
認知症の症状が出ている場合、成年後見制度の利用を検討しましょう。この制度は、認知症などで判断能力が不十分な人を法律的に支援する仕組みです。
成年後見制度の申立ては家庭裁判所に行います。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。申立てには診断書や財産目録など複数の書類が必要で、費用は申立て手数料として約1万円、さらに鑑定費用が5〜10万円程度かかることが一般的です。
成年後見人には、家族が選ばれることもありますが、専門職(弁護士、司法書士など)が選ばれることも多いです。後見人には財産管理や契約などを行う権限が与えられます。
共有名義不動産の売却や管理の手続き
認知症の人が共有者にいる不動産を売却するには、基本的に成年後見人を立てる必要があります。成年後見人が選任されたら、その後見人と他の共有者全員の同意によって売却が可能になります。
ただし、成年後見人が不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。裁判所は本人の利益になるかどうかを判断した上で許可を出します。この判断には数週間から数ヶ月かかることもあります。
また、共有名義不動産の管理(修繕や賃貸など)についても、成年後見人は裁判所の監督のもとで行います。大きな修繕や用途変更には裁判所の許可が必要になることがあります。
専門家に相談するタイミングと選び方
専門家への相談は、早ければ早いほど選択肢が広がります。以下のようなタイミングでの相談をおすすめします。
- 認知症の診断を受けたとき
- 共有名義の不動産の売却や活用を考え始めたとき
- 共有者間で意見の相違が生じ始めたとき
専門家選びのポイントは、それぞれの専門分野を理解することです。弁護士は法律全般、司法書士は不動産登記や成年後見、税理士は税金対策に強みがあります。最近では「家族信託専門家」を名乗る専門家も増えています。
相談する際は、「認知症と共有名義の問題に詳しいか」を事前に確認すると良いでしょう。また、複数の専門家のセカンドオピニオンを聞くことも大切です。相談料は30分5,000円前後が一般的ですが、最初の相談を無料にしている事務所もあります。
よくある質問と回答

共有名義の解消はできるの?
共有名義の解消は、全員が同意すれば可能です。例えば、兄弟で共有している土地を、一人が買い取って単独名義にする方法などがあります。ただし、すでに認知症の共有者がいる場合は、成年後見人を立てる必要があります。また、持分の売買には譲渡所得税、贈与の場合は贈与税がかかる可能性がありますので、税理士にも相談することをおすすめします。
認知症の親の同意なしに売却はできる?
原則として、認知症の親の同意なしに共有不動産を売却することはできません。ただし、以下の方法が考えられます。
一つは成年後見制度を利用する方法です。成年後見人が選任されれば、その後見人の同意によって売却が可能になります。ただし、家庭裁判所の許可が必要です。
もう一つは、共有物分割請求という方法です。これは共有関係を解消するために裁判所に請求する手続きです。裁判所の判断によっては、不動産の売却と代金分割が命じられることもあります。ただし、時間と費用がかかる点に注意が必要です。
兄弟間で意見が分かれたときの解決法
兄弟間で共有不動産の処分や管理について意見が分かれることは非常に多いです。この場合の解決法には主に次の3つがあります。
1つ目は話し合いによる解決です。第三者(専門家など)を交えた話し合いの場を設けることで、冷静な判断ができることがあります。
2つ目は調停・審判の利用です。家庭裁判所での調停は、裁判よりも和やかな雰囲気で解決策を探れます。話し合いで解決しない場合は、審判に移行することもあります。
3つ目は前述の共有物分割請求です。どうしても合意に至らない場合の最終手段です。
どの方法を選ぶにせよ、感情的にならずに「何が親や家族全体にとって最善か」という視点で考えることが大切です。
まとめ
共有名義と認知症の問題は、事前の備えがあるかないかで大きく状況が変わります。認知症は誰にでも起こりうる病気であり、共有名義の財産は多くの家族が持っています。だからこそ、今からできる対策を進めておくことが重要です。
家族が後悔しないために今すぐできる3つのこと
- 家族会議を開催する:まずは家族全員で財産管理について話し合いましょう。特に高齢の親がいる場合は、親の意向を確認しておくことが大切です。「もしも認知症になったら…」という仮定の話をするのは難しいかもしれませんが、この話し合いが将来の大きな安心につながります。
- 共有名義財産の棚卸しをする:家族で所有している共有名義の財産(不動産、預金など)をリストアップしましょう。それぞれの財産について、共有者は誰か、持分はどうなっているかを確認します。不動産は法務局で登記簿を取り寄せると正確な情報がわかります。
- 専門家に相談する:自分たちの状況に合った対策を専門家に相談しましょう。弁護士、司法書士、税理士などの専門家は、それぞれの視点からアドバイスしてくれます。特に「認知症対策に詳しい専門家」を選ぶと良いでしょう。初回相談を無料にしている事務所もありますので、気軽に相談してみてください。
専門家相談先リスト
以下は、認知症と共有名義の問題に関して相談できる専門家の一例です。
- 弁護士:法律全般、トラブル解決、成年後見申立て
- 司法書士:不動産登記、成年後見申立て、家族信託
- 税理士:贈与税対策、相続税対策
- 行政書士:任意後見契約、遺言書作成
- 社会福祉士:成年後見人、高齢者福祉全般
チェックリスト:我が家の共有名義リスク診断
最後に、あなたの家庭の「共有名義リスク」を診断するチェックリストをご紹介します。以下の項目に該当するものがあれば、早めの対策をおすすめします。
□ 65歳以上の家族が共有名義の財産を持っている □ 共有名義の財産について家族で話し合ったことがない □ 共有者の中に物忘れが増えている人がいる □ 共有名義の不動産を将来売却する可能性がある □ 共有者間で将来の財産管理について意見が分かれている □ 共有名義の解消や対策について専門家に相談したことがない
チェック項目が多ければ多いほど、早めの対策が必要です。この記事で紹介した方法を参考に、あなたの家族に合った対策を考えてみてください。
認知症は突然訪れることがあります。その時になって慌てないよう、今できることから始めましょう。家族の笑顔と財産を守るために、一歩踏み出すことが大切です。

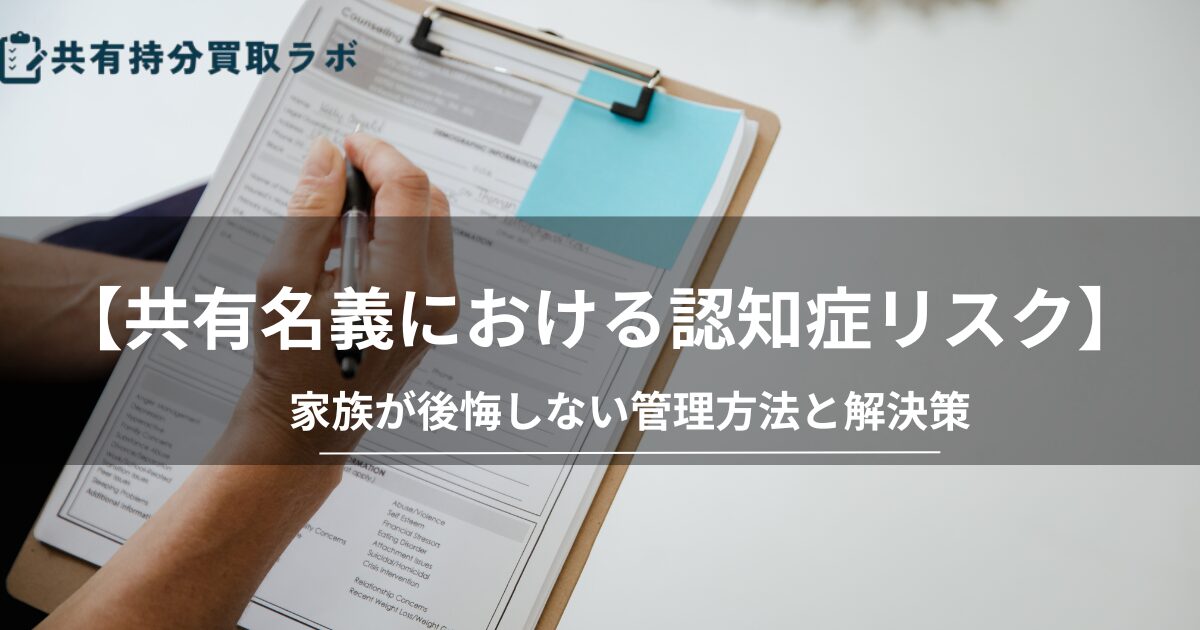

コメント