「この土地は長年使っているから自分のものだ」という主張が法的に認められることがあります。これが「時効取得」と呼ばれる制度です。特に複数人で所有する「共有不動産」の場合、この時効取得の問題は複雑になります。
例えば、相続によって複数人の名義になった実家の土地や建物を、ずっと一人だけが管理し続けているケースを考えてみましょう。固定資産税もすべて支払い、20年以上にわたって自分の土地だと思って使い続けてきた場合、他の共有者の持分を時効によって取得できるのでしょうか。
共有不動産の時効取得は一般的な時効取得より難しいとされていますが、条件によっては可能です。この記事では、共有不動産の時効取得が認められる条件や必要な手続き、立証のポイントなどを初心者にもわかりやすく解説します。
不動産の権利関係でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
時効取得とは?初心者向け基礎知識

時効取得とは、他人の物を一定期間にわたって自分のものとして占有し続けた場合に、その物の所有権を取得できる制度です。民法第162条に規定されており、社会生活の安定や長期にわたる事実状態の尊重を目的としています。
時効取得には大きく分けて「短期取得時効」と「長期取得時効」の2種類があります。短期取得時効は、占有を始めたときに「自分のものだと信じていて、その信じ方に過失がなかった場合」に10年で成立します。一方、長期取得時効は、占有を始めたときに「他人のものだと知っていた場合や、調査不足で知らなかった場合」に20年で成立します。
ここで重要なのは、時間が経っただけでは時効取得は成立しないという点です。後ほど詳しく説明する5つの要件をすべて満たし、さらに「時効の援用」という手続きを行うことで初めて時効取得が認められます。
一般的な不動産の時効取得と共有不動産の時効取得の違いは、主に「自分のものだと思っているか(所有の意思)」の立証の難しさにあります。共有不動産の場合、自分以外の共有者がいることを知っていることが多いため、「完全に自分のものだと思っている」という状態を証明するのが難しいのです。
共有不動産の時効取得に必要な5つの要件

共有不動産を時効取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
要件①:他人の物であること(共有持分の性質)
時効取得の対象となるのは「他人の物」です。共有不動産の場合、自分の持分については時効取得の対象にはなりませんが、他の共有者の持分は「他人の物」として時効取得の対象になります。
例えば、AさんとBさんが2分の1ずつ共有している土地があるとします。Aさんはすでに自分の持分(2分の1)を持っているので、それを時効取得することはできません。しかし、Bさんの持分(残りの2分の1)については、条件を満たせば時効取得することが可能です。
要件②:一定期間の継続した占有(10年or20年)
時効取得には一定期間の継続した占有が必要です。短期取得時効なら10年間、長期取得時効なら20年間の占有が必要になります。
共有不動産の場合、「共有物である」と知っていることが多いため、多くのケースでは「20年」の長期取得時効の要件を満たす必要があります。この20年間は途切れることなく継続して占有していることが条件です。
要件③:平穏かつ公然の占有
占有は「平穏」かつ「公然」でなければなりません。「平穏」とは、暴力や脅迫などによらず穏やかに占有していることを意味します。例えば、他の共有者を脅して使用させないようにしているような場合は「平穏」とは言えません。
「公然」とは、隠れて占有するのではなく、誰から見ても占有していることがわかる状態を指します。例えば、誰にも知られないように秘密裏に不動産を使用している場合は「公然」とは言えません。
共有不動産の場合は、他の共有者に知られないように使用することは難しいので、「公然」の要件は比較的満たしやすいと言えます。
要件④:所有の意思をもった占有(自主占有)
時効取得で最も重要な要件が「所有の意思をもった占有(自主占有)」です。これは「自分がその不動産の所有者である」という意識で占有していることを意味します。
共有不動産の時効取得が難しいと言われる最大の理由は、この「所有の意思」の立証が難しいからです。なぜなら、共有者は通常、不動産が共有であることを知っているため、「完全に自分のものだ」と思っているとは言い難いからです。
ただし、以下のような場合には「所有の意思」が認められる可能性があります。
- 長年にわたり一人で不動産を管理し、他の共有者が一切関与していない
- 固定資産税をすべて自分で支払っている
- 修繕や改築などを自分の判断で行っている
- 相続時に「単独所有だ」と信じていた
要件⑤:善意・無過失(短期取得時効の場合)
短期取得時効(10年)を主張する場合には、「善意」かつ「無過失」であることが必要です。「善意」とは、その不動産が自分のものだと信じていること、「無過失」とは、そう信じることに落ち度がなかったことを意味します。
例えば、親から「この土地は相続で全部あなたのものになった」と聞かされ、登記簿も確認せずにそのまま信じて10年以上占有していた場合などが考えられます。ただし、通常は登記簿を確認すれば共有名義であることがわかるため、「無過失」が認められるケースは限られます。
共有不動産の場合、多くのケースでは長期取得時効(20年)を目指すことになります。
共有不動産の時効取得が難しい理由

共有不動産の時効取得が難しいと言われる理由をさらに詳しく見ていきましょう。
「所有の意思」の立証の難しさ
先述の通り、共有不動産の時効取得で最も難しいのは「所有の意思」の立証です。所有の意思は、単に主観的に「自分のものだ」と思っているだけでは不十分で、客観的な事実から判断されます。
共有者は通常、不動産が共有であることを知っているため、「他の共有者の権利も認識した上で占有している」とみなされがちです。これは「所有の意思」とは相反する状態です。
共有者の認識の問題
共有不動産の時効取得では、占有者が「共有者だという認識」を持っていると、時効取得が難しくなります。例えば、「自分は共有持分2分の1を持っていて、残りの2分の1は兄が持っている」と認識していれば、「自分が全部の所有者だ」という所有の意思は否定されます。
この点は裁判でも重視されており、共有者としての認識がある場合に時効取得が認められたケースは少ないのが現状です。
共同相続した不動産の特殊性
相続によって共有状態になった不動産の場合、さらに難しい問題があります。被相続人(亡くなった人)から不動産を借りていた相続人は、相続によって共有者になっても、その占有の性質は「借主」のままとみなされることがあります(民法第185条)。
つまり、親の家に住んでいた子が、親の死後にその家を相続しても、他の相続人(兄弟姉妹など)との関係では「借主」としての地位を引き継ぐことになり、「所有の意思」が認められにくいのです。
裁判例から見る時効取得の難しさ
実際の裁判例を見ると、共有不動産の時効取得が認められるケースは限られています。最高裁判所の判例(昭和47年9月8日判決)では、共同相続人の一人が「自分だけが相続した」と信じる特別な事情があった場合に時効取得が認められています。
この判例以降も、共有不動産の時効取得が認められるのは、「単独所有と信じるに足る特別な事情がある」「他の共有者が長期間にわたって全く関与していない」といった例外的なケースに限られています。
共有不動産の時効取得が認められるケース

では、どのような場合に共有不動産の時効取得が認められるのでしょうか。いくつかの具体例を見てみましょう。
具体的な成功事例
共有不動産の時効取得が認められた代表的なケースとしては、以下のようなものがあります。
- 相続人の一人が「自分だけが相続した」と信じるに足る特別な事情があった場合
- 遺産分割協議書が存在すると信じていたが、実際には無効だった場合
- 長年にわたり一人で不動産を管理し、他の共有者が全く関与せず、固定資産税もすべて支払っていた場合
- 親から「この土地は全部あなたのもの」と言われ、他の相続人も長年それに異議を唱えなかった場合
時効取得が認められやすい状況の特徴
共有不動産の時効取得が認められやすい状況には、いくつかの共通点があります。
まず、占有者が「単独所有者である」と信じる合理的な理由があることが重要です。次に、他の共有者が長期間(20年以上)にわたって全く関与していないこと、つまり不動産の管理や費用負担に一切参加していないことも重要な要素です。
また、占有者が不動産の維持管理を全面的に行い、固定資産税などの費用も全額負担していることも認められやすさに影響します。
相続による共有持分の時効取得のポイント
相続による共有不動産の場合、時効取得のポイントは「なぜ自分が単独所有者だと信じたのか」という点です。例えば、被相続人(親など)から「この家は全部あなたに相続させる」と言われていた場合や、他の相続人も「その家はあなたのものだ」と認めていた場合などは、「単独所有と信じた」と主張しやすくなります。
ただし、相続の場合は他の相続人の存在を知っているのが普通なので、「他の相続人の権利を知らなかった」と主張するのは難しいことが多いです。そのため、他の相続人が長期間にわたって権利を主張せず、自分だけが不動産を管理し続けてきたという事実が重要になります。
固定資産税の全額支払いなど客観的事実の重要性
共有不動産の時効取得では、「所有の意思」を客観的に証明できる事実が非常に重要です。その中でも特に重視されるのが「固定資産税の支払い」です。固定資産税は所有者が支払うものなので、長年にわたって一人で全額を支払っていれば、「自分が所有者だ」という意思の表れとみなされやすくなります。
その他にも、不動産の修繕や改築を自分の判断で行っていること、近隣住民からも所有者として認識されていることなど、客観的に「所有者としての振る舞い」をしていたことを示す事実が重要です。
共有不動産の時効取得の立証方法

共有不動産の時効取得を主張する際には、5つの要件をすべて満たしていることを立証する必要があります。特に重要なのは「所有の意思をもった占有」の立証です。具体的な立証方法を見ていきましょう。
自主占有を証明するための具体的な証拠
「所有の意思をもった占有(自主占有)」を証明するための証拠としては、以下のようなものが有効です。
- 固定資産税の納税通知書と領収書(20年分あると理想的)
- 不動産の修繕・改築の領収書や契約書
- 不動産の管理に関する資料(庭の手入れ、雪下ろしなどの記録)
- 公共料金の支払い記録
- 住民票や選挙人名簿(居住の証明)
- 近隣住民や親戚からの証言(所有者として認識されていたことの証明)
これらの証拠をできるだけ多く集め、長期間にわたって自分が「所有者として」不動産を管理していたことを示すことが重要です。
固定資産税の支払い証明や維持管理の記録
特に重要な証拠が「固定資産税の支払い証明」です。固定資産税は所有者が支払うものなので、長年にわたって一人で全額を支払っていれば、「自分が所有者だ」という意思の表れとして評価されます。
固定資産税の納税通知書は通常、所有者に送られるものです。納税通知書が自分宛に送られてきて、それを支払い続けていたという事実は、「所有者として振る舞っていた」という有力な証拠になります。
また、不動産の維持管理に関する記録も重要です。例えば、屋根の修理や外壁の塗り替え、庭の手入れなどを自分の判断と費用で行ってきたことを示す記録や領収書は、「所有者としての振る舞い」を証明する有力な証拠となります。
第三者の証言や公的書類の活用法
時効取得の立証では、客観的な第三者の証言も重要な証拠となります。例えば、近隣住民が「20年以上、Aさんがこの家の所有者として住んでいて、他の人は全く関わっていなかった」と証言してくれれば、有力な証拠となります。
また、公的書類も積極的に活用しましょう。例えば、住民票や選挙人名簿、水道・電気・ガスなどの公共料金の契約書や支払い記録なども、長期間にわたって自分が居住し、管理していたことを示す証拠となります。
立証における注意点と工夫
共有不動産の時効取得の立証では、いくつかの注意点があります。
まず、証拠は「量」よりも「質」が重要です。例えば、固定資産税の支払い証明が20年分すべてあるのが理想ですが、全部がなくても、定期的に支払っていたことが分かる証拠があれば有効です。
また、「自分が所有者だと思っていた」という主観的な主張だけでなく、「所有者として客観的にどのように振る舞っていたか」を示す証拠を集めることが重要です。例えば、他の共有者に許可を求めずに自分の判断で不動産の改築を行ったという事実は、「自分が所有者だと思っていた」ことの有力な証拠となります。
さらに、証拠は早めに集め始めることをおすすめします。時効取得の主張は20年以上前の事実に基づくものなので、時間が経つほど証拠の収集が難しくなります。特に領収書や契約書などの書類は紛失しやすいので、計画的に保管しておくことが重要です。
共有不動産の時効取得手続きの流れ
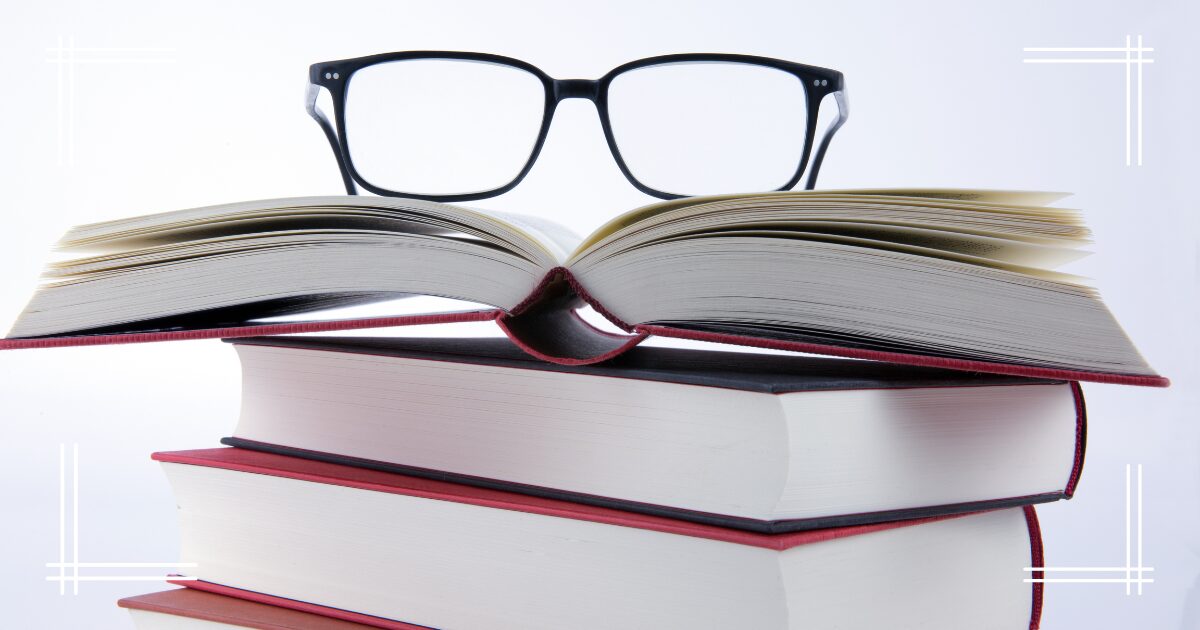
共有不動産の時効取得の要件を満たしていると考えられる場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。具体的な流れを見ていきましょう。
法務局での登記簿謄本取得と共有者の確認
まず最初に行うべきは、法務局で不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、現在の所有者(共有者)を確認することです。登記簿謄本からは、共有者の氏名、住所、持分割合などの情報が得られます。
登記簿謄本の取得は、法務局の窓口で申請するか、オンラインで申請することができます。手数料は600円程度です。
共有者を確認したら、その共有者の現在の住所や連絡先を調査します。登記簿に記載されている住所が古い場合もあるので、必要に応じて住民票の取得や戸籍調査を行います。
時効の援用と内容証明郵便の送付
時効取得の要件を満たしていることが確認できたら、次は「時効の援用」を行います。時効の援用とは、時効によって権利を取得したいという意思表示のことです。
時効の援用は、共有者に対して「時効援用通知書」を送付することで行います。この通知書には、「いつからいつまで占有していたか」「どのような形で占有していたか」「時効取得の要件を満たしていると考える理由」などを記載します。
通知書は内容証明郵便で送付するのが一般的です。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を送ったかが公的に証明される郵便サービスで、後々のトラブル防止のために重要です。
共有者の同意が得られた場合の手続き
時効援用通知書を送付して、共有者が時効取得に同意してくれれば、比較的スムーズに手続きを進めることができます。同意が得られた場合は、「時効取得を原因とする所有権移転登記」を申請します。
この登記申請には、以下の書類が必要です。
- 登記申請書
- 時効取得の事実を証明する書類(固定資産税の納税証明書など)
- 共有者の同意書
- 印鑑証明書(共有者のもの)
- 住民票(時効取得者のもの)
登記申請は、法務局の窓口で行うか、オンラインで申請することができます。手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
共有者が同意しない場合の裁判手続き
時効援用通知書を送付しても共有者が同意しない場合は、「時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟」を提起することになります。
訴訟では、時効取得の要件をすべて満たしていることを証明する必要があります。特に「所有の意思をもった占有」の立証が重要で、前述した証拠を用いて主張します。
訴訟は地方裁判所に提起し、勝訴して判決が確定すれば、その判決に基づいて所有権移転登記を申請することができます。訴訟には専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼することをおすすめします。
時効取得ができない場合の対処法

共有不動産の時効取得が難しい場合や、要件を満たしていない場合でも、共有状態を解消するための方法はいくつかあります。それぞれの方法について見ていきましょう。
共有者からの持分買取交渉
最も一般的な方法は、他の共有者から持分を買い取ることです。他の共有者が持分を売却する意思がある場合は、適正な価格で買い取ることで単独所有にすることができます。
持分の買取価格は、不動産の市場価格に持分割合を掛けた金額が基準となりますが、共有持分は単独所有よりも価値が低いとされるため、実際には割引価格になることが多いです。
交渉がまとまれば、「売買を原因とする所有権移転登記」を申請することになります。この登記申請には、売買契約書、印鑑証明書、住民票などが必要です。
共有物分割請求による解決
他の共有者が持分の売却に応じない場合は、「共有物分割請求」という方法もあります。これは、共有状態を解消するよう裁判所に請求する方法です。
共有物分割請求には、以下の3つの方法があります。
- 現物分割:不動産を物理的に分割する方法
- 換価分割:不動産を売却して代金を分ける方法
- 価格賠償:一方が他方の持分を買い取る方法
土地や建物は物理的に分割しづらいため、実際には「換価分割」か「価格賠償」になることが多いです。裁判所は各共有者の事情を考慮して、最も公平な分割方法を決定します。
不動産の一括売却の検討
共有不動産をそのまま維持することが難しい場合は、不動産全体を売却して代金を持分割合に応じて分配するという方法もあります。
この方法のメリットは、共有状態を完全に解消できることと、不動産全体を売却することで共有持分だけを売却するよりも高い価格で売れる可能性があることです。
ただし、不動産を売却するためには共有者全員の同意が必要なので、一人でも反対すると売却できません。その場合は前述の「共有物分割請求」に進むことになります。
専門の買取業者への相談
他の共有者との交渉が難しい場合や、速やかに現金化したい場合は、共有持分専門の買取業者に相談することも一つの方法です。
共有持分専門の買取業者は、一般の不動産会社では買い取りが難しい共有持分を買い取ってくれます。市場価格よりは安くなる傾向がありますが、迅速に現金化できるメリットがあります。
また、買取業者の中には弁護士と提携しているところもあり、他の共有者との交渉や法的手続きもサポートしてくれる場合があります。
共有不動産の時効取得に関するよくある質問(FAQ)

共有不動産の時効取得に関して、よくある質問にお答えします。
相続した共有不動産は時効取得できる?
相続した共有不動産の時効取得は一般的に難しいとされています。なぜなら、相続人は通常、不動産が共有であることを知っているからです。
ただし、以下のような特別な事情がある場合には時効取得が認められる可能性があります。
- 遺言や遺産分割協議で自分が単独で相続したと信じていた場合
- 他の相続人が長期間にわたって権利を主張せず、自分だけが不動産を管理し続けてきた場合
相続した共有不動産の時効取得を主張する場合は、これらの特別な事情を具体的に証明する必要があります。
時効取得の費用はどのくらい?
時効取得にかかる費用は、共有者の同意があるかどうかによって大きく異なります。
共有者の同意がある場合は、登記申請にかかる費用(登録免許税、司法書士報酬など)で5万円から10万円程度が一般的です。
一方、共有者の同意がなく訴訟になる場合は、弁護士費用(着手金、成功報酬)、裁判所への印紙代、証拠収集費用などで数十万円から数百万円程度かかることが一般的です。訴訟の複雑さや不動産の価値によって費用は大きく変わります。
共有者が行方不明の場合はどうする?
共有者が行方不明の場合でも、時効取得自体は可能です。ただし、時効の援用通知を送ることができないという問題があります。
この場合は、「不在者財産管理人選任申立て」という手続きを行い、裁判所に共有者の財産を管理する人を選任してもらいます。選任された財産管理人に対して時効の援用通知を送り、その後の手続きを進めることになります。
なお、共有者の生死が不明で5年以上経過している場合は「失踪宣告」の申立てを行うという方法もあります。
時効取得を主張されたらどう対応する?
逆に、あなたが所有する共有持分について他の共有者から時効取得を主張された場合の対応も知っておきましょう。
まず、時効取得の要件を本当に満たしているかを確認することが重要です。特に「所有の意思をもった占有」の要件を満たしているかどうかを検討しましょう。
時効取得の要件を満たしていないと考えられる場合は、内容証明郵便で反論の意思を伝え、必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします。
一方、時効取得の要件を満たしていると思われる場合は、無用な争いを避けるために話し合いによる解決を検討することも一つの選択肢です。例えば、時効取得に同意する代わりに一定の金銭を支払ってもらうという和解も考えられます。
まとめ:共有不動産の時効取得を成功させるポイント
共有不動産の時効取得について解説してきましたが、最後に成功させるためのポイントをまとめましょう。共有不動産の時効取得は一般的な時効取得よりも難しいものの、条件を満たせば認められる可能性があります。
成功のカギとなるのは「所有の意思をもった占有(自主占有)」を客観的に証明できるかどうかです。そのためには、固定資産税の支払い証明や不動産の維持管理記録など、所有者として振る舞ってきたことを示す証拠を日頃から集めておくことが重要です。また、長期間(20年)にわたって継続して占有していることも必須条件です。
法的手続きについては、できるだけ早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。特に、「所有の意思」の立証方法や「時効の援用」の方法など、専門的な知識が必要な部分は、専門家のアドバイスを受けることで成功率が高まります。
仮に時効取得が難しい場合でも、共有持分の買取交渉や共有物分割請求など、他の方法で共有状態を解消する選択肢もあります。共有不動産の問題は一つの方法にこだわらず、複数の選択肢を検討することが大切です。
要件を満たすための日頃からの心がけ
共有不動産の時効取得を将来的に主張する可能性がある場合は、日頃から以下のことを心がけておくと良いでしょう。
まず、固定資産税の納税通知書や領収書は必ず保管しておきましょう。次に、不動産の修繕や改築を行った際の契約書や領収書も保管しておきます。さらに、不動産の管理に関する記録(庭の手入れ、雪下ろしなど)も可能な限り残しておくことをおすすめします。
また、他の共有者に許可を求めずに自分の判断で不動産を管理・利用することも「所有の意思」を示すうえで重要です。ただし、他の共有者との関係が悪化しないよう、バランスを取ることも必要です。
専門家に相談するタイミングと選び方
共有不動産の時効取得を検討する際は、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。特に以下のようなタイミングでは、専門家への相談が有効です。
- 時効取得の要件を満たしているか判断に迷う場合
- 時効の援用の方法がわからない場合
- 他の共有者が時効取得に同意しない場合
- 共有者が行方不明の場合
専門家の選び方としては、不動産の時効取得や共有持分に関する実績や知識がある弁護士や司法書士を選ぶことが重要です。初回相談が無料の事務所も多いので、複数の専門家に相談して相性の良い人を見つけることをおすすめします。
弁護士に依頼する場合の費用の目安は、着手金が20万円から50万円程度、成功報酬が不動産価値の5%から10%程度と考えておくとよいでしょう。ただし、事案の複雑さによって費用は大きく変わります。
時効取得以外の選択肢も視野に入れる重要性
共有不動産の問題は、時効取得だけにこだわらず、他の選択肢も検討することが重要です。時効取得の要件を満たしていない場合や、裁判のリスクや費用を避けたい場合は、以下のような方法も検討しましょう。
- 他の共有者との話し合いによる持分の買取
- 共有物分割請求による解決
- 不動産全体の売却と代金分配
- 共有持分専門の買取業者への売却
各方法にはメリット・デメリットがあるので、自分の状況や目的に合った方法を選ぶことが大切です。どの方法が最適かは、不動産の価値や共有者との関係、自分の資金状況などによって異なります。
今すぐ実行できる具体的なアクション3つ
共有不動産の時効取得について理解を深めた今、ぜひ以下の3つのアクションを実行してみてください。
1. 登記簿謄本を取得して共有状態を確認する
まず最初に行うべきことは、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して、不動産の正確な共有状態を確認することです。登記簿謄本からは、共有者の氏名、住所、持分割合などの情報が得られます。
登記簿謄本は法務局の窓口で600円程度で取得できます。また、オンラインでも申請可能です。登記情報を正確に把握することで、どのような対応が必要かの判断材料になります。
2. 時効取得の証拠となる書類を整理する
時効取得を主張する可能性がある場合は、固定資産税の納税証明書、不動産の修繕・改築の領収書、公共料金の支払い記録など、これまでの不動産の管理・利用状況を示す書類を整理しましょう。
特に重要なのは固定資産税の支払い証明です。過去20年分の納税証明書があると理想的ですが、すべてがなくても、定期的に支払っていたことが分かる証拠があれば有効です。役所で納税証明書を取得することも可能です。
3. 不動産・相続問題に詳しい専門家に相談する
共有不動産の時効取得は法律的に複雑な問題なので、不動産問題や相続問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
初回相談が無料の事務所も多いので、複数の専門家に相談して、自分の状況に最適なアドバイスをもらいましょう。専門家のアドバイスを受けることで、時効取得が可能かどうかの判断や、他の選択肢の検討も含めた総合的な解決策を見つけることができます。
これらのアクションを実行することで、共有不動産の問題解決に向けた第一歩を踏み出すことができます。共有不動産の問題は時間がかかることが多いので、早めの行動が重要です。

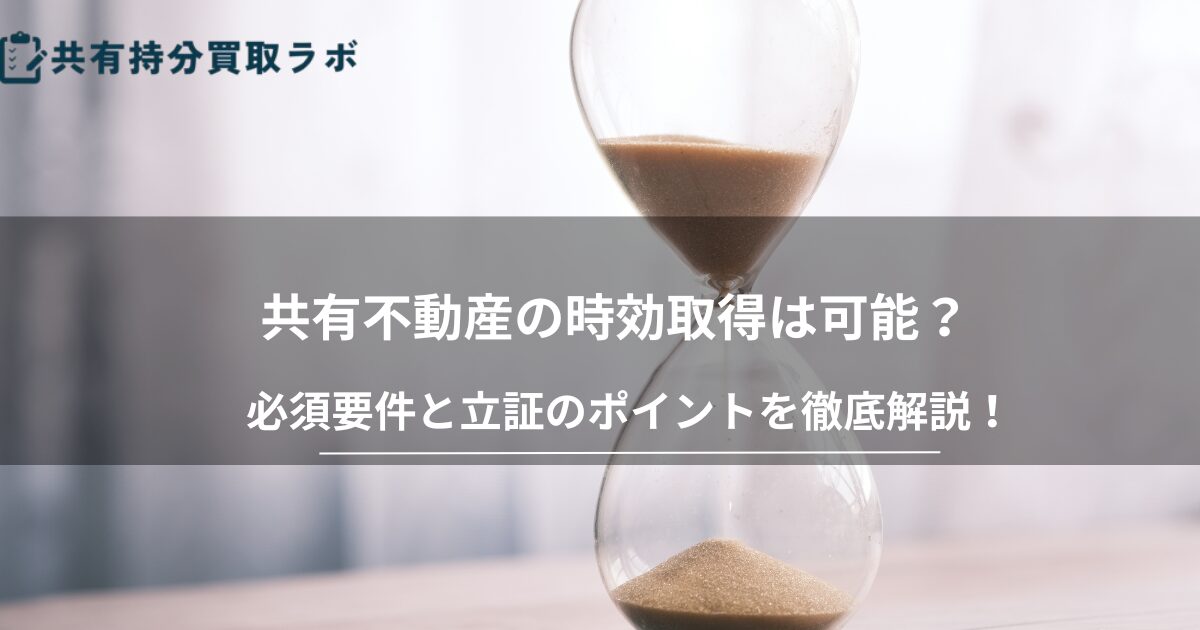

コメント