不動産の共有持分でお悩みではありませんか?「共有持分を売却したいけど、どうすればいいの?」「トラブルなく譲渡する方法はある?」このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
共有持分の譲渡は、一般的な不動産売却とは異なる特有の難しさがあります。事前の知識がないまま進めると、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
でも安心してください。この記事では、共有持分の譲渡に関するトラブル事例とその対処法を初心者にもわかりやすく解説します。
これから共有持分の譲渡を考えている方はもちろん、すでに共有持分をお持ちで将来的な対策を立てたい方にもおすすめの内容です。この記事を最後まで読めば、共有持分譲渡の落とし穴を避け、スムーズな取引を実現するためのノウハウが身につくはずです。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有持分って何?初心者向け基本知識

共有持分とは?簡単に言うと「不動産の部分所有権」
共有持分とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有している場合に、それぞれが持っている所有権の割合のことです。たとえば、あなたと友人の2人で土地を購入し、費用を半分ずつ出した場合、あなたの共有持分は2分の1(50%)となります。
重要なのは、共有持分は物理的に土地や建物を分ける「区分所有」とは異なり、持分割合に応じた「権利」を持つという点です。土地にラインを引いて「ここからここまでがあなたの土地」というわけではありません。
共有持分が発生する主なケースは以下の通りです。
- 相続で複数の相続人に不動産が分配された場合
- 夫婦や親子などで共同購入した場合
- 離婚による財産分与で共有になった場合
- 資金調達のために投資家と共同で不動産を購入した場合
例えば、ご両親が亡くなり、3人兄弟で実家を相続した場合、法定相続分に従って各自が3分の1ずつの共有持分を持つことになります。
共有持分の権利と制限
共有持分を持つということは、その不動産に対して一定の権利を持つことを意味します。しかし、同時に様々な制限もあります。
共有者として持つ主な権利:
- 自分の持分を自由に売却、贈与できる(民法第206条に基づく)
- 不動産の全体を使用できる(他の共有者も同様)
- 共有物の管理について発言権を持つ
一方で、以下のような制限があります:
- 不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要(民法第251条に基づく変更行為)
- 大規模な改修や用途変更には共有者の同意が必要
- 単独で勝手に賃貸することはできない
- 共有物の保存行為以外は、持分の割合に応じた決議が必要
これらの権利と制限は民法で定められており、2023年4月に施行された民法改正により一部の規定が変更されています。特に共有物の管理に関するルールが整備され、持分の過半数で決議できる事項が明確化されました。
なぜ共有持分はトラブルが起きやすいのか
共有持分がトラブルの温床になりやすい理由は、「複数の所有者の意思決定が必要」という点にあります。特に以下のような場合に問題が発生しやすくなります:
- 共有者同士の人間関係が悪化している
- 共有者の一部が連絡が取れなくなっている
- 共有者間で不動産の活用方法について意見が対立している
- 共有者の一部が経済的に困窮している
- 相続を繰り返すことで共有者の数が増えていく(数次相続)
- 共有者の中に未成年者や認知症の方がいる場合(法定代理人の問題)
例えば、兄弟で相続した実家を「売却したい」と考える兄と「今のまま残しておきたい」と考える妹では、意見の食い違いからトラブルに発展することがあります。
また、共有持分のまま相続が繰り返されると、共有者が10人、20人と増えていき、全員の同意を得ることが実質的に不可能になることもあります。これを「所有者不明土地問題」と呼び、社会問題にもなっています。
共有持分の譲渡方法と特徴

共有持分を手放す方法はいくつかあります。それぞれに特徴があるので、自分の状況に合った方法を選びましょう。
売買による譲渡
売買による譲渡は、お金と引き換えに共有持分を手放す最も一般的な方法です。売却先としては、主に以下の2つが考えられます:
他の共有者への売却
最もスムーズな方法は、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらうことです。他の共有者にとっても、持分が増えることで不動産に対する権利が強まるメリットがあります。
例えば、あなたと兄弟2人で共有している土地があるとします。あなたが3分の1の持分を持っていて、これを他の兄弟に売却すれば、買い取った兄弟の持分は3分の2になり、より大きな発言権を持つことができます。
第三者への売却
他の共有者が買い取りを希望しない場合は、第三者への売却も可能です。ただし、共有持分は単独所有の不動産と比べて需要が少なく、一般の買い手を見つけるのは困難です。
そのため、共有持分専門の買取業者に売却するケースが多くなります。業者への売却は手続きがスムーズな反面、市場価格よりも低い価格での買取になることが多いので注意が必要です。例えば、一般的な相場の50~70%程度の価格になることもあります。
贈与による譲渡
贈与は、無償で共有持分を譲ることです。主に家族間で行われることが多く、特に以下のようなケースで活用されます:
- 相続税対策として親から子へ生前贈与する
- 共有者間のトラブルを避けるため、信頼できる家族に譲る
- 管理の負担から解放されたいが、見知らぬ人に売却したくない場合
贈与の場合、贈与税が課税される可能性があります。ただし、年間110万円までの基礎控除があるため、持分価値がこの範囲内であれば贈与税はかかりません。
共有物分割による解消
共有状態そのものを解消する方法として、共有物分割があります。主に以下の3つの方法があります:
- 現物分割:物理的に不動産を分割する方法(例:土地を分筆する)
- 換価分割:不動産を売却して、その代金を持分に応じて分配する方法
- 代償分割:一人が不動産を取得し、他の共有者に金銭で補償する方法
共有物分割は、共有者間の合意があれば円満に進められますが、合意が得られない場合は「共有物分割請求訴訟」という法的手段を取ることになります。
なお、民法では「共有物分割請求権」として共有者の権利を保障しています(民法第256条)。この権利は原則としていつでも行使できますが、共有者間の合意により最長5年間は請求できないという特約を結ぶことも可能です。共有物分割禁止特約を契約書に盛り込むことで、一定期間は共有状態を維持することができます。
共有持分譲渡で起こりがちなトラブル事例
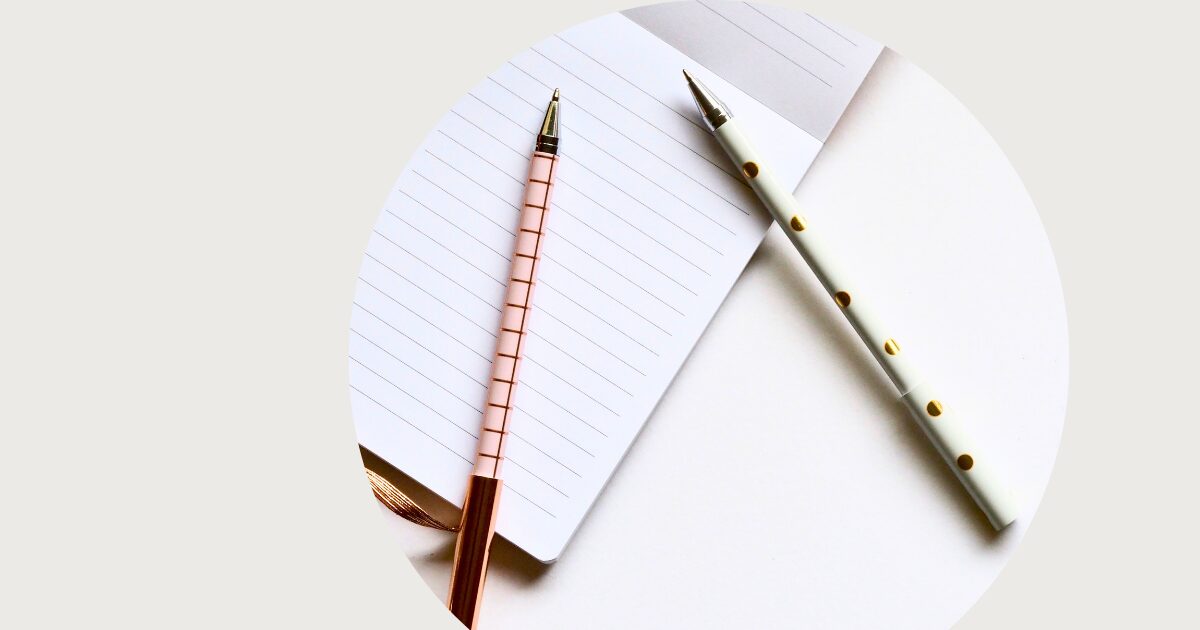
共有持分の譲渡では様々なトラブルが発生する可能性があります。共有持分は一般的な不動産取引とは異なる特殊性を持つため、事前に起こりうるトラブルを知っておくことが重要です。ここでは、実際によく起こるトラブル事例を紹介します。
トラブル事例1:他の共有者とのトラブル
共有持分の譲渡において最も多いのが、他の共有者との間で発生するトラブルです。
事例:事前相談なしの売却で関係悪化
Aさんは相続で取得した実家の土地(3人兄弟で3分の1ずつ共有)の自分の持分を、他の兄弟に相談せずに不動産投資家に売却しました。結果、残された兄弟2人は見知らぬ投資家と共有状態になり、「なぜ相談してくれなかったのか」と猛反発。家族関係が完全に壊れてしまいました。
このようなケースでは、事前に他の共有者への相談や買取の打診をしておくことが重要です。たとえ法的には自分の持分を自由に売却できるとしても、共有者間の信頼関係を壊さないための配慮が必要です。
トラブル事例2:第三者への売却による問題
自分の共有持分を第三者に売却すると、思わぬトラブルが発生することがあります。
事例:敷地への無断立ち入りトラブル
Bさんは亡き父から相続した土地の4分の1の持分を持っていましたが、管理の手間を避けるため、不動産買取業者に売却しました。しばらくして、その土地に住んでいる叔父から連絡があり、「知らない人が敷地内に勝手に入ってきて写真を撮っている」と苦情が。業者が物件の調査のために立ち入っていたことがわかりました。
共有者は法律上、共有物の全体を使用する権利があるため、新たな共有者となった第三者も敷地内に立ち入る権利を持ちます。このような事態を避けるためには、売却先の選定に十分注意する必要があります。
トラブル事例3:買取業者とのトラブル
共有持分専門の買取業者の中には、悪質な手法で利益を得ようとする業者も存在します。
事例:買取後の強引な営業
Cさんは相続した共有持分を買取業者に売却しました。その後、業者は残りの共有者に対して「この物件全体を売却しないと共有物分割請求訴訟を起こす」と脅し、安い価格での買取を迫りました。残りの共有者は不安になり、市場価値よりもかなり低い価格で持分を手放すことになりました。
買取業者の中には、このように取得した持分を「人質」として、残りの共有者から利益を搾取しようとする業者もいます。信頼できる業者を選ぶことが重要です。
トラブル事例4:共有物分割請求訴訟に発展するケース
共有持分を買い取った第三者が、共有物分割請求訴訟を起こすケースも少なくありません。
事例:突然の訴訟提起で強制売却に
Dさんは両親から相続した実家に住み続けていましたが、兄が自分の持分を投資家に売却していました。ある日、その投資家から「共有物分割請求訴訟」を起こされ、裁判所の判断で不動産全体を競売にかけることになりました。結果、長年住み慣れた実家を失うことになりました。
共有物分割請求は共有者の「権利」であり、裁判所に請求があれば原則として認められます。このリスクを理解し、事前に対策を講じておくことが大切です。
トラブル事例5:税金や費用の負担をめぐるトラブル
共有持分の譲渡後に、税金や維持費の負担をめぐってトラブルになることもあります。
事例:固定資産税の滞納問題
Eさんは共有マンションの持分を第三者に売却しましたが、その買主が固定資産税を支払わないまま行方をくらましました。結果、残された共有者に支払いの督促状が届き、延滞税まで請求されることになりました。
不動産の固定資産税は共有者全員に連帯納税義務があるため、一部の共有者が支払わない場合でも、他の共有者が全額を負担しなければならない可能性があります。譲渡先の信頼性を確認することが重要です。
共有持分譲渡の前に確認すべきこと

共有持分を譲渡する前に、以下のポイントをしっかり確認しておくことで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
共有者間での事前の話し合い
共有持分を譲渡する際に最も重要なのは、共有者間での話し合いです。特に確認すべきポイントは以下の通りです:
- 共有者全員の意向(売却賛成か反対か)
- 他の共有者が買い取る意思があるかどうか
- 共有物全体を売却する可能性はあるか
- 第三者への売却に対する他の共有者の反応
例えば、「自分の共有持分を売却したい」と考えているなら、まずは他の共有者に「持分を買い取る意思はあるか」と尋ねてみましょう。もし買い取る意思があれば、共有者間での譲渡が最もスムーズな方法です。
話し合いの場では感情的にならず、お互いの立場を尊重することが大切です。必要に応じて専門家(不動産会社や弁護士)に仲介してもらうのも一つの方法です。
共有持分の価値と売却相場を把握する
共有持分の適正価格を知るためには、まず不動産全体の価値を把握し、そこから持分割合に応じた金額を算出します。ただし、共有持分は単独所有の不動産より価値が下がることを念頭に置いておく必要があります。
共有持分の価値の目安
一般的に共有持分の価値は、以下のような要素で変動します:
- 共有者の数(多いほど価値は下がる)
- 他の共有者との関係性(良好なら価値は上がる)
- 不動産の使用状況(誰も使用していないほど価値は上がる)
- 共有物分割の可能性(分割しやすいほど価値は上がる)
共有持分の売却相場は、通常の不動産と異なり、市場価格の30%~80%程度になることが多いです。特に投資家や買取業者への売却では、50%前後になるケースが一般的です。
譲渡にかかる税金や費用の確認
共有持分の譲渡には様々な税金や費用がかかります。事前に把握しておきましょう。
主な税金
- 譲渡所得税:売却利益に対して課税されます。所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)は約20%、5年以下(短期譲渡所得)は約40%の税率です。
- 贈与税:無償で譲渡する場合に課税されます。基礎控除額(年間110万円)を超える場合のみ発生します。
- 不動産取得税:買主側が支払う税金ですが、売却価格に影響する可能性があります。
その他の費用
- 登記費用:持分移転登記には司法書士報酬と登録免許税がかかります(約5~10万円)
- 印紙税:売買契約書に貼る収入印紙の費用(売買金額によって変動)
- 仲介手数料:不動産会社を通じて売却する場合(売買価格の3%+6万円+消費税)
これらの費用を考慮に入れた上で、譲渡によって得られる実質的な金額を計算しておくことが大切です。
必要な書類と手続きの準備
共有持分の譲渡には多くの書類と手続きが必要です。スムーズに進めるために、以下の準備をしておきましょう:
必要な主な書類
- 権利証または登記識別情報
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 住民票(3ヶ月以内のもの)
- 固定資産税評価証明書
- 固定資産税納税通知書
手続きの流れ
- 共有者間での話し合い・意思確認
- 買主の選定(他の共有者または第三者)
- 不動産の査定・価格交渉
- 売買契約の締結
- 決済・所有権移転登記
特に第三者への売却では、契約書の内容をしっかり確認することが重要です。専門家(弁護士・司法書士)のチェックを受けることをおすすめします。
トラブルを防ぐための対処法
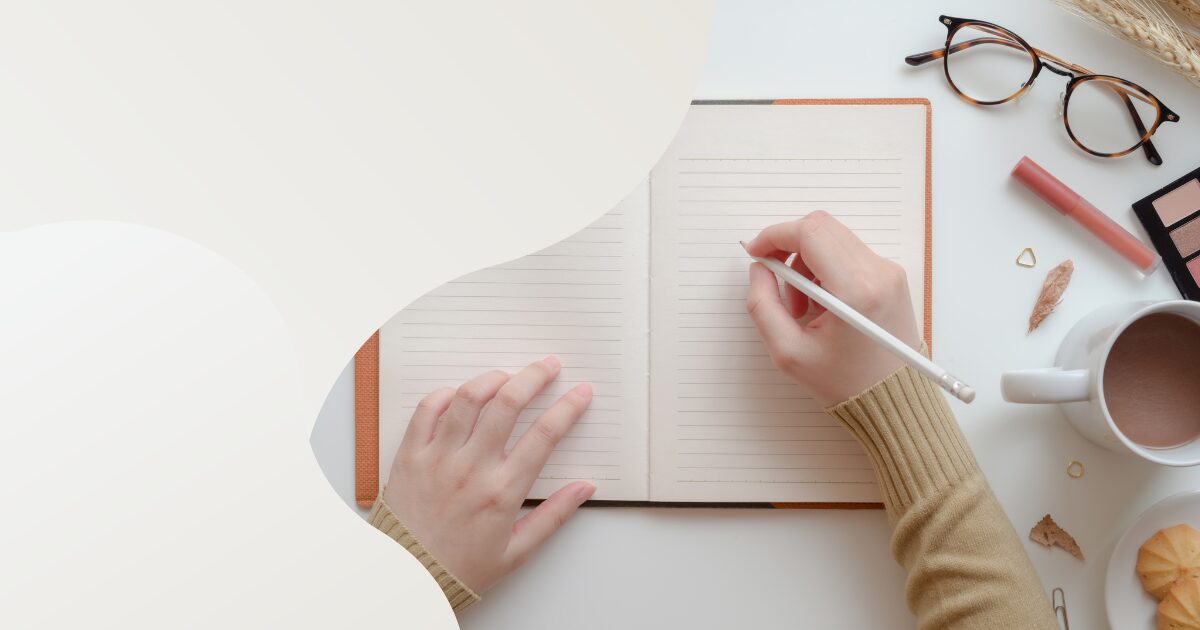
共有持分の譲渡に伴うトラブルを防ぐためには、以下のような対処法が効果的です。
他の共有者への事前相談と同意を得る方法
法律上は自分の共有持分を他の共有者の同意なく売却できますが、トラブル防止のためには事前相談が欠かせません。
効果的な相談方法
- フォーマルな場を設ける:電話やLINEではなく、直接会って話し合う場を設けましょう。
- 売却の理由を明確に伝える:なぜ売却したいのか、理由を正直に伝えることで理解を得やすくなります。
- まずは買取の打診をする:「もし興味があれば、あなた(他の共有者)に買い取ってもらいたい」と伝えましょう。
- 第三者への売却の可能性も伝える:他の共有者が買い取らない場合は第三者への売却も検討していることを伝え、心の準備をしてもらいます。
- 期限を設ける:「○月○日までに返事がなければ、第三者への売却を進めます」と伝えることで、曖昧な状態が続くのを防ぎます。
例えば、「私は経済的な事情で持分を手放す必要があります。できれば親族である皆さんに買い取ってもらえると安心です。もし難しければ、1ヶ月後には専門業者への売却も検討したいと思います」といった伝え方が効果的です。
適正価格での譲渡を実現するための査定のポイント
共有持分の適正価格を知るためには、複数の査定を比較することが重要です。
査定時のポイント
- 複数の査定を取る:少なくとも3社以上から査定を取り、相場を把握しましょう。
- 共有持分専門の業者に依頼する:一般の不動産会社では共有持分の適正評価が難しい場合があります。
- 現地調査を依頼する:書類上の査定だけでなく、実際に物件を見て査定してもらうことで正確な評価が得られます。
- 査定の根拠を確認する:なぜその価格になるのか、根拠を説明してもらいましょう。
- 買取と仲介の両方の査定を取る:買取は早く売却できる反面、価格は低くなる傾向があります。両方の査定を比較することで、自分の優先順位(金額か速さか)に合った選択ができます。
例えば、一般的な不動産の相場が1,000万円で、あなたの持分が3分の1(約333万円相当)だとしても、共有持分という性質上、実際の査定額は150万円~250万円程度になることも珍しくありません。
信頼できる専門家(不動産会社・弁護士)の選び方
共有持分の譲渡は専門的な知識が必要なため、信頼できる専門家のサポートが重要です。
不動産会社選びのポイント
- 共有持分の取扱実績がある:一般の不動産会社よりも、共有持分専門の会社の方が知識と経験が豊富です。
- 宅地建物取引業の免許番号を確認する:免許番号が「大臣〇号」や「都道府県知事〇号」の形式になっているか確認しましょう。
- 会社の実在性を確認する:住所や電話番号が明記されているか、実際に事務所があるかなどを確認します。
- 強引な営業をしていない:「すぐに契約しないと値段が下がる」などと急かす業者は避けましょう。
- 口コミや評判を調べる:インターネットでの評判や、可能であれば過去の取引者からの情報を得ることも大切です。
弁護士選びのポイント
- 不動産・相続の専門家である:弁護士でも得意分野は異なるため、不動産や相続を専門とする弁護士を選びましょう。
- 共有持分のトラブル解決実績がある:過去に共有持分関連の案件を扱った経験があるか確認します。
- 費用体系が明確である:着手金や成功報酬など、費用の仕組みを明確に説明してくれる弁護士を選びましょう。
- 相談しやすい雰囲気がある:専門知識だけでなく、気軽に相談できる人柄も重要です。
例えば、弁護士への相談料は30分5,000円~1万円程度、着手金は20万円~50万円程度が相場ですが、案件の複雑さによって変動します。
共有持分譲渡の契約書作成時の注意点
共有持分譲渡の契約書には、一般的な不動産売買契約書とは異なる特有の注意点があります。
契約書に含めるべき重要項目
- 共有持分の明確な特定:登記簿上の表示や持分割合を正確に記載します。
- 売買代金の支払方法と時期:一括払いか分割払いか、支払日はいつかを明記します。
- 引渡条件:実際の不動産の使用状況や、引渡時の条件を明記します。
- 登記費用の負担者:通常は買主負担ですが、明確に記載しておきます。
- 特約条項:共有者間の取り決めや、将来的な共有物分割請求に関する制限などを記載できます。
- 瑕疵担保責任の範囲:売主がどこまで責任を負うかを明確にします。
特に重要なのは「特約条項」です。例えば、「買主は5年間は共有物分割請求をしない」「買主は他の共有者に持分買取を強要しない」などの条項を入れておくことで、将来のトラブルを防止できる可能性があります。
共有者が勝手に持分を売却した場合の対処法

既に他の共有者が勝手に持分を売却してしまった場合は、どのように対応すべきでしょうか。突然知らない第三者と共有関係になってしまうのは不安かもしれませんが、冷静に対処することが重要です。ここでは具体的な対処法を見ていきましょう。
売却された共有持分を買い戻す方法
他の共有者が持分を第三者に売却してしまった場合、その持分を買い戻すことも一つの選択肢です。
買い戻しの進め方
- 新しい共有者への連絡:登記情報から新しい共有者の連絡先を調べ、買取の意向を伝えます。
- 価格交渉:相場より高額になることが多いですが、交渉の余地はあります。
- 契約と登記:合意に達したら、売買契約を締結し、所有権移転登記を行います。
買い戻しに必要な費用は、新しい共有者が購入した金額よりも高くなることが一般的です。例えば、元の共有者が100万円で売却した持分を買い戻す場合、150万円~200万円程度の費用がかかることも珍しくありません。
新しい共有者との関係構築のポイント
買い戻しが難しい場合は、新しい共有者と良好な関係を構築することが重要です。
関係構築のポイント
- まずは対話の機会を持つ:敵対関係になる前に、直接会って話し合いの場を設けましょう。
- 共有不動産の利用状況を説明する:現在どのように利用されているか、どのような管理がされているかを伝えます。
- 互いの意向を確認する:新しい共有者が何を目的に持分を取得したのかを確認します。
- 今後の方針について合意を形成する:管理方法や将来的な売却の可能性について話し合います。
- 必要に応じて使用貸借契約を結ぶ:一方が不動産を使用している場合、使用条件を明確にした契約を結ぶことでトラブルを防止できます。
例えば、「私たち家族がこの家に住んでいることをご理解いただき、当面は現状維持でお願いしたいです。将来的には買い取りも検討しますので、それまでお互いに良好な関係を保ちましょう」といった提案ができるとよいでしょう。
共有物分割請求への対応策
新しい共有者から共有物分割請求が提起された場合の対応策も知っておく必要があります。
共有物分割請求への対応
- まずは話し合いでの解決を模索する:裁判に発展する前に、互いに納得できる解決策を探ります。
- 弁護士に相談する:請求を受けた段階で、早急に弁護士に相談しましょう。
- 分割方法の提案を検討する:現物分割が可能か、代償分割(金銭での補償)が可能かなど、自分にとって有利な分割方法を検討します。
- 裁判所での調停に応じる:訴訟前の調停で解決できる可能性もあります。
- 必要なら対抗手段を講じる:例えば、自分も他の持分を買い集めて発言力を強めるなどの対抗策も考えられます。
共有物分割請求訴訟では、裁判所は原則として「共有関係の解消」を認める傾向にあります。そのため、完全に拒否するのではなく、どのような形で分割するかに焦点を当てた対応が重要です。
法的措置を取る場合の流れ
状況によっては法的措置を取ることも検討する必要があります。
法的措置の流れ
- 弁護士への相談:まずは弁護士に現状を説明し、取り得る法的措置について相談します。
- 証拠の収集:トラブルの内容を裏付ける証拠(会話の記録、メールのやり取り、契約書など)を集めます。
- 内容証明郵便の送付:まずは内容証明郵便で相手に対して是正を求めることが一般的です。郵便局で手続きでき、料金は約500円+郵便料金です。
- 調停の申立て:裁判前の手続きとして、裁判所での調停を申し立てることができます。
- 訴訟の提起:調停で解決しない場合は、訴訟に移行します。
法的措置には時間とコストがかかります。調停の申立て手数料は数千円ですが、訴訟になると訴額に応じた手数料(数万円〜数十万円)に加え、弁護士費用(着手金20万円〜、成功報酬20万円〜)がかかります。できるだけ早い段階での解決を目指しましょう。
共有持分の譲渡にかかる税金と費用

共有持分の譲渡には様々な税金や費用がかかります。事前に把握して準備しておきましょう。
譲渡所得税の計算方法(長期・短期)
共有持分を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。計算方法は以下の通りです:
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
取得費:不動産を取得した際の費用(購入金額や相続時の評価額など) 譲渡費用:売却に伴う仲介手数料、印紙税、測量費用など
取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」の制度も利用できます。
計算した譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率がかかります:
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5% = 約20.315%
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税30% + 復興特別所得税0.63% + 住民税9% = 約39.63%
例えば、10年前に相続した共有持分(取得費200万円)を500万円で売却し、譲渡費用が30万円かかった場合: 譲渡所得 = 500万円 – (200万円 + 30万円) = 270万円 税額 = 270万円 × 20.315% = 約54.8万円
なお、確定申告は譲渡した年の翌年2月16日〜3月15日の間に行う必要があります。申告を忘れると、追徴課税などのペナルティが発生する可能性がありますので注意しましょう。
贈与の場合の贈与税
共有持分を無償で譲渡(贈与)する場合は、受け取る側に贈与税が課税されます。基礎控除額(年間110万円)を超える部分に対して課税されます。
贈与税の税率は、受け取る金額によって段階的に上がります(一般的な贈与の場合):
- 200万円以下:10%
- 400万円以下:15%
- 600万円以下:20%
- 1,000万円以下:30%
- 1,500万円以下:40%
- 3,000万円以下:45%
- 3,000万円超:50%
例えば、300万円相当の共有持分を贈与された場合: 課税価格 = 300万円 – 110万円(基礎控除) = 190万円 税額 = 190万円 × 10% = 19万円
なお、配偶者や直系血族(親子など)間の贈与の場合、特例措置が適用できるケースもあります。
登記費用や印紙税などの諸費用
共有持分の譲渡に伴うその他の費用も把握しておきましょう。
登記費用
- 登録免許税:固定資産税評価額 × 持分割合 × 2%(土地・建物の所有権移転登記の場合)
- 司法書士報酬:一般的に3〜10万円程度(案件の複雑さによる)
印紙税 売買契約書に貼付する収入印紙の費用です。売買金額によって変わります:
- 10万円超50万円以下:500円
- 50万円超100万円以下:1,000円
- 100万円超500万円以下:2,000円
- 500万円超1,000万円以下:1万円
その他の費用
- 仲介手数料(不動産会社を通じて売却する場合):(売買価格 × 3% + 6万円)× 消費税
- 測量費用(境界確定が必要な場合):10〜30万円程度
- 不動産鑑定費用(正確な評価が必要な場合):10〜30万円程度
税金対策と控除の活用方法
共有持分の譲渡に関わる税金を少しでも抑えるための対策を紹介します。
3,000万円特別控除の活用
居住用財産を譲渡した場合、最大3,000万円までの特別控除が適用できます。共有持分の譲渡でも、以下の条件を満たせば適用可能です:
- 自分が住んでいた(または親族が住んでいた)不動産であること
- 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること
- 過去に同じ特例を使用していないこと(原則として譲渡した年とその前2年、後3年の間)
長期譲渡所得として税率を下げる
短期譲渡所得(税率約40%)と長期譲渡所得(税率約20%)では税率が大きく異なります。可能であれば、所有期間が5年を超えてから売却することで税負担を軽減できます。
小規模宅地等の特例の検討
相続で取得した不動産の共有持分を譲渡する前に、「小規模宅地等の特例」の適用可能性を検討しましょう。この特例を使うと、相続税評価額が最大80%減額されます。ただし、適用には厳しい条件があるため、専門家に相談することをおすすめします。
配偶者への贈与特例の活用
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与を行う場合、最大2,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。共有不動産のうち自分の持分を配偶者に贈与する場合にも活用できます。
例えば、夫婦で共有しているマンション(全体の価値4,000万円)で、夫の持分(2,000万円相当)を妻に贈与する場合、贈与税がかからずに単独所有にすることが可能です。
共有持分譲渡の成功事例
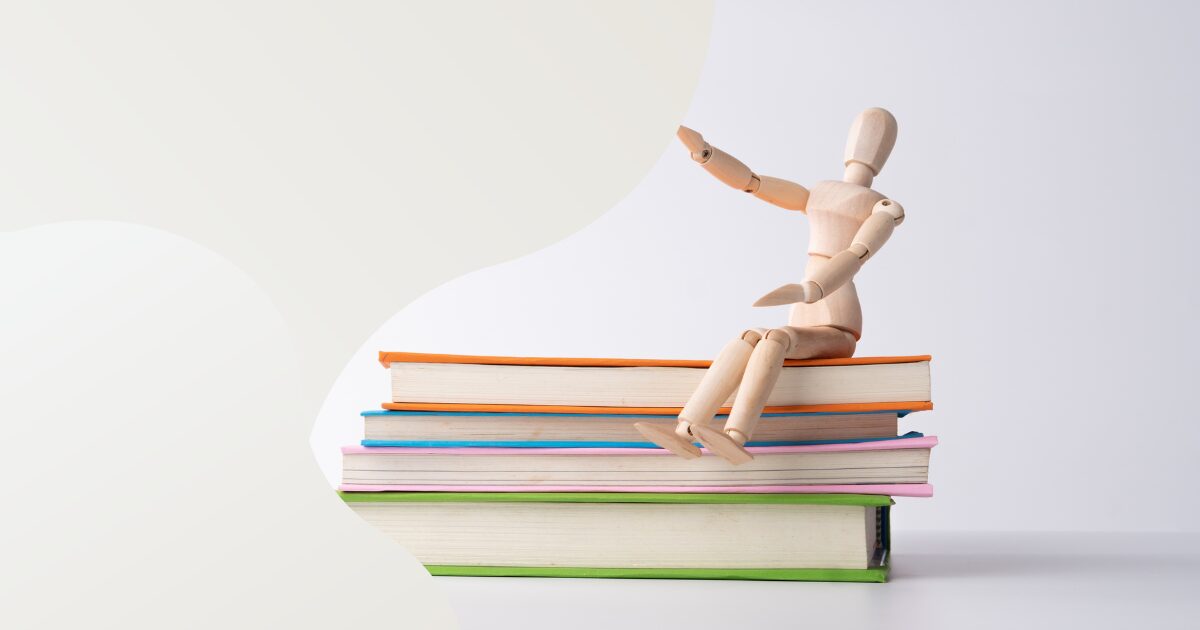
共有持分の譲渡を成功させた事例を紹介します。実際の成功パターンを知ることで、自分の状況に合った解決策が見つかるかもしれません。
成功事例1:他の共有者との円満な話し合いによる解決
ケース:Fさん(60代女性)は、亡くなった父親から兄弟3人で相続した実家の土地(3分の1ずつ所有)の自分の持分を売却したいと考えていました。遠方に住んでおり、管理も難しく、また老後の資金にしたいという事情がありました。
解決策:Fさんは兄弟に持分売却の意向を伝え、3人で話し合いの場を設けました。弟は「実家の跡地は残しておきたい」という思いが強く、Fさんの持分を買い取る意向を示しました。不動産鑑定士に土地の評価を依頼し、市場価格の約70%(Fさんの持分相当額約800万円)で弟に売却することで合意。弁護士に契約書の作成を依頼し、円満に譲渡が完了しました。
成功のポイント:
- 早い段階で他の共有者に意向を伝えた
- 第三者(不動産鑑定士)による客観的な評価を取り入れた
- 契約内容を弁護士に確認してもらい、将来のトラブルを防止した
成功事例2:専門業者を活用した高額売却
ケース:Gさん(40代男性)は離婚した元妻と共同で購入したマンション(2分の1ずつ所有)の持分を売却したいと考えていました。元妻は「自分は住み続けたいので買取る余裕はない」と主張し、一般の不動産会社では「共有持分は扱っていない」と断られていました。
解決策:インターネットで調べて共有持分専門の不動産仲介会社に相談したところ、「投資用として共有持分を探している顧客がいる」との情報を得ました。仲介会社の提案で、元妻との間で「5年間は共有物分割請求をしない」「元妻が住み続ける限り賃料は請求しない」などの条件を取り決めた上で、投資家に市場価格の約65%(Gさんの持分相当額約1,200万円)で売却することができました。
成功のポイント:
- 共有持分専門の業者に相談した
- 元妻の意向を尊重した条件を設定した
- 買主と元妻のトラブルを防ぐための取り決めを行った
成功事例3:共有物分割による単独所有化
ケース:Hさん夫妻は、Hさんの兄と共有していた実家の土地(Hさん夫妻2分の1、兄2分の1で共有)を巡って意見が対立していました。Hさん夫妻は土地に新居を建てたいと考えていましたが、兄は売却して現金化したいと主張。話し合いは平行線をたどっていました。
解決策:弁護士に相談したところ、「現物分割」の可能性を提案されました。土地の形状が長方形で分割しやすかったため、測量士に依頼して2つの区画に分筆。Hさん夫妻と兄がそれぞれ単独所有する形で共有関係を解消しました。結果的に、Hさん夫妻は自分たちの区画に家を建て、兄は自分の区画を売却して現金化するという、双方の希望を叶えることができました。
成功のポイント:
- 専門家(弁護士・測量士)の助言を取り入れた
- 不動産の特性(分割しやすい形状)を活かした解決策を見つけた
- 双方の希望を尊重した解決策を模索した
成功のためのポイントとコツ
上記の事例から、共有持分譲渡を成功させるためのポイントとコツをまとめると:
- 早めの相談と丁寧な説明:他の共有者に早めに相談し、譲渡の理由を丁寧に説明することで理解を得やすくなります。
- 専門家の活用:弁護士、不動産鑑定士、測量士など、専門家の知識を活用することで適切な解決策が見つかりやすくなります。
- 柔軟な発想:「売却」だけでなく、「分割」「交換」など様々な選択肢を検討することが重要です。
- 相手の立場を尊重:共有者や買主の立場や希望を尊重し、Win-Winの関係を構築することがスムーズな解決につながります。
- 将来のトラブル防止:契約書に特約条項を入れるなど、将来のトラブルを防止する工夫が大切です。
まとめ:共有持分譲渡で失敗しないためのチェックリスト

ここまで解説してきた内容をもとに、共有持分譲渡で失敗しないためのチェックリストをまとめました。譲渡を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
事前確認事項のチェックリスト
- □ 登記簿謄本で正確な共有持分割合を確認した
- □ 不動産の市場価値と共有持分の評価額を把握した
- □ 他の共有者に売却の意向を伝えた
- □ 他の共有者からの買取意向を確認した
- □ 共有不動産の管理状況や使用状況を把握した
- □ 譲渡にかかる税金や費用の概算を計算した
- □ 必要な書類(権利証、印鑑証明書など)を揃えた
- □ 住宅ローンの残債がある場合はその扱いを確認した
譲渡手続きのステップ
- 共有者間での話し合い:譲渡の意向を伝え、他の共有者による買取の可能性を探る
- 専門家への相談:不動産会社や弁護士に相談し、最適な譲渡方法を検討する
- 査定と価格設定:複数の査定を取り、適正な価格を設定する
- 買主の選定:他の共有者か第三者(一般購入者・専門業者)かを決定する
- 契約条件の交渉:価格だけでなく、支払方法や特約事項なども含めて交渉する
- 契約書の作成と締結:専門家に依頼して適切な内容の契約書を作成する
- 決済と所有権移転登記:代金の受け渡しと同時に登記手続きを行う
- 確定申告:必要に応じて譲渡所得の確定申告を行う(翌年2月16日〜3月15日)
トラブル防止のための注意点
- ✓ 口頭だけの約束はせず、必ず書面にする
- ✓ 共有持分専門の業者か確認する(宅建業免許の有無もチェック)
- ✓ 契約書には将来のトラブル防止のための特約条項を入れる
- ✓ 売買代金は必ず記録に残る方法(銀行振込など)で受け取る
- ✓ 登記手続きは司法書士に依頼し、確実に行う
- ✓ 譲渡後も固定資産税の支払い状況などを確認する
専門家に相談すべきタイミング
- 他の共有者との話し合いが難航している場合
- 複雑な権利関係がある場合(抵当権が設定されているなど)
- 共有物分割を検討している場合
- 税金対策を考えたい場合
- 高額な取引になる場合
- 共有者が遠方にいる、または連絡が取れない場合
専門家への相談費用はかかりますが、後々のトラブルを防ぐための「保険」と考えるとよいでしょう。初回相談は無料の専門家も多いので、積極的に活用してください。
よくある質問(Q&A)

最後に、共有持分の譲渡に関してよくある質問とその回答をまとめました。共有持分に関する知識を深め、トラブルを未然に防ぐための参考にしてください。
Q1:共有持分は他の共有者の同意なく譲渡できますか?
A: 法律上は、自分の共有持分だけであれば他の共有者の同意なく譲渡することが可能です。これは民法第206条の「所有者は自由に所有物の処分をする権利を有する」という規定に基づいています。
ただし、トラブル防止の観点からは、事前に他の共有者に相談し、理解を得ることが望ましいでしょう。特に、家族間での共有の場合は、相談なしの譲渡が人間関係悪化につながる可能性があります。
Q2:共有持分の適正価格はどう決まりますか?
A: 共有持分の適正価格は主に以下の要素で決まります:
- 不動産全体の市場価値
- 持分割合
- 共有状態によるディスカウント
一般的には「不動産全体の市場価値 × 持分割合 × ディスカウント率」で計算されます。ディスカウント率は状況によって異なりますが、通常は30%〜70%程度です。
例えば、市場価値1,000万円の不動産の3分の1の持分であれば、333万円×(1-0.5)=約166万円が目安となりますが、状況によって大きく変動します。複数の専門業者の査定を比較することをおすすめします。
Q3:共有物分割請求とは何ですか?
A: 共有物分割請求とは、共有状態を解消するために共有者が裁判所に申し立てる手続きです。民法第256条に基づき、共有者は原則としていつでも共有物の分割を請求することができます。
分割方法には主に以下の3つがあります:
- 現物分割:不動産を物理的に分割して各自が単独所有する
- 換価分割:不動産を売却して代金を分配する
- 代償分割:一部の共有者が不動産を取得し、他の共有者に金銭で補償する
裁判所は事案に応じて最も適切な分割方法を選択します。実務上は、土地の形状や利用状況によって判断されることが多く、分割困難な場合は換価分割になるケースが多いです。
共有物分割請求訴訟の流れは以下の通りです:
- 裁判所に訴状を提出(訴訟費用は訴額に応じて数万円〜数十万円)
- 相手方(他の共有者)への訴状送達
- 第1回口頭弁論(裁判所での審理)
- 調停手続きへの移行(多くの場合、訴訟前に調停が行われます)
- 調停不成立の場合、訴訟再開
- 判決
なお、共有者間の契約で一定期間(最長5年)は分割請求できないという特約を結ぶことも可能です。この「共有物分割禁止特約」は、譲渡契約時に盛り込んでおくとトラブル防止に効果的です。
Q4:共有持分を買取業者に売却するメリット・デメリットは?
A: 共有持分を買取業者に売却する際のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
- 迅速に売却できる(通常1〜2週間程度)
- 確実に買い手が見つかる
- 面倒な交渉が少ない
- 現状のままで買い取ってもらえる
デメリット
- 相場より安い価格になることが多い(市場価値の30〜60%程度)
- 悪質な業者だと他の共有者とのトラブルになる可能性がある
- 買取後に高値で買戻しを迫られるケースもある
- 特約条項がないと、買取業者が共有物分割請求をしてくる可能性がある
買取業者を選ぶ際は、実績や評判をよく調査し、契約内容をしっかり確認することが重要です。
:将来的に買い戻す可能性を考慮して、資金計画を立てておく
これらの対策を講じることで、譲渡後のトラブルリスクを大幅に軽減できます。
以上が、共有持分の譲渡に関する基本知識とトラブル対策です。共有持分は複雑な権利関係を含むため、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることをおすすめします。
今すぐ実行できる3つのアクション
共有持分の譲渡を検討されている方に、今すぐ実行できる3つのアクションをご提案します:
- 登記簿謄本を取得して正確な権利関係を確認する 法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、正確な持分割合や抵当権の有無を確認しましょう。オンラインでも取得可能で、費用は1通600円程度です。これにより、現在の正確な権利関係が把握でき、今後の対策の土台となります。特に相続により共有状態になった場合は、相続登記が済んでいるかどうかも確認してください。2024年4月からは相続登記が義務化されており、未登記の場合は最優先で対応する必要があります。
- 共有持分専門の不動産会社に無料査定を依頼する 共有持分専門の不動産会社に無料査定を依頼し、持分の市場価値を把握しましょう。複数の会社に依頼することで、より正確な相場観がつかめます。査定結果をもとに、譲渡の是非や方法を検討する材料にしてください。査定依頼時には、不動産の現況写真や固定資産税評価証明書などを準備しておくと、より正確な査定結果が得られます。
- 他の共有者と話し合いの場を設ける 他の共有者に連絡を取り、共有不動産の今後について話し合いの場を設けましょう。お互いの意向を確認し、持分の買取可能性や共有物分割の可能性を探ります。話し合いは感情的にならず、お互いの立場を尊重して進めることが大切です。可能であれば、話し合いの内容を議事録として残しておくと、後々の誤解を防ぐことができます。また、メールやLINEよりも直接会って話すことで、より円滑なコミュニケーションが期待できます。
これらのアクションを実行することで、共有持分譲渡の第一歩を踏み出すことができます。複雑に思える共有持分の問題も、適切な知識と対策で解決への道が開けるはずです。早めの行動が、将来のトラブルを防ぐ鍵となります。

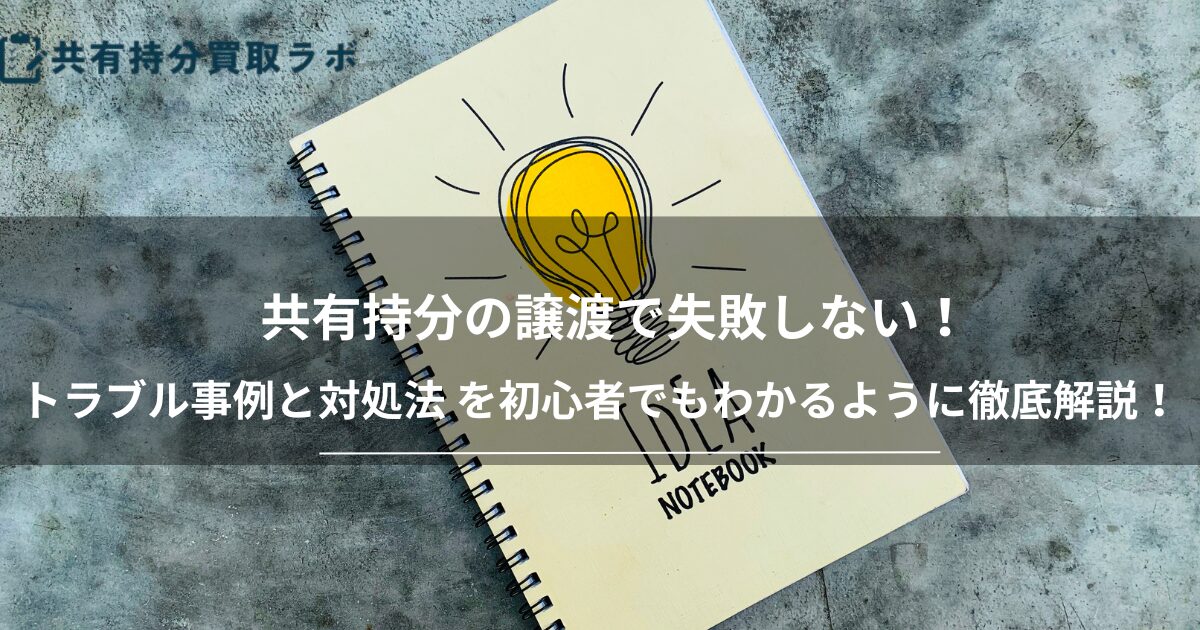

コメント