「準共有持分」という言葉を初めて耳にした方は少なくないでしょう。不動産の相続や権利関係について調べていると、突然この言葉に出会い、戸惑った経験はありませんか?
不動産に関する権利関係は複雑で、特に「共有」と「準共有」の違いは一般の方にとってわかりにくいものです。しかし、これらの違いを理解しておくことは、将来的な権利トラブルを防ぐために非常に重要です。
この記事では、準共有持分とは何か、共有持分との違い、そして実際に準共有持分を持つことになった際のトラブル回避策までを、専門用語をなるべく使わずに解説していきます。借地権などの権利を複数人で持つ場合や、相続で準共有状態になった場合に、どのように対応すればよいのかがわかるようになります。
準共有持分について正しい知識を身につけて、将来起こりうるトラブルに備えましょう。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
準共有持分の基本知識

準共有持分とは何か?
準共有持分とは、土地や建物そのものではなく、借地権や地上権などの「所有権以外の財産権」を複数の人で共同して持っている状態のことを指します。
たとえば、親から借地権(他人の土地を借りて使う権利)を子どもたち数人で相続した場合、その借地権は「準共有」の状態になります。それぞれの子どもは、その借地権の「準共有持分」を持つことになるのです。
共有は目に見える「モノ(土地や建物など)」を複数人で持つ状態ですが、準共有は目に見えない「権利」を複数人で持つ状態だと考えるとわかりやすいでしょう。
準共有が発生する一般的なケース
準共有が発生するケースは意外と身近にあります。主なケースとしては以下のようなものがあります。
- 借地権を複数人で相続した場合
- 地上権(他人の土地の上に建物を建てる権利)を共同で購入した場合
- 特許権や著作権などの知的財産権を複数人で持っている場合
- マンションの敷地利用権を区分所有者全員で持っている場合
特に多いのが相続によるケースです。親が借地権を持っていた場合、その相続人全員がその借地権の準共有者となります。
法律上の位置づけ
準共有については、民法第264条に「所有権以外の財産権が数人の者に属するときは、この節(共有に関する規定)の規定を準用する」と定められています。つまり、準共有には基本的に共有と同じルールが適用されるということです。
ただし、準共有の対象となる権利の性質によって、細かいルールが異なることもありますので注意が必要です。例えば、特許権の準共有の場合は特許法の規定が優先されます。
共有持分と準共有持分の違い

共有持分の基本的な説明
共有持分とは、1つの不動産(土地や建物)を複数の人が共同で所有している状態で、各自が持つ所有権の割合のことです。
例えば、兄弟2人で実家の家を相続し、それぞれが2分の1ずつの持分を持っている場合、その家は2人の「共有」状態となり、各自は「共有持分」を持つことになります。
共有関係にある場合、共有者は自分の持分に応じて不動産全体を使用する権利を持ちますが、不動産全体を処分(売却や賃貸など)する場合は、全員の同意が必要になります。
準共有持分との決定的な違い
共有持分と準共有持分の最も大きな違いは、「対象となるもの」です。
- 共有持分:土地や建物などの「物」に対する所有権
- 準共有持分:借地権や地上権などの「権利」に対する持分
つまり、共有は「モノ」を複数人で持つ状態、準共有は「権利」を複数人で持つ状態というわけです。
もう一つの違いは適用される法律や制限です。共有には民法の共有に関する規定が直接適用されますが、準共有には同じ規定が「準用」されます。これは、権利の性質に応じて適用方法が変わることがあるためです。
図解で理解する共有と準共有の考え方
【共有の場合】 土地や建物(物)→ 複数人で所有 → 各自が共有持分を持つ
【準共有の場合】 借地権や特許権(権利)→ 複数人で保有 → 各自が準共有持分を持つ
共有は物理的に存在するものに対する所有権を分け合いますが、準共有は目に見えない権利を分け合うという点を覚えておくとよいでしょう。
準共有持分が発生する具体的なケース

借地上の建物を相続した場合
最も一般的なケースの1つが、借地上に建てられた建物の相続です。
例えば、Aさんが借地上に自宅を建てて住んでいたとします。Aさんが亡くなり、子どものBさんとCさんが相続することになった場合:
- 建物(自宅)→ BさんとCさんの共有(共有持分)
- 借地権 → BさんとCさんの準共有(準共有持分)
このように、建物は「共有」、借地権は「準共有」となる点が特徴です。
複数人で借地権を購入した場合
借地権を複数人で購入するケースもあります。
例えば、兄弟でアパートを経営するために、借地権を共同で購入した場合、その借地権は兄弟の「準共有」となります。兄弟それぞれが、出資額に応じた「準共有持分」を持つことになるのです。
特許権や著作権などの知的財産権の場合
特許権や著作権など、知的財産権の場合も準共有関係が発生します。
たとえば、複数人で共同開発した技術に対して特許を取得した場合、その特許権は開発者たちの準共有となります。この場合、持分の割合は貢献度などによって決められることが多いです。
準共有持分の権利と制限

準共有者が持つ基本的な権利
準共有者には、以下のような基本的な権利があります。
- 準共有物(権利)を持分に応じて使用・収益する権利
- 自分の持分を自由に処分(売却・贈与など)する権利
- いつでも準共有関係の解消を請求できる権利(分割請求権)
例えば、借地権を2人で準共有している場合、それぞれが自分の持分(例:2分の1)に応じて、その借地を使用したり、そこから得られる収益を受け取ったりする権利を持ちます。
準共有物の使用・収益・処分に関するルール
準共有状態にある権利の使用や管理については、以下のようなルールがあります。
- 通常の管理行為(軽微な修繕など)→ 持分の過半数の同意
- 重要な変更(大規模な改修など)→ 全員の同意
- 準共有物全体の処分(売却など)→ 全員の同意
- 各自の持分の処分(売却など)→ 単独で可能
例えば、2人で借地権を準共有している場合、その借地に建物を建てるような重要な変更を行うには、2人とも同意する必要があります。
他の準共有者の同意が必要なケース
他の準共有者の同意が必要なケースとして、主に以下のようなものがあります。
- 準共有物全体を売却する場合
- 準共有物に大きな変更を加える場合
- 準共有物を担保に入れる場合
- 準共有物の用途を変更する場合
特に注意したいのは、単独で決められることと全員の同意が必要なことの境界線です。例えば、自分の持分だけを売却するのは単独で決められますが、準共有物全体を売却するには全員の同意が必要です。
準共有持分で起こりやすいトラブル事例

相続時のトラブル
相続時には以下のようなトラブルが起きやすくなります。
「親から借地権を相続したが、相続人の一人が遠方に住んでいて連絡が取れない。そのため、借地上の建物の建て替えや借地契約の更新ができない」
このようなケースでは、相続人全員の同意が得られないことで、権利の円滑な行使ができなくなるリスクがあります。相続が発生した時点で、準共有者全員で話し合い、将来的な対応を決めておくことが大切です。
権利の売却・譲渡に関するトラブル
準共有持分の売却や譲渡に関しても、トラブルが生じることがあります。
「親族間で準共有している借地権について、一部の準共有者が自分の持分を第三者に売却。その結果、知らない人と準共有関係になってしまい、意思決定が難しくなった」
自分の持分は自由に処分できるという権利がある一方で、新たな準共有者との関係構築が難しくなるというリスクも存在します。そのため、持分を売却する際には、まず他の準共有者に打診するなどの配慮が必要です。
管理や費用負担をめぐるトラブル
準共有物の管理費用などをめぐるトラブルも多く発生します。
「借地権を準共有している相続人の中で、一部の人だけが借地料を支払い続けているが、他の相続人は費用負担を拒否している」
このようなケースでは、費用を負担している人だけが不公平感を抱き、準共有者間の関係が悪化するリスクがあります。準共有関係になった時点で、費用負担のルールを明確にしておくことが大切です。
トラブル回避のための実践的アドバイス

事前の取り決めの重要性
準共有関係になった場合、まず最初にすべきことは、準共有者全員での話し合いです。
特に以下の点について、事前に取り決めをしておくことが重要です。
- 準共有物(権利)の使用方法
- 管理費用の負担割合
- 意思決定の方法
- 将来的な準共有関係の解消方法
例えば、「借地料は持分に応じて負担する」「重要な決定は全員で協議する」「将来的には誰かが買い取る」などの基本的なルールを決めておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
契約書・覚書の作成ポイント
話し合いの結果は、必ず書面に残しておきましょう。口頭での約束だけでは、後から「そんな約束はしていない」というトラブルになりかねません。
契約書や覚書には、以下の内容を盛り込むことをおすすめします。
- 準共有者全員の氏名・連絡先
- 準共有物の詳細(権利の内容、登記情報など)
- 各自の持分割合
- 使用・管理に関するルール
- 費用負担の方法
- 意思決定の方法
- 紛争解決の方法
- 将来的な準共有関係の解消方法
特に「将来的な準共有関係の解消方法」については具体的に記載することが重要です。例えば、「10年後に〇〇さんが他の準共有者から持分を買い取る」「将来売却する場合は市場価格の8割で他の準共有者に優先的に売却する」など、具体的な条件を決めておくとよいでしょう。
専門家への相談タイミング
準共有関係に関するトラブルを防ぐためには、適切なタイミングで専門家に相談することも重要です。以下のようなタイミングでの相談をおすすめします。
- 相続で準共有関係が発生したとき
- 準共有者間で話し合いがうまくいかないとき
- 準共有持分を売却・購入する検討をしているとき
- 準共有関係を解消したいとき
特に「司法書士」や「不動産に詳しい弁護士」への相談が効果的です。彼らは準共有に関する法律や実務に詳しく、適切なアドバイスを提供してくれます。
専門家への相談費用は1時間あたり5,000円~10,000円程度が一般的ですが、将来的なトラブルを防ぐための投資と考えれば十分に価値があるものです。
準共有持分の登記について

準共有持分の登記方法
準共有持分を登記する方法は、共有持分の登記とほぼ同じです。不動産登記簿の権利部に、権利の種類(借地権など)と準共有者の氏名、持分を記載します。
例えば、借地権を準共有する場合、以下のように登記されます。
[権利部(甲区)]
借地権
準共有者:山田太郎
持分:2分の1
準共有者:山田花子
持分:2分の1
登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、費用は登記の内容や物件によって異なりますが、5万円~10万円程度が目安です。
登記簿の見方と確認ポイント
不動産登記簿で準共有持分を確認する際のポイントは以下の通りです。
- 権利の種類(借地権、地上権など)
- 準共有者の氏名と住所
- 各自の持分割合
- 権利取得の原因(相続、売買など)
- 権利に関する制限(抵当権など)
特に、「持分割合」は重要な確認ポイントです。持分割合は分数(例:2分の1、3分の1)で表示され、この割合に応じて権利や義務が発生します。
登記費用と必要な書類
準共有持分の登記に必要な書類と費用は、登記の種類によって異なります。
【必要な書類の例】
- 登記申請書
- 権利証(登記識別情報)
- 準共有者全員の印鑑証明書
- 権利取得の証明書類(相続の場合は戸籍謄本など)
- 登録免許税の納付証明書
【費用の目安】
- 登録免許税:不動産の価値や登記の種類によって異なる(数万円~数十万円)
- 司法書士報酬:5万円~10万円程度
登記手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼することをおすすめします。
準共有持分の売却・処分方法

準共有持分を売却する際の手順
準共有持分を売却する際の基本的な手順は以下の通りです。
- 売却価格の査定
- 他の準共有者への優先的な打診
- 買主との交渉
- 売買契約の締結
- 所有権移転登記
特に注意したいのは、準共有持分の市場価値は、通常の不動産と比べて低くなる傾向があることです。一般的に、準共有持分の売却価格は、物件全体の価格×持分割合の70%~80%程度になることが多いです。
他の準共有者への優先的な購入機会の提供
自分の準共有持分を売却する場合、法律上の義務ではありませんが、まず他の準共有者に売却の意向を伝え、購入の機会を提供することが望ましいです。
これには以下のようなメリットがあります。
- 他の準共有者が買い取れば、準共有関係がシンプルになる
- 第三者に売却するよりも手続きが簡単
- トラブルを避けることができる
例えば、「市場価格より1割引で他の準共有者に先に打診する」などのルールを事前に決めておくと、スムーズな取引が可能になります。
第三者へ売却する場合の注意点
他の準共有者が購入を希望しない場合は、第三者への売却を検討することになります。その際の注意点は以下の通りです。
- 買主に準共有の制限事項を正確に説明する
- 他の準共有者の情報(氏名・連絡先など)を提供する
- 将来的な準共有関係の解消可能性について説明する
- 専門の不動産業者や弁護士に相談する
準共有持分は特殊な商品であるため、購入希望者が限られます。そのため、「共有持分専門の買取業者」に相談するのも一つの方法です。市場価格よりも安くなる傾向がありますが、確実に売却できるというメリットがあります。
専門家からのアドバイス
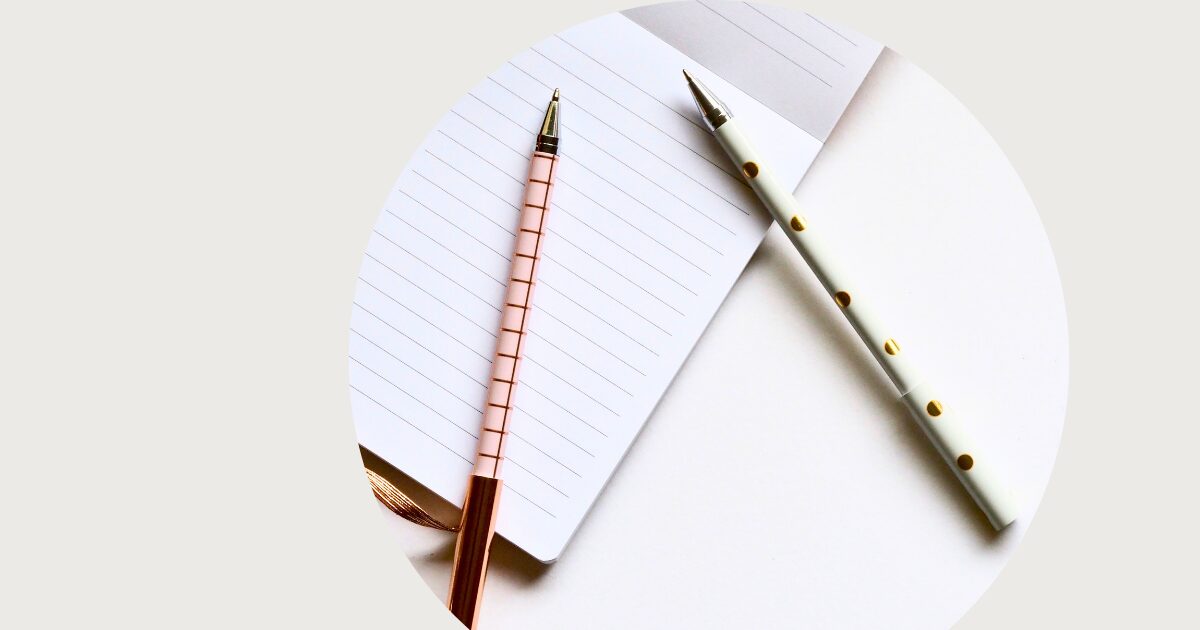
弁護士からの法的アドバイス
不動産問題に詳しい弁護士からは、以下のようなアドバイスがよく聞かれます。
「準共有関係は、将来的なトラブルのリスクが高いため、可能であれば早めに解消することをおすすめします。特に相続で発生した準共有関係は、感情的な要素も絡みやすいため注意が必要です。」
また、「準共有者間で合意形成ができない場合は、民法上の『共有物分割請求』を検討することもできます。ただし、裁判所を通じての解決となるため、時間とコストがかかることは覚悟しておく必要があります。」
共有物分割請求の裁判には通常1年~2年程度かかり、弁護士費用も30万円~100万円程度必要になることが一般的です。
不動産専門家からの実務的アドバイス
不動産取引の専門家からは、以下のような実務的なアドバイスがあります。
「準共有持分を売却する場合、一般的な不動産市場での売却は難しいことが多いです。そのため、他の準共有者や準共有持分専門の買取業者への売却を優先的に検討することをおすすめします。」
また、準共有関係にある借地権などは、将来的な更新や建て替えの際に全員の同意が必要になります。そのため、準共有者間の連絡体制や意思決定のルールを事前に決めておくことが重要です。
よくある質問と回答

- 準共有持分を相続放棄することはできますか?
はい、相続放棄することは可能です。ただし、相続放棄は相続財産全体に対して行うものであり、準共有持分だけを選択的に放棄することはできません。相続放棄は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
- 準共有者の一人が行方不明の場合、どうすればよいですか?
行方不明者の財産管理人を選任する手続きを家庭裁判所で行うことができます。財産管理人が選任されれば、その人が行方不明者に代わって意思決定を行うことができるようになります。手続きには3ヶ月~6ヶ月程度かかることが一般的です。
- 準共有持分の評価額はどのように算出されますか?
基本的には「物件全体の価値×持分割合」で計算されますが、準共有状態であることによる制約があるため、実際の市場価値はそれよりも20%~30%程度低くなることが多いです。正確な評価額は不動産鑑定士に依頼することで算出できます。
- 準共有持分の固定資産税はどのように支払いますか?
固定資産税は原則として各準共有者が持分に応じて負担します。ただし、税務署からは代表者に対して納税通知書が送られるため、準共有者間で支払い方法について事前に取り決めておくことが重要です。
本記事のポイント整理
この記事では、準共有持分について以下のポイントを解説しました。
- 準共有持分とは、借地権などの「所有権以外の財産権」を複数人で持つ状態のこと
- 共有持分との大きな違いは、対象が「物」か「権利」か
- 準共有関係では、使用・管理・処分に関するルールが法律で定められている
- 相続や権利の売却などでトラブルが起きやすい
- トラブル防止には、事前の取り決めと書面化が重要
- 準共有持分の売却は、通常の不動産よりも難しい面がある
準共有関係は複雑で、トラブルが起きやすい状態です。しかし、正しい知識と適切な対応によって、リスクを最小限に抑えることができます。
準共有持分に関わる際のチェックリスト
準共有持分に関わる際は、以下のチェックリストを参考にしてください。
- □ 準共有物(権利)の内容を正確に把握しているか
- □ 準共有者全員の氏名・連絡先を把握しているか
- □ 各自の持分割合を確認しているか
- □ 使用・管理のルールが決まっているか
- □ 費用負担の方法が明確になっているか
- □ 意思決定の方法が決まっているか
- □ 将来的な準共有関係の解消方法を検討しているか
- □ 必要な登記手続きを行っているか
- □ トラブル発生時の対応方法を話し合っているか
これらの項目をチェックし、準備不足の点があれば早めに対応することをおすすめします。
困ったときの相談先
準共有持分に関して困ったことがあれば、以下の専門家に相談することをおすすめします。
- 司法書士:登記手続きや法律上の権利関係について
- 弁護士:トラブル解決や法的対応について
- 不動産専門家:準共有持分の評価や売買について
- 税理士:相続税や譲渡所得税などの税金について
早めの相談が、大きなトラブルを防ぐカギとなります。多くの専門家は初回相談を無料または低額で提供していますので、気軽に相談してみることをおすすめします。
すぐに実行できる具体的なアクション3つ
準共有状態の確認と書面化
現在準共有関係にある場合は、権利の内容、準共有者、持分割合を確認し、書面にまとめましょう。費用負担や意思決定のルールも含めて、覚書として残しておくことで将来のトラブルを防げます。具体的には、準共有者全員の署名入りの覚書を作成し、各自が保管するようにしましょう。
準共有者との定期的な連絡体制の構築
年に1回程度、準共有者全員で状況確認の機会を設けましょう。連絡先の更新や今後の方針について話し合うことで、突然のトラブルを防ぐことができます。特にメールアドレスや電話番号のリストを作成し、定期的に更新することが大切です。オンラインストレージなどを活用して、共有すべき書類や情報を常に最新の状態に保っておくことも有効です。
専門家への相談と将来計画の策定
準共有関係の将来的な解消も視野に入れ、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。現在の状況を説明し、最適な解決策(持分の集約、権利の売却、共有物分割請求など)について具体的なアドバイスを受けることが重要です。特に相続から発生した準共有関係では、5年以内に何らかの方針を決めておくことが望ましいです。専門家への相談費用は初期投資と考え、将来的なトラブル防止のための保険と捉えましょう。
これらのアクションを実行することで、準共有持分に関するリスクを大幅に減らすことができます。正しい知識と適切な対応で、準共有関係を上手に管理していきましょう。

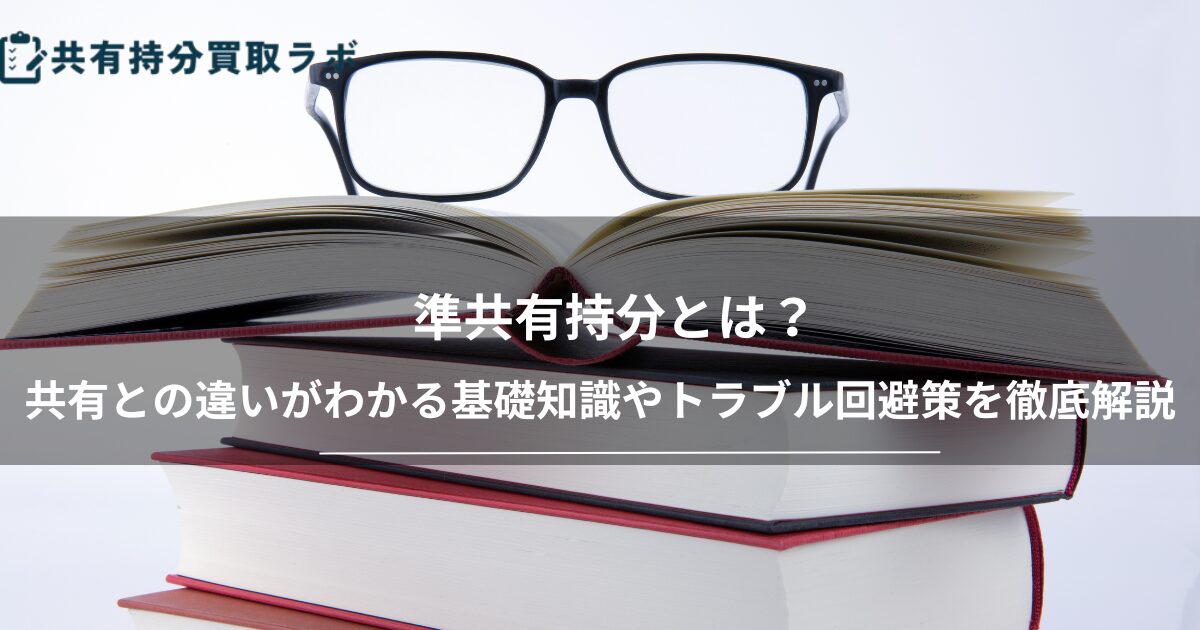

コメント