共有不動産のトラブルでお悩みではありませんか?親から相続した実家を兄弟で共有しているけれど、なかなか売却できない。共有者の一人が行方不明で連絡が取れず、不動産を有効活用できない。こういった問題を解決する手段として「共有物分割請求」があります。
共有物分割請求とは、共有状態にある不動産などの財産を分割して、共有関係を解消するための法的手続きです。しかし、この手続きを行うにあたって気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。「いくらかかるの?」「どうやって弁護士を選べばいいの?」といった疑問を持つ方は多いと思います。
この記事では、共有物分割請求にかかる弁護士費用の相場から、費用を抑える方法、賢い弁護士の選び方まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。この記事を読めば、自分の状況に最適な選択ができるようになり、余計な費用をかけずに共有状態を解消する道筋が見えてくるでしょう。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有物分割請求の基本知識

共有物分割請求ってどういう意味?
共有物分割請求とは、複数の人が共同で所有している財産(多くの場合は不動産)について、その共有状態を終わらせるために行う手続きです。簡単に言えば、「この共有状態をやめて、それぞれの権利をはっきりさせたい」と申し立てることです。
共有物分割請求はどんなときに必要になる?
共有物分割請求が必要になるケースはいくつかあります。よくあるのは、次のような状況です。
相続で共有状態になった不動産の活用方法で意見が分かれているとき。例えば、ある兄弟は実家を売却したいと考え、別の兄弟はそのまま住み続けたいと考えている場合です。
共有者の一人が行方不明で連絡が取れず、不動産の管理や処分ができないとき。共有不動産を売却するには全員の同意が必要なため、一人でも連絡が取れないと身動きが取れなくなります。
共有者同士で不動産の維持費用の負担について争いがあるとき。固定資産税や修繕費などの負担方法で意見が合わないケースです。
共有物分割請求の流れはどうなってる?
共有物分割請求の流れは大きく分けて3つのステップがあります。
- 協議(話し合い): まずは共有者同士で話し合いを行います。全員が合意すれば、最も簡単かつ費用も少なく解決できます。
- 調停: 話し合いがまとまらない場合は、裁判所の調停手続きに進みます。裁判官と調停委員が間に入って解決を図ります。
- 訴訟: 調停でも合意に至らなかった場合、最終的に共有物分割請求訴訟を提起します。裁判所が判決で共有状態の解消方法を決定します。
訴訟になると時間と費用がかかるため、できるだけ協議や調停の段階で解決することが理想的です。しかし、意見の対立が激しい場合や、共有者が多数いる場合は、訴訟に発展することも少なくありません。
共有物分割請求にかかる弁護士費用の相場

弁護士費用の基本構成を知ろう
共有物分割請求の弁護士費用は、大きく分けて「着手金」と「報酬金」の2種類で構成されています。
報酬金は、事件が解決した後に支払う成功報酬のようなものです。この金額は「依頼者が得た経済的利益」に応じて計算されることが多く、共有物分割請求の場合も同様です。
着手金の相場はどれくらい?
共有物分割請求における着手金の相場は、20〜30万円程度です。この金額は依頼する弁護士事務所によって異なりますが、あまりに安すぎる場合は経験が浅い可能性もあるため注意が必要です。
着手金の金額は、事案の複雑さや共有者の人数によっても変わります。例えば、共有者が多数いる場合や、相手方が激しく争う姿勢を見せている場合などは、着手金が高くなる傾向があります。
報酬金はどうやって決まるの?
報酬金の計算方法は主に2つのパターンがあります。
1つ目は「持分の時価の3分の1」を経済的利益として計算する方法です。例えば、時価6000万円の不動産を2人で平等に共有している場合、あなたの持分は3000万円。その3分の1である1000万円を経済的利益として、報酬金を算出します。
2つ目は「共有持分の時価の5〜10%」を報酬金とする方法です。例えば、あなたの持分が3000万円なら、報酬金は150〜300万円ということになります。
どちらの計算方法を採用するかは弁護士事務所によって異なるため、依頼前に必ず確認しましょう。
総額でいくらくらいかかるの?
共有物分割請求の弁護士費用の総額は、着手金と報酬金を合わせて50〜150万円程度が一般的な相場です。ただし、事案が複雑化したり、訴訟が長引いたりすると、更に費用がかさむ可能性があります。
また、弁護士費用以外にも、訴訟費用(印紙代・切手代)や不動産鑑定費用などがかかる場合があります。これらを含めると、総額で100〜200万円程度を見込んでおくと安心です。
共有物分割請求は決して安い手続きではありませんが、長期間にわたって共有状態が続くことによる経済的損失や精神的負担を考えると、適切な解決のために必要な投資とも言えます。
弁護士費用の計算方法を徹底解説

共有持分の時価からどう算出するの?
弁護士費用を計算する際の基本となるのが「共有持分の時価」です。これは簡単に言えば、あなたが持っている持分の市場価値のことです。
例えば、時価1億円の不動産を4人で平等に共有している場合、あなたの持分の時価は2500万円となります。この金額をもとに弁護士費用が計算されます。
共有持分の時価を正確に把握するためには、不動産鑑定士による鑑定や、不動産会社による査定を受けるのが一般的です。ただし、弁護士費用の見積もりを出す段階では、固定資産税評価額などを参考に概算で計算することもあります。
「持分の時価の3分の1」を経済的利益として計算するケース
多くの弁護士事務所では、「持分の時価の3分の1」を経済的利益として弁護士費用を計算します。これは、旧弁護士報酬規程に基づく伝統的な計算方法です。
計算例を見てみましょう。時価9000万円の不動産を3人で平等に共有している場合:
- あなたの持分の時価は9000万円 ÷ 3 = 3000万円
- 経済的利益は3000万円 ÷ 3 = 1000万円
- この1000万円をもとに弁護士費用を計算します
具体的な計算方法は弁護士事務所によって異なりますが、一例として、着手金が経済的利益の5%、報酬金が経済的利益の10%とすると以下の金額になります。
- 着手金:1000万円 × 5% = 50万円
- 報酬金:1000万円 × 10% = 100万円
となります。
共有持分の時価の5〜10%を報酬とするケース
もう一つの計算方法は、「共有持分の時価の5〜10%」を報酬とする方法です。これは比較的新しい計算方法で、シンプルで分かりやすいのが特徴です。
同じく時価9000万円の不動産を3人で平等に共有している場合:
- あなたの持分の時価は9000万円 ÷ 3 = 3000万円
- 着手金は固定額(例:30万円)
- 報酬金は3000万円 × 5〜10% = 150〜300万円
どちらの計算方法が適用されるかで、弁護士費用に大きな差が出ることもあります。そのため、複数の弁護士事務所から見積もりを取り、比較検討することが大切です。
具体的な計算例でわかりやすく説明
より具体的な事例で計算例を見てみましょう。
【事例】時価6000万円のマンションを夫婦で共有(持分割合:夫60%、妻40%)している場合の、夫側の弁護士費用
<計算方法1:持分の時価の3分の1を経済的利益とする場合>
- 夫の持分の時価:6000万円 × 60% = 3600万円
- 経済的利益:3600万円 ÷ 3 = 1200万円
- 着手金(経済的利益の5%):1200万円 × 5% = 60万円
- 報酬金(経済的利益の10%):1200万円 × 10% = 120万円
- 合計:60万円 + 120万円 = 180万円
<計算方法2:共有持分の時価の一定割合を報酬とする場合>
- 夫の持分の時価:6000万円 × 60% = 3600万円
- 着手金:30万円(固定額)
- 報酬金(持分の時価の5%):3600万円 × 5% = 180万円
- 合計:30万円 + 180万円 = 210万円
このように、どちらの計算方法を採用するかで、弁護士費用の総額に差が出ることがあります。また、解決方法(協議、調停、訴訟)や事案の難易度によっても費用は変動します。
弁護士費用以外にかかる費用

訴訟費用(印紙代・切手代)の相場
共有物分割請求を訴訟で行う場合、裁判所に支払う費用として印紙代と切手代がかかります。
印紙代は訴訟物の価額によって決まります。共有物分割請求の場合、不動産の固定資産評価額をもとに計算されます。土地については固定資産評価額の6分の1、建物については3分の1を計算し、さらにあなたの持分割合で割った金額が訴訟物の価額となります。
例えば、固定資産評価額が3000万円の土地を2人で平等に共有している場合: 訴訟物の価額 = 3000万円 ÷ 6 ÷ 2 = 250万円 この場合の印紙代は約2万円程度です。
切手代は裁判所からの郵便物を送るための費用で、被告(相手方)の人数によって変わります。一般的に、相手が1人の場合は6000円程度、1人増えるごとに2000円程度追加されます。
不動産鑑定費用はいくらくらい?
共有物分割請求訴訟では、不動産の価値を正確に把握するために、裁判所が不動産鑑定を命じることがあります。この鑑定費用も当事者負担となります。
不動産鑑定費用は、対象となる不動産の種類や規模によって異なりますが、一般的な一戸建て住宅やマンションであれば、20〜30万円程度が相場です。土地だけなら20万円前後、建物だけなら20万円前後、土地と建物を合わせると30〜40万円程度かかることが多いです。
大規模な不動産や商業施設、複数の不動産が対象となる場合は、さらに高額になることもあります。
その他かかる可能性のある費用は?
弁護士費用、訴訟費用、不動産鑑定費用以外にも、以下のような費用がかかる可能性があります。
- 戸籍謄本等の取得費用: 共有者の現住所を調査するために必要な戸籍謄本や住民票の取得費用。1通あたり数百円ですが、複数必要になることもあります。
- 交通費: 裁判所や弁護士事務所に出向く際の交通費。
- コピー代: 資料のコピー代。大量の資料がある場合は数千円になることも。
- 調査費用: 共有者が行方不明の場合など、調査が必要な場合の費用。
- 共有物の管理費用: 訴訟中も共有物の管理は必要で、その費用は共有者が持分に応じて負担します。
これらの費用は個々のケースによって大きく異なるため、一概にいくらとは言えませんが、弁護士と契約する際に詳細を確認しておくとよいでしょう。
費用の総額イメージと予算の立て方
共有物分割請求にかかる費用の総額は、事案の複雑さや解決方法によって大きく変わりますが、概ね以下のような目安となります。
- 協議で解決する場合: 30〜50万円程度
- 調停で解決する場合: 50〜80万円程度
- 訴訟で解決する場合: 100〜200万円程度
予算を立てる際は、最悪のケース(訴訟まで発展する場合)を想定して準備しておくと安心です。また、共有持分の価値と比較して、費用対効果が見合うかどうかも検討する必要があります。
例えば、あなたの持分が500万円程度の不動産で、弁護士費用が200万円以上かかるようであれば、別の解決方法(例:持分の売却)を検討した方が良いケースもあります。
共有物分割請求の弁護士選びのポイント

専門性の高い弁護士を選ぶコツ
共有物分割請求は不動産法や相続法の知識が必要な専門性の高い案件です。そのため、この分野に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。専門性の高い弁護士を選ぶコツをいくつか紹介します。
まず、弁護士のホームページやブログを確認し、共有物分割請求や不動産トラブルに関する記事を多く書いているかチェックしましょう。具体的な解決事例が掲載されていれば、その分野の経験があると判断できます。
次に、初回相談の際に、過去に共有物分割請求を何件扱ったことがあるか質問してみましょう。経験豊富な弁護士であれば、類似案件の経験やその結果について説明してくれるはずです。
また、相談時の対応も重要です。あなたの状況を丁寧に聞き取り、わかりやすく説明してくれる弁護士は信頼できる可能性が高いです。逆に、質問に対する回答が曖昧だったり、専門用語を多用して説明が分かりにくかったりする場合は注意が必要です。
初回相談が無料の法律事務所の探し方
弁護士費用を抑えるためには、初回相談が無料の法律事務所を探すのも一つの方法です。探し方のコツをご紹介します。
インターネットで「共有物分割請求 弁護士 初回相談無料」などのキーワードで検索すると、該当する法律事務所が見つかります。特に、不動産トラブルや相続問題を得意分野としている事務所に注目しましょう。
弁護士会の無料相談会を利用するのも良い方法です。各地の弁護士会では定期的に無料相談会を開催しており、そこで共有物分割請求について相談できます。その後、相性の良い弁護士に依頼することも可能です。
また、法テラス(日本司法支援センター)も法律相談を実施しています。収入などの条件を満たせば、初回の法律相談が無料で受けられます。
初回相談が無料だからといって、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。複数の弁護士に相談して比較検討することが大切です。
着手金の安い弁護士事務所の特徴
着手金の安い弁護士事務所にはいくつかの特徴があります。
まず、新しく開業した事務所や若手弁護士の事務所は、実績を積むために着手金を低く設定していることがあります。経験は多くないかもしれませんが、熱心に取り組んでくれる可能性もあります。
また、特定分野に特化した事務所は、効率的な業務処理によって着手金を抑えていることがあります。共有物分割請求を多く扱っている事務所であれば、ノウハウがあるため低コストで対応できる場合もあります。
さらに、報酬体系を工夫している事務所もあります。着手金を低く抑える代わりに成功報酬を高めに設定するなど、様々なプランを用意している事務所もあるので、総額で比較することが重要です。
ただし、極端に着手金が安い場合は、隠れた費用がないか、実績や経験が十分かなど、慎重に確認する必要があります。
複数の事務所から見積もりを取る方法
弁護士費用の相場を知り、最適な弁護士を選ぶためには、複数の事務所から見積もりを取ることが重要です。その方法をご紹介します。
まず、3〜5件程度の弁護士事務所をリストアップしましょう。前述の方法で専門性の高い弁護士や初回相談が無料の事務所を探します。
次に、各事務所に連絡して初回相談の予約を取ります。この時点で、共有物分割請求の案件であることと、見積もりが欲しい旨を伝えておくとスムーズです。
相談の際には、自分の状況を具体的に説明し、以下の点を必ず確認しましょう。
- 着手金と報酬金の金額とその計算方法
- 弁護士費用以外にかかる費用の見込み
- 解決までの見通しと期間
- 解決方法についての提案
各事務所の見積もりを比較する際は、単に金額だけでなく、提案内容や弁護士との相性も考慮することが大切です。安いだけの弁護士より、少し高くても信頼できる弁護士の方が、結果的に満足度が高いこともあります。
また、見積もりの内容が不明確な場合は、遠慮せず質問しましょう。後から「聞いていない費用が発生した」というトラブルを避けるためにも、事前の確認が重要です。
弁護士費用を抑える方法

協議や調停の段階で解決する努力をしよう
共有物分割請求は、協議→調停→訴訟という流れで進みますが、早い段階で解決するほど費用を抑えられます。一般的に、訴訟まで発展した場合と比べて、協議や調停で解決できれば、弁護士費用は約2/3程度に抑えることができます。
例えば、訴訟で解決した場合の弁護士費用が100万円だとすると、調停で解決すれば約70万円、協議で解決すれば約50万円程度になる可能性があります。
協議での解決を目指すために、以下のようなことを心がけましょう。
- 共有者同士の話し合いの場を設ける
- 感情的にならず、冷静に自分の希望を伝える
- 相手の立場や事情も考慮する
- 互いに妥協点を探る姿勢を持つ
- 必要に応じて弁護士に協議への同席を依頼する
特に、弁護士が協議に同席すると、専門的な観点からアドバイスが得られるため、スムーズに話し合いが進むことがあります。
法テラスの費用立て替え制度を活用しよう
経済的に余裕がない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用の負担を軽減できる可能性があります。
この制度は、一定の収入・資産基準を満たす方を対象に、弁護士費用や訴訟費用を立て替えてくれるものです。立て替えられた費用は、原則として分割で返済することになります。
利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 資力が一定額以下であること(単身者の場合は月収が20万円以下かつ保有資産が180万円以下)
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
申込みは法テラスの窓口で行います。申込み時には収入や資産を証明する書類が必要です。審査に通れば、法テラスと契約している弁護士に依頼することができます。
なお、この制度は立て替え払いであり、後日返済が必要である点に注意が必要です。
司法書士への依頼で費用を抑える方法
場合によっては、弁護士ではなく司法書士に依頼することで費用を抑えられる可能性があります。司法書士は、一定の範囲内で法律相談や代理業務を行うことができます。
特に、簡易裁判所での訴訟(訴額が140万円以下の事件)であれば、認定司法書士(特定司法書士とも呼ばれる)に依頼することができます。弁護士と比べて報酬が安い傾向にあり、費用を抑えられる可能性があります。
ただし、共有物分割請求は通常、地方裁判所の管轄となるため、訴訟代理は弁護士に限られます。そのため、司法書士に依頼できるのは主に以下のような業務に限定されます。
- 法律相談
- 協議段階でのサポート
- 書類作成の補助
共有物分割請求の全過程を司法書士だけに任せることはできませんが、初期段階のサポートを依頼することで、全体の費用を抑える工夫はできるでしょう。
複数事務所の見積もり比較のコツ
前述した通り、複数の弁護士事務所から見積もりを取ることは、費用を抑えるための重要なステップです。見積もりを比較する際のコツをいくつか紹介します。
まず、見積もりの内訳を詳細に確認しましょう。着手金と報酬金の金額だけでなく、その計算方法や、追加で発生する可能性のある費用も含めて比較することが大切です。
次に、解決方法や解決までの期間についての見通しも比較しましょう。単に安いだけでなく、効率的に解決できる見込みがあるかどうかも重要な判断材料です。
また、成功報酬の計算方法にも注目しましょう。「持分の時価の3分の1」を経済的利益とする方法と、「共有持分の時価の5〜10%」を報酬とする方法では、どちらが有利かは個々のケースによって異なります。自分のケースではどちらが安くなるのか計算してみましょう。
さらに、弁護士との相性も重要です。長期間にわたる協力関係になるため、コミュニケーションがスムーズに取れる弁護士を選ぶことで、ストレスを減らし、結果的に良い解決につながります。
最後に、特典や割引がないか確認しましょう。初回相談無料、着手金割引、複数案件の同時依頼割引など、様々な特典を設けている事務所もあります。
共有物分割請求以外の共有状態解消方法

共有持分を専門業者に売却する選択肢
共有物分割請求は時間と費用がかかるため、別の解決方法として「共有持分を専門業者に売却する」という選択肢もあります。これは特に、以下のような場合に検討する価値があります。
- 早急に現金化したい
- 共有者との関係を悪化させたくない
- 弁護士費用を捻出するのが難しい
- 共有物分割請求の結果が見通せない
共有持分の買取りを専門とする不動産業者は、他の共有者の同意がなくても、あなたの持分だけを買い取ってくれます。通常の不動産売買と比べると安い価格になることが多いですが、手続きが簡単で、早ければ数週間程度で現金化できるメリットがあります。
複数の業者から査定を取ることで、より良い条件で売却できる可能性が高まります。ただし、共有持分は通常の不動産と比べて流通性が低いため、市場価格の50〜70%程度の査定額になることが一般的です。
共有持分専門業者への売却は、すぐに現金化できるメリットがある反面、市場価格より安く売却することになるデメリットもあります。そのため、急ぎでない場合は、他の解決方法と比較検討することをおすすめします。
他の共有者に持分を買い取ってもらう交渉術
共有状態を解消する方法として、他の共有者にあなたの持分を買い取ってもらうという選択肢もあります。これは特に、不動産を実際に使用している共有者がいる場合に有効な方法です。
例えば、親から相続した実家に兄弟の一人が住んでいる場合、住んでいる兄弟にあなたの持分を買い取ってもらうことで、両者がWin-Winの関係になる可能性があります。あなたは現金を得られ、住んでいる兄弟は単独所有になって自由に不動産を活用できるようになります。
効果的な交渉のためには、以下のようなポイントを押さえましょう。
まず、持分の適正価格を把握することが重要です。不動産会社の査定や不動産鑑定士の評価を参考にして、妥当な金額を提示しましょう。市場価格の80〜90%程度が一般的な相場です。
次に、相手にとってのメリットを強調します。例えば「単独所有になればリフォームや建て替えも自由にできる」「将来的な売却や活用がしやすくなる」といった点は大きなメリットです。
また、一括払いが難しい場合は、分割払いの提案や、不動産担保ローンの活用など、柔軟な支払い方法を提案することも交渉を成功させるコツです。
交渉は感情的にならず、ビジネスライクに進めることが大切です。必要に応じて弁護士や不動産仲介業者に間に入ってもらうと、スムーズに進む場合もあります。
それぞれの方法のメリット・デメリット
共有状態を解消する方法には、共有物分割請求、専門業者への売却、他の共有者への売却など、いくつかの選択肢があります。それぞれのメリットとデメリットを整理しましょう。
【共有物分割請求】 メリット:
- 法的に強制力がある
- 裁判所が公平な判断をしてくれる
- 共有者が多数いても解決可能
デメリット:
- 費用が高額(50〜150万円程度)
- 時間がかかる(半年〜数年)
- 共有者との関係が悪化する可能性がある
【専門業者への売却】 メリット:
- 手続きが簡単で早い(数週間〜数ヶ月)
- 他の共有者の同意が不要
- すぐに現金化できる
デメリット:
- 市場価格より安くなる(市場価格の50〜70%程度)
- 他の共有者とのトラブルが生じる可能性がある
- 業者選びを間違えるとさらに安く買いたたかれることも
【他の共有者への売却】 メリット:
- 専門業者より高値で売却できる可能性がある(市場価格の80〜90%程度)
- 共有者間の関係を良好に保ちやすい
- 弁護士費用が抑えられる
デメリット:
- 交渉が難航する可能性がある
- 共有者に資金力がない場合は実現しない
- 価格設定で揉めることがある
費用対効果から見た最適な選択方法
どの方法を選ぶべきかは、個々の状況によって異なります。費用対効果の観点から最適な選択をするためのポイントをご紹介します。
まず、持分の価値と比較して解決方法の費用を考えましょう。例えば、あなたの持分が300万円程度の不動産で、共有物分割請求に100万円以上かかるようであれば、専門業者への売却(150〜210万円程度)の方が経済的に合理的かもしれません。
次に、時間的な制約も重要です。すぐに現金が必要な場合は、訴訟よりも売却の方が適しています。逆に、時間に余裕があり、最大限の経済的利益を得たい場合は、共有物分割請求や他の共有者との交渉が有利です。
また、共有者との関係性も考慮すべき要素です。家族間の共有で関係を良好に保ちたい場合は、できるだけ話し合いでの解決を目指すべきでしょう。一方、すでに関係が悪化していたり、共有者が多数いたりする場合は、法的手段の方が効果的な場合もあります。
さらに、不動産の特性も影響します。分割しやすい土地なら現物分割の可能性が高く、共有物分割請求が有利かもしれません。一方、マンションの一室のような分割が難しい物件では、売却の方が現実的です。
最終的には、弁護士や不動産の専門家に相談しながら、あなたの状況に最適な解決方法を選ぶことが大切です。複数の選択肢を検討し、メリット・デメリットを比較した上で決断しましょう。
よくある質問(Q&A)

弁護士に依頼せず自分で共有物分割請求はできる?
結論から言えば、弁護士に依頼せずに自分で共有物分割請求を行うこと(本人訴訟)は法律上可能です。しかし、実務的には非常に難しいと言わざるを得ません。
共有物分割請求訴訟は法律知識が必要なだけでなく、訴状の作成や証拠の収集、法廷での主張立証など、専門的なスキルが求められます。特に相手方に弁護士がついている場合、法律の素人が対等に争うのは極めて困難です。
また、訴訟の途中で和解交渉になった場合も、法的知識がないと不利な条件での和解を強いられる可能性があります。
弁護士費用を節約したい気持ちは理解できますが、結果的に得られる経済的利益が減ってしまっては本末転倒です。少なくとも初回相談だけでも弁護士に依頼し、自分で対応可能かどうか相談することをおすすめします。
なお、裁判所では書式のひな型を提供していたり、書類の書き方について説明してくれる窓口があったりする場合もありますので、本人訴訟を検討している方は、まず最寄りの裁判所に問い合わせてみるとよいでしょう。
訴訟に負けた場合も弁護士費用は発生する?
訴訟の結果に関わらず、弁護士費用は基本的に発生します。着手金は依頼した時点で支払う費用なので、訴訟の結果に関係なく返金されません。
報酬金については、事務所によって扱いが異なります。完全成功報酬制を採用している事務所では、敗訴した場合は報酬金が発生しないこともあります。一方、部分的に成功した場合(例:希望していた現物分割ではなく換価分割になった場合)は、その成功の程度に応じて報酬金が発生するケースが多いです。
弁護士との契約時に、敗訴した場合の報酬金についてどのような取り決めになっているか、必ず確認しておきましょう。また「敗訴」の定義についても明確にしておくことが重要です。
なお、共有物分割請求訴訟では完全な「敗訴」というケースは少なく、裁判所が何らかの形で共有関係を解消する判決を出すことが多いです。ただし、希望していた分割方法と異なる結果になることはあり得ます。
相手側の弁護士費用も負担する必要がある?
民事訴訟の原則として、各自が自分の弁護士費用を負担することになっています。つまり、共有物分割請求訴訟においても、相手側の弁護士費用をあなたが負担する必要はありません。
ただし、訴訟費用(印紙代や鑑定費用など)については、裁判所の判断により負担割合が決められます。一般的には持分割合に応じて分担されることが多いですが、訴訟の経過や結果によっては、一方に多くの負担を命じることもあります。
なお、調停や和解で解決する場合は、弁護士費用や訴訟費用の負担についても当事者間で合意することがあります。例えば「各自が自己の弁護士費用を負担し、訴訟費用は折半する」といった合意です。
いずれにせよ、弁護士費用の負担については契約時に弁護士とよく相談し、不明な点があれば質問するようにしましょう。
予想外の高額費用を請求されるケースとその対策
弁護士費用に関して予想外の高額請求が発生するケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 訴訟が長期化した場合: 当初の見込みより訴訟が長引くと、弁護士の稼働時間が増え、追加費用が発生することがあります。
- 事案が複雑化した場合: 予想外の争点が出てきたり、証拠調べが複雑になったりすると、追加費用が発生する可能性があります。
- 成功報酬の計算方法に誤解があった場合: 成功報酬の計算方法を誤解していると、予想より高額になることがあります。
これらのリスクに対する対策としては、以下のことが有効です。
まず、弁護士との契約書を必ず作成し、費用の発生条件や計算方法を明確にしておきましょう。口頭での説明だけでは後々トラブルの元になります。
次に、追加費用が発生する可能性のある事態について、あらかじめ弁護士に確認しておきましょう。「どのような場合に追加費用が発生するのか」「その場合の目安はいくらか」といった点です。
また、定期的に弁護士から進捗状況と費用の見通しについて報告を受けるようにしましょう。訴訟の進行に応じて費用の見通しも変わることがあるため、常に最新の情報を把握しておくことが大切です。
もし予想外の高額請求を受けた場合は、まずは弁護士に説明を求めましょう。納得できない場合は、弁護士会の紛議調停制度を利用することも検討できます。
まとめ
共有物分割請求の弁護士費用相場と賢い選び方について、詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。
共有物分割請求の弁護士費用は、着手金と報酬金を合わせて50〜150万円程度が一般的な相場です。着手金は20〜30万円、報酬金は経済的利益に応じて計算されることが多く、これに訴訟費用や不動産鑑定費用などが加わります。
弁護士費用の計算方法には、「持分の時価の3分の1」を経済的利益とする方法と、「共有持分の時価の5〜10%」を報酬とする方法の2つがあります。どちらが有利かは個々のケースによって異なるため、複数の弁護士事務所から見積もりを取ることが大切です。
弁護士選びのポイントとしては、共有物分割請求の経験が豊富な弁護士を選ぶこと、初回相談が無料の事務所を探すこと、複数の事務所の見積もりを比較することなどが挙げられます。また、着手金が安い事務所を選ぶことも費用を抑える一つの方法です。
費用を抑えるためには、訴訟まで発展させず、協議や調停の段階で解決することが効果的です。また、法テラスの費用立て替え制度を利用したり、初期段階のサポートを司法書士に依頼したりする方法もあります。
共有物分割請求以外の解決方法としては、共有持分を専門業者に売却する方法や、他の共有者に持分を買い取ってもらう方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。
共有物分割請求は決して安い手続きではありませんが、長期的な視点で見れば、共有状態によるデメリットから解放される価値は大きいと言えます。適切な弁護士選びと解決方法の検討を通じて、最善の結果を目指しましょう。
今すぐ実行できる3つのアクション
- 無料相談を活用する: まずは3社程度の弁護士事務所の初回無料相談を予約しましょう。インターネットで「共有物分割請求 弁護士 初回相談無料」で検索すると、該当する事務所が見つかります。相談時には自分のケースを詳しく説明し、費用の見積もりを取りましょう。
- 共有持分の価値を調査する: 弁護士費用の計算基礎となる共有持分の価値を把握するため、不動産会社に査定を依頼しましょう。複数の不動産会社から査定を取ることで、より正確な価値が分かります。また、固定資産税評価証明書を取得しておくと、訴訟費用の計算にも役立ちます。
- 共有者との話し合いの場を設ける: 訴訟に発展する前に、まずは共有者全員での話し合いの場を設けましょう。日時と場所を決めて書面で通知し、話し合いの内容は議事録として残しておくことをおすすめします。感情的にならず、各自の希望と妥協点を冷静に話し合うことで、訴訟よりも低コストで解決できる可能性があります。

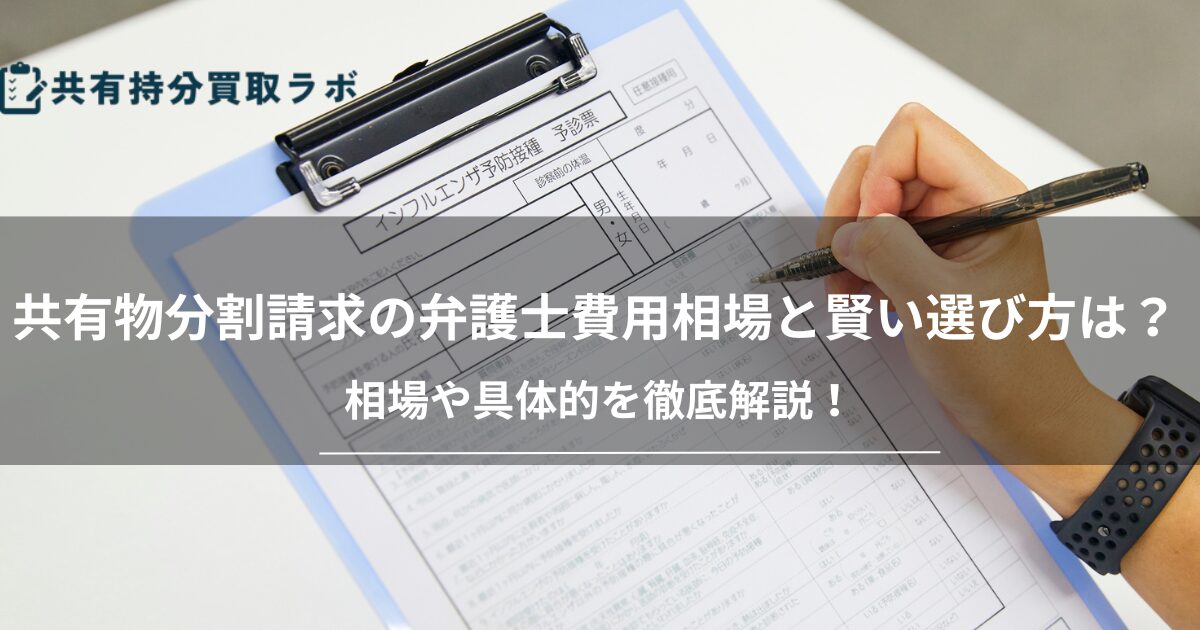

コメント