マンションを複数の人で共同所有している「共有名義」の状態。これは夫婦や親子、兄弟姉妹などで不動産を共同購入するケースでよく見られます。しかし、このマンションを売却しようとすると、一人で所有している場合と比べて複雑な手続きやトラブルが発生することがあります。
「共有者の一人が売却に反対している」「連絡が取れない共有者がいる」「売却後のお金の分け方で揉めている」など、様々な問題が起こりうるのです。
この記事では、マンション共有名義の売却を考えている方に向けて、スムーズな売却のための手順やトラブルを避けるためのポイントを、専門家の視点からわかりやすく解説します。複雑に思える手続きも、正しい知識があれば安心して進められます。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マンション共有名義とは?知っておきたい基本の「き」

マンション共有名義とは、一つのマンションを複数の人が共同で所有している状態のことです。登記簿には所有者として複数の名前が記載され、それぞれが「持分」と呼ばれる所有権の割合を持っています。
たとえば、夫婦で購入した場合は「夫:2分の1、妻:2分の1」というように記載されることが多いです。親子で共有している場合は「親:3分の2、子:3分の1」など、出資額に応じて割合が決まることもあります。
共有名義になっている主な理由としては:
- 住宅ローンの借入額を増やすため(共働き夫婦の場合など)
- 相続によって複数人の所有になった
- 親子で資金を出し合って購入した
- 兄弟姉妹で親の家を相続した
- 投資目的で友人や知人と共同購入した
などが挙げられます。
この共有状態は、民法上「共有物」として扱われ、原則として共有者全員の同意がなければ売却できません(民法第251条)。ここが単独所有と大きく異なるポイントであり、売却時のトラブルの原因にもなっています。
マンション共有名義売却の基本的な流れを理解しよう

共有名義マンションの売却は、単独所有の場合よりも手順が増えますが、基本的な流れを知っておけば安心です。ここでは、売却の準備から完了までのプロセスを見ていきましょう。
1. 売却前の準備と確認事項
まず最初に、共有者全員で話し合いを持ち、売却について合意を得ることが必要です。この段階で以下のことを確認しておきましょう。
- 売却することへの全員の同意
- 希望する売却価格の範囲
- 売却後の資金分配方法
- 売却にかかる費用の負担割合
- 各自の今後の住まいの予定
特に重要なのは全員の同意です。一人でも反対していると、原則として売却ができません。早い段階で十分な話し合いを持ち、全員が納得できる条件を探りましょう。
2. 必要書類の確認と準備
共有名義の売却では、通常より多くの書類が必要になります。主な書類は以下の通りです。
- 全共有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 全共有者の実印
- 登記済権利証または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書
- マンションの管理費等の領収書
- 全共有者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
これらの書類をスムーズに集められるよう、共有者間で連絡を取り合い、協力して準備を進めましょう。特に遠方に住んでいる共有者がいる場合は、早めに依頼しておくことが大切です。
3. 信頼できる不動産会社の選定
共有名義の物件を扱った経験が豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。以下のポイントを参考に選びましょう。
- 共有名義物件の売却実績があるか
- 共有者全員の意見を公平に聞いてくれるか
- トラブル発生時の対応策を提案できるか
- 連絡や報告がこまめにできるか
- 複数の共有者への対応が丁寧か
- 売買契約書の共有名義版の雛形を持っているか
査定を依頼する際は、共有名義であることを必ず伝え、過去の共有物件の売却事例や成功例について質問してみるとよいでしょう。また、複数の不動産会社(最低3社)に査定を依頼して比較することをおすすめします。
4. 適正な売却価格の設定
売却価格は共有者全員で話し合って決めることが理想的です。ただし、それぞれが異なる希望額を持っていることもあります。そんな時は次の方法が役立ちます。
- 複数の不動産会社から査定を取り、平均値を参考にする
- 周辺の類似物件の売却事例を調べる
- 早く売りたい人と高く売りたい人の妥協点を探る
- 将来の不動産市場の見通しも考慮する
実際の市場価格よりも高く設定すると売れるまでに時間がかかり、その間に共有者の事情が変わってしまうリスクもあります。現実的な価格設定が、スムーズな売却につながります。
5. 買主との契約から決済までの流れ
買主が見つかると、売買契約を結びます。共有名義の場合は、全共有者が売主として契約書に実印で押印する必要があります。
契約時には手付金が支払われ、その後、決済・引き渡し日に残金が支払われます。決済日には原則として全共有者が立ち会うことが望ましいですが、委任状を用いて代理人に任せることも可能です。
決済後、売却代金は共有持分に応じて分配されるのが一般的ですが、共有者間の合意があれば、別の割合で分けることもできます。
共有名義マンション売却でよくあるトラブルと解決策

共有名義のマンション売却では、様々なトラブルが発生することがあります。ここでは、よくあるトラブルとその解決策を紹介します。
共有者の一人が売却に反対する場合の対応
共有者の誰かが売却に反対している場合、まずは反対理由を丁寧に聞き、話し合いで解決を目指します。主な反対理由と対応策は:
- 売却価格に不満がある → 査定額の根拠を示し、市場の実態を説明する
- 住み続けたい → 売却益で新しい住まいを提案する
- 税金面での懸念がある → 税理士に相談して具体的なシミュレーションを示す
- 思い出の物件を手放したくない → 感情面に配慮しつつ、維持費や将来の負担などの現実的な側面を伝える
これらの話し合いでも解決しない場合は、「共有物分割請求」という法的手段があります。ただし、裁判所を通じての解決となるため、時間や費用がかかることを覚悟する必要があります。
売却に反対する共有者に対して、第三者である専門家(弁護士や不動産コンサルタント)から客観的な意見を伝えてもらうことも効果的です。また、一定期間の猶予を設けることで、心の準備ができる場合もあります。
共有者と連絡が取れない場合の対策
共有者が行方不明だったり、連絡が取れなかったりする場合は、売却手続きが進められなくなります。このような場合の対応策としては:
- 親族や知人を通じて連絡を試みる
- 住民票や戸籍の附票を取得して現住所を調べる
- 内容証明郵便で売却の意向を伝える
- 不在者財産管理人の選任を裁判所に申し立てる
特に不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を管理する人を裁判所が選任する制度で、この管理人が売却に同意することで手続きを進められるようになります。申立ては共有者や利害関係人(債権者など)が行うことができます。ただし、申立てから選任までに3〜6ヶ月程度の時間がかかることを見込んでおく必要があります。また、申立て費用として予納金(30万円程度)が必要です。
売却金の分配でトラブルになるケース
売却後のお金の分け方でもめることも少なくありません。特に以下のようなケースに注意が必要です。
- 登記上の持分と実際の出資額が異なる場合
- 一部の共有者がリフォーム費用を負担していた場合
- ローン返済額に差がある場合
- 固定資産税などの費用負担が不均等だった場合
これらのトラブルを防ぐためには、売却前に分配方法について書面で合意しておくことが重要です。必要に応じて弁護士や税理士などの専門家に相談し、公平な分配方法を検討しましょう。
専門家が教える!スムーズな共有名義マンション売却のためのポイント

共有名義マンションの売却をスムーズに進めるためのポイントを、専門家の視点からお伝えします。
売却前に確認すべき重要事項
売却を始める前に、以下の項目をしっかりと確認しておきましょう。
- 登記簿謄本で共有者全員の名前と持分を確認する
- 住宅ローンが残っている場合は、残債額を正確に把握する
- マンションの管理費や修繕積立金の滞納がないか確認する
- 固定資産税の納付状況を確認する
- マンションの修繕履歴や設備の状態を把握する
これらの情報は、適正な売却価格を設定するためにも、買主からの質問に答えるためにも重要です。特に管理費や修繕積立金の滞納があると、売却の障害になることがあるので注意が必要です。
信頼できる仲介会社の選び方
共有名義物件の売却経験が豊富な仲介会社を選ぶことが成功の鍵です。複数の不動産会社に査定を依頼する際は、以下の点を比較しましょう。
- 共有名義物件の売却実績と知識
- 提案する販売戦略の具体性
- 査定額の根拠の明確さ
- 担当者の共有者全員への対応の丁寧さ
- 類似物件の成約事例の豊富さ
特に大手と地域密着型の両方から話を聞くと、多角的な視点が得られます。相場感や売却にかかる期間の見通しも、複数社から聞いておくと安心です。
税金対策と知っておくべき特例
マンション売却時には様々な税金がかかりますが、条件によっては特例が適用され、税負担を軽減できる場合があります。
- 3,000万円特別控除:居住用財産を売却した場合、最大3,000万円まで利益から控除できる
- 買い替え特例:住み替えで新たに住宅を購入する場合、譲渡所得税の課税を繰り延べられる
- 軽減税率の適用:所有期間が10年を超える場合、税率が優遇される
- 相続財産を売却した場合の取得費加算の特例:相続から3年10ヶ月以内に売却する場合に適用可能
ただし、共有名義の場合は適用条件が複雑になることもあるため、税理士に相談することをおすすめします。特に共有者ごとに居住実態が異なる場合は、適用できる特例が変わってくることがあります。例えば、3,000万円特別控除は「住んでいた人」にしか適用されないため、共有者の中で実際に居住していなかった人には適用されません。
共有名義解消の選択肢と比較

マンションの売却以外にも、共有名義を解消する方法はいくつかあります。状況に応じて最適な方法を選びましょう。
共有持分の買取りという選択
共有者の一人が他の共有者の持分を買い取る方法です。たとえば、夫婦で共有していたマンションを離婚時に一方が買い取るケースなどが該当します。
メリット:
- 不動産を手放さずに済む
- 市場価格より安く取引できる可能性がある
- 仲介手数料などのコストを抑えられる
デメリット:
- 買取り資金の準備が必要
- 適正価格の設定で揉めることがある
- 住宅ローンの組み直しが必要な場合がある
持分の買取りを検討する際は、不動産鑑定士に依頼して適正な価格を算出してもらうことで、トラブルを防げます。
共有物分割請求とは
共有者の話し合いで解決できない場合の最終手段として、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てる方法があります。これは民法上の権利として認められているもので、共有関係を解消するための手続きです。
裁判所は基本的に以下の3つの方法で判断します。
- 現物分割:物理的に分割できる場合(マンションでは難しい)
- 競売分割:競売にかけて得た代金を分配する
- 価格賠償:一部の共有者が他の共有者に対価を支払って所有権を取得する
マンションの場合は物理的に分割することが難しいため、ほとんどのケースで「競売分割」か「価格賠償」になります。競売の場合、市場価格より安くなる傾向があるため、できれば話し合いでの解決が望ましいでしょう。
裁判による解決は最終手段と考え、まずは粘り強く話し合いを続けることをおすすめします。
マンション共有名義売却の重要ポイント総まとめ
ここまで共有名義マンションの売却について詳しく見てきました。最後に重要なポイントをまとめます。
- 共有者全員の合意を得ることが大前提
- 早い段階から書類の準備と連絡体制の確立を行う
- 共有名義物件の売却経験が豊富な不動産会社を選ぶ
- 売却金の分配方法を事前に文書で合意しておく
- 税金面の特例適用条件を確認し、専門家に相談する
- トラブル発生時は感情的にならず、法的手段も視野に入れる
- 売却後の住まいの計画も並行して考える
共有名義マンションの売却は、複数の人の意見や事情を調整する必要があり、単独所有の場合より手間がかかります。しかし、事前に正しい知識を持ち、計画的に進めることで、トラブルを最小限に抑えることができます。
売却の成功は、共有者間のコミュニケーションと信頼関係がカギを握ります。お互いの立場を尊重し、専門家のアドバイスも取り入れながら、全員がWin-Winとなる結果を目指しましょう。
よくある質問(FAQ)
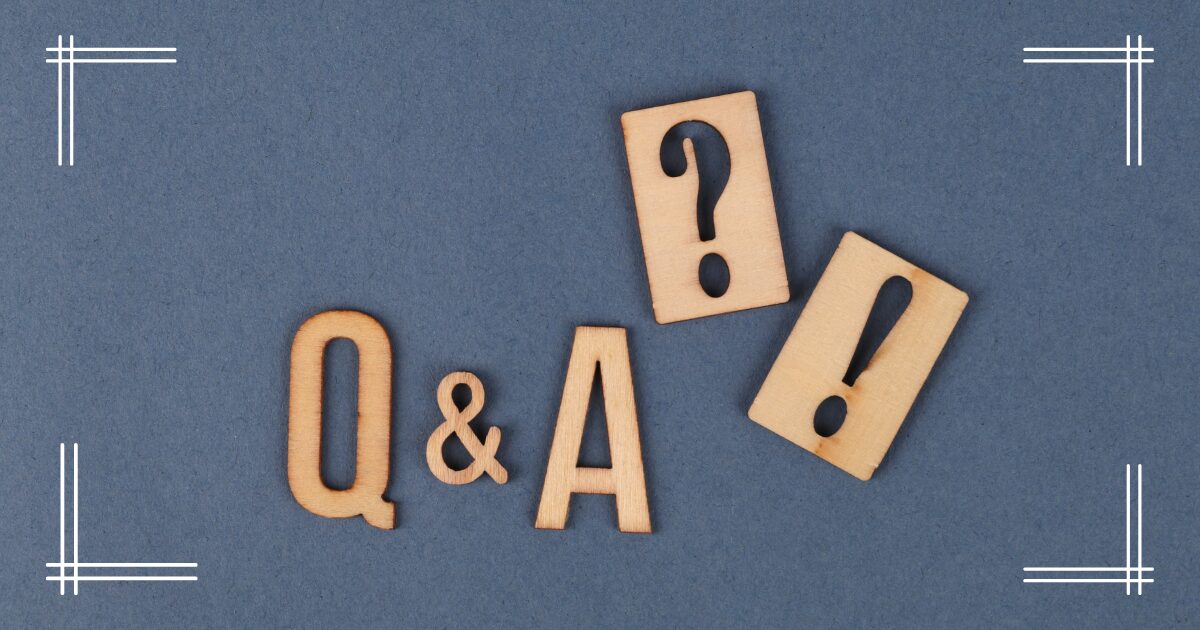
- 共有名義人の一人が死亡した場合、売却手続きはどうなりますか?
亡くなった共有者の持分は相続人に引き継がれます。まず相続手続きを行い、登記名義を相続人に変更した上で売却手続きを進める必要があります。相続人が複数いる場合は、さらに共有者が増えることになるため、早めに遺産分割協議を行うことをおすすめします。なお、相続登記が完了するまでに1〜2ヶ月程度かかることを見込んでおきましょう。
- 持分割合が不均等な場合の売却利益の分配方法は?
基本的には登記簿に記載された持分割合に応じて分配するのが原則です。ただし、共有者間の合意があれば、出資額や住宅ローンの返済額など実質的な負担に応じた分配方法に変更することも可能です。その場合は、必ず書面で合意内容を残しておきましょう。後々のトラブル防止のために、分配方法については公正証書にしておくことも一案です。
- 共有名義の解消にかかる費用の目安はいくらですか?
方法によって異なります。通常の売却なら仲介手数料(売却価格の3〜3.6%+税)、印紙税(1〜6万円程度)、抵当権抹消費用(1〜2万円程度)などがかかります。共有物分割請求の場合は、弁護士費用(30〜50万円程度)や裁判費用(予納金10〜20万円程度)が必要です。また、税金面では譲渡所得税(所有期間や居住実態によって変動)がかかる場合があります。
- 共有物分割請求にかかる期間はどのくらいですか?
一般的には申立てから解決まで1年〜1年半程度かかることが多いです。ただし、当事者間の対立が激しい場合や、共有者が多数いる場合はさらに長期化することもあります。裁判の途中でも和解が成立すれば早期解決の可能性もあります。
- 売却後の確定申告はどうすればいいですか?
売却した年の翌年(1月1日〜3月15日)に、共有者それぞれが確定申告を行う必要があります。譲渡所得は分離課税となり、所有期間や居住実態によって税率が異なります。特例適用の可能性もあるため、税理士に相談することをおすすめします。共有名義の場合、特例適用条件が複雑になることがあるので、専門家のアドバイスが特に重要です。
今すぐできる3つの具体的アクション
- 登記簿謄本を取得して共有状況を確認する:法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、正確な共有者と持分割合を確認しましょう。オンラインでも取得可能です(法務局の登記情報提供サービスを利用、1通700円程度)。これにより現状を正確に把握でき、今後の計画の基礎となります。
- 共有者全員での話し合いの場を設定する:売却の意向や条件について、共有者全員が参加する話し合いの日程を調整しましょう。遠方の方とはオンラインミーティングも効果的です。この話し合いでは、売却の是非、希望価格、分配方法などを議題にします。議事録を作成して、合意事項を文書化しておくことも重要です。
- 共有名義物件に強い不動産会社に査定を依頼する:複数の不動産会社(最低3社)に査定を依頼し、共有名義物件の売却実績についても質問しましょう。大手と地域密着型の両方を選ぶと、多角的な視点が得られます。査定結果を比較することで、適正価格の目安がわかり、今後の方針決定に役立ちます。
マンション共有名義の売却は複雑ですが、正しい知識と計画的な行動で、スムーズに進めることができます。まずは上記の3つのアクションから始めて、一歩ずつ進めていきましょう。

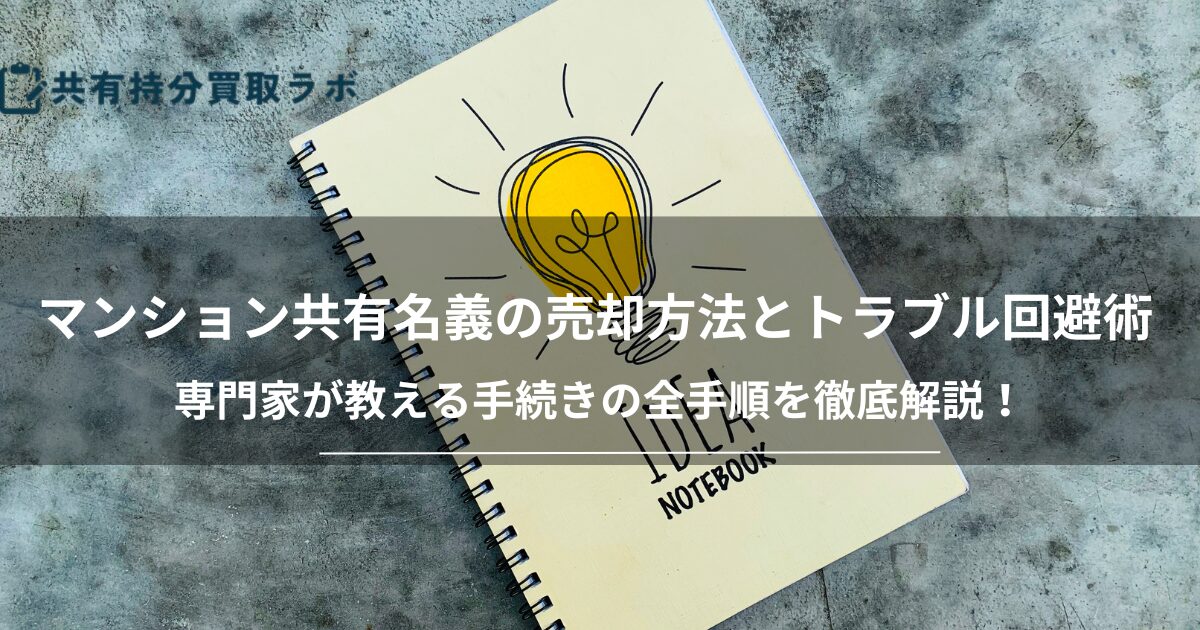

コメント