マイホームを夫婦で購入する、実家を兄弟で相続する―こんなとき、皆さんは「共有持分」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。不動産を複数人で所有する際に必ず決めなければならない「共有持分」。この割合を適当に決めてしまうと、思わぬ税金が発生したり、住宅ローン控除が受けられなかったりと、後々大きな問題を引き起こす可能性があります。
この記事では、不動産を購入するときと相続で取得するときの、それぞれの共有持分の決め方と計算方法について、初心者の方にもわかりやすく解説します。共有持分の基本から応用まで、実例を交えて説明しますので、不動産の共同購入や相続を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有持分の基礎知識

共有持分とは?シンプルに説明
共有持分とは、一つの不動産を複数の人が所有するときに、それぞれの人がどれだけの割合で所有しているかを示すものです。
例えば、夫婦で家を購入し、夫が3分の2、妻が3分の1の持分を持つという場合、その家の所有権は夫が66.7%、妻が33.3%ということになります。
よく勘違いされるのが、「持分が半分ならば、家の半分を物理的に所有している」という考え方です。実際には、持分はあくまで権利の割合を示すものであり、不動産全体に対する所有権の比率を表しています。つまり、どの部屋が誰のものというわけではなく、不動産全体に対する権利の割合を示しているのです。
共有名義と共有持分の違い
「共有名義」と「共有持分」は似ていますが、厳密には異なる概念です。共有名義とは、不動産の所有者が複数人いる状態を指し、登記簿上に複数の名前が記載されることを意味します。一方、共有持分は、その共有名義人それぞれが持つ所有権の割合のことです。
例えば、「夫と妻の共有名義で家を購入した」というのは、所有者が夫と妻の二人であることを示しています。そして、「夫の持分が2分の1、妻の持分が2分の1」というのが、それぞれの所有権の割合を表しているのです。
共有持分が発生する主なケース
共有持分が発生する代表的なケースには、以下のようなものがあります。
- 夫婦や親子などで不動産を共同購入する場合
- 相続により複数の相続人が不動産を取得する場合
- 親から子へ不動産の一部を生前贈与する場合
- 友人や知人と共同で投資用不動産を購入する場合
特に多いのは、夫婦での住宅購入と相続による取得です。夫婦で住宅ローンを組む場合は、それぞれの負担額に応じて持分を設定することが一般的です。また、相続の場合は法定相続分に基づいて持分が決まることが多いですが、遺言があれば別の割合になることもあります。
購入時の共有持分の決め方

基本原則:購入費用の負担割合で決める理由
不動産を共同で購入する場合、共有持分は基本的に「購入費用の負担割合」に合わせて決めるのが原則です。なぜなら、負担割合と持分割合が異なると、負担額よりも持分が多い人は、実質的に他の共有者から贈与を受けたと見なされる可能性があるからです。
例えば、3,000万円の不動産を夫婦で購入し、夫が2,500万円、妻が500万円を負担したにもかかわらず、持分を夫7割、妻3割にすると、妻は実際の負担(500万円=16.7%)より多い持分(3割=900万円)を得ることになります。この差額の400万円分は、税務上「夫から妻への贈与」と見なされ、贈与税の対象となる可能性があるのです。
このような税金問題を避けるためにも、持分割合は購入費用の負担割合に合わせることが重要です。
具体的な計算方法と計算式
共有持分の計算方法はシンプルです。以下の計算式で求めることができます。
持分割合 = 自分の負担額 ÷ 不動産の総額
この「負担額」には、頭金だけでなく、住宅ローンの借入額も含まれます。また、「不動産の総額」には、物件価格だけでなく、仲介手数料や登記費用、不動産取得税なども含まれることがあります。これらの諸費用も取得費として認められるためです。
シンプルな計算例(夫婦で負担額が異なるケース)
具体的な例で見てみましょう。
4,000万円の不動産を夫婦で購入する場合で、夫が3,000万円、妻が1,000万円を負担するとします。この場合の持分割合は以下のように計算します。
夫の持分割合 = 3,000万円 ÷ 4,000万円 = 0.75 = 75% 妻の持分割合 = 1,000万円 ÷ 4,000万円 = 0.25 = 25%
登記上は、夫の持分は4分の3(75%)、妻の持分は4分の1(25%)となります。
住宅ローンが絡む場合の計算方法
多くの方は、不動産購入時に住宅ローンを利用します。この場合、誰がどれだけのローンを借りるかによって持分割合が変わってきます。
例えば、5,000万円の不動産を購入する際に、夫が頭金1,000万円と住宅ローン3,000万円、妻が住宅ローン1,000万円を負担するとします。この場合の持分割合は以下のようになります。
夫の負担額 = 1,000万円(頭金)+ 3,000万円(ローン)= 4,000万円 妻の負担額 = 1,000万円(ローン)
夫の持分割合 = 4,000万円 ÷ 5,000万円 = 0.8 = 80% 妻の持分割合 = 1,000万円 ÷ 5,000万円 = 0.2 = 20%
このように、住宅ローンの借入額も負担額に含めて計算します。ただし、住宅ローンの種類によって、考え方が少し変わることがありますので、次のセクションで詳しく説明します。
購入時の共有持分計算の応用例
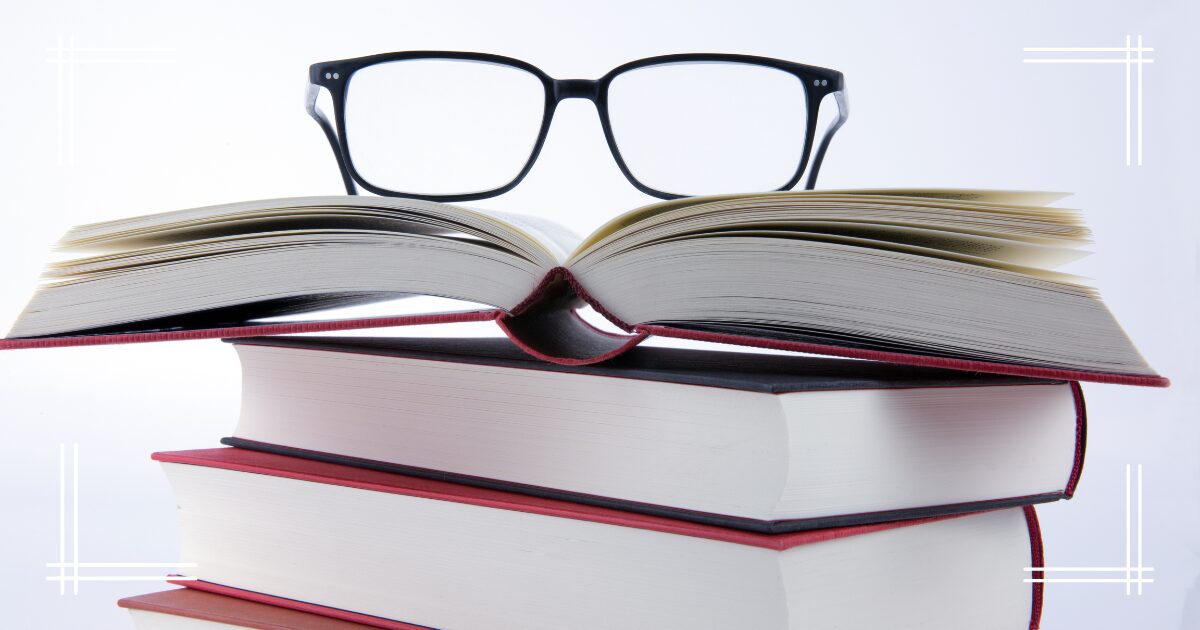
ペアローンを組む場合の持分割合
ペアローンとは、夫婦などの複数人がそれぞれ別々に住宅ローンを組む方法です。この場合、それぞれの借入額と頭金の負担額の合計が、各自の負担額となります。
例えば、4,000万円の不動産を購入する際に、夫が頭金500万円と住宅ローン2,500万円、妻が住宅ローン1,000万円を負担するとします。この場合の持分割合は次のようになります。
夫の負担額 = 500万円(頭金)+ 2,500万円(ローン)= 3,000万円 妻の負担額 = 1,000万円(ローン)
夫の持分割合 = 3,000万円 ÷ 4,000万円 = 0.75 = 75% 妻の持分割合 = 1,000万円 ÷ 4,000万円 = 0.25 = 25%
ペアローンの場合は、それぞれの借入額がそれぞれの負担額となるため、持分割合の計算がシンプルです。また、両者とも住宅ローン控除を受けられるというメリットがあります。
連帯保証型住宅ローンの場合の持分割合
連帯保証型住宅ローンとは、主債務者(主にローンを借りる人)と連帯保証人(主債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済する人)の関係でローンを組む方法です。
この場合、ローンの借入額は主債務者の負担となりますが、連帯保証人も頭金などを負担することがあります。持分割合は、それぞれの実際の負担額に応じて決めます。
例えば、4,000万円の不動産を購入する際に、夫(主債務者)が住宅ローン3,500万円、妻(連帯保証人)が頭金500万円を負担するとします。この場合の持分割合は次のようになります。
夫の負担額 = 3,500万円(ローン) 妻の負担額 = 500万円(頭金)
夫の持分割合 = 3,500万円 ÷ 4,000万円 = 0.875 = 87.5% 妻の持分割合 = 500万円 ÷ 4,000万円 = 0.125 = 12.5%
連帯保証型の場合、主債務者の負担額が大きくなりやすいため、持分割合も偏りやすくなります。また、住宅ローン控除は主債務者のみが受けられるという点にも注意が必要です。
端数が出た場合の調整方法と注意点
持分割合を計算すると、きれいな数字にならないことがあります。例えば、87.5%のような端数が出ることがあります。登記上は分数で表記されるため、87.5%は「8分の7」と表記されます。
しかし、時には端数を調整して、よりシンプルな割合にしたいと考える方もいるでしょう。例えば、87.5%を90%に、12.5%を10%に調整するといった具合です。
このような調整を行う場合、調整幅が大きいと贈与税の問題が生じる可能性があります。具体的には、調整により実質的に持分が増える方は、増えた分の持分に相当する金額を、他の共有者から贈与されたと見なされる可能性があるのです。
例えば、持分87.5%の人の持分を90%に増やすと、2.5%分の持分が増えます。4,000万円の不動産であれば、2.5%は100万円に相当します。この場合、100万円分の贈与があったと見なされる可能性があるのです。
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、調整幅が小さければ贈与税は発生しませんが、大きな調整を行う場合は注意が必要です。
親から資金援助を受ける場合の持分割合
不動産購入の際に、親から資金援助を受けるケースも少なくありません。この場合の持分割合の決め方は、資金援助の形態によって異なります。
- 贈与の場合:親から贈与された資金は、贈与を受けた人の自己資金と見なします。例えば、子が親から500万円の贈与を受け、それを頭金に充てた場合、その500万円は子の負担額に含まれます。
- 借入の場合:親からお金を借りた場合、その借入金は子の負担額になります。親は共有者にはなりません。
- 出資の場合:親が不動産購入に出資する場合、親も共有者になります。出資額に応じた持分割合が親に発生します。
例えば、5,000万円の不動産を購入する際に、夫が住宅ローン3,000万円、妻が貯金1,000万円、夫の親が贈与で1,000万円を負担するとします。この場合、親からの贈与1,000万円は夫の負担額に含まれますので、持分割合は次のようになります。
夫の負担額 = 3,000万円(ローン)+ 1,000万円(親からの贈与)= 4,000万円 妻の負担額 = 1,000万円(貯金)
夫の持分割合 = 4,000万円 ÷ 5,000万円 = 0.8 = 80% 妻の持分割合 = 1,000万円 ÷ 5,000万円 = 0.2 = 20%
このように、親からの資金援助の形態によって、持分割合の計算方法が変わってきます。特に出資の場合は親も共有者になりますので、将来の相続などを考慮して慎重に検討する必要があります。
相続時の共有持分の決め方

法定相続分とは何か
親や配偶者が亡くなった場合、その財産は相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合、法律で定められた割合(法定相続分)に従って財産が分配されるのが原則です。
法定相続分は、相続人の続柄によって以下のように定められています。
- 配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子1/2(複数の子がいる場合は均等に分ける)
- 配偶者と親が相続人の場合:配偶者2/3、親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
例えば、夫が亡くなり、妻と2人の子供が相続人となる場合、妻の相続分は1/2、子供2人の相続分はそれぞれ1/4となります。
法定相続分による持分割合の計算例
具体的な例で見てみましょう。
父が所有していた6,000万円の不動産を、母と子供2人(長男と長女)が相続するケースを考えます。この場合、法定相続分に基づいた持分割合は以下のようになります。
母(配偶者)の持分割合 = 1/2 = 50% 長男の持分割合 = (1/2) ÷ 2 = 1/4 = 25% 長女の持分割合 = (1/2) ÷ 2 = 1/4 = 25%
このように、法定相続分に基づいて持分割合が決まります。登記上は、母の持分は2分の1、長男と長女の持分はそれぞれ4分の1と表記されます。
遺言書がある場合の持分割合
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していた場合、その内容に従って財産が分配されます。遺言書があれば、法定相続分とは異なる割合で相続することが可能です。
例えば、父が「不動産は長男に7割、長女に3割相続させる」という遺言を残していた場合、母の同意があれば、長男の持分割合は70%、長女の持分割合は30%となります。
ただし、遺言があっても、配偶者や子供には「遺留分」と呼ばれる最低限受け取れる相続分があります。遺留分を侵害するような遺言は、遺留分権利者が「遺留分侵害額請求」をすることで、一部修正される可能性があります。
相続放棄があった場合の持分計算
相続人の中に相続放棄をする人がいた場合、その人の分は他の相続人に分配されます。
例えば、父が亡くなり、母と子供2人(長男と長女)が相続人となる場合で、長女が相続放棄したとします。この場合、長女の相続分は消滅し、母と長男で相続することになります。
母(配偶者)の持分割合 = 1/2 = 50% 長男の持分割合 = 1/2 = 50%(長女の分も含む)
このように、相続放棄があると、他の相続人の持分割合が変わることになります。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
共有持分で注意すべきポイント
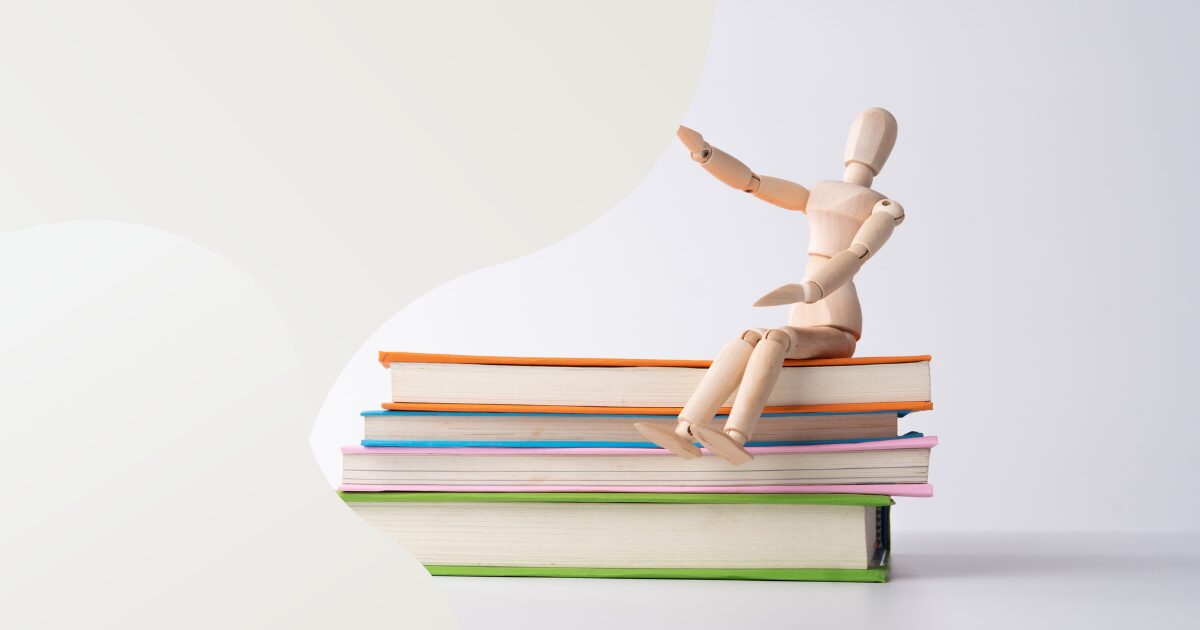
税金面での注意点(贈与税など)
共有持分を決める際に最も注意すべきポイントの一つが税金の問題です。特に、以下の点に注意が必要です。
- 贈与税:出資額と持分割合が一致していない場合、持分割合が多い人は、実質的に贈与を受けたと見なされ、贈与税が課される可能性があります。
- 不動産取得税:共有持分を取得する際に、その持分割合に応じて不動産取得税が課されます。
- 固定資産税:共有不動産の固定資産税は、原則として共有者全員が連帯して納税する義務がありますが、実務上は持分割合に応じて分担することが多いです。
贈与税については、年間110万円の基礎控除がありますので、贈与と見なされる金額がこの範囲内であれば問題ありません。また、親から子への住宅取得資金の贈与については、一定の条件下で非課税措置が受けられる場合もあります。
住宅ローン控除に関する注意点
住宅ローン控除を最大限活用するためにも、共有持分の決め方は重要です。住宅ローン控除は、ローンの借入者が自分の持分に対応する部分についてのみ受けられます。
例えば、夫婦でペアローンを組み、夫の持分が70%、妻の持分が30%の場合、夫は自分のローン残高のうち70%に対応する部分について、妻は自分のローン残高のうち30%に対応する部分について、それぞれ控除を受けることができます。
一方、持分割合がローンの借入割合と一致していない場合、住宅ローン控除を十分に活用できない可能性があります。例えば、夫が100%ローンを借り入れているにもかかわらず、持分が80%しかない場合、残りの20%部分については控除を受けられません。
共有持分を間違えて設定した場合のリスク
共有持分を間違えて設定してしまった場合、以下のようなリスクが考えられます。
- 贈与税の追徴:税務調査などで、出資額と持分割合の不一致が指摘され、贈与税が追徴される可能性があります。
- 住宅ローン控除の一部否認:持分割合とローンの借入割合が一致していない場合、住宅ローン控除の一部が否認される可能性があります。
- 将来の売却時のトラブル:持分割合が実態と異なると、将来の売却時に共有者間でトラブルが発生する可能性があります。
こうしたリスクを回避するためにも、共有持分は購入費用の負担割合に合わせて正確に設定することが重要です。
持分変更の方法と手続き
共有持分を変更したい場合は、「持分移転登記」の手続きが必要です。これは、ある共有者から別の共有者に持分の一部または全部を移転する手続きです。
持分変更の主な方法には、以下のものがあります。
- 贈与:ある共有者が他の共有者に持分を贈与する方法です。この場合、贈与税が発生する可能性があります。
- 売買:ある共有者が他の共有者に持分を売却する方法です。適正な価格で取引する必要があります。
- 共有物分割:裁判所の判断により共有関係を解消し、持分を再配分する方法です。
持分変更の登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。必要な書類や手続きの流れについては、専門家に相談することをおすすめします。
共有持分にまつわるよくある質問

共有持分を後から変更できるか
共有持分は、共有者間の合意があれば後から変更することができます。ただし、変更には「持分移転登記」の手続きが必要であり、贈与税などの税金問題が生じる可能性があります。
持分を増やす側の共有者は、増加分の持分に相当する金額を、減らす側の共有者に支払うことが原則です。この支払いがない場合、贈与と見なされ、贈与税の対象となる可能性があります。
また、住宅ローン控除を受けている場合、持分変更により控除額が変わる可能性がありますので、そのリスクも考慮する必要があります。
共有持分を売却したい場合の手続き
共有持分を売却する方法には、以下のようなものがあります。
- 他の共有者に売却:最も円滑に進みやすい方法です。他の共有者が購入に応じれば、共有関係がシンプルになります。
- 第三者に売却:他の共有者が購入に応じない場合、第三者に売却することも可能です。ただし、不動産業者や一般の購入希望者は、共有持分のみの購入には消極的なことが多いです。
- 共有持分専門の買取業者に売却:共有持分を専門に買い取る業者もあります。一般的な不動産買取よりも価格は低くなりがちですが、確実に売却できる可能性が高まります。
共有持分を売却する際は、他の共有者に優先的に購入の意思を確認するのがマナーです。また、売却価格は、不動産全体の価値に持分割合を乗じた金額を基準に考えるのが一般的です。
まとめ
共有持分の決め方と計算方法について、購入時と相続時のケースに分けて解説しました。共有持分を正しく設定することで、思わぬ税金トラブルを避け、住宅ローン控除などの恩恵を最大限に受けることができます。
購入時の共有持分は、基本的に購入費用の負担割合に合わせて決めるのが原則です。住宅ローンを利用する場合は、ローンの種類(ペアローンか連帯保証型か)によって計算方法が変わることに注意しましょう。
相続時の共有持分は、法定相続分に基づいて決まるのが原則ですが、遺言書がある場合はその内容が優先されます。また、相続放棄があった場合は、他の相続人の持分割合が変わります。
共有持分は、税金や住宅ローン控除、将来の売却などに影響する重要な要素です。不安なことがあれば、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。これから不動産を共同購入する方、相続で共有持分を取得する方は、この記事を参考に、適切な持分割合を設定してください。
参考資料・相談窓口
共有持分について詳しく知りたい方や、具体的な相談をしたい方のために、参考となる相談窓口をご紹介します。
- 法律相談:司法書士、弁護士に相談することで、持分設定や登記手続きに関する法的なアドバイスを受けることができます。
- 税務相談:税理士に相談することで、持分設定に伴う税金問題や、住宅ローン控除の最適化などについてアドバイスを受けることができます。
- 不動産相談:宅地建物取引士や不動産コンサルタントに相談することで、共有持分の実務的な側面についてアドバイスを受けることができます。
- 法テラス:日本司法支援センター(法テラス)では、法律相談を無料または低額で受けることができる場合があります。
- 地方自治体の相談窓口:多くの自治体では、不動産や相続に関する無料相談会を定期的に開催しています。お住まいの自治体のホームページなどで確認してみましょう。
今すぐ実行できる3つのアクション
- 持分割合を確認する:すでに共有不動産をお持ちの方は、登記簿謄本で現在の持分割合を確認しましょう。負担額と大きく異なる場合は、専門家に相談することを検討してください。
- 負担額の記録を残す:これから不動産を共同購入する方は、誰がいくら負担したかの記録をしっかり残しておきましょう。領収書や振込記録など、客観的な証拠を保存することが重要です。
- 専門家に相談する:共有持分の設定や変更を検討している方は、税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。特に、税金面のリスクや住宅ローン控除の最適化については、専門的なアドバイスが役立ちます。
共有持分は一度設定すると変更には手間とコストがかかりますので、最初から正しく設定することが大切です。この記事が皆さんの正しい共有持分設定の助けになれば幸いです。

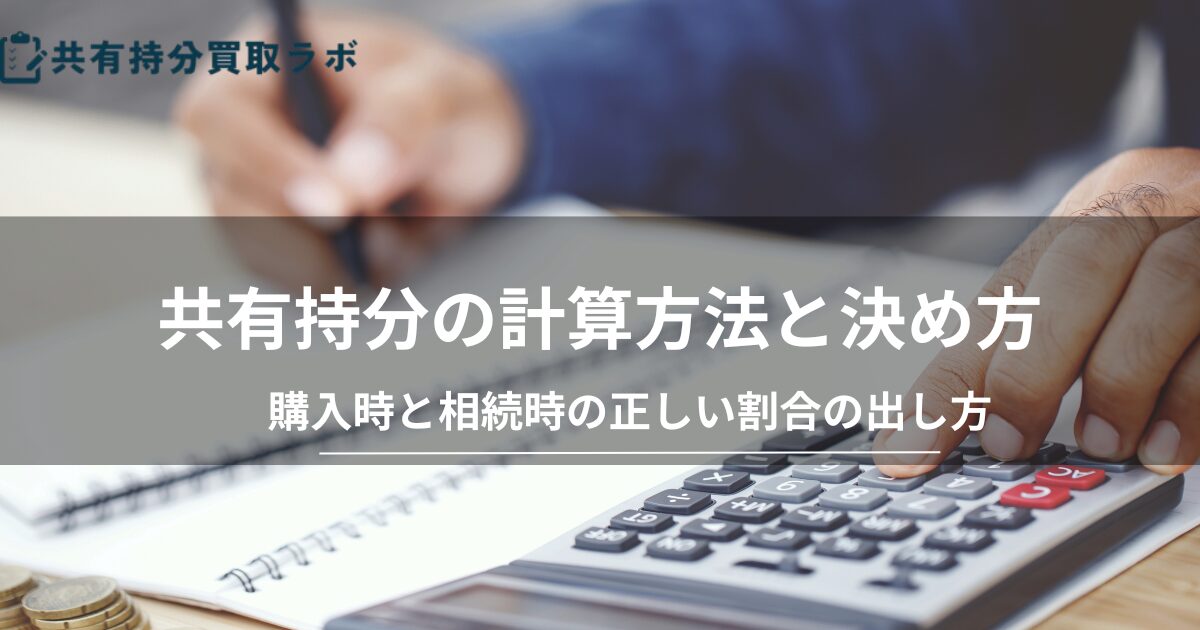

コメント