不動産の共有持分を放棄したいと考えているものの、手続きや費用について不安を感じている人もいるのではないでしょうか?共有持分の放棄は、一見シンプルに思えても、実際には様々な注意点や落とし穴が存在します。
この記事では、共有持分放棄に関する基本的な知識から、かかる費用、手続きの流れ、そして知っておくべき重要な注意点までを、初心者にもわかりやすく解説します。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有持分放棄とは?そもそもの基本を解説

「共有持分」とは、一つの不動産を複数の人で所有している状態で、それぞれが持っている所有権の割合のことです。たとえば、親から相続した実家を兄弟3人で共有している場合、各人が「3分の1の共有持分」を持つことになります。
「共有持分放棄」とは、自分が持っているこの所有権の割合(持分)を手放すことを意味します。放棄すると、その持分は他の共有者に自動的に分配されます。
共有持分を放棄したいと考える主な理由としては以下のようなものがあります。
- 共有者間でトラブルが発生し、関わりたくなくなった
- 不動産の維持費や固定資産税の負担が重い
- 遠方に住んでいて不動産の管理が難しい
- 不動産自体に価値がなく、負担になっている
ここで重要なのは、「相続放棄」と「共有持分放棄」の違いです。両者は似ているようで全く異なる手続きです。相続放棄は相続財産全体を放棄するもので、相続の発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。一方、共有持分放棄は、すでに自分が所有している特定の不動産の持分だけを放棄するもので、法務局での登記手続きが必要になります。
誰でもわかる放棄のプロセス

共有持分放棄は「単独行為」と呼ばれるもので、自分の意思表示だけで効力が発生します。つまり、他の共有者の同意や許可を得る必要はなく、自分の判断だけで放棄することができます。
しかし、実際には登記手続きを完了するためには他の共有者の協力が必要になります。これが後に説明する大きな問題点の一つです。
放棄した持分はどうなるのでしょうか?民法によれば、放棄された持分は他の共有者に自動的に分配されます。
たとえば、A、B、Cの3人で土地を共有していて、それぞれの持分が均等(各3分の1)だったとします。ここでAが持分を放棄すると、AのJ分の1の持分はBとCに均等に分配されます。その結果、BとCはそれぞれ2分の1の持分を持つことになります。
このしくみから、共有持分放棄は「早い者勝ち」と言われることがあります。なぜなら、複数の共有者が順番に持分を放棄していくと、最後に残った人が全ての持分(つまり不動産全体の所有権)を引き受けることになるからです。
例えば先ほどの例で、Aが放棄した後、Bも放棄すると、Bの持分はすべてCに移り、Cが単独所有者となります。そして、単独所有者になった人は、もはや持分を「放棄」することはできません(所有権全体の放棄は別の手続きになります)。
共有持分放棄にかかる費用の全容|驚きの金額とは?

共有持分放棄には、意外と多くの費用がかかります。主な費用項目は以下の通りです。
1. 登録免許税
登記手続きに必要な税金です。計算方法は以下のとおりです。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 放棄する持分の割合 × 税率(2%)
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産で、3分の1の持分を放棄する場合: 1,000万円 × (1/3) × 0.02 = 約6.7万円が登録免許税としてかかります。
2. 司法書士への報酬
共有持分放棄の登記手続きを司法書士に依頼する場合、一般的に5万円〜10万円程度の報酬が発生します。複雑なケースや共有者が多い場合はさらに高額になることもあります。
3. 書類取得費用
登記手続きに必要な書類(登記簿謄本、住民票、印鑑証明書など)の取得費用として、合計で3,000円〜5,000円程度かかります。固定資産税評価証明書の取得なども必要になる場合があります。
4. その他の費用
場合によっては、以下のような追加費用も発生します。
- 内容証明郵便の費用(他の共有者が協力しない場合):1,000円〜2,000円程度
- 登記引取請求訴訟の費用(後述):裁判所への収入印紙代や弁護士費用など、場合によっては数十万円規模になることも
共有持分を放棄する側だけでなく、放棄された持分を引き継ぐ側(他の共有者)にも費用が発生する可能性があります。特に「みなし贈与」として贈与税が課税されるケースがあるので注意が必要です。
放棄された持分の価値が高い場合、それを受け取る側は贈与税の対象となることがあります。基礎控除(年間110万円)を超える部分には贈与税がかかるので、高額な不動産の場合は税金面での検討も重要です。
共有持分放棄の手続き方法|ステップごとの完全ガイド

共有持分放棄の手続きは、大きく分けて以下のステップで進みます。
ステップ1:持分放棄の意思表示
まず、自分が持分を放棄する意思があることを他の共有者に伝えます。口頭でも法的には有効ですが、後のトラブル防止のため、書面で伝えるのが安全です。特に共有者との関係が良好でない場合は、内容証明郵便を使って通知するとよいでしょう。
ステップ2:必要書類の準備
持分放棄の登記に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 持分放棄証書(自分が持分を放棄することを証明する書類)
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産税評価証明書(場合によって必要)
ステップ3:他の共有者との協議
持分放棄の登記は、放棄する人(登記義務者)と放棄された持分を受け取る人(登記権利者=他の共有者)の共同申請となります。そのため、他の共有者に登記手続きへの協力を依頼します。
具体的には、他の共有者にも登記申請書に署名・押印してもらったり、必要書類(印鑑証明書など)を提出してもらったりする必要があります。
ステップ4:登記申請
必要書類がすべて揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記を申請します。登録免許税を納付し、申請書と必要書類を提出します。
自分で手続きを行うこともできますが、書類の不備などで申請が受理されないリスクもあります。確実に手続きを行うためには、司法書士に依頼するのが安心です。
ステップ5:登記完了の確認
登記申請から約1〜2週間後、登記が完了します。登記完了後は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して内容を確認しましょう。これで共有持分放棄の手続きは完了です。
【要注意】共有持分放棄で失敗しないための3つの重要ポイント

共有持分放棄で失敗しないために、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
ポイント1:登記が完了しないと放棄の効果は対外的に認められない
共有持分の放棄は、意思表示だけで法的には有効ですが、登記を完了しなければ対外的(第三者に対して)には効力が認められません。登記が完了しないと以下のようなリスクがあります。
- 固定資産税の支払い義務が継続する
- 不動産から発生する損害賠償責任を負う可能性がある
- 将来的に相続が発生した場合、相続人が混乱する
ポイント2:「みなし贈与」として課税されるケース
共有持分放棄は、場合によっては税務上「みなし贈与」と判断されることがあります。つまり、持分を受け取った側(他の共有者)に贈与税が課税される可能性があるのです。
特に親族間での持分放棄の場合、税務署が「贈与の意図があった」と判断するリスクが高まります。高額な不動産の場合は、事前に税理士に相談するのが賢明です。
ポイント3:一度放棄すると取り消せない
共有持分の放棄は、一度行うと原則として取り消すことができません。「やっぱり放棄をやめたい」と思っても、他の共有者が同意しない限り元に戻すことはできません。
放棄を決断する前に、十分に考慮し、可能であれば専門家(司法書士や弁護士)に相談することをおすすめします。
共有者が協力してくれない!そんなときの具体的な解決策

共有持分放棄の大きな問題点として、登記手続きには他の共有者の協力が必要なことが挙げられます。では、他の共有者が協力してくれない場合、どうすればよいのでしょうか?
内容証明郵便で意思表示を証明する
まず、内容証明郵便を使って、持分放棄の意思があることを正式に通知します。この郵便は、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるものです。
内容証明郵便には以下の内容を記載します。
- 持分放棄の意思表示
- 対象となる不動産の情報(所在地、登記簿上の表示など)
- 登記手続きへの協力依頼
- 協力しない場合は法的手段を取る可能性があること
「登記引取請求訴訟」を提起する
内容証明郵便を送っても協力が得られない場合は、「登記引取請求訴訟」という裁判を起こすことができます。これは、登記手続きに必要な協力を法的に求める訴訟です。
登記引取請求訴訟を起こすには、以下の書類を裁判所に提出します。
- 訴状
- 持分放棄の意思表示を証明する資料(内容証明郵便の控えなど)
- 対象不動産の登記簿謄本
- その他、必要に応じた証拠書類
訴訟には費用と時間がかかります。裁判所に納める収入印紙代(訴額によって変動)、弁護士に依頼する場合は弁護士費用、さらに訴訟が長引けば追加費用も発生します。一般的に、訴訟費用だけで10万円〜30万円程度、弁護士費用を含めると数十万円になることもあります。
また、訴訟には通常数ヶ月〜1年程度の時間がかかります。共有者が複数いる場合、それぞれに対して訴訟を起こす必要があるため、さらに複雑になることもあります。
訴訟以外の解決策
訴訟は費用と時間がかかるため、他の解決策も検討する価値があります。例えば:
- 第三者(司法書士や弁護士など)に間に入ってもらい、交渉を進める
- 共有持分を放棄する代わりに小額の金銭を支払うことを提案する
- 後述する代替策(共有持分の売却など)を検討する
共有持分放棄より良い選択肢?専門家が教える賢い対処法
共有持分放棄には様々な問題点やハードルがあることがわかりました。では、他にどのような選択肢があるのでしょうか?ここでは、共有持分放棄の代替策として考えられる方法を紹介します。
共有持分の売却という選択肢
共有持分を放棄するのではなく、売却する方法があります。売却先としては以下が考えられます。
- 他の共有者への売却:最も自然な選択肢です。他の共有者が購入してくれれば、共有関係から離脱でき、さらに対価を得ることができます。
- 第三者への売却:他の共有者が購入してくれない場合、第三者に売却することも可能です。ただし、共有持分は単独所有の不動産よりも価値が低く評価される傾向があり、買い手を見つけるのが難しいことがあります。
- 専門業者への売却:共有持分を専門に買い取る業者もあります。市場価格よりは安くなりますが、確実に売却でき、手続きもスムーズです。
専門業者による共有持分買取サービスの活用法
最近は、共有持分を専門に買い取る業者が増えています。これらの業者は、通常の不動産市場では売りにくい共有持分を買い取り、様々な方法で活用します。
専門業者を利用するメリットは以下の通りです。
- 確実に売却できる(買い手探しの手間がない)
- 手続きがスムーズ(業者側が手続きをサポートしてくれることが多い)
- 即金で現金化できる
- 他の共有者との交渉や連絡が不要
ただし、買取価格は市場価格の50%以下になることも多いため、価格面では不利になります。それでも、持分放棄の手続きの手間や費用を考えると、総合的にはメリットがある場合も少なくありません。
共有物分割請求という方法
共有関係を解消する別の方法として、「共有物分割請求」という裁判があります。これは、共有物を分割するか、または売却して代金を分配することを求める裁判です。
共有物分割請求のメリットは、共有関係を完全に解消できることです。デメリットは、裁判に時間と費用がかかることと、他の共有者との関係が悪化する可能性があることです。
どの選択肢が自分に合っているかの判断基準
どの方法を選ぶべきかは、以下の要素を考慮して判断するとよいでしょう。
- 不動産の価値(高額なら売却の方が得な場合が多い)
- 他の共有者との関係性(良好なら話し合いで解決できる可能性が高い)
- 時間的猶予(急いでいるなら専門業者への売却が早い)
- 費用負担の可能性(放棄や裁判には予想以上の費用がかかることも)
- 税金の影響(各方法で税金の扱いが異なる)
迷った場合は、司法書士や弁護士、不動産の専門家に相談することをおすすめします。初回相談は無料の事務所も多いので、複数の専門家の意見を聞いてみるとよいでしょう。
まとめ:共有持分放棄を成功させるための実践的アドバイス
ここまで、共有持分放棄についての基本知識、費用、手続き、注意点、そして代替策について詳しく解説してきました。最後に、共有持分放棄を考えている方へ、実践的なアドバイスを3つご紹介します。
1. 事前に専門家に相談する
共有持分放棄は一見シンプルに思えても、実際には法律的な知識や経験が必要な手続きです。失敗すると時間と費用の無駄になるだけでなく、思わぬトラブルを招くことも。司法書士や弁護士など、不動産登記の専門家に事前に相談することで、多くの失敗を防ぐことができます。
初回相談が無料の事務所も多いので、まずは気軽に相談してみましょう。相談する際は、不動産の登記簿謄本や固定資産税の納税通知書など、基本的な資料を用意しておくとスムーズです。
2. 他の共有者との関係構築を大切にする
共有持分放棄の最大の難関は、登記手続きに他の共有者の協力が必要なことです。他の共有者との関係が悪化していると、手続きが難航したり、裁判に発展したりする可能性があります。
可能であれば、持分放棄の意思を伝える前に、他の共有者との関係改善を図りましょう。また、持分放棄が他の共有者にもたらすメリット(固定資産税の負担割合の変化など)を説明し、協力を得やすくする工夫も重要です。
3. 放棄以外の選択肢も検討する
共有持分放棄は、共有関係から抜け出す一つの方法にすぎません。場合によっては、売却や共有物分割請求など、他の方法の方がメリットが大きいこともあります。
特に不動産に一定の価値がある場合は、放棄よりも売却を検討した方が経済的に有利になることが多いです。選択肢を広げて検討することで、最適な解決策を見つけやすくなります。
今すぐ実行できる3つのアクション
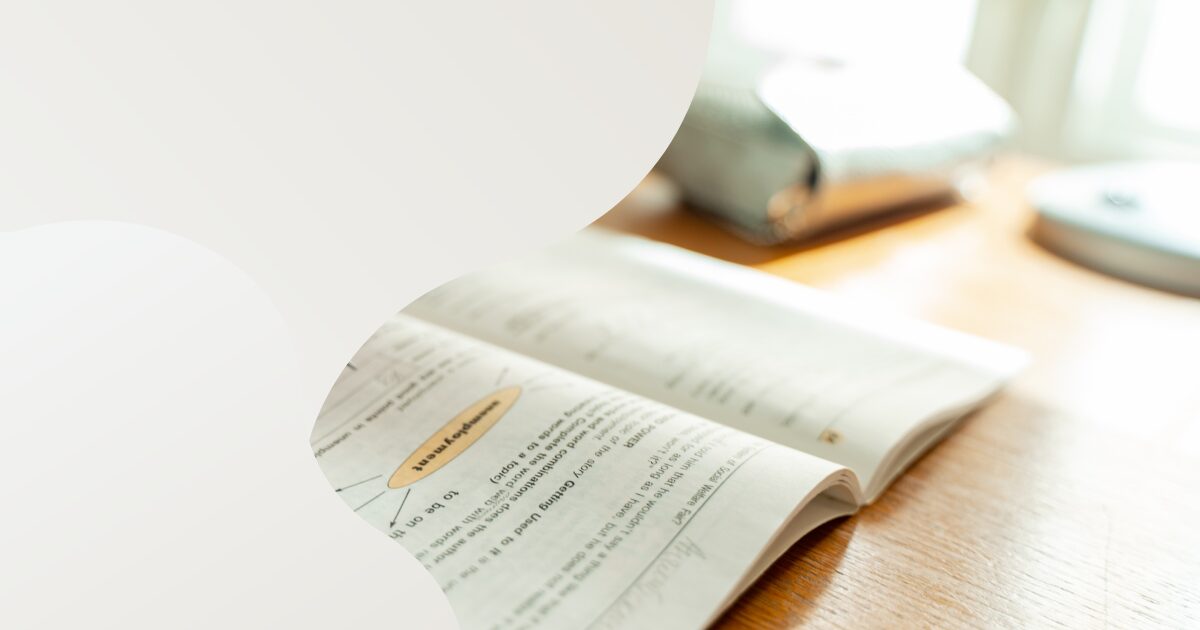
この記事を読んだ後、具体的に何をすべきか迷っている方のために、今すぐ実行できる3つのアクションをご提案します。
- 不動産の価値を確認する:まずは自分の共有持分がどれくらいの価値があるのか知ることが大切です。法務局で登記簿謄本を取得し、市区町村役場で固定資産税評価証明書を入手しましょう。これらの資料を基に、不動産会社などで簡易査定を依頼することもできます。
- 他の共有者と話し合いの場を設ける:メールや電話ではなく、可能であれば直接会って、共有不動産についての今後をじっくり話し合いましょう。持分放棄の意向を伝えるとともに、他の共有者の意見や希望も聞くことが重要です。
- 専門家への相談予約を入れる:司法書士や弁護士事務所に連絡し、共有持分についての相談予約を入れましょう。初回無料相談を行っている事務所も多いので、複数の専門家の意見を聞くことをおすすめします。相談時には、登記簿謄本や固定資産税納税通知書などの資料を持参すると具体的なアドバイスが得られます。
共有持分の問題は一朝一夕には解決しない場合もありますが、適切な知識と対策を持って臨めば、最良の結果を得ることができます。この記事が皆さんの共有持分放棄についての理解を深め、最適な判断をする一助となれば幸いです。
よくある質問(FAQ)

- 共有持分放棄は税務署に届け出る必要がありますか?
共有持分放棄自体に税務署への届出義務はありませんが、放棄された持分が他の共有者に移転することで「みなし贈与」と判断される場合があります。その場合、持分を受け取った側に贈与税申告の必要が生じる可能性があります。
- 共有者全員が持分放棄することはできますか?
共有者全員が持分を放棄することはできません。少なくとも1人は所有者として残る必要があります。全員が所有権から離れたい場合は、国庫に帰属させる手続き(所有権放棄)を検討する必要がありますが、この手続きは非常に複雑で、実現が難しいケースが多いです。
- 共有持分放棄の登記手続きはどのくらいの期間で完了しますか?
必要書類がすべて揃っていれば、登記申請から完了まで通常1〜2週間程度です。ただし、他の共有者の協力が得られない場合や、登記引取請求訴訟が必要になった場合は、数ヶ月〜1年以上かかることもあります。

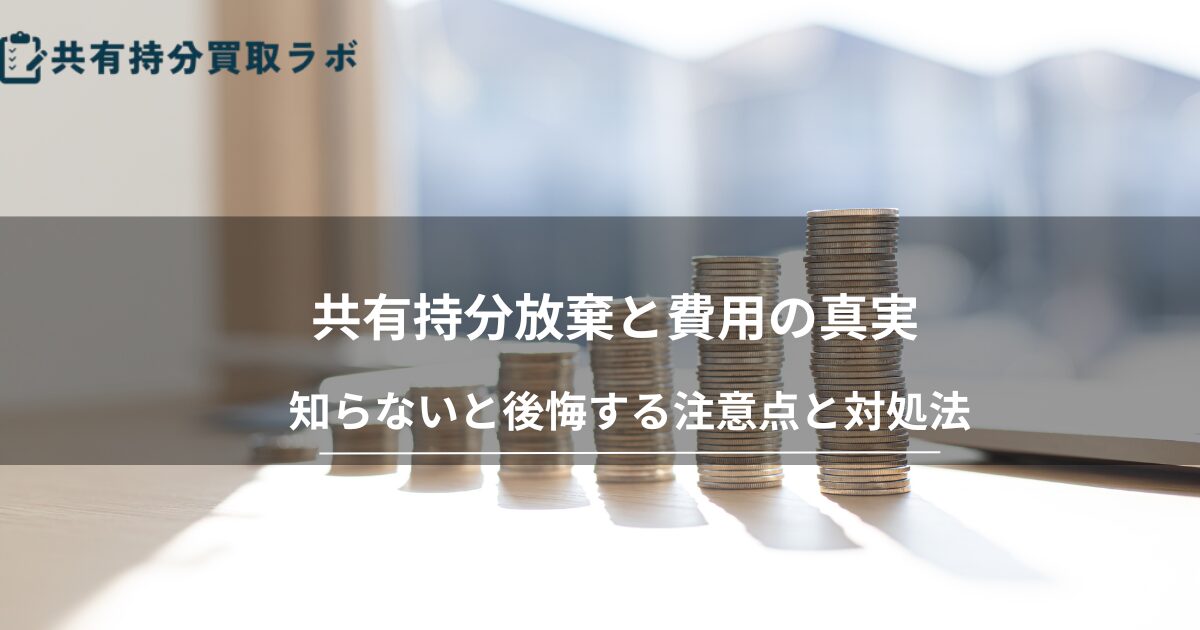

コメント