不動産を複数の人で共同所有している場合、あなたはその不動産の「共有持分」を持っていることになります。たとえば、両親から相続した実家を兄弟3人で共有している場合、それぞれが3分の1ずつの共有持分を持っていることになります。
この共有持分は、あなたの財産の一部として扱われます。そのため、もしあなたに借金などの債務があり、返済が滞った場合、債権者(お金を貸している側)はあなたの共有持分を差し押さえて、競売にかけることができるのです。
差し押さえとは、債務者(お金を借りている側)の財産を強制的に押さえることで、競売とはその財産を公開の場で売却することを意味します。この過程は通常、以下のような流れで進みます。
- 債権者が裁判所に申立てを行い、差押命令を取得する
- 差押命令が債務者(あなた)に通知される
- 法的手続きを経て、共有持分が競売にかけられる
- 競売で落札された代金から債務の返済に充てられる
この記事では、共有持分の差押えと競売のリスクを理解し、それを回避するための具体的な方法について詳しく解説します。特に財産を守るための緊急対策に焦点を当て、実践的なアドバイスを提供します。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有持分の差押えが起こる主な原因

借金の返済ができなくなった場合(債務不履行)
最も一般的な原因は、ローンやクレジットカードの返済ができなくなることです。たとえば、住宅ローンの返済が3ヶ月以上滞ると、金融機関は法的手続きを開始することがあります。2023年の調査によると、差押えに至るケースの約68%がこの債務不履行によるものとされています。
税金の滞納による差押え
固定資産税や所得税などの税金を長期間滞納すると、税務署や自治体が差押えを行うことがあります。特に固定資産税は不動産に直接関わる税金のため、滞納すると共有持分が差押えの対象になりやすいです。税金滞納による差押えは全体の約15%を占めています。
裁判の判決による強制執行
民事裁判で敗訴し、損害賠償金などの支払いを命じられた場合、その支払いができないと共有持分が差し押さえられることがあります。この場合、判決確定後すぐに強制執行の手続きが始まることもあるため、特に注意が必要です。
実際の事例から学ぶ
Aさん(45歳)は両親から相続した実家を姉と共有していました。Aさんは事業に失敗して多額の債務を抱え、返済が滞ったため、Aさんの共有持分(2分の1)が差し押さえられました。その結果、知らない第三者が競売で持分を購入し、家を売却するよう求めてきたため、最終的に姉も住み慣れた実家を出ざるを得なくなりました。
このような事態を防ぐためには、事前の対策が非常に重要です。次のセクションでは、共有持分の差押えと競売がもたらすリスクについて詳しく見ていきましょう。
共有持分の差押えと競売によるリスク

財産的な損失
共有持分が競売にかけられると、通常は市場価値よりもかなり安い価格で売却されてしまいます。一般的な不動産取引に比べて、競売物件は平均で市場価値の6〜7割程度の価格でしか売れないことが多いのです。これはつまり、本来得られるはずだった財産の3〜4割が失われることを意味します。
居住権の喪失リスク
あなたが住んでいる家の共有持分が競売で第三者に落札された場合、新しい共有者から立ち退きを求められる可能性があります。日本の法律では、共有物の分割請求権というものがあり、共有者はいつでも共有物の分割(つまり売却など)を請求できるのです。これにより、長年住み慣れた家から出ていかなければならなくなるケースも少なくありません。
他の共有者への影響
一人の共有者の持分が差し押さえられると、他の共有者も大きな影響を受けます。先ほど触れた「分割請求」により、他の共有者も意に反して不動産全体の売却を強いられる可能性があるのです。また、新たな共有者との関係構築も必要になり、精神的な負担が増加します。
信用情報への悪影響
差押えを受けると、その情報が信用情報機関に記録されることがあります。これにより、今後数年間にわたって新たなローンを組むことが難しくなったり、クレジットカードの審査に通らなくなったりする可能性があります。信用情報の回復には通常5〜7年程度かかるとされています。
精神的・社会的影響
財産が差し押さえられるという経験は、精神的にも大きな負担となります。不安やストレス、恥辱感などを感じる人も多く、これが健康問題につながることもあります。また、家族や親族との関係が悪化するケースも見られます。
これらのリスクを考えると、共有持分の差押えは何としても避けたいものです。次のセクションでは、差押えを防ぐための事前対策について詳しく解説します。
差押えを防ぐための事前対策

適切な債務管理と返済計画
差押えを防ぐ最も基本的な方法は、債務を適切に管理し、計画的に返済することです。収入に見合った借入額を守り、無理のない返済計画を立てることが大切です。
特に注意すべきは、複数の借入先がある場合です。各債務の金利や返済期限を整理し、優先順位をつけて返済するようにしましょう。収入の20〜30%以上を債務の返済に充てている場合は、すでに危険信号と考えられます。
もし返済が難しくなってきたと感じたら、すぐに債権者に連絡して返済条件の変更(リスケジュール)を相談することが重要です。多くの金融機関は、早期に相談があれば柔軟に対応してくれることが多いのです。
共有名義の見直し
共有持分のリスクを減らす方法として、不動産の所有形態を見直すことも検討すべきです。例えば、以下のような選択肢があります。
家族信託の活用: 信頼できる家族に財産を信託することで、債権者からの差押えリスクを軽減できることがあります。ただし、これには専門家のアドバイスが必要です。
共有持分の贈与: 債務リスクが生じる前に、信頼できる家族に共有持分の一部を贈与しておくという方法もあります。ただし、贈与税の問題や詐害行為取消権(債権者を害する目的での財産処分を無効にできる権利)の問題もあるため、専門家に相談することが必要です。
担保設定の工夫
もし借入が必要な場合、共有持分以外の財産を担保にする可能性を検討することも一つの方法です。例えば、預金や有価証券、他の単独所有の不動産などを担保にすることで、共有持分への差押えリスクを減らせる場合があります。
専門家への早期相談の重要性
財産管理や債務問題については、早い段階で専門家(弁護士や司法書士、ファイナンシャルプランナーなど)に相談することが非常に重要です。専門家は、あなたの状況に応じた最適な対策を提案してくれるでしょう。
特に、以下のような状況に当てはまる場合は、すぐに専門家に相談することをお勧めします:
- 毎月の返済額が収入の30%を超えている
- 複数の借入先から催促を受けている
- 税金の滞納が続いている
- 共有財産について共有者間でトラブルが発生している
専門家への相談費用は平均で初回5,000円〜30,000円程度ですが、これは差押えによる損失と比べればわずかな金額です。早めの対策が将来の大きな損失を防ぐことができるのです。
差押え通知を受けた後の緊急対応策
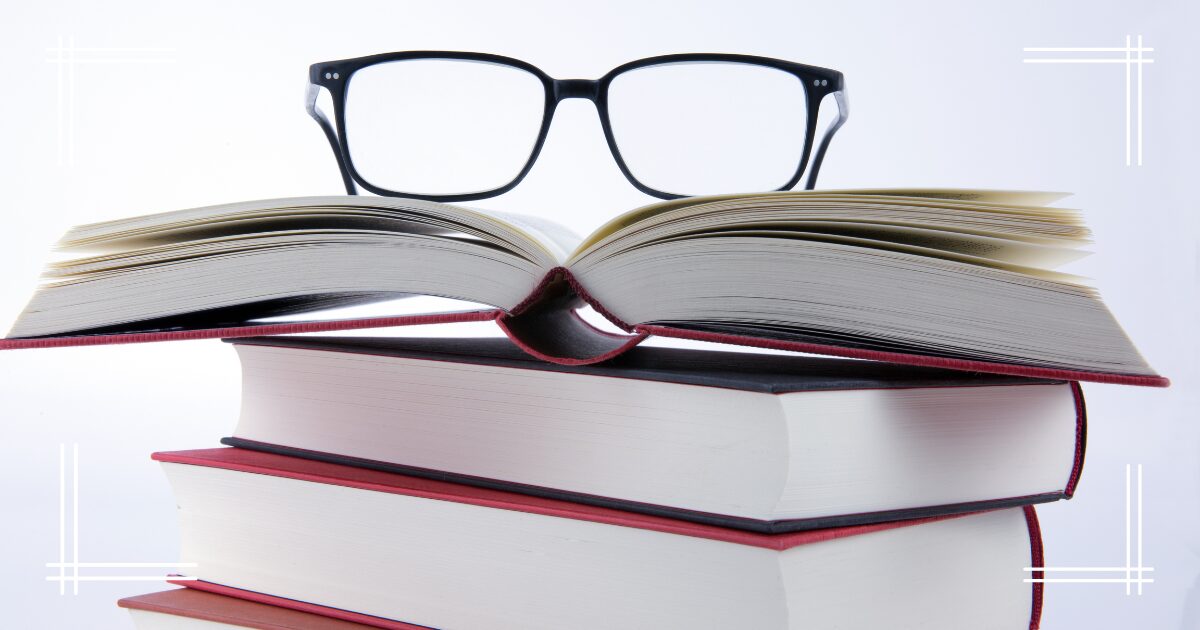
差押え通知の見方と理解
差押え通知(正式には「差押命令」や「差押通知書」)を受け取った場合、まずその内容をしっかり理解することが重要です。通知には以下のような情報が含まれています:
- 債権者(お金を貸している側)の名前と連絡先
- 差押えの対象となる財産(共有持分)の詳細
- 債務の金額と内訳
- 異議申立ての期限(通常は1〜2週間)
- 今後の法的手続きの流れ
通知書の内容がわかりにくい場合でも、慌てて放置したり無視したりしないでください。これは法的な文書であり、対応しないと状況が悪化する一方です。
即時に取るべき行動
差押え通知を受け取ったら、以下の行動をできるだけ早く取りましょう:
- 通知内容を詳しく確認し、債務の内容や金額に誤りがないか確認する
- 通知に記載されている期限(特に異議申立期限)を確認する
- 可能であれば、すぐに債権者に連絡して話し合いの機会を求める
- 専門家(弁護士や司法書士)に相談する予約を取る
- 返済のために利用可能な資金や資産を確認する
特に重要なのは、異議申立ての期限を守ることです。この期限を過ぎると、差押えに異議を唱える法的な権利を失ってしまう可能性があります。
弁護士や司法書士への相談方法
差押え通知を受け取った場合、法律の専門家に相談することが非常に重要です。専門家への相談は以下のような手順で行いましょう:
- 債務整理や強制執行に詳しい弁護士や司法書士を探す(地元の弁護士会や日本司法書士会連合会のウェブサイトで検索できます)
- 電話で初回相談の予約を取る(この際、「共有持分の差押え通知を受け取った」と明確に伝えましょう)
- 相談時には、差押え通知書や関連する借用書、返済記録などの書類を持参する
- 現在の収入や他の債務状況なども正直に伝える
初回相談の費用は法律事務所によって異なりますが、多くの場合、30分〜1時間で5,000円〜10,000円程度です。中には無料相談を実施している事務所もあります。また、法テラス(日本司法支援センター)では、収入が一定以下の方に対して無料法律相談を提供しています。
債権者との交渉テクニック
専門家のアドバイスを受けながら、債権者と直接交渉することも重要です。交渉の際には以下のポイントを心がけましょう:
- 誠実な態度で臨み、逃げも隠れもしないことを示す
- 現在の財政状況を正直に説明する
- 具体的な返済プランを提案する
- 分割払いや返済期間の延長など、柔軟な対応を求める
- 交渉内容は必ず書面で残す
特に効果的なのは、一部でも即時に支払いを行うことです。例えば、債務総額の10〜20%程度を即時に支払い、残りを分割払いにするという提案は、債権者に受け入れられやすいとされています。
交渉は必ずしも成功するとは限りませんが、試みる価値は十分にあります。次のセクションでは、もし交渉が難しい場合に検討すべき、競売を回避するための法的手段について解説します。
競売を回避するための法的手段

請求異議の訴えについて
差押えに法的な問題がある場合、「請求異議の訴え」を起こすことで差押えを無効にできる可能性があります。これは以下のような場合に有効です:
- 既に債務を完済している
- 債務の一部または全部が時効になっている
- 差押えの対象となった財産があなたのものではない
- 差押えの手続きに法的な瑕疵(かし)がある
請求異議の訴えを起こすには、弁護士に依頼して裁判所に訴状を提出します。費用は一般的に着手金15万円〜30万円程度、成功報酬として20万円〜40万円程度が相場です。ただし、訴訟の難易度や弁護士によって大きく異なります。
執行停止の申立て
差押えや競売の手続きが進行中であっても、「執行停止の申立て」を行うことで一時的に手続きを止めることができる場合があります。これには、差押えを続行すると回復が困難な損害が生じることを証明する必要があります。
この間に債務の解決策を見つけることができれば、差押えを回避できる可能性があります。申立ての費用は、弁護士費用を含めて10万円〜15万円程度が一般的です。
第三者による買取り
競売を回避する別の方法として、親族や友人などの第三者にあなたの共有持分を買い取ってもらうという選択肢もあります。この場合、買取金額で債務を返済し、差押えを解除してもらいます。
この方法のメリットは、市場価値に近い金額で持分を売却できる可能性があることと、信頼できる人に持分が渡るため、将来的な協力が得やすいことです。ただし、適切な買取先を見つけることが難しい場合もあります。
任意売却の選択肢
競売よりもよい条件で不動産を売却する方法として「任意売却」があります。これは、債権者の同意を得て、通常の不動産取引として物件を売却する方法です。
任意売却のメリットは以下の通りです:
- 競売よりも高値で売却できることが多い(市場価値の8〜9割程度)
- 売却までの時間的猶予が得られる(通常3〜6ヶ月)
- 引越し費用の捻出が認められることがある
- 近隣に知られずに売却できる
任意売却を成功させるためには、債権者の協力が不可欠です。そのためには、誠実な姿勢で交渉に臨み、具体的な売却計画を提示することが重要です。任意売却の手続きは、不動産会社や司法書士、弁護士などの専門家に依頼すると円滑に進めることができます。
共有持分の保護に役立つ法的制度

民事再生法の活用
個人の債務問題を解決する法的手段として「個人再生」があります。これは民事再生法に基づく手続きで、債務を大幅に減額しながらも、自宅などの資産を手元に残せる可能性がある制度です。
個人再生のメリットは以下の通りです:
- 債務総額を最大で5分の1まで減額できる(例:500万円の債務が100万円になる)
- 住宅ローンがある自宅は、ローン支払いを継続することで手元に残せる(住宅資金特別条項)
- 減額された債務は3〜5年の分割払いが認められる
- 手続き開始後は債権者からの取立てが止まる
個人再生の申立てには、弁護士費用を含めて30万円〜50万円程度の費用がかかります。また、減額後の債務を確実に返済できる安定した収入があることが条件となります。
個人版私的整理ガイドライン
2011年に導入された「個人版私的整理ガイドライン」は、裁判所を通さずに債務問題を解決する方法です。主に自然災害の被災者を対象としていましたが、現在では対象が拡大されています。
この制度のメリットは、自宅を手元に残しながら債務の減額や返済条件の見直しができる点です。ただし、債権者全員の同意が必要なため、適用できるケースは限られています。
申出の費用は、原則として2万円程度の登録費用のみですが、専門家に依頼する場合は別途費用がかかります。
自己破産との比較
最終的な手段として「自己破産」があります。これは裁判所に破産を申し立て、債務の支払い義務を免除してもらう制度です。
自己破産のメリットは、ほぼすべての債務から解放されることです。一方、デメリットとしては、財産(共有持分を含む)のほとんどが換金されることや、一定期間信用情報に記録が残ることなどがあります。
自己破産の申立て費用は、弁護士費用を含めて20万円〜40万円程度が一般的です。
債務整理のメリット・デメリット
債務整理(個人再生、任意整理、自己破産など)は、共有持分の差押えを回避するための有効な手段ですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
一般的なメリットは以下の通りです:
- 債務の減額や返済条件の見直しが可能
- 手続き開始後は債権者からの取立てが止まる
- 法的な保護を受けられる
一方、デメリットとしては以下が挙げられます:
- 信用情報機関に記録が残る(5〜10年間)
- 新たな借入やクレジットカードの作成が困難になる
- 手続きに費用と時間がかかる
どの方法が最適かは個々の状況によって異なるため、必ず専門家に相談して判断することが重要です。
専門家の選び方と相談時のポイント

弁護士の選定基準
共有持分の差押え問題に対応するためには、適切な専門家を選ぶことが重要です。弁護士を選ぶ際は、以下のポイントを考慮しましょう:
- 債務整理や不動産問題の経験が豊富か
- 初回相談の費用や全体の費用体系が明確か
- 説明がわかりやすく、質問に丁寧に答えてくれるか
- 事務所の対応が迅速か
- 口コミや評判はどうか
大手の事務所ではなく、個人の事情に寄り添った対応をしてくれる中小規模の事務所が適している場合もあります。複数の事務所に相談して比較検討することをお勧めします。
司法書士との連携
債務額が140万円以下の場合は、弁護士よりも費用が安い司法書士に依頼することも検討しましょう。司法書士は特に以下のような場面で力を発揮します:
- 債務整理(特に任意整理)
- 不動産登記に関する手続き
- 簡易裁判所での訴訟代理
弁護士と司法書士が連携することで、費用を抑えながら効果的な対応が可能になる場合もあります。
相談時に準備すべき書類
専門家に相談する際は、以下の書類を準備しておくと効率的に話を進められます:
- 差押え通知書
- 共有持分に関する登記簿謄本
- 債務の契約書や借用書
- 返済履歴がわかる資料
- 収入や資産状況がわかる資料(給与明細、預金通帳など)
- その他の債務に関する資料
これらの書類がすべて揃っていなくても、相談すること自体は可能です。まずは手元にある資料だけでも相談に行くことが重要です。
費用相場と支払い方法
法律専門家への依頼費用は、案件の複雑さや地域によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです:
- 初回相談:無料〜10,000円程度
- 差押え異議申立て:5万円〜15万円程度
- 任意整理:1社あたり2万円〜4万円程度
- 個人再生:30万円〜50万円程度
- 自己破産:20万円〜40万円程度
多くの事務所では分割払いに応じてくれるため、一括で支払えなくても相談する価値はあります。また、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、収入が少ない方でも法律サービスを利用することができます。
共有持分トラブルの予防策
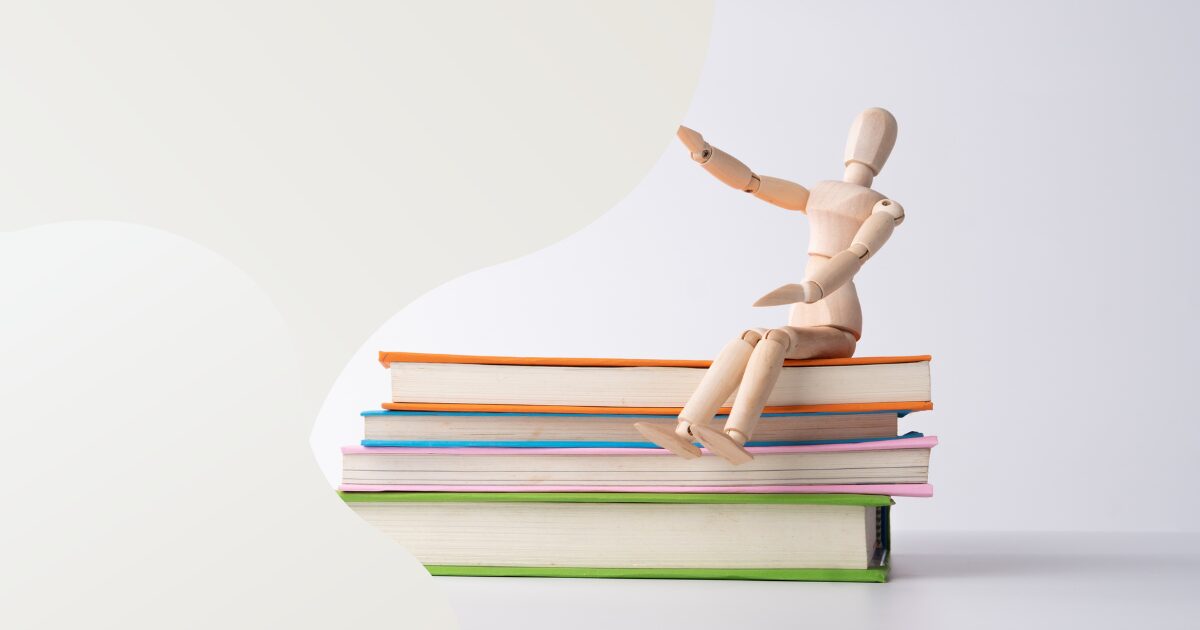
共有契約書の作成
共有持分に関するトラブルを未然に防ぐためには、共有者間で明確な「共有契約書」を作成しておくことが効果的です。この契約書には以下のような内容を含めるとよいでしょう:
- 各共有者の持分割合
- 管理方法や管理費用の分担
- 持分を売却する場合の他の共有者への優先買取権の設定
- 将来的な分割方法についての合意
- 債務不履行時の対応策
特に重要なのは、持分を第三者に譲渡する前に他の共有者に通知し、優先的に買い取る権利を与える条項です。これにより、知らない第三者が共有者になることを防げます。
共有契約書の作成には、不動産に詳しい弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。費用は5万円〜10万円程度が一般的です。
遺産分割における注意点
相続によって不動産の共有状態が生じることは非常に多いのですが、この段階で将来のリスクを減らす工夫ができます:
- 可能であれば、不動産は共有せず、単独所有とする
- 共有にする場合は、リスクの低い共有者(債務が少ない、安定した収入がある人など)の持分割合を大きくする
- 遺産分割協議書に共有不動産の管理や将来の売却についての取り決めを含める
- 共有ではなく、他の財産との交換や代償分割を検討する
遺産分割は一度行うと修正が難しいため、将来のリスクも考慮した上で慎重に決めることが重要です。
不動産の共有持分購入時の注意点
共有持分を購入する際は、以下の点に特に注意しましょう:
- 他の共有者の信用状況や財務状況を可能な限り確認する
- すべての共有者と面談し、将来の不動産利用についての考えを確認する
- 共有契約書を作成し、持分の処分制限や優先買取権を設定する
- 可能であれば、単独所有できる不動産を選ぶ
特に投資目的での共有持分購入は、慎重に検討する必要があります。表面上の利回りだけでなく、将来的なリスクも含めて判断することが大切です。
定期的な権利関係の見直し
共有関係にある場合は、定期的(1年に1回程度)に以下のような見直しを行いましょう:
- 登記簿謄本を取得し、差押えなどがないか確認する
- 他の共有者の状況(健康、経済状況など)に変化がないか確認する
- 不動産の評価額や市場動向を把握する
- 必要に応じて共有契約書の内容を更新する
このような定期的なチェックにより、問題が大きくなる前に対処することができます。登記簿謄本の取得費用は1通数百円程度で、オンラインでも取得可能です。
まとめ:財産を守るための包括的アプローチ

共有持分の差押えと競売のリスクは、適切な知識と対策によって大幅に軽減することができます。本記事で解説した内容を振り返りましょう。
まず、共有持分の差押えは主に債務不履行、税金滞納、裁判の判決などによって起こります。差押えが行われると、財産的損失、居住権の喪失、他の共有者への影響、信用情報への悪影響、精神的・社会的影響など多くのリスクがあります。
これらのリスクを回避するためには、以下のポイントを押さえることが重要です:
- 予防が最も重要:債務管理の徹底、共有名義の見直し、担保設定の工夫など、事前対策を講じる
- 早期の専門家相談:問題が小さいうちに弁護士や司法書士に相談する
- 差押え通知を受けたら即行動:内容を理解し、期限内に適切な対応を取る
- 法的手段の活用:請求異議の訴え、執行停止の申立て、任意売却などの選択肢を検討する
- 共有者間の協力:他の共有者と協力して問題解決に当たる
また、差押えを予防するための共有契約書の作成や、相続時の適切な対応なども効果的です。定期的に権利関係を見直し、問題の早期発見に努めることも大切です。
差押え・競売対策チェックリスト
自分の状況を確認するための簡単なチェックリストを以下に示します:
- □ 債務の返済状況は健全か(延滞はないか)
- □ 税金の滞納はないか
- □ 共有者全員と良好な関係を保っているか
- □ 共有契約書などの取り決めはあるか
- □ 定期的に登記簿謄本を確認しているか
- □ 収入に見合った生活をしているか
- □ 何か問題があった場合の相談先(専門家)を知っているか
これらの項目に不安がある場合は、早めに対策を講じることをお勧めします。
相談先リソース
共有持分の差押えについて相談できる主な窓口は以下の通りです:
- 法テラス(日本司法支援センター):0570-078374
- 各地の弁護士会の法律相談センター
- 日本司法書士会連合会総合相談センター
- 各自治体の無料法律相談窓口
- 国税庁の納税相談窓口(税金関連の場合)
これらの窓口では、初期段階の相談を無料または低料金で受けられる場合があります。
よくある質問(FAQ)
共有持分の差押えに時効はあるか
債権には一般的に時効があります。例えば、通常の貸金債権は10年、商事債権は5年、利息や賃料は5年で時効となります。ただし、債権者が裁判所に訴えを起こしたり、債務者が債務を承認したりすると時効が中断するため注意が必要です。
また、一度差押えが実行されると、その手続き自体に時効はありません。債権の時効が成立する前に差押えが行われた場合、その効力は継続します。
親族間の共有持分でも差押えは可能か
はい、親族間の共有持分であっても差押えは可能です。法律上、債権者は債務者の財産に対して差押えをする権利を持っており、その財産が親族との共有物であっても例外ではありません。
ただし、親族間で適切な対策(例:共有契約書での取り決め、家族信託の活用など)を講じておくことで、リスクを軽減できる場合があります。
競売になった場合の最低落札価格はどう決まるのか
競売における最低落札価格(最低売却価格)は、裁判所が選任した不動産鑑定士による評価額を基準に決定されます。ただし、この評価額は通常の市場価格よりも2〜3割程度低く設定されることが一般的です。
また、1回目の入札で購入希望者がいなかった場合、2回目以降の入札では価格がさらに下がることもあります。これが、競売物件が市場価値よりも大幅に安く売却される理由の一つです。
共有者に優先買取権はあるのか
法律上、共有持分が競売にかけられる場合、他の共有者に法定の優先買取権はありません。つまり、他の共有者も一般の入札者と同じ条件で入札に参加する必要があります。
ただし、事前に共有契約書などで、持分を売却する場合には他の共有者に優先買取の機会を与えるという取り決めをしておくことは可能です。こうした取り決めは、差押え前の任意売却の場面では有効ですが、強制競売では必ずしも認められないことがあります。
差押え後も物件に住み続けることは可能か
差押えが行われただけでは、すぐに退去する必要はありません。通常、競売で物件が落札され、新しい所有者が引き渡しを求めてくるまでは住み続けることができます。
競売から所有権移転、そして明け渡しまでには通常数ヶ月から半年程度の期間があるため、その間に新しい住居を探す時間的余裕はあります。ただし、新所有者から明け渡しを求められた場合、正当な理由なく拒否し続けることはできません。
今すぐできる3つの行動
最後に、共有持分の差押えリスクから財産を守るために、今すぐできる具体的な行動を3つ紹介します:
1. 現在の債務状況を総点検する
まずは自分の債務状況を正確に把握することから始めましょう。すべての借入先、借入額、金利、返済期限などを一覧表にまとめてください。返済が厳しい債務がある場合は、債権者に連絡して返済条件の見直しを相談することも検討しましょう。
具体的な行動:
- すべての借入の返済予定表を集める
- 延滞している債務がないか確認する
- 返済負担が収入の30%を超えている場合は対策を考える
2. 不動産の登記簿謄本を取得して確認する
共有不動産に関する正確な情報を得るために、登記簿謄本を取得しましょう。法務局の窓口やオンラインサービスで数百円程度で取得できます。登記簿謄本では、持分割合、所有者情報、抵当権や差押えの有無などを確認できます。
具体的な行動:
- 法務局またはオンラインで登記簿謄本を取得する
- 記載内容に誤りがないか確認する
- 知らない抵当権や差押えがないか確認する
3. 共有者間で話し合いを持つ
共有不動産に関するリスクを軽減するには、共有者間のコミュニケーションが非常に重要です。定期的に話し合いの場を持ち、不動産の管理や将来的な方針について合意形成を図りましょう。
具体的な行動:
- 共有者全員が参加する話し合いの場を設ける
- 各自の経済状況や今後の意向について率直に話し合う
- 必要に応じて、共有契約書の作成を検討する
これらの行動は、専門的な知識や多額の費用がなくても、今すぐに始められるものです。予防的な対策を講じることで、将来的な差押えリスクを大幅に軽減することができます。
共有持分の差押えと競売のリスクは、多くの人にとって身近な問題です。特に相続などで不動産を共有している場合、このリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。本記事で紹介した知識と対策が、あなたの大切な財産を守るための一助となれば幸いです。



コメント