親や親族から不動産を相続することになったとき、「共有持分」や「相続放棄」という言葉を耳にすることがあるでしょう。特に兄弟姉妹で一つの不動産を相続する場合には、共有持分という言葉がよく出てきます。でも、この「共有持分」と「相続放棄」は何が違うのでしょうか?また、共有持分に関する問題に直面したとき、どのような選択肢があるのでしょうか?
この記事では、共有持分と相続放棄の違いを分かりやすく解説し、不動産の共有持分に関するトラブルを防ぐための5つの選択肢と対策法をご紹介します。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有持分と相続放棄の違いを詳しく解説

共有持分と相続放棄の違いは大きく5つあります。それぞれを詳しく見ていきましょう。
1. タイミングの違い
共有持分は、相続登記が完了した後、つまり既に相続した後の状態を指します。一方、相続放棄は、相続登記の前、つまり相続するかどうかを決める段階で行うものです。
例えば、親が亡くなり、実家の相続問題が発生したとします。この時点で「相続放棄」をするかどうかを決めます。もし相続放棄をしなければ、相続登記を行い、他の相続人と共に不動産の「共有持分」を持つことになります。
2. 対象範囲の違い
相続放棄は、亡くなった方の全ての財産(プラスもマイナスも含めて)を対象とします。一部の財産だけを放棄することはできません。対して、共有持分は、既に相続した特定の不動産における自分の権利の割合を指します。
これは重要な違いで、「不動産の共有持分だけを相続放棄したい」という希望は実現できません。相続放棄をすると、不動産だけでなく、預貯金や株式などのプラスの財産も全て放棄することになります。
3. 手続き方法の違い
相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要な正式な法的手続きです。一方、共有持分の放棄(相続後に自分の持分を手放すこと)は、自分の意思表示だけで成立し、家庭裁判所への手続きは必要ありません。ただし、共有持分を放棄した事実を登記するには、他の共有者との共同申請が必要になります。
4. 期限の違い
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。これに対して、共有持分の放棄には期限がなく、いつでも行うことができます。
ただし、共有持分の放棄は「早い者勝ち」とも言われています。全ての共有者が持分を放棄してしまうと、最後の一人は放棄できなくなる可能性があるからです。
5. 効果の違い
相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人ではなかった」ことになります。これに対して、共有持分の放棄は、既に自分のものとなった持分を手放すことになります。
相続放棄の場合、次順位の相続人に相続権が移りますが、共有持分の放棄の場合は、放棄された持分が他の共有者に移ります。
共有持分を相続して困るケース

共有持分を相続すると、様々な問題が発生する可能性があります。主なケースを見てみましょう。
共有者間のトラブル事例
相続によって発生した共有関係は、後々トラブルの原因になりやすいです。特に以下のようなケースが多く見られます。
Aさんの事例:実家を3人兄弟で相続し、それぞれが3分の1ずつの持分を持つことになりました。しかし、Aさんは実家のリフォームを希望していましたが、他の兄弟は「お金をかけるくらいなら売却したい」と主張。結局、誰も譲らず、リフォームも売却もできないまま、家は老朽化していきました。
このように、共有不動産の利用方法について意見が分かれると、どうしても話がまとまりにくくなります。
管理や売却が難しくなる問題
共有不動産を売却するためには、原則として共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば、売却できません。また、大規模なリフォームなど、不動産に変更を加える行為も、共有者全員の同意が必要です。
例えば、「古い家を取り壊して更地にしたい」と思っても、他の共有者が「思い出の家を壊したくない」と反対すれば、取り壊しはできません。
税金や費用の負担問題
共有不動産には、固定資産税などの税金や、維持管理費がかかります。これらの費用は本来、持分に応じて負担するものですが、支払いを拒否する共有者がいると、他の共有者が余計な負担を強いられることになります。
子世代への負の遺産の連鎖
共有関係がそのまま次の世代に引き継がれると、問題はさらに複雑になります。例えば、兄弟3人が共有している不動産があり、それぞれに2人ずつ子どもがいたとすると、次の世代では6人での共有になります。共有者が増えるほど、意見をまとめるのは難しくなります。
「共有持分だけを相続放棄できない」という事実

相続で困りごとが発生したとき、「この不動産だけ相続したくない」と思うことがあるかもしれません。しかし、重要な事実として覚えておいていただきたいのは、特定の財産だけを相続放棄することはできないということです。
なぜ特定の遺産だけを相続放棄できないのか
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の全ての遺産について、相続する権利を放棄するものです。民法では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」(民法第915条)と定められています。
つまり、相続は「全部承認するか、全部放棄するか」の二択しかないのです。「この不動産は相続したくないけど、預貯金は相続したい」というような、つまみ食いはできません。
相続放棄のデメリット(プラスの財産も放棄することになる)
相続放棄をすると、困った不動産を相続しなくて済む一方で、預貯金や有価証券などのプラスの財産も全て放棄することになります。これが、相続放棄の最大のデメリットです。
よくある誤解と正しい知識
「共有持分だけを相続放棄できる」と誤解している人も少なくありません。しかし、これは法律上不可能です。ただし、相続した後に「共有持分を放棄する」という別の選択肢はあります。この違いを理解することが、賢い選択をするための第一歩です。
共有持分の問題に対する選択肢①:相続放棄

それでは、共有持分の問題に対して取りうる5つの選択肢を見ていきましょう。まず最初は「相続放棄」です。
相続放棄のメリット・デメリット
メリット:
- 被相続人の借金や債務を引き継がなくて済む
- 相続に関する手続きや管理の負担から完全に解放される
- 他の相続人とのトラブルに巻き込まれない
デメリット:
- プラスの財産(預貯金、有価証券など)も相続できなくなる
- 一度相続放棄すると原則として撤回できない
- 放棄した財産の行方について発言権がなくなる
相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きは、以下の流れで行います。
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出
- 申述書には「相続放棄申述書」、「戸籍謄本」、「被相続人の住民票除票または戸籍の附票」などを添付
- 裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届くのを待つ
相続放棄の申述費用は、収入印紙代として800円かかります。また、戸籍謄本などの書類取得費用が別途必要です。
相続放棄が特におすすめのケース
相続放棄は、以下のようなケースで特に有効です。
- 被相続人の借金や債務が資産を上回っている場合
- 相続財産がほとんどなく、手続きの手間だけがかかりそうな場合
- 他の相続人との関係が悪く、トラブルに巻き込まれたくない場合
相続放棄の注意点
相続放棄を選ぶ場合の注意点として、以下のことを覚えておきましょう。
- 一度相続放棄をすると、原則として撤回できない
- 相続放棄しても「生命保険金」や「死亡退職金」は受け取ることができる(これらは相続財産ではないため)
- 相続放棄をすると、自分の子どもにも相続権は移らない(代襲相続は発生しない)
共有持分の問題に対する選択肢②:一旦相続して売却する

共有持分の問題に対する2つ目の選択肢は、「一旦相続して売却する」という方法です。
共有持分を売却するメリット・デメリット
メリット:
- 持分の価値に応じた現金を手に入れられる
- 共有不動産の管理や税金の負担から解放される
- 他のプラスの財産も相続できる
デメリット:
- 共有持分は市場価値が低く、大幅に安い価格での売却になりがち
- 買い手を見つけるのが難しい場合がある
- 共有者から反発を受ける可能性がある
共有持分の売却方法
共有持分を売却する方法は、主に以下の2つがあります。
- 他の共有者に売却する:最も円満な解決方法です。不動産を実際に使用している共有者であれば、あなたの持分を買い取るメリットがあります。市場価格の80〜90%程度で売却できる可能性があります。
- 買取業者に売却する:他の共有者が買い取らない場合は、共有持分専門の買取業者に売却する方法もあります。ただし、市場価格の50〜70%程度になることが一般的です。
共有持分を売却する場合、自分の持分だけであれば、他の共有者の同意は不要です。これが、この方法の大きなメリットの一つです。
共有持分の適正価格の見極め方
共有持分の適正価格は、以下の式で算出することが一般的です。
共有持分の価値 = 不動産の市場価格 × 持分割合 × 減価率
ここでの「減価率」は、共有不動産の制約やリスクを反映した割引率で、通常は0.5〜0.7(50%〜70%)が使われます。
例えば、市場価格が3,000万円の不動産で、あなたの持分が3分の1の場合: 3,000万円 × 1/3 × 0.6 = 600万円 が一つの目安となります。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の売却価格は買い手との交渉によって決まります。複数の業者から見積もりを取ることで、より適正な価格を把握できるでしょう。
売却時の注意点
共有持分を売却する際の注意点は以下の通りです。
- 共有者間の信頼関係を損なわないよう、事前に売却の意思を伝えることが望ましい
- 悪質な買取業者に注意する(極端に安い買取価格を提示する業者や、急かして契約を迫る業者など)
- 契約書の内容をしっかり確認する(特に売却後の責任範囲について)
共有持分の問題に対する選択肢③:一旦相続して持分放棄

3つ目の選択肢は、「一旦相続して持分放棄する」という方法です。
持分放棄のメリット・デメリット
メリット:
- 他のプラスの財産は相続できる
- 持分に関する税金や管理費用の負担から解放される
- 手続きが比較的簡単(自分の意思表示のみで成立)
デメリット:
- 持分の対価を得られない(お金に換えられない)
- 放棄した持分が他の共有者に移るため、共有者から反発を受ける可能性がある
- 登記手続きには他の共有者の協力が必要
持分放棄の手続き方法
持分放棄の手続きは、以下の流れで行います。
- 他の共有者に対して、持分を放棄する意思を表明する(口頭でも効力は発生するが、後のトラブルを避けるため書面が望ましい)
- 持分放棄による所有権移転登記を行う(他の共有者との共同申請が必要)
- 登記申請書類(登記申請書、持分放棄証書、印鑑証明書など)を法務局に提出
持分放棄の登記費用は、登録免許税として不動産の評価額に応じた金額(一般的に数万円程度)がかかります。また、司法書士に依頼すれば、報酬として3〜5万円程度が必要です。
持分放棄後の税金問題
持分放棄を行うと、放棄した持分は他の共有者に移ります。この時、税法上は「贈与」とみなされる可能性があり、持分を受け取った共有者に贈与税が課される場合があります。
贈与税は、持分の評価額から基礎控除額(年間110万円)を差し引いた金額に対して課税されます。不動産の価値が高い場合、かなりの金額になることもあるので注意が必要です。
「早い者勝ち」と言われる理由
持分放棄は「早い者勝ち」とも言われています。なぜなら、全ての共有者が持分を放棄してしまうと、最後の一人は放棄できなくなる可能性があるからです。
例えば、3人で共有している不動産があり、2人が持分を放棄してしまうと、最後の1人は単独所有者となり、「放棄」という概念が成立しなくなります(放棄するには、放棄先となる他の共有者が必要)。そのため、持分放棄を検討している場合は、他の共有者が同じことを考えていないか確認することも大切です。
共有持分の問題に対する選択肢④:共有物分割請求

4つ目の選択肢は、「共有物分割請求」です。これは、裁判所に対して共有状態の解消を求める法的手続きです。
共有物分割請求とは何か
共有物分割請求とは、共有者の誰かが裁判所に対して「共有状態を解消してほしい」と請求する手続きです。民法第256条では、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と定められています。
つまり、他の共有者が反対していても、自分の意思だけで共有物分割請求を行うことができるのです。
共有物分割請求のメリット・デメリット
メリット:
- 他の共有者の同意がなくても、共有状態を解消できる
- 裁判所の判断による公平な解決が期待できる
- 長期間続いた共有トラブルに終止符を打てる
デメリット:
- 弁護士費用など、かなりの費用がかかる(50〜150万円程度)
- 時間がかかる(半年〜数年)
- 共有者間の関係が完全に壊れる可能性がある
- 必ずしも希望通りの結果になるとは限らない
共有物分割請求の手続き方法
共有物分割請求の手続きは、以下の流れで行います。
- 弁護士に相談し、共有物分割請求訴訟を提起
- 裁判所での審理(現地調査や不動産鑑定なども行われる)
- 裁判所の判断による判決
共有物分割請求は法的手続きが複雑なため、弁護士への依頼が必須となります。費用は案件の複雑さにもよりますが、一般的に着手金として20〜30万円、成功報酬として20〜30万円程度、合計で50〜150万円程度かかります。
裁判所の判断基準と結果の3パターン
裁判所は、以下の3つの方法のいずれかで共有状態を解消します。
- 現物分割:不動産を物理的に分割する方法。土地であれば分筆して、それぞれの共有者が単独所有する形になります。
- 換価分割:不動産を売却し、その代金を持分に応じて分配する方法。競売にかけられることが多く、市場価格より安くなりがちです。
- 価格賠償:一人の共有者が不動産全体を取得し、他の共有者に対して持分相当額の金銭を支払う方法。
裁判所は、この3つの方法の中から最も公平で合理的な方法を選びます。ただし、必ずしも自分の希望通りの結果になるとは限らないのがリスクです。
共有持分の問題に対する選択肢⑤:限定承認
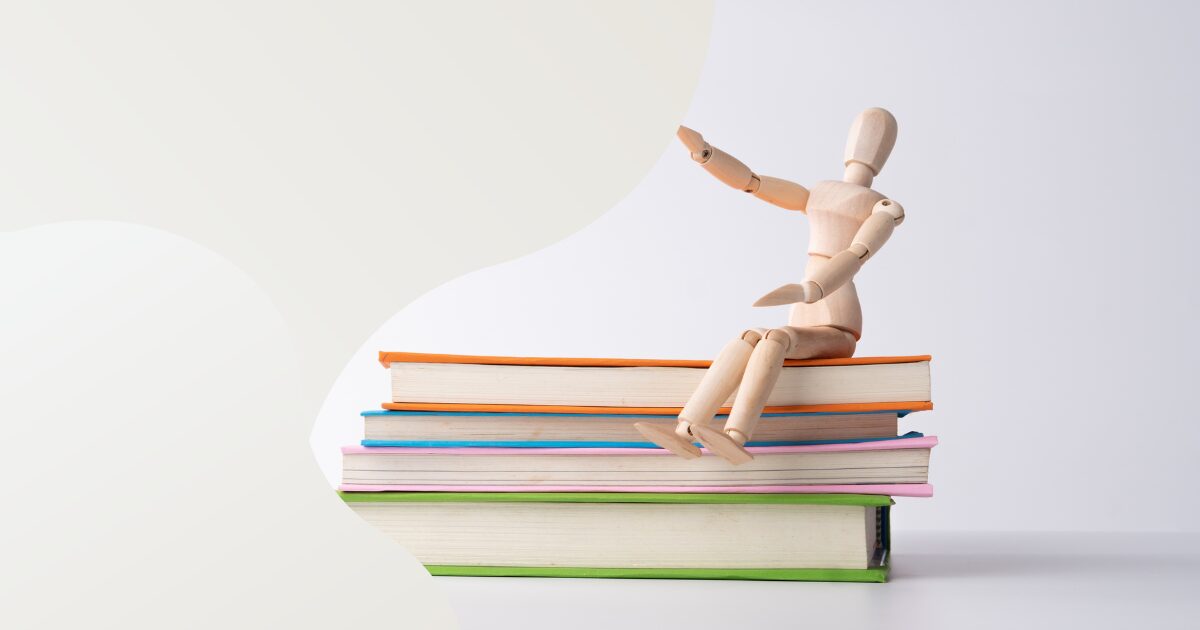
5つ目の選択肢は、「限定承認」です。これは、相続放棄と単純承認(通常の相続)の中間的な選択肢です。
限定承認とは何か
限定承認とは、相続財産の限度内で被相続人の債務を返済する方法です。つまり、「相続財産がプラスならその範囲内で債務を返済し、残りを取得する。相続財産がマイナスなら財産の範囲内で債務を返済し、それ以上の負担はしない」という選択肢です。
限定承認のメリット・デメリット
メリット:
- 被相続人の債務が資産を上回っていても、自己の財産から支払う必要がない
- 相続放棄と違い、プラスの財産が残れば相続できる
デメリット:
- 手続きが複雑で時間がかかる
- 相続人全員が共同で行わなければならない
- 財産目録の作成など、手間がかかる
限定承認の手続き方法
限定承認の手続きは、以下の流れで行います。
- 相続人全員が共同で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述書を提出
- 申述が受理されたら、相続財産の調査と財産目録の作成
- 官報や新聞などで債権者に対する公告
- 相続財産から債務の弁済
- 残った財産があれば、相続人が相続
限定承認の申述費用は、収入印紙代として800円かかります。また、公告費用や財産目録作成のための調査費用なども必要です。
限定承認が特におすすめのケース
限定承認は、以下のようなケースで特に有効です。
- 被相続人の債務の総額が不明な場合
- 複数の相続人がいて、全員が相続放棄ではなく限定承認を希望する場合
- 相続財産にプラスの価値がある可能性が高く、それを相続したい場合
限定承認は、手続きは複雑ですが、「全部相続するか全部放棄するか」の二択ではない第三の選択肢として知っておく価値があります。
それぞれの選択肢の比較と最適な選び方

ここまで5つの選択肢を紹介してきましたが、どれが最適かは状況によって異なります。ここでは、ケース別の選択肢を比較してみましょう。
ケース別の最適な選択肢
ケース1: 共有不動産以外にプラスの財産がたくさんある場合 → 一旦相続して売却する、または共有物分割請求が有利
相続放棄するとプラスの財産も全て放棄することになるため損をします。一旦相続してから、共有持分を売却するか、共有物分割請求で解決するのが合理的です。
ケース2: 被相続人に多額の借金があり、資産より債務の方が多い場合 → 相続放棄が有利
債務超過の場合は、相続放棄によって債務の支払い義務から解放されるのが最善です。
ケース3: 共有者間の関係が悪く、トラブルになりそうな場合 → 相続放棄、または一旦相続して売却が有利
人間関係のトラブルを避けるなら、最初から関わらない相続放棄が有効です。それが難しい場合は、相続後すぐに売却して関係を切ることも検討できます。
ケース4: 債務の総額が不明だが、プラスの財産もありそうな場合 → 限定承認が有利
借金の総額が分からない場合は、限定承認でリスクを限定しつつ、プラスの財産を相続する可能性を残す方法が合理的です。
判断のポイントと優先順位
選択肢を決める際の判断ポイントとしては、以下の優先順位で考えるとよいでしょう。
- 財産状況(プラスかマイナスか)
- 他の共有者との関係性
- 時間的・金銭的余裕
- 将来的な不動産の価値・活用可能性
専門家に相談すべきタイミング
以下のようなケースでは、早めに専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に相談することをおすすめします。
- 相続財産の中に不動産と借金の両方がある場合
- 共有者間で既にトラブルが発生している場合
- 相続放棄の期限(3ヶ月)が迫っている場合
- 限定承認を検討している場合
- 共有物分割請求を検討している場合
専門家への相談費用は一般的に5,000円〜30,000円程度ですが、早めに相談することで、後々の大きなトラブルや損失を避けられることもあります。
費用対効果の考え方
各選択肢にはそれぞれ費用がかかります。その費用と得られる効果を比較して判断することが大切です。
相続放棄:申述費用は数千円程度と安いが、プラスの財産も全て放棄することになる
持分売却:売却額の3〜6%程度の仲介手数料がかかるが、持分の価値に応じた現金を得られる
持分放棄:登記費用として数万円程度かかるが、対価は得られない
共有物分割請求:弁護士費用など50〜150万円程度かかるが、公平な解決が期待できる
限定承認:手続費用は数万円程度だが、手間がかかる
将来のトラブルを防ぐための対策
共有持分に関するトラブルは、事前の対策で防げることも多いです。ここでは、将来のトラブルを防ぐための対策を紹介します。
生前対策の重要性
共有持分のトラブルを根本的に防ぐには、そもそも共有状態を作らないことが重要です。特に親世代の方は、自分の不動産が将来共有状態にならないよう、生前に対策しておくことをおすすめします。
例えば、生前贈与や生前売却など、生きているうちに不動産の所有権を整理しておくことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。
遺言書の活用方法
トラブルを防ぐ最も効果的な方法の一つが、遺言書の作成です。遺言書には、不動産を誰に相続させるかを明確に指定することができます。例えば、「長男に自宅不動産を相続させる、その代わり次男と長女には預貯金から各〇〇円を相続させる」というように具体的に記載することで、共有状態の発生を防ぐことができます。
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、自分で全文を手書きするもので、費用はほとんどかかりませんが、形式不備で無効になるリスクがあります。2020年7月からは法務局での保管制度も始まり、安全性が高まっています。保管申請手数料は3,900円です。
公正証書遺言は公証役場で作成するもので、無効になるリスクは低いものの、公証人手数料(一般的に5万円〜15万円程度)がかかります。
確実性を重視するなら公正証書遺言、費用を抑えたいなら自筆証書遺言がおすすめです。どちらを選ぶにせよ、遺言書があることで相続トラブルが大幅に減ることは間違いありません。
共有名義を避ける方法
不動産の共有名義を避けるためには、以下のような方法があります。
1つの不動産は1人に相続させる 例えば、複数の不動産がある場合は、それぞれを別々の相続人に相続させるのがよいでしょう。1つの不動産を複数人で共有するより、それぞれが別の不動産を単独所有する方がトラブルは少なくなります。
代償分割を活用する 代償分割とは、不動産を1人が相続し、その代わりに他の相続人に金銭などを支払う方法です。例えば、3,000万円の不動産を長男が相続し、次男と長女にそれぞれ1,000万円ずつ支払うといった形です。
換価分割を検討する 不動産を売却して、その代金を相続人で分ける方法です。不動産そのものを相続するより、現金化して分ける方が簡単なケースも多いです。
家族間での話し合いのポイント
相続問題は、法律だけでなく感情の問題でもあります。将来のトラブルを防ぐためには、家族間での率直な話し合いが重要です。
話し合いのポイント:
- 早い段階から、将来の相続について話し合う機会を持つ
- お互いの希望や考えを尊重する
- 感情的にならず、冷静に話し合う
- 必要に応じて、専門家(弁護士・司法書士など)に同席してもらう
- 合意事項は書面に残しておく
特に、実家の不動産については「思い出」や「愛着」という感情的な要素も絡むため、生前から少しずつ話し合っておくことが大切です。
よくある質問(Q&A)

相続放棄の期限を過ぎてしまった場合はどうすればいい?
相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった場合でも、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という点が重要です。例えば、海外に住んでいて親の死亡を知らなかったなど、正当な理由がある場合は、その事実を知った時点から3ヶ月以内に手続きをすれば認められることがあります。
また、相続財産の全部または一部を処分していなければ、「相当の期間内」であれば特別に裁判所が相続放棄を認めてくれる場合もあります。
期限を過ぎてしまった場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄をすると相続人の子供(代襲相続人)はどうなる?
相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人ではなかった」ことになります。そのため、相続放棄した人の子供(代襲相続人)も相続権を持ちません。
例えば、父親が亡くなり、長男が相続放棄をした場合、長男の子供(孫)には相続権は移りません。次の相続順位である次男や長女などに相続権が移ります。
共有持分を放棄するとどこに帰属する?
共有持分を放棄すると、民法第255条により、その持分は他の共有者に移ります。その際、他の共有者の持分割合に応じて分配されます。
例えば、A、B、Cの3人が、それぞれ50%、30%、20%の持分を持っている状態で、Cが持分を放棄した場合、Cの20%はAとBの持分割合(5:3)に応じて分配されます。結果、Aは約62.5%(50%+20%×5/8)、Bは約37.5%(30%+20%×3/8)の持分を持つことになります。
共有者全員が持分放棄するとどうなる?
理論上は、共有者全員が持分放棄することはできません。なぜなら、持分放棄は他の共有者に持分が移ることを前提としているからです。全員が放棄すると、最後の一人は放棄先がなくなるため放棄できません。
ただし、2021年4月に施行された「相続土地国庫帰属法」により、一定の条件を満たす相続土地については、国庫への帰属が認められるようになりました。申請料(10,000円)と承認後の審査手数料(30,000円〜)がかかりますが、管理や処分に困っている土地を手放す選択肢として検討できます。
まとめ
この記事では、共有持分と相続放棄の違いから始まり、共有持分に関する問題に対する5つの選択肢を詳しく解説してきました。それぞれの選択肢にはメリット・デメリットがあり、状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。
各選択肢のおさらい
相続放棄:すべての遺産を放棄する。債務も引き継がなくて済む反面、プラスの財産も放棄することになる。
一旦相続して売却する:自分の持分の価値に応じた対価を得られる。他の共有者の同意がなくても可能。
一旦相続して持分放棄:持分に関する負担から解放されるが、対価は得られない。他の共有者に持分が移る。
共有物分割請求:裁判所の判断で強制的に共有状態を解消できる。費用と時間がかかる。
限定承認:相続財産の範囲内で債務を返済する。相続人全員の合意が必要で手続きが複雑。
共有持分問題への対応の基本姿勢
共有持分の問題に対しては、以下の基本姿勢で対応することをおすすめします。
- 情報収集を十分に行う:相続財産の内容(プラスとマイナスの両方)をできるだけ正確に把握する。
- 感情に流されず冷静に判断する:特に家族間の相続では感情が入りやすいが、経済的な観点からも冷静に判断する。
- 専門家のアドバイスを活用する:必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談する。
- 将来のことも考える:目先の問題だけでなく、次世代への影響も考慮して判断する。
専門家相談の重要性
共有持分や相続放棄に関する問題は、法律的に複雑な側面があります。また、一度決断すると取り消すことが難しいケースも多いです。そのため、重要な決断をする前には、専門家に相談することをおすすめします。
特に以下のような専門家が相談相手として適しています。
- 弁護士:相続放棄や共有物分割請求などの法的手続きについて
- 司法書士:不動産の登記手続きや相続手続きについて
- 税理士:相続税や贈与税などの税金問題について
今すぐできる3つのアクション
この記事を読んで「自分にも共有持分の問題がある」と思った方は、以下の3つのアクションをすぐに実行してみてください。
- 相続財産の調査・把握: 相続財産(不動産、預貯金、有価証券、借金など)の全体像を把握しましょう。不動産については、登記簿謄本を取得して正確な権利関係を確認することをおすすめします。登記簿謄本は法務局で取得でき、1通600円程度です。
- 共有者との話し合いの場を設ける: 共有状態にある不動産について、他の共有者と今後どうするかを話し合う機会を持ちましょう。お互いの希望や考えを率直に伝え合うことで、解決の糸口が見つかる可能性があります。
- 専門家への無料相談を活用する: 弁護士会や司法書士会では、無料相談会を定期的に開催しています。また、多くの法律事務所では初回相談を無料としていることもあります。まずは無料相談を活用して、専門家の意見を聞いてみましょう。
共有持分の問題は放置すればするほど複雑になりがちです。早め早めの対応を心がけることで、スムーズな解決につながります。この記事が、皆さんの問題解決の一助となれば幸いです。

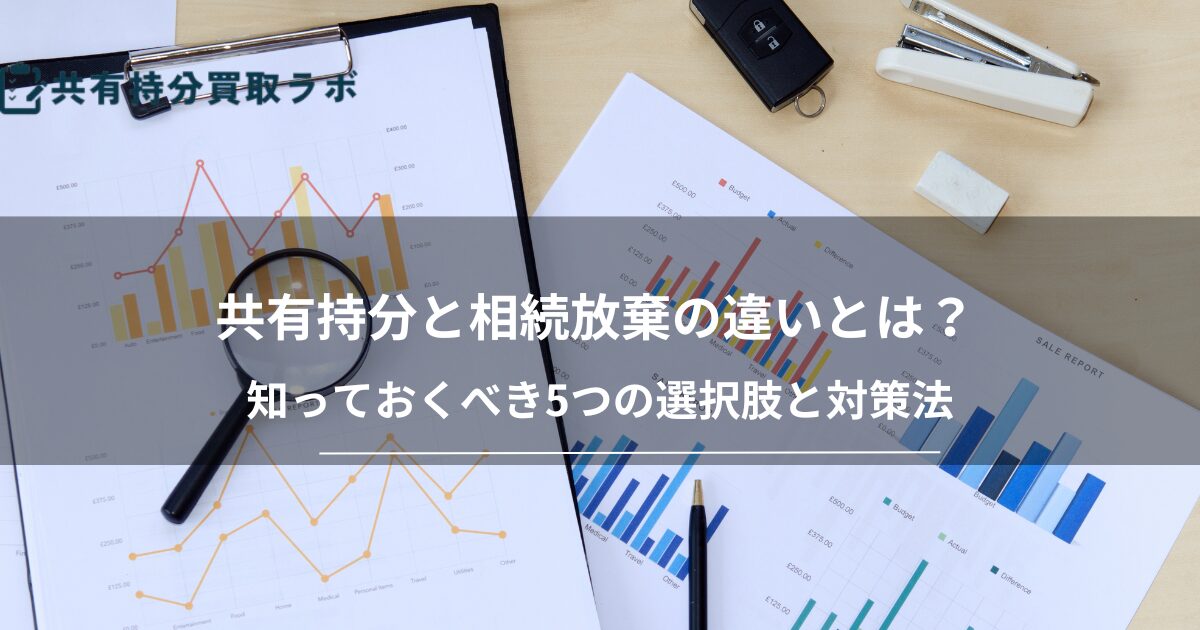

コメント