不動産を複数人で所有する「共有持分」と、無償で貸し借りする「使用貸借」。この二つが組み合わさると、思わぬトラブルの種になることをご存知でしょうか?
特に相続が発生したときや不動産を売却したいときに、共有者間で意見が対立してしまうと、解決までに長い時間と多額の費用がかかってしまうことも少なくありません。
この記事では、共有持分と使用貸借に関する基本的な知識から、トラブルを未然に防ぐための具体的な対策までを、専門家ではない方にもわかりやすく解説します。将来の不安を取り除き、スムーズな相続や売却を実現するために必要なポイントを押さえていきましょう。
共有持分は権利関係が複雑で、一般の不動産会社では扱うのが難しい案件が多いです。そのため、法律事務所と提携しており、共有持分専門の不動産会社に相談することが重要です。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有持分とは?一人だけの所有じゃない不動産の基礎知識

共有持分とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有している状態のことです。たとえば、AさんとBさんが一軒の家を持分2分の1ずつで所有している場合、その家は二人の「共有物」となり、それぞれが「共有持分」を持っていることになります。
共有持分が発生する代表的なケースは以下のようなものです。
- 父が亡くなって実家を兄弟3人で相続した
- 夫婦で共同名義のマンションを購入した
- 親族数人で投資用の土地を共同購入した
共有状態では、持分の割合に応じて固定資産税などの費用負担が発生します。また、建物の建て替えなどの「変更行為」には共有者全員の同意が必要ですが、修繕などの「管理行為」は持分の過半数で決めることができます。
共有状態にあるかどうかは、登記簿の権利部(甲区)を確認すれば分かります。所有者の名前が複数記載されていて、それぞれの持分が「〇分の〇」という形で示されていれば、その不動産は共有状態にあります。
共有持分の割合は原則として平等ですが、共有者間の合意や遺言などによって不平等な割合に設定することもできます。登記簿に記載されている持分は、対外的に主張できる権利の割合を示しています。
使用貸借とは?無償で貸す・借りるときの基礎知識

使用貸借とは、無償で物を貸し借りする契約のことです。賃貸借契約との大きな違いは「お金のやり取りがない」という点です。民法では「借主は、無償で使用および収益をし、契約が終了したときは、借りたものを返還する」と定められています。
典型的な例としては、「親が子どもに家を無償で貸している」「兄弟の一人が実家に住み続けている」といったケースが挙げられます。
使用貸借は法律上、書面による契約が必須ではないため、口頭での約束だけで成立してしまいます。ただし、口頭だけの契約は後々「貸したつもりはない」「いつまでも住めると言われた」などと言い争いになるリスクがあります。
使用貸借の特徴として、借主は基本的に目的物(不動産など)を自由に使用できますが、貸主の承諾なく第三者に転貸することはできません。また、契約に期間の定めがない場合、貸主はいつでも返還を請求できるという点も重要です。
実は使用貸借は「好意」に基づく契約として扱われるため、賃貸借契約と比べて借主の権利が弱く、保護も薄いのが特徴です。このことが後々のトラブルにつながることもあります。
共有持分×使用貸借で起こりやすいトラブル事例とその原因

共有持分と使用貸借が組み合わさると、さまざまなトラブルが発生しやすくなります。実際によく見られるケースを見てみましょう。
相続発生時のトラブル
親が亡くなり、実家を兄弟で共有相続したものの、一人の兄弟だけが住み続けているケースを考えてみましょう。この状態が長く続くと、住んでいる兄弟は「自分の家」という感覚になり、他の兄弟は「自分たちの権利が侵害されている」と感じるようになります。相続から10年、20年と経つうちに感情的な対立が深まり、話し合いすら難しくなってしまうことがあります。
実際の事例では、親の死後30年以上も一人の兄弟が実家に住み続け、他の兄弟が売却を求めて訴訟になったケースもあります。裁判所は「長期間の使用貸借関係が成立していた」と判断し、住んでいた兄弟に退去を命じました。
売却希望時のトラブル
共有不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。一部の共有者が売却に反対すると、不動産を売ることができなくなります。
例えば、3人の共有者のうち2人は売却を希望しているものの、使用貸借で住んでいる1人が「ここが気に入っているから絶対に売りたくない」と主張すると、売却が進まなくなります。
不動産価格が高い都市部では、このようなトラブルが資産価値の何千万円という損失につながることもあります。
共有者間の意見対立による問題
共有不動産の管理や修繕について、共有者間で意見が割れることもよくあります。使用している人は「快適に住むためには修繕が必要」と主張しますが、使用していない共有者は「費用をかけたくない」と考えがちです。
あるケースでは、屋根の修繕費用の負担をめぐって共有者間で意見が対立し、結局修繕が先延ばしになった結果、雨漏りが発生して建物の傷みが進み、最終的に修繕費用が当初の3倍になってしまったということもありました。
使用貸借の終了を巡るトラブル
使用貸借契約は、期間の定めがなければ貸主はいつでも返還を請求できます。しかし、長年住み続けている借主からすれば、突然の退去要求は大きな負担です。
ある事例では、親族間の使用貸借で20年以上住み続けていた借主に対して、貸主が突然退去を要求。借主は「黙示の賃貸借契約が成立していた」と主張して争いになりましたが、裁判所は使用貸借契約の成立を認め、6か月の猶予期間を設けて退去を命じました。
相続トラブルを防ぐための具体的な対策

共有持分と使用貸借に関連する相続トラブルを防ぐためには、事前の準備が欠かせません。
遺言書の活用で相続後の共有状態を回避する
相続トラブルを防ぐ最も効果的な方法の一つが遺言書の活用です。遺言書で不動産の承継者を一人に指定しておけば、相続後に共有状態になるのを避けることができます。
例えば「長男Aに自宅を相続させる」と遺言書に明記しておけば、他の相続人には別の財産で相続分を調整するという方法が考えられます。遺言書は自筆証書遺言でも良いですが、法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」(手数料3,900円)を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
共有物分割協議は早めに行う
遺言書がない場合、相続人同士で「共有物分割協議」を行い、不動産の帰属を決めることが重要です。この協議は相続発生後すぐに行うことをおすすめします。時間が経つほど各相続人の生活状況や考え方が変わり、合意が難しくなるからです。
分割協議では「不動産は一人が相続し、その代わりに他の相続人には現金で代償を支払う」といった方法が一般的です。
例えば、相続財産が2,000万円の実家と1,000万円の預金で、相続人が2人の場合、一人が実家を相続してもう一人に500万円を支払えば、それぞれが1,500万円ずつ相続したことになります。
使用貸借状態にある共有不動産の相続対策
すでに使用貸借状態で誰かが住んでいる共有不動産を相続する場合、契約書の有無を確認しましょう。契約書がない場合は、可能な限り書面化することをおすすめします。その際、使用期間や費用負担、将来的な売却の可能性などについても明確にしておくことが重要です。
相続人の中に現在住んでいる人がいる場合は、その人が不動産を取得するか、または他の相続人に代償金を支払う形で話し合うことが円満な解決につながります。
相続人が複数いる場合の注意点
相続人が多いほどトラブルのリスクは高まります。特に複雑な関係性がある場合(再婚家庭や疎遠な親族など)は、専門家を交えた話し合いが有効です。
相続発生から3年以内に共有関係を解消できない場合、遺産分割調停や審判といった法的手続きを検討する必要があります。調停の申立費用は1,000円程度ですが、弁護士に依頼すると着手金20〜30万円、成功報酬として経済的利益の10〜20%程度がかかることが一般的です。
売却トラブルを防ぐための実践的な対策

共有不動産の売却にはいくつかの障壁があります。ここでは売却トラブルを回避するための対策を見ていきましょう。
共有持分売却の現実と難しさを知る
共有持分だけを売却しようとしても、通常の不動産市場では買い手を見つけるのが難しいのが現実です。実際、共有持分の買取価格は単独所有の場合と比べて50〜70%も低くなることがあります。
不動産会社の調査によると、共有持分のみの売却は成約までに平均9か月以上かかるとされています。これは単独所有物件の約3倍の期間です。
他の共有者からの同意を得るためのアプローチ
共有物を売却するためには、すべての共有者の同意が必要です。同意を得るための効果的なアプローチとしては、以下のような方法があります。
まず、売却の必要性や利点を丁寧に説明することが大切です。たとえば「修繕費用がかさむ」「遠方に住んでいて管理が難しい」「相続税の支払いのために現金化が必要」など、具体的な理由を伝えましょう。
また、売却に消極的な共有者に対しては、売却後の利益配分で優遇するという提案も有効です。例えば、法定持分よりも多く受け取れるようにするなどの工夫ができます。
使用貸借状態の不動産売却時の手順
使用貸借で誰かが住んでいる不動産を売却する場合、まずは使用貸借契約を終了させる必要があります。契約に期間の定めがなければ、貸主はいつでも返還を請求できますが、借主の生活状況に配慮して十分な猶予期間(通常は6か月程度)を設けることが望ましいでしょう。
実際の事例では、退去までの猶予期間と引越し費用の負担を提示することで、円満に話がまとまったケースが多いようです。借主に対して丁寧な説明と誠意ある対応を心がけることが重要です。
共有持分買取請求権の活用法
どうしても共有者全員の同意が得られない場合は、「共有持分買取請求権」の活用を検討しましょう。これは、共有者の一人が他の共有者に対して自分の持分を買い取るよう請求できる権利です。
法的根拠はやや複雑ですが、共有物分割請求権の一環として認められている権利です。一定の条件下で、裁判所に共有持分の買取りを請求することができます。この手続きには弁護士への相談が必要で、費用は30〜50万円程度が目安となります。
共有持分×使用貸借の適切な契約書作成のポイント

トラブルを防ぐためには、適切な契約書の作成が不可欠です。ここでは、契約書作成のポイントを解説します。
契約書に必ず入れるべき重要項目
共有持分と使用貸借に関する契約書には、以下の項目を必ず入れるようにしましょう。
- 当事者の氏名・住所
- 対象不動産の所在地・面積・登記情報
- 使用貸借の目的
- 使用貸借の期間
- 各種費用の負担方法(固定資産税、修繕費など)
- 第三者への転貸の禁止
- 契約解除の条件
- 返還時の原状回復義務
- 契約違反時の措置
特に期間設定は重要です。「死亡するまで」など不確定な期限ではなく、「○年間」など明確な期間を設定し、更新条件も記載しておくことをおすすめします。
将来の相続・売却を見据えた特約の入れ方
将来のトラブルを防ぐためには、以下のような特約も検討する価値があります。
- 共有者が死亡した場合の持分の取扱い
- 共有者の一人が売却を希望した場合の優先買取権
- 一定期間経過後の売却合意
具体的な文言としては、「共有者の一人が自己の持分を第三者に譲渡しようとする場合は、あらかじめ他の共有者に対して譲渡の申出をし、他の共有者が希望する場合は、その共有者に対して優先的に譲渡するものとする」といった条項が考えられます。
専門家に依頼する際のチェックポイント
契約書作成を専門家に依頼する際は、以下の点に注意しましょう。
- 不動産取引の経験が豊富かどうか
- 相続問題にも詳しいかどうか
- 依頼内容と費用の見積もりが明確かどうか
弁護士や司法書士に依頼する場合、契約書作成の費用は5〜10万円程度が相場です。ただし、複雑な条件がある場合はそれ以上になることもあります。費用対効果を考えると、将来のトラブル回避のための投資と考えられるでしょう。
共有関係を解消する方法とその手順
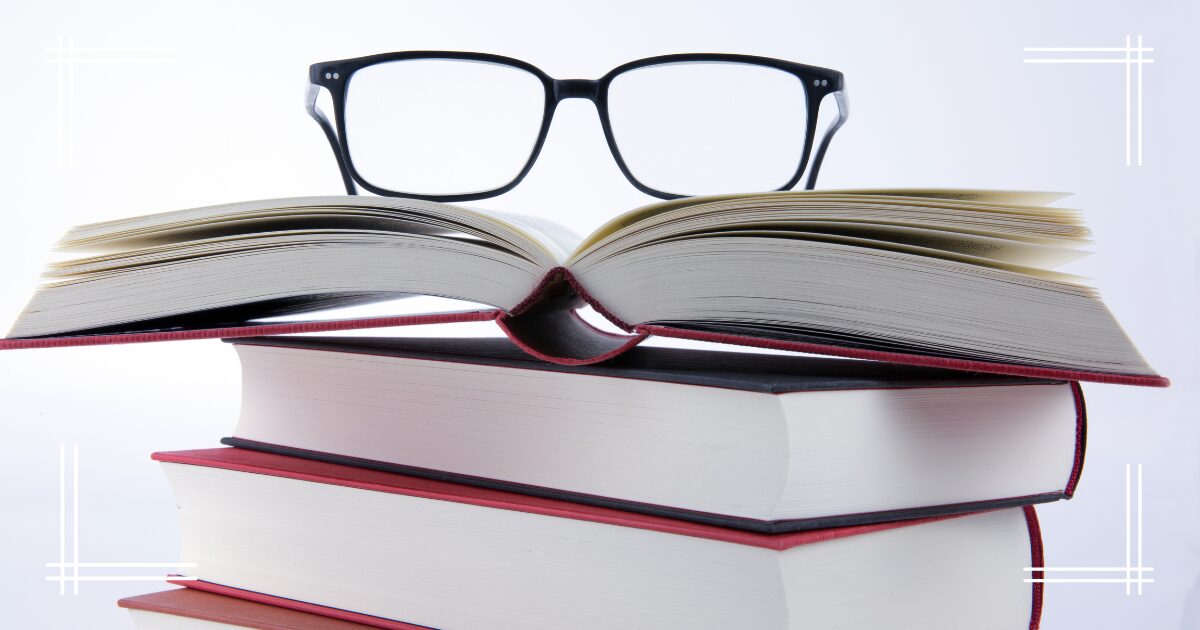
共有関係そのものを解消する方法も知っておくと安心です。ここでは主な解消方法を紹介します。
共有物分割請求の手続きと費用
共有物分割請求とは、共有関係を解消するために裁判所に分割を請求する手続きです。民法では「共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と定められています。
分割方法には、現物分割(土地を分ける)、換価分割(売却して代金を分ける)、価格賠償(一人が取得して他の共有者に金銭を支払う)の3種類があります。不動産の性質上、換価分割が命じられることが多いようです。
持分の集約による単独所有化
共有関係を解消する穏便な方法として、一人の共有者が他の共有者の持分を買い取り、単独所有とする方法があります。
この方法のメリットは、外部に売却する必要がなく、当事者間の合意のみで解決できる点です。市場価格よりもやや低い金額で合意できれば、双方にとってメリットがある解決策となります。
実際の事例では、相続で4人が共有していた実家を、住んでいる一人が他の3人から持分を買い取り、単独所有としたケースがあります。3人は現金化できて満足し、住んでいる人も安心して住み続けられるという、Win-Winの解決策となりました。
任意売却による解決方法
共有者全員が売却に合意すれば、不動産を売却して代金を持分に応じて分配するという方法も有効です。この「任意売却」は、裁判所を介さずに共有関係を解消できる最も簡単な方法です。
不動産会社の調査によると、共有物件の任意売却では、単独所有物件と比べて売却期間が1.5倍程度長くなる傾向がありますが、それでも裁判所を介する方法よりは格段に早く解決します。
売却時には、共有者全員の印鑑証明書や実印が必要になるため、事前に準備しておくことをおすすめします。
裁判による共有関係解消の実例
裁判所の判断による共有関係解消の実例としては、以下のようなケースが報告されています。
ある事例では、相続で共有となった賃貸アパートについて、管理方法を巡って共有者間で意見が対立。共有物分割請求訴訟の結果、裁判所は「換価分割」を命じ、競売による売却代金の分配が行われました。
別の事例では、共有マンションに一部の共有者が居住していましたが、他の共有者からの分割請求に対して、裁判所は「価格賠償方式」による分割を命じました。居住者が不動産を取得し、他の共有者に時価相当額を支払うという判決です。
これらの事例からわかるように、裁判所は個々の事情を考慮して、最も公平で実現可能な解決策を模索します。ただし、裁判による解決は時間とコストがかかるため、できれば当事者間の話し合いでの解決が望ましいでしょう。
専門家への相談ポイントと選び方
共有持分や使用貸借に関する問題は専門的な知識が必要です。ここでは適切な専門家の選び方について説明します。
どんな専門家に相談すべきか
問題の性質によって、相談すべき専門家は異なります。
- 契約書作成や法的アドバイス → 弁護士、司法書士
- 登記手続きや権利関係の確認 → 司法書士
- 不動産の評価・売却 → 不動産鑑定士、宅地建物取引士
- 税金対策 → 税理士
特に複雑なケースでは、複数の専門家にチーム対応してもらえる「ワンストップ型」の事務所を選ぶと便利です。また、不動産や相続問題に強い専門家を選ぶことが重要です。
相談前に準備しておくべき資料
専門家に相談する前に、以下の資料を準備しておくと相談がスムーズに進みます。
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 固定資産税評価証明書
- 住宅地図や測量図
- 既存の契約書や協定書
- 共有者全員の連絡先
- 相続関係が関わる場合は、戸籍謄本
これらの資料は、法務局や市区町村役場で取得できます。登記簿謄本の取得費用は1通600円程度、固定資産税評価証明書は300〜500円程度です。
専門家選びで失敗しないためのチェックリスト
専門家選びで失敗しないためには、以下のポイントをチェックしましょう。
- 共有持分・相続問題の実績があるか
- 無料相談や初回相談割引を実施しているか
- 料金体系が明確か
- 説明がわかりやすいか
- 複数の解決策を提案してくれるか
特に重要なのは「相性」です。長期的な関係になる可能性が高いため、信頼できると感じられる専門家を選びましょう。
相談費用の目安
専門家への相談費用の目安は以下の通りです。
- 弁護士:初回相談 5,000〜10,000円(30分)、着手金 20〜50万円
- 司法書士:初回相談 無料〜5,000円、書類作成 1〜10万円
- 税理士:初回相談 5,000〜10,000円、相続税申告 20〜50万円
- 不動産鑑定士:簡易評価 3〜5万円、正式鑑定 10〜30万円
多くの専門家は初回無料相談を実施していますので、まずはそうしたサービスを利用して、相性を確かめることをおすすめします。
まとめ:共有持分×使用貸借のトラブルを防ぐ黄金ルール

共有持分と使用貸借に関するトラブルを防ぐためのポイントをまとめます。
最重要ポイント
共有持分と使用貸借の関係における最も重要なポイントは「曖昧さを排除すること」です。口頭の約束や暗黙の了解に頼らず、すべてを書面化することがトラブル防止の基本となります。
また、将来を見据えた取り決めを行うことも重要です。今は問題なくても、相続や売却のタイミングでトラブルになることが多いため、そうした事態を想定した準備が必要です。
トラブル防止のための3つの黄金ルール
- すべてを書面化する:口頭の約束だけでなく、使用期間、費用負担、将来の売却可能性などをすべて契約書に明記しましょう。
- 定期的な話し合いの場を設ける:年に1回程度、共有者全員で集まり、不動産の状況や各自の意向を確認する機会を作りましょう。
- 早めに専門家に相談する:問題が複雑化する前に、専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応が可能になります。
これらのルールを守ることで、共有持分と使用貸借に関するトラブルの多くを回避することができるでしょう。
読者へのアクションプラン
今すぐにできる具体的な行動として、以下の3つを提案します。
- 共有不動産の登記簿を取得し、正確な持分割合と共有者を確認しましょう。
- 使用貸借の状態にある場合は、契約書を作成するか、既存の契約書を見直しましょう。特に使用期間や費用負担について明確にすることが大切です。
- 共有者全員で今後の方針について話し合う場を設け、将来的な売却や相続についての意向を確認しましょう。
これらのアクションを実行することで、将来的なトラブルを大幅に減らすことができます。特に問題が発生する前の予防策が最も効果的であることを忘れないでください。
よくある質問(FAQ)

Q1: 共有持分を相続したが、使用していない場合の権利は?
A1: 使用していなくても、持分に応じた権利があります。具体的には、不動産の管理方法の決定に参加する権利、分割請求権、持分に応じた収益を受け取る権利などです。ただし、他の共有者が長期間にわたって使用している場合、使用貸借や黙示の合意があったと解釈される可能性もあります。
Q2: 使用貸借の終了を一方的に通告できる?
A2: 期間の定めがない使用貸借の場合、貸主は原則としていつでも返還を請求できます。ただし、裁判例では「借主の生活状況に配慮し、相当な猶予期間を設けるべき」という判断が示されています。突然の退去要求は「権利の濫用」と判断される可能性もあるため、6か月程度の猶予期間を設けるのが一般的です。
Q3: 共有者の一人が亡くなった場合、使用貸借はどうなる?
A3: 貸主が亡くなった場合、使用貸借契約は原則として相続人に承継されます。ただし、契約が「当事者の一身に専属する」と解釈される場合は、契約が終了する可能性もあります。借主が亡くなった場合は、通常、契約は終了し、相続人が当然に使用権を引き継ぐわけではありません。個別の状況によって判断が異なるため、このようなケースでは早めに弁護士に相談することをおすすめします。
Q4: 共有持分だけを担保に入れることはできる?
A4: 共有持分だけを担保に入れることは法律上可能です。ただし、実務上は金融機関が共有持分だけを担保とした融資に消極的なケースが多いのが現実です。共有持分を担保にした場合、競売になっても買い手がつきにくく、担保価値が低いと判断されるためです。金融機関の調査によると、共有持分の担保評価は単独所有物件の30〜50%程度にとどまることが多いようです。
Q5: 使用貸借と占有の関係は?
A5: 使用貸借により借主は不動産を「占有」している状態になります。この占有状態が長期間続くと、「取得時効」の問題が発生する可能性があります。民法では、他人の物を20年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有した場合、その所有権を取得できる可能性があります。
ただし、使用貸借の場合は「所有の意思」が認められにくいため、使用貸借の状態から時効取得が認められるためには、使用貸借関係の否定(「返す必要はない」という明確な意思表示)とその後の20年間の占有が必要となります。明確な契約書があれば、このようなリスクを回避できます。
今回の記事では、共有持分と使用貸借という組み合わせが招きやすいトラブルと、その予防策について詳しく解説しました。
特に重要なのは「すべてを書面化すること」「定期的な話し合いの場を設けること」「早めに専門家に相談すること」の3点です。
相続や不動産の問題は一度トラブルになると解決までに長い時間とコストがかかります。事前の対策で回避できるトラブルも多いので、この記事で紹介した対策を早めに実行に移すことをおすすめします。不安なことがあれば、専門家への相談も検討してみてください。
そして最後に、すぐに実行できる具体的なアクション3つをもう一度おさらいしておきましょう。
- 共有不動産の登記簿を取得し、正確な持分割合と共有者を確認する
- 使用貸借状態の場合は契約書を作成または見直し、特に使用期間と費用負担を明確にする
- 共有者全員で今後の方針について話し合う場を設け、将来的な売却や相続についての意向を確認する
これらのステップを踏むことで、将来のトラブルを大幅に減らすことができるでしょう。

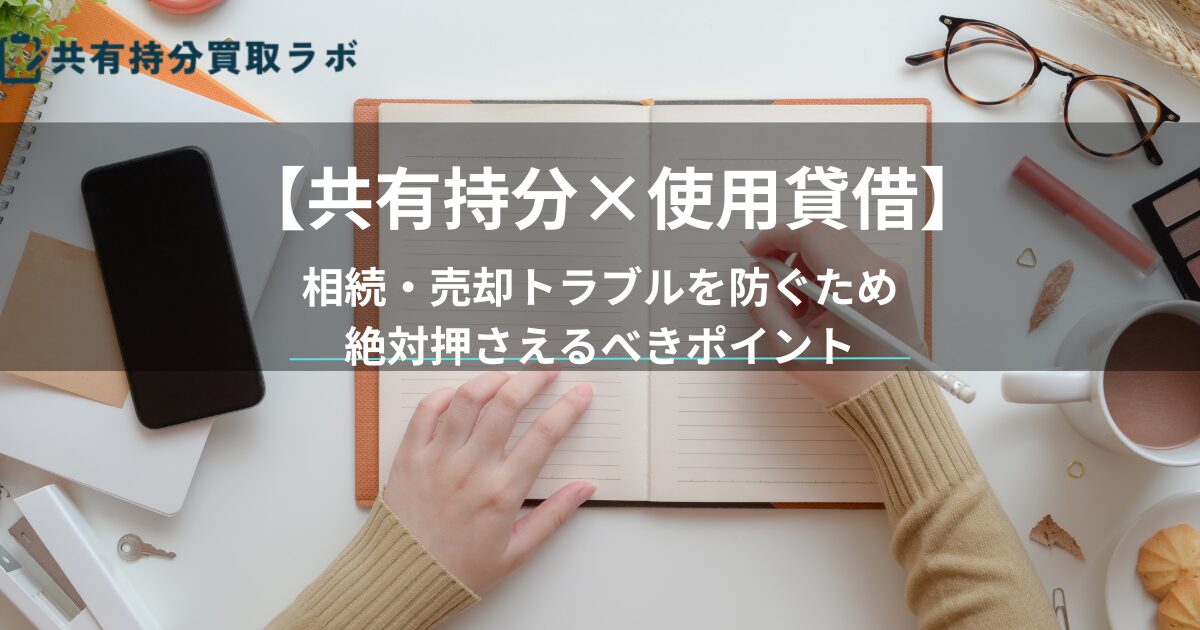

コメント