不動産取引の中でも特に注意が必要なのが「未登記建物の共有持分の売却」です。一般的な不動産売買とは異なる手続きやリスクがあるため、知識不足のまま取引を進めると思わぬトラブルに発展することがあります。
この記事では、未登記建物の共有持分を安全に売却するための基礎知識から具体的な手続き、そしてトラブル回避のポイントまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
未登記建物とは何か?

未登記建物とは、簡単に言えば法務局に建物の登記がされていない建物のことです。日本では建物を建てた後、法務局に登記をするのが一般的ですが、この登記は義務ではないため、登記せずに建てられた建物や、登記を怠ったままになっている建物が少なからず存在します。
特に古い建物や農村部の倉庫、離島の建物などでは未登記のままになっているケースが多く見られます。最近の調査によると、全国の建物のおよそ5%程度が未登記だと言われています。これは決して少ない数字ではありません。
未登記建物の「共有持分」とは、このような未登記建物を複数の人が共同で所有している状態を指します。例えば、親から子供たちに相続された実家が登記されていなかった場合、子供たちは未登記建物の共有持分を持つことになります。
登記されている建物と未登記建物の大きな違いは、所有権の公示方法にあります。登記されている建物であれば、誰でも法務局で登記簿を取得して所有者を確認できますが、未登記建物の場合はそれができません。そのため、所有権の証明が難しく、取引の際には特別な注意が必要になるのです。
未登記建物の共有持分を売却する前に知っておくべきこと

未登記建物の共有持分を売却する前に、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
まず大切なのが、未登記建物の所有権確認です。登記がない以上、法務局の書類だけでは所有権を証明できないため、固定資産税の納税証明書や固定資産評価証明書、建築確認申請書の写しなど、所有を裏付ける書類を集める必要があります。特に固定資産税の納税者情報は所有権の有力な証拠となるため、これらの書類は必ず準備しましょう。
次に共有持分の確定と権利関係の整理も重要です。例えば3人で共有している場合、各人の持分割合(例:Aさん2分の1、Bさん4分の1、Cさん4分の1)を明確にする必要があります。相続によって共有状態になった場合は、相続関係を示す戸籍謄本なども必要になります。
売却前の準備としては、次の書類を揃えておくと安心です。
- 固定資産税納税証明書(過去3〜5年分)
- 固定資産評価証明書
- 建物の間取り図や写真
- 建築確認申請書の写し(入手できる場合)
- 所有権を証明する公正証書や契約書の写し
- 相続の場合は戸籍謄本一式
未登記建物の評価方法については、一般的な不動産と異なる点があります。登記がないため正確な床面積や建築年が公的に証明されておらず、評価が難しいことが多いです。そのため、不動産鑑定士に依頼して評価書を作成してもらうことも一つの選択肢です。また、未登記であることを理由に市場価格より20〜30%程度低く評価されることもあるため、あらかじめ心づもりをしておきましょう。
未登記建物の共有持分売却の手続きステップ

未登記建物の共有持分を売却する手続きは、通常の不動産売却と比べていくつかの違いがあります。ここでは、売却までの流れを4つのステップに分けて説明します。
ステップ1:売却前の調査と書類準備
まず最初に行うべきことは、建物の現状調査です。建物の状態、敷地の境界、他の共有者の意向など、売却に影響する要素を確認します。特に未登記建物は図面や正確な情報が不足していることが多いため、実測調査を行うことも検討しましょう。
また、前述した所有権を証明する書類や、共有者全員の同意書なども準備する必要があります。共有者が多い場合は、全員の同意を得るのに時間がかかることもあるため、早めに交渉を始めることをおすすめします。実際に、共有者の同意取り付けには平均して1〜3か月程度かかるケースが多いです。
ステップ2:買主の探し方と注意点
未登記建物の共有持分は、一般の不動産市場で売りに出しても買い手がつきにくいことがあります。理由は単純で、多くの購入希望者は登記の有無を重視するからです。そのため、以下のような販売戦略が効果的です。
・他の共有者に買取りを打診する ・不動産投資家など、未登記物件に抵抗のない専門家層をターゲットにする ・地元の不動産業者に相談する(地域の事情に詳しい業者が適切)
買主を見つける際の注意点として、未登記であることをしっかり説明し、将来的なリスクも含めて誠実に情報開示することが大切です。「未登記」という事実を隠して売却すると、後々トラブルになる可能性が高くなります。
ステップ3:売買契約書の作成と特約事項
通常の不動産売買契約書とは異なり、未登記建物の共有持分売却の契約書には特別な条項を盛り込む必要があります。具体的には次のような特約事項が重要です。
・未登記建物であることの明記 ・所有権の証明方法に関する記載 ・将来登記する場合の協力義務 ・他の共有者の権利に関する説明 ・瑕疵担保責任(現在は「契約不適合責任」)の範囲
売買契約書は、できれば不動産取引に詳しい弁護士や司法書士に作成してもらうことをおすすめします。専門家への依頼費用は5〜10万円程度かかりますが、将来的なトラブル防止のための投資と考えると決して高くはありません。
ステップ4:代金受け渡しと権利移転の方法
最後のステップは、売買代金の受け渡しと権利移転です。通常の不動産取引では、決済と同時に所有権移転登記を行いますが、未登記建物の場合はこの部分が大きく異なります。
権利移転は、主に次のような方法で行われます。
・所有権移転に関する公正証書の作成 ・固定資産税の名義変更 ・建物賃貸借契約がある場合は賃借人への通知 ・建物に付随する保険や公共料金の名義変更
公正証書の作成には公証人役場で1〜2万円程度の費用がかかります。また、固定資産税の名義変更手続きは各市区町村の税務課で行います。これらの手続きが完了して初めて、法的に権利移転が認められると考えてよいでしょう。
未登記建物の共有持分売却で起こりやすいトラブル

未登記建物の共有持分売却では、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。事前に知っておくことで、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。
最も多いのは所有権証明に関するトラブルです。「実は他にも所有者がいた」「相続関係が複雑で権利関係が不明確」といったケースは珍しくありません。実際の事例では、売却後に別の相続人が現れて所有権を主張し、裁判に発展したケースもあります。このようなトラブルを避けるためには、徹底した事前調査と戸籍収集が欠かせません。
他の共有者とのトラブルも頻繁に起こります。共有持分を売却する際には原則として他の共有者の同意は法的には不要ですが、事前に知らせずに売却すると感情的なもつれが生じることがあります。また、持分割合の認識違いから紛争になるケースもあります。共有者間でコミュニケーションを密にし、書面で合意内容を残しておくことが重要です。
境界や面積に関する紛争も要注意です。未登記建物は正確な測量図面がないことが多く、実際の面積と想定していた面積が異なるケースがあります。特に隣接地との境界が不明確な場合、後々大きなトラブルに発展することがあるため、可能であれば売却前に測量を行うことをおすすめします。測量費用は建物の大きさにもよりますが、一般的に10〜20万円程度と考えておくとよいでしょう。
買主とのトラブル事例としては、「建物の状態が説明と違う」「雨漏りがある」などの物理的な不具合に関するクレームが多いです。未登記建物は古い物件が多いため、事前に建物状況調査(インスペクション)を実施し、その結果を買主に開示することで、後々のトラブルを防ぐことができます。インスペクション費用は5〜10万円程度ですが、この投資がトラブル防止につながります。
トラブルを未然に防ぐためのポイント

未登記建物の共有持分売却におけるトラブルを未然に防ぐためには、いくつかの重要なポイントがあります。
事前確認すべき5つのチェックリスト
- 所有権の確実な証明方法の確認:固定資産税納税証明書、購入時の契約書、相続関係の書類などが揃っているか
- 共有者全員の把握と連絡:全ての共有者を把握し、連絡が取れる状態になっているか
- 建物の物理的状態の確認:老朽化、雨漏り、シロアリ被害などの有無
- 固定資産税の納付状況:未納がないか確認(未納があると名義変更ができないことも)
- 境界確認と近隣関係:隣地との境界は明確か、近隣トラブルはないか
これらのチェックポイントを一つずつ確認していくことで、売却プロセスをスムーズに進めることができます。
専門家への相談:司法書士・不動産鑑定士の役割
未登記建物の取引は複雑なため、専門家のサポートを受けることが非常に重要です。特に以下の専門家の力を借りると安心です。
司法書士は、未登記建物の権利関係を整理し、適切な売買契約書の作成をサポートしてくれます。また、将来的に登記する場合のアドバイスも得られます。相談料は初回30分5,000円程度から、契約書作成は5〜10万円程度が相場です。
不動産鑑定士は、未登記建物の適正価格の査定を行います。市場価値を客観的に評価してもらうことで、適正な売却価格を設定できます。簡易的な評価で3〜5万円、詳細な鑑定評価書なら10〜20万円程度かかります。
土地家屋調査士は、建物の実測や境界確定を専門とする専門家です。特に境界トラブルを避けたい場合は、事前に依頼することをおすすめします。測量費用は10〜20万円程度が一般的です。
これらの専門家への費用は決して安くありませんが、後々のトラブルを考えると必要な投資と言えるでしょう。
共有者間の合意形成のコツ
共有者が複数いる場合、全員の合意を形成することが非常に重要です。合意形成を円滑に進めるためのコツをご紹介します。
まず、早い段階から情報共有を始めることが大切です。突然「売りたい」と言うのではなく、建物の状況や維持費の問題などを共有しながら、少しずつ売却の必要性について理解を求めていきましょう。
次に、全ての共有者にとってメリットがある提案をすることが重要です。例えば、売却益の分配方法について話し合い、公平な分配案を提示することで合意を得やすくなります。
話し合いの内容は必ず書面に残すことをおすすめします。「言った、言わない」のトラブルを避けるためにも、メールやLINEだけでなく、正式な合意書を作成しておくと安心です。
売買契約書に盛り込むべき特約条項
未登記建物の共有持分売却における売買契約書には、以下のような特約条項を盛り込むことをおすすめします。
- 未登記建物であることの明示:建物が未登記であることを明記し、買主がそれを理解した上で購入すること
- 所有権の証明方法:固定資産税納税証明書等によって所有権を証明すること
- 境界確定に関する事項:境界が未確定の場合はその旨と、将来境界トラブルが発生した場合の対応
- 他の共有者の権利に関する説明:他の共有者の存在と、その権利内容の説明
- 契約不適合責任の範囲:建物の瑕疵や不具合に関する責任の範囲と期間
- 将来登記する場合の協力義務:将来建物を登記する際に必要な協力をする義務
これらの特約条項を明確に定めることで、売主・買主双方の権利と義務が明確になり、トラブルを防止することができます。
未登記建物を登記するメリットと手続き

未登記建物を登記するメリットは数多くあります。特に重要なのは、所有権が公示されることによる安全性の向上です。登記されていれば、法務局で誰でも所有者を確認できるため、所有権をめぐるトラブルが大幅に減少します。
また、登記されることで金融機関からの融資を受けやすくなります。未登記建物は担保価値が低く評価されることが多いですが、登記されていれば正式な担保として認められやすくなります。実際に、登記建物と未登記建物では、融資可能額が30〜50%程度異なるケースもあります。
さらに、売却する際の市場価値も上昇します。登記されていれば購入希望者の不安要素が減り、適正価格での売却が期待できます。市場価値の向上率は物件にもよりますが、一般的に10〜20%程度と言われています。
未登記から登記への手続きの流れは以下のとおりです。
- 建物の表題登記申請準備:建物の所在、構造、床面積などを示す書類の準備
- 建物図面の作成:土地家屋調査士による実測・図面作成
- 所有権証明書類の準備:建築確認通知書、工事請負契約書、固定資産税納税証明書など
- 表題登記申請:法務局への申請
- 所有権保存登記申請:表題登記完了後、所有権を登記
この手続きに必要な費用としては、土地家屋調査士への依頼費用が15〜25万円程度、登録免許税が床面積に応じて計算され(木造住宅の場合、床面積1平方メートルにつき200円)、その他書類収集や印紙代などで数万円かかります。合計すると、一般的な住宅で20〜30万円程度の費用を見込んでおく必要があります。
手続きにかかる時間は、建物の状況や書類の揃い具合によって大きく異なりますが、スムーズに進んだ場合でも1〜2か月程度、複雑なケースでは半年以上かかることもあります。
登記後の売却手続きは、通常の不動産取引と同じになります。つまり、売買契約締結後、決済と同時に所有権移転登記を行うという流れです。未登記時の売却と比べると、はるかにスムーズで安全な取引が可能になります。
未登記建物の共有持分売却に関するQ&A

ここでは、未登記建物の共有持分売却に関してよくある質問と回答をまとめます。
- 未登記建物の共有持分だけを売ることはできますか?
はい、可能です。ただし、他の共有者への事前連絡や、境界・権利関係の明確化など、通常の物件以上に慎重な対応が必要です。また、買主を見つけるのが難しい場合もあります。
- 共有者全員の同意がないと売却できませんか?
法律上は、自分の持分だけであれば他の共有者の同意なく売却できます。ただし、実務上はトラブル防止のため、事前に他の共有者に通知し、できれば同意を得ることが望ましいです。
- 未登記建物を売却する際の税金の注意点は?
未登記でも登記済みでも、売却時の税金(譲渡所得税)の計算方法は基本的に同じです。ただし、取得費や譲渡費用の証明が難しいケースがあるため、領収書や契約書などの資料は大切に保管しておきましょう。また、3,000万円の特別控除や長期譲渡所得の軽減税率などの特例を適用できるケースもありますので、税理士に相談することをおすすめします。
- 相続した未登記建物の売却で特に注意すべき点は?
相続した未登記建物を売却する場合、まず相続関係をしっかり整理することが重要です。相続人全員の戸籍謄本を収集し、法定相続分や遺言の有無を確認します。また、相続登記をせずに売却することも可能ですが、その場合は相続人全員の同意書が必要になることが多いです。特に遠方に住む相続人がいる場合は、手続きに時間がかかることを想定しておきましょう。
- 複数の共有者がいる場合、どのように合意形成すればよいですか?
まずは全共有者による話し合いの場を設けることが大切です。直接会えない場合はオンライン会議などを活用しましょう。売却理由、希望価格、分配方法などを明確にし、できるだけ全員が納得できる提案をします。意見が分かれる場合は、不動産の専門家や弁護士などの第三者に仲介してもらうのも一つの方法です。最終的な合意内容は必ず書面にまとめ、全員の署名をもらっておくことが重要です。
まとめ:安全な取引のための最終チェックポイント

未登記建物の共有持分売却は、通常の不動産取引よりも複雑で注意が必要です。最後に、安全な取引のための最終チェックポイントをまとめます。
売却前の最終確認事項
・所有権を証明する書類は全て揃っているか ・共有者全員に売却の意向を伝えているか ・建物の状態を正確に把握し、買主に伝えているか ・固定資産税などの未納はないか ・境界や近隣関係に問題はないか ・売買契約書の特約事項は適切か
これらのポイントを一つひとつ確認することで、トラブルのリスクを大幅に減らすことができます。
専門家に相談すべきタイミング
未登記建物の共有持分売却では、次のようなタイミングで専門家に相談することをおすすめします。
・売却を検討し始めた初期段階(全体的なアドバイスを得るため) ・共有者間の合意形成が難しい場合(中立的な立場からの助言が必要なとき) ・売買契約書を作成する段階(適切な特約条項設定のため) ・税金の計算が複雑な場合(適切な節税対策のため)
早い段階から専門家に相談することで、後々の大きなトラブルを防ぐことができます。
取引後のフォローアップ
売買契約完了後も、以下のようなフォローアップが必要です。
・固定資産税の名義変更が完了したか確認 ・建物に関する保険や公共料金の名義変更 ・他の共有者への売却完了の通知 ・必要に応じて近隣住民への挨拶(新所有者の紹介)
これらのフォローアップを丁寧に行うことで、取引後のトラブルを防ぐことができます。
安心して取引を進めるための総合ポイント
未登記建物の共有持分売却を安全に進めるための総合的なポイントは、「情報開示」「書面化」「専門家活用」の3つです。
「情報開示」とは、建物の状態や権利関係について、買主に対して誠実に情報を提供することです。隠し事があると後々トラブルの原因になります。
「書面化」とは、共有者間の合意や買主との取り決めなど、全てのやり取りを書面に残すことです。口頭での約束は後で解釈が分かれる可能性があります。
「専門家活用」とは、不動産取引や法律の専門家のサポートを受けることです。少しコストはかかりますが、長い目で見れば安心の投資と言えるでしょう。
最後に、未登記建物の共有持分売却は確かに通常の不動産取引より複雑ですが、適切な知識と準備があれば安全に進めることができます。この記事を参考に、トラブルのない取引を実現してください。
今すぐ実行できる具体的なアクション3つ
- 所有権証明書類の収集を始める:固定資産税納税証明書、建物の写真、間取り図などの基本書類を今すぐ集め始めましょう。市区町村の税務課で取得できる書類もあります。
- 共有者全員のリストアップと連絡:誰が共有者なのか整理し、連絡先を確認しましょう。そして売却の意向を伝え、できるだけ早く話し合いの場を設定してください。
- 地元の不動産専門家への相談予約:未登記建物に詳しい司法書士や不動産会社に相談の予約を入れましょう。初回相談は無料の場合も多いので、まずは電話やメールで問い合わせてみてください。
未登記建物の共有持分売却は複雑ですが、正しい知識と適切な準備があれば、安全に取引を完了させることができます。ぜひこの記事を参考に、一歩ずつ着実に進めていきましょう。

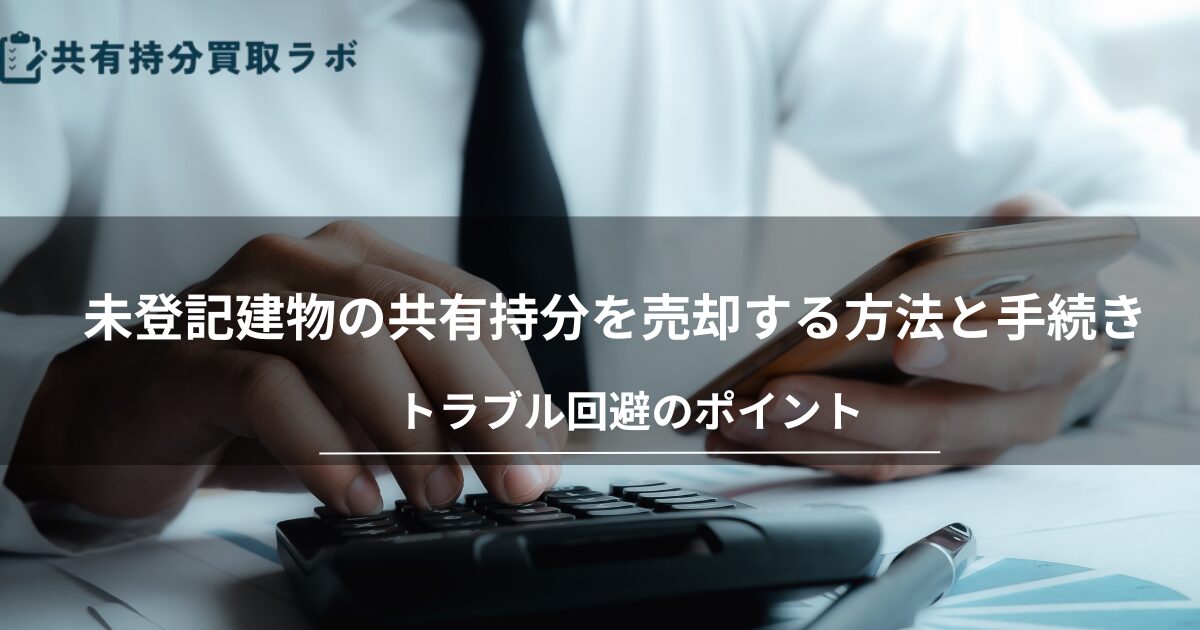

コメント