「マイホームを購入する際に、親子で共有名義にしたほうがいいのだろうか?」 「親の家を相続する際に、兄弟と共有名義にするべきか?」 「親子で共有名義にするとどんなメリットやデメリットがあるの?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。不動産の所有形態は、将来の住まい方や家族関係、税金、売却時の手続きなどに大きく影響します。特に親子での共有名義は、メリットもある一方で、思わぬトラブルのもとになることもあります。
この記事では、不動産の親子共有名義について、そのメリットとデメリット、注意すべきポイントを初心者の方にもわかりやすく解説します。将来を見据えた選択をするための参考にしてください。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
親子共有名義の基本と種類を理解しよう
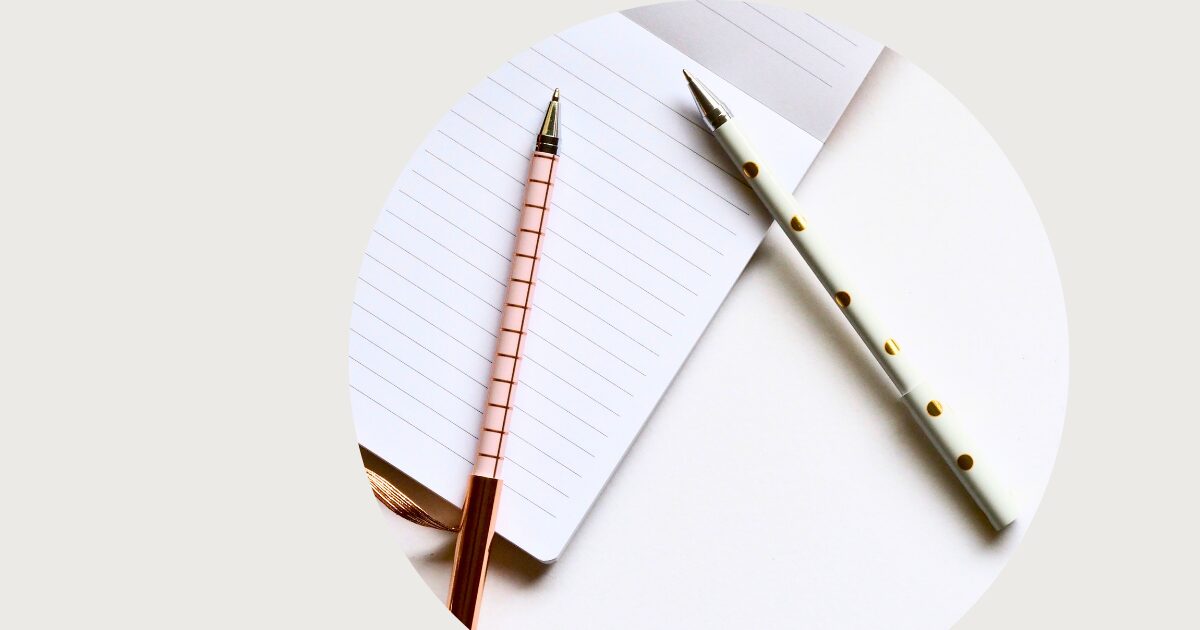
まず、「共有名義」とは何かから説明しましょう。共有名義とは、一つの不動産(土地や建物)を複数の人が共同で所有している状態を指します。登記簿には所有者として複数の名前が記載され、それぞれが「持分」と呼ばれる所有割合を持っています。
例えば、親と子で家を共有する場合、「父:2分の1、息子:2分の1」というように登記されることが多いです。もちろん「父:3分の2、息子:3分の1」のように、不均等な割合にすることも可能です。
親子間で共有名義が発生する典型的なケースとしては、以下のようなものがあります:
- 親子で資金を出し合って新しく不動産を購入する場合
- 親が所有していた不動産の一部を子に贈与する場合
- 親の死亡により相続が発生し、複数の子どもで共有する場合
- 親の生前に将来の相続を見据えて共有名義に変更する場合
共有状態では、民法上「共有物」として扱われ、基本的な管理は持分の過半数で決定できますが、売却などの重要な変更には共有者全員の同意が必要です(民法第251条、第252条)。この「全員の同意が必要」というルールが、後述するようなトラブルの原因になることもあります。
親子で不動産を共有名義にする7つのメリット

親子で不動産を共有名義にすることには、いくつかのメリットがあります。具体的に見ていきましょう。
1. 住宅ローンの借入可能額が増える
親子で共有名義にして共同で住宅ローンを組むと、それぞれの収入を合算して審査されるため、借入可能額が増えることがあります。例えば、子どもだけでは5,000万円しか借りられなかったところ、親と共同で申し込むことで7,000万円の住宅ローンが組める可能性があります。
特に若い世代が理想の物件を購入する際には、親の信用力や収入を借りることで、より良い条件や広い物件を選べるようになります。
ただし、親子ローンには年齢制限があることに注意が必要です。多くの金融機関では、完済時の親の年齢が80歳以下などの条件があります。例えば、30年ローンで60歳の親が共同名義になる場合は完済時に90歳になるため、審査に通らないケースがほとんどです。実際には65〜70歳までの親であれば、10〜15年程度の短期ローンなら共同名義者になれる可能性があります。
2. 親の資金援助を明確な形で残せる
親が子どものマイホーム購入を資金面で援助する場合、共有名義にすることで援助の形を明確に残せます。単に頭金として援助するだけでなく、親も所有者になることで資産として形に残ります。
これは、親の気持ちとしても安心感があるほか、将来的な兄弟姉妹間のトラブル防止にもつながります。例えば、親が一人の子だけに多額の援助をした場合、後の相続時に「不公平だ」と他の子どもが感じる可能性もありますが、共有名義であれば明確に記録が残ります。
また、親の資金援助が贈与ではなく「不動産の共有持分の取得」という形になれば、贈与税の問題を回避できるケースもあります。ただし、実際の資金の流れと持分割合が著しくかけ離れている場合は、税務署から「隠れた贈与」と見なされるリスクもあるため、専門家に相談して適切な割合を決めることが重要です。
3. 将来の相続手続きが簡略化できる
親の持分を将来相続する予定の子どもがあらかじめ共有者になっておくと、親が亡くなった後の相続手続きが一部簡略化されることがあります。全ての不動産を相続するよりも、親の持分だけを相続するほうが手続き上シンプルなケースもあります。
特に親が複数の不動産を所有している場合、生前に一部の不動産を子どもと共有にしておくことで、相続財産の分散と相続手続きの簡略化が図れます。例えば、親が3つの不動産を所有している場合、1つは長男と共有、もう1つは次男と共有、残りは親の単独所有のままにしておけば、将来の遺産分割協議がスムーズになる可能性があります。
ただし、相続税の総額自体が減るわけではないことに注意が必要です。あくまで手続きの簡略化と心理的な分割効果を狙った方法です。
4. 親子で費用や税金の負担を分散できる
共有名義にすると、固定資産税などの費用を持分割合に応じて分散できます。また、将来売却した際の譲渡所得も分散されるため、税率の累進性を考えると全体としての税負担が軽減されることがあります。
例えば、3,000万円の譲渡所得が出た場合、一人で全額課税されるより、親子で1,500万円ずつに分散したほうが、場合によっては税金の合計額が少なくなる可能性があります。
なお、固定資産税の納税通知書は代表者(通常は筆頭所有者)にのみ送られるため、内部的な精算方法をあらかじめ決めておくとトラブル防止になります。
5. 親の介護や同居の際の権利関係が明確になる
親子で同居する予定がある場合、共有名義にしておくと親の居住権が法的に保証されます。子どもだけの名義だと、万が一の際に親の居住権が不安定になる可能性もありますが、共有であれば親も所有者として権利を持っています。
特に親の老後を見据えて子どもの家に親が住む場合などは、共有名義にしておくことで親の安心感にもつながります。
6. 資産管理を共同で行える安心感
高齢の親にとって、不動産の管理(リフォームの判断や賃貸の手続きなど)は負担になることがあります。子どもと共有名義にしておくことで、子どもも正式な所有者として管理に参加できるため、親の負担軽減につながります。
また、子どもも自分の資産という意識を持つことで、適切な維持管理への意欲が高まるというメリットもあります。
7. 親の認知症など判断能力低下時のリスク軽減
親が認知症などで判断能力が低下した場合、不動産の売却や大きな修繕などの判断が難しくなります。共有名義であれば、子どもも所有者として一定の判断ができるため、完全に手続きがストップするリスクを軽減できます。
ただし、重要な変更には共有者全員の同意が必要なので、親が判断能力を失った場合は成年後見人の選任などが必要になる場合もあります。それでも、完全に親だけの名義であるよりは対応の幅が広がります。
親子共有名義の要注意!知っておくべき5つのデメリット

親子共有名義には上記のようなメリットがある一方で、見落としがちなデメリットもあります。以下に主なデメリットを解説します。
1. 売却や賃貸などの際に全員の同意が必要
共有名義の最大のデメリットは、不動産の売却や担保設定(住宅ローンなど)、大規模なリフォームなどの際に、共有者全員の同意が必要になることです。例えば、子どもが転勤で引っ越すことになり、家を売却したいと思っても、親が「思い出の家だから売りたくない」と反対すれば、売却できません。
逆に、親が老人ホームに入居するために売却したいと思っても、子どもが反対すれば同様です。共有者間で意見が分かれると、不動産が有効活用できないまま凍結状態になってしまうリスクがあります。
2. 親子関係の変化による影響
親子関係が良好なうちは問題なくても、将来的に関係が悪化した場合に大きな問題となります。例えば、子どもの離婚や親の再婚などによって家族関係が変化した場合、共有関係が複雑になるリスクがあります。
特に子どもが離婚した場合、場合によっては元配偶者が財産分与として持分を要求するケースもあり、家族以外の第三者が共有者になる可能性もあります。
3. 持分だけを第三者に売却されるリスク
共有持分は、他の共有者の同意がなくても第三者に売却できるというリスクがあります。例えば、経済的に困窮した子どもが自分の持分だけを業者に売却してしまうと、親は見知らぬ第三者と共有関係になってしまいます。
こうなると、トラブルの原因になるばかりか、不動産の価値自体も下がってしまう可能性があります。第三者が共有者になると、その後の売却や管理も格段に難しくなります。
4. 税金面での不利益が生じる可能性
共有名義にすることで、一部の税金控除が受けられなくなるケースがあります。例えば、住宅ローン控除は居住者のみが対象となるため、子どもが住んでいる家を親子共有にしている場合、親の持分については控除を受けられません。
また、3,000万円の特別控除(居住用財産を売却した場合に適用される税金の特例)なども、実際に住んでいない共有者の持分には適用されないことがあります。将来の売却を見据えると、税金面でのデメリットを考慮する必要があります。
5. 親の債務や子の債務が不動産に影響するリスク
親や子どもどちらかが債務を抱えた場合、その持分に差押えがかかるリスクがあります。例えば、子どもが事業に失敗して多額の負債を抱えると、その子どもの持分が債権者に差し押さえられる可能性があります。
同様に、親が何らかの保証人になっていて債務を負った場合も同じリスクがあります。共有名義にすることで、お互いの経済状況が不動産に影響する可能性が高まることを認識しておく必要があります。
親子共有名義でよくあるトラブルと解決策

親子共有名義でよく発生するトラブルとその解決策について見ていきましょう。実際の事例を交えて説明します。
共有者の一人が売却に反対するケース
【事例】 父と息子で共有していた実家を、息子は転勤を機に売却したかったが、父は「長年住んだ家を手放したくない」と反対。話し合いが平行線をたどり、実家は空き家になったまま数年が経過した。
【解決策】 このようなケースでは、以下の解決策が考えられます:
- 第三者である専門家(弁護士や不動産コンサルタント)に間に入ってもらい、客観的な判断を仰ぐ
- 反対している側の不安や懸念点を丁寧に聞き、対応策を検討する(例:売却後の住まいの確保など)
- 一方が他方の持分を買い取る方法を検討する
- どうしても話し合いがつかない場合は、「共有物分割請求」という法的手段を検討する
共有物分割請求とは、裁判所に共有関係の解消を求める手続きで、最終的には裁判所の判断で解決される仕組みです。ただし、家族間の関係悪化にもつながるため、最終手段と考えるべきでしょう。
維持費や修繕費の負担で揉めるケース
【事例】 母と娘で共有しているマンションで、大規模修繕の費用負担について意見が対立。母は「持分割合に応じて払うべき」、娘は「実際に住んでいるのは母だけだから、母が多く負担すべき」と主張して揉めた。
【解決策】 維持費や修繕費の負担については、以下のようなアプローチが有効です:
- 事前に書面で費用負担のルールを決めておく(持分割合通りか、居住者が多く負担するかなど)
- 修繕積立金とは別に、共有者間で修繕用の積立金を作っておく
- 一般的には民法上、持分割合に応じた負担が原則なので、それをベースに話し合う
- 実際の使用状況を考慮した「使用貸借料」の概念を導入して調整する
いずれにしても、共有名義にする際に、こうした費用負担についてあらかじめ合意しておくことが重要です。
共有者の一人が住んでいる場合の家賃や使用に関するトラブル
【事例】 父と息子で共有している家に父だけが住んでいたが、息子が「自分の持分があるのだから、家賃を払ってほしい」と要求して対立した。
【解決策】 共有不動産に一部の共有者だけが住んでいる場合は、以下のような対応が考えられます:
- 適正な家賃相場の一部(持分割合に応じた額)を居住者が非居住者に支払う取り決めをする
- 居住者が固定資産税や修繕費を全額負担する代わりに、家賃は不要とする取り決めをする
- 共有契約書や覚書を作成し、居住条件や費用負担を明確にしておく
こうしたケースは、共有名義にする時点で将来を見据えた取り決めをしておくことが非常に重要です。口頭の約束だけでは、後々「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。
親子共有名義の不動産に関する税金の知識

親子共有名義の不動産に関連する税金についても理解しておきましょう。
取得時の税金
不動産を取得する際には、不動産取得税や登録免許税がかかります。共有名義の場合、これらの税金は基本的に持分割合に応じて計算されます。
例えば、4,000万円の不動産を親と子で半分ずつ共有名義にする場合、不動産取得税は親と子がそれぞれ2,000万円分の税金を負担することになります。
また、すでに親が所有している物件の持分を子に贈与して共有名義にする場合は、贈与税が課税されます。ただし、年間110万円までの基礎控除や、住宅取得資金の贈与に関する特例などを利用することで、税負担を軽減できる可能性があります。特に住宅取得資金贈与の非課税特例は、令和5年(2023年)末までの時限措置で、条件を満たせば1,000万円(一般住宅)または1,500万円(省エネ住宅等)までの贈与が非課税となる制度です。
所有期間中の税金
所有期間中にかかる固定資産税や都市計画税も、原則として持分割合に応じた負担となります。ただし、納税通知書は代表者(通常は筆頭所有者)にのみ送られるため、内部的な精算が必要になることがあります。
例えば、固定資産税が年間15万円の場合、親と子が1/2ずつの共有なら、それぞれ7.5万円ずつ負担するのが原則です。
売却時の税金
不動産を売却した際の譲渡所得税は、共有者それぞれが自分の持分に対応する譲渡所得に対して納税します。居住用財産の場合、実際に住んでいた共有者は「3,000万円特別控除」などの特例を利用できる可能性がありますが、住んでいなかった共有者は特例を利用できないケースが多いです。
例えば、親子共有の家に子だけが住んでいて売却した場合、子の持分は居住用財産として特例が使えますが、親の持分には特例が適用されないことがあります。
長期譲渡所得(所有期間5年超)の場合の税率は所得税15%、住民税5%の合計20%(復興特別所得税を含めると20.315%)ですが、短期譲渡所得(所有期間5年以下)の場合は所得税30%、住民税9%の合計39%(復興特別所得税を含めると39.63%)となり、大きな差があります。共有持分を売却する際は、取得時期からの期間に注意が必要です。
相続時の税金
親が亡くなった場合、親の持分は相続財産として相続税の対象になります。共有名義にしていても、親の持分については相続税がかかることに変わりはありません。
ただし、あらかじめ共有名義にしておくことで、親の相続財産総額を減らす効果はあります。例えば、6,000万円の不動産を親が単独で所有していると6,000万円全額が相続財産ですが、親子で半分ずつ共有していれば、親の相続財産は3,000万円となります。
相続税は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えた部分に対して課税されるので、相続財産が少なければ相続税自体がかからない可能性も高まります。ただし、生前贈与で共有名義にした場合は、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるルール(3年以内の贈与加算)があるため注意が必要です。
親子共有にする前に必ず検討すべき代替案

親子共有名義には上記のようなメリット・デメリットがありますが、他の選択肢も含めて検討することが大切です。以下にいくつかの代替案を紹介します。
親名義のみにして子に賃貸する方法
親が不動産を所有し、子どもには賃貸契約を結んで住んでもらう方法です。この場合、所有権は親のみにあるため、将来的な売却や管理の判断がシンプルになります。子どもは家賃を支払うことになりますが、市場相場より安い「親子間賃貸」とすることも可能です。
この方法のメリットは、親が確実に家賃収入を得られること、将来的に親の介護費用などが必要になった際に売却の判断を親主導でできることなどです。デメリットは、子どもが住宅ローン控除を受けられないこと、子どもの住居費負担が継続することなどが挙げられます。
子名義のみにして親が使用貸借する方法
不動産を子ども名義にして、親は使用貸借(無償で借りる)契約を結んで住む方法です。この場合、親の相続財産を減らせるメリットがありますが、子どもの一存で親に退去を求められるリスクもあります。信頼関係が前提となる方法です。
子ども名義にする場合は、住宅取得資金贈与の非課税特例(令和5年まで最大1,500万円)を活用できる可能性があり、贈与税対策としても有効です。また、子どもが住宅ローンを組む場合は、住宅ローン控除も全額適用されます。
信託契約を活用する方法
最近注目されている方法として、「家族信託」があります。これは、親が所有する不動産を子どもに信託し、法的な所有権(受託者)と利益を受ける権利(受益権)を分離する仕組みです。親は受益権を保持したまま、子どもに管理・処分権を委ねることができます。
家族信託のメリットは、親の認知症リスクに備えられること(後見制度よりも柔軟な対応が可能)、相続時に遺言と組み合わせて複雑な承継プランを実現できることなどです。デメリットは、設定に専門家への報酬(30万円〜50万円程度)がかかること、まだ一般的でないため金融機関によっては対応に慣れていないことなどが挙げられます。
不動産管理会社を設立する方法
不動産規模が大きい場合や複数の不動産がある場合は、不動産管理会社(LLC、合同会社など)を設立し、そこに不動産を所有させる方法もあります。会社の株式や持分を親子で保有することで、実質的な共有状態を作りつつ、法的には会社が単独所有者となるため、意思決定がスムーズになります。
この方法は、不動産規模が大きい場合や事業用不動産の場合に検討価値がありますが、設立・運営コストがかかるため、一般的な居住用不動産ではオーバースペックになることも多いです。
それぞれの方法のメリット・デメリットの比較
以下の表は、各選択肢のメリットとデメリットを簡潔にまとめたものです。
親子共有名義:
- メリット:ローン借入額増加、将来の相続手続き簡略化、費用分散
- デメリット:全員の同意が必要、関係悪化時のリスク、税金控除の制限
親名義のみ(子に賃貸):
- メリット:所有権がシンプル、親の管理権確保、賃料収入
- デメリット:子どもの住宅ローン控除なし、相続税対策にならない
子名義のみ(親が使用貸借):
- メリット:相続税対策になる、子どもの住宅ローン控除あり
- デメリット:親の居住権が不安定、子どもの債務リスク
家族信託:
- メリット:親の意思尊重と子どもの管理権の両立、認知症対策
- デメリット:手続きが複雑、コストがかかる
状況や目的によって最適な選択肢は異なりますので、専門家に相談しながら検討することをおすすめします。
親子共有名義にする際の具体的な手続きと注意点

親子共有名義にする際の具体的な手続きと注意点について解説します。
新規購入時に共有名義にする手順
新しく不動産を購入する際に共有名義にする場合は、以下の手順になります:
- 不動産購入契約時に、買主を親子連名で記載する
- 住宅ローンを組む場合は、親子ともに借入審査を受ける
- 決済・引き渡し時に、共有者全員が署名・押印する
- 所有権移転登記を共有名義で行う(司法書士に依頼するのが一般的)
購入時から共有名義にする場合は比較的シンプルですが、住宅ローンを組む金融機関によっては、共有者全員がローン契約者になることを求められる場合があります。
既存の不動産を共有名義に変更する方法
すでに親または子が単独で所有している不動産を共有名義に変更する場合は、以下の手順になります:
- 持分の一部を贈与または売買する(例:親が持分の2分の1を子に贈与)
- 贈与の場合は贈与契約書、売買の場合は売買契約書を作成する
- 所有権一部移転登記を行う(司法書士に依頼するのが一般的)
- 贈与の場合は贈与税の申告(暦年課税の特例などを検討)、売買の場合は印紙税などの諸費用が必要
既存の不動産を共有名義に変更する場合は、税金面での考慮が特に重要です。贈与税や登録免許税などのコストを事前に確認しておきましょう。
適切な持分割合の決め方と考慮すべきポイント
持分割合をどう設定するかは、以下のポイントを考慮して決めるとよいでしょう:
- 出資割合に応じた設定(購入資金をどれだけ出したか)
- 将来の居住予定(誰がどのくらい住む予定か)
- 税金対策(相続税や贈与税の影響)
- 将来の売却時の取り分
例えば、親が頭金の大部分を出し、子どもがローンを返済する場合は、最初は親の持分を大きくし、ローンの返済に応じて子どもの持分を増やしていく方法も考えられます。
共有名義にする前に作成しておくべき書類や取り決め
トラブル防止のために、以下のような書類や取り決めを事前に作成しておくことをおすすめします:
- 共有者間の合意書または覚書(各自の権利と義務を明記)
- 費用負担の取り決め(固定資産税、修繕費などの分担方法)
- 将来の売却に関する取り決め(一定期間後の売却合意など)
- 一方が住む場合の家賃や使用に関する取り決め
- 将来の持分変更に関する合意(ローン返済に応じた持分変更など)
特に重要なのは、将来起こりうるトラブルを想定した取り決めです。「親子だから大丈夫」という考えは避け、ビジネスライクに書面で合意しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
今すぐできる3つの具体的アクション

親子共有名義について理解を深めたところで、次のステップとして今すぐ実行できる具体的なアクションを3つ紹介します。
1. 家族で不動産の将来計画について話し合いの場を設ける
まずは家族で集まり、不動産の将来についてオープンに話し合いましょう。以下のポイントを議題にすると効果的です:
- それぞれが不動産に対してどのような希望や計画を持っているか
- 5年後、10年後、20年後にどのように住みたいか、または活用したいか
- 将来的な売却の可能性はあるか
- 親の老後の住まいをどうするか
- 兄弟姉妹が複数いる場合、公平性をどう確保するか
話し合いの結果を議事録として残しておくと、後々の意思確認に役立ちます。この段階では細かい法律や税金の知識は不要ですので、率直な気持ちを共有することを重視してください。
アドバイスとしては、将来の生活状況の変化(親の介護必要性、子どもの転勤可能性など)も視野に入れることが重要です。感情的にならずに現実的な視点で話し合うことを心がけましょう。
2. 現在の不動産の登記簿謄本と評価額を確認する
現在の不動産の正確な状況を把握するために、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、以下の点を確認しましょう:
- 現在の所有者と持分割合
- 抵当権などの付帯条件
- 土地の地目や面積、建物の構造や床面積
登記簿謄本は法務局で取得できます(1通約600円)。オンラインでも申請可能で、法務局の登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)が便利です。
また、不動産の現在の評価額も把握しておくことが重要です。以下の方法で概算値を知ることができます:
- 固定資産税評価証明書を取得する(市区町村役場で発行、300円〜500円程度)
- 不動産一括査定サイト(HOME4UやSUUMOなど)で市場価格の目安を調べる
- 近隣の類似物件の相場を調査する(不動産情報サイトの売り出し価格を参考に)
これらの情報は、共有名義にする際の持分割合や税金対策を検討する基礎データとなります。評価額は路線価から計算することもできますが、専門家のアドバイスを受けるとより正確です。
3. 不動産や相続に詳しい専門家に相談する
親子共有名義に関する判断は、法律や税金の専門知識が必要です。以下のような専門家に相談することをおすすめします:
- 弁護士(不動産法務に詳しい方):法的リスクやトラブル防止策の相談
- 税理士:税金面での有利不利の判断、相続対策の相談
- 司法書士:登記手続きの方法や費用の相談
- ファイナンシャルプランナー:家計全体を見据えた資産設計の相談
初回相談は無料または数千円程度で受けられる専門家も多いので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。複数の専門家の意見を聞くことで、より良い判断ができるようになります。相談前には、現在の資産状況や将来の希望をまとめた資料を準備しておくと効率的です。
また、国や自治体が提供する無料相談窓口も活用できます。例えば、法テラス(日本司法支援センター)では法律相談を、各自治体の住宅相談窓口では不動産関連の相談を受け付けています。まずはこうした公的機関に相談してから、必要に応じて専門家に依頼するという段階的なアプローチも費用を抑える点でおすすめです。
親子共有名義は、メリットもあれば注意すべきリスクもある選択肢です。家族の状況や将来計画を踏まえて、慎重に検討することが大切です。この記事が、あなたの家族にとって最適な選択をするための参考になれば幸いです。士:税金面での有利不利の判断、相続対策の相談
- 司法書士:登記手続きの方法や費用の相談
- ファイナンシャルプランナー:家計全体を見据えた資産設計の相談
初回相談は無料または数千円程度で受けられる専門家も多いので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。複数の専門家の意見を聞くことで、より良い判断ができるようになります。
親子共有名義は、メリットもあれば注意すべきリスクもある選択肢です。家族の状況や将来計画を踏まえて、慎重に検討することが大切です。この記事が、あなたの家族にとって最適な選択をするための参考になれば幸いです。

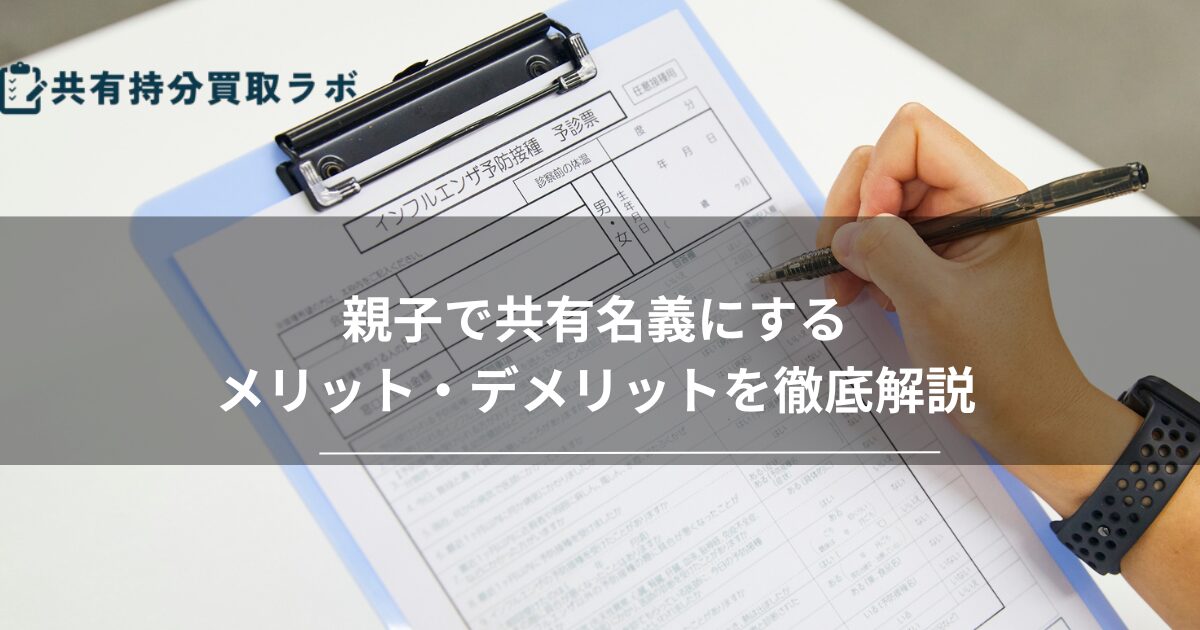

コメント