不動産を複数の人で所有している状態を「共有」といいます。この共有状態では、それぞれの人が持っている権利の割合のことを「共有持分」と呼びます。例えば、ある土地を兄弟3人で相続した場合、それぞれが3分の1ずつの持分を持つことになるのです。
共有持分は不動産登記簿に記載され、「持分3分の1」などと表示されます。この持分があることで、不動産から得られる収益や将来売却する際の代金も、その割合に応じて分配される仕組みになっています。
しかし、共有状態は様々な問題を引き起こすことがあります。
そのため、「共有持分を一人に集める(全部移転する)」という選択肢が検討されることがあるのです。この記事では、共有持分の全部移転についての基本から実践的なアドバイスまでを徹底解説していきます。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有持分の全部移転が必要になるケース

共有持分の全部移転が必要になる典型的なケースをいくつか見ていきましょう。
まず最も多いのが「相続」です。親が亡くなった後、不動産が子どもたち複数人に相続されることで共有状態になります。しかし、実際にその不動産に住んでいるのは子どものうちの一人だけというケースがよくあります。この場合、住んでいる人が他の相続人から持分を買い取って、自分の名義にまとめることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
次に多いのが「夫婦での共有」です。結婚して共同で購入した不動産を、離婚の際に一方に集約したいというケースです。または、夫婦の一方が高齢になり、相続対策として配偶者に全部移転することもあります。
また「共同事業者間での整理」も見られます。複数人で投資用不動産を購入したものの、事業方針の違いや資金需要の変化から、一人の所有にまとめたいというケースです。
さらに「親族間での資産整理」もあります。例えば、親が子や孫に少しずつ贈与していた不動産の持分を、将来的な管理のしやすさを考えて一人にまとめることがあります。
これらのケースに共通するのは、「複数人での所有による意思決定の複雑さ」と「将来的なトラブル防止」という課題です。共有持分を全部移転することで、不動産の管理や処分がスムーズになり、家族や関係者間の揉め事を未然に防ぐことができるのです。
共有持分の全部移転前に知っておくべきこと

共有持分の全部移転を考える前に、いくつか理解しておくべき基本的なことがあります。
まず、共有持分の移転には原則として「共有者全員の合意」は必要ありません。自分の持分は自分の財産ですので、他の共有者の同意なく第三者に売却や贈与することができます。ただし、家族間などで行う場合は、後々のトラブル防止のためにも、事前に十分な話し合いをしておくことが賢明です。
次に、共有持分の移転方法には大きく分けて「売買」と「贈与」があります。売買の場合は適正な価格での取引が求められ、贈与の場合は税金面での配慮が必要になります。どちらの方法を選ぶかによって、必要な書類や発生する税金が異なってきますので、目的に合わせた選択が重要です。
また、共有持分の全部移転を行う際には、不動産の価値評価をしっかり行うことが大切です。特に相続や贈与の場合、税務上の問題が生じないよう、適正な評価額を把握しておく必要があります。路線価や実勢価格、収益還元法など、複数の評価方法を検討することをおすすめします。
さらに、共有持分の移転には「登記」が必要です。登記を行わないと、法律上の所有権移転が完了したことにならず、将来的なトラブルの原因になります。登記手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼することが一般的です。
最後に、共有持分の移転には様々な「費用」がかかります。登録免許税や印紙税などの税金、司法書士への報酬、場合によっては不動産取得税なども発生します。これらの費用を事前に把握しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
これらの基本事項を理解した上で、具体的な手続きを進めていくことが、トラブルなく共有持分の全部移転を実現するコツです。
共有持分の全部移転手続きの流れ

共有持分の全部移転を行う際の基本的な手続きの流れを、わかりやすく説明していきます。
手順1:共有者間での合意形成
まず最初のステップは、共有者間での話し合いです。誰がどの持分を取得するのか、対価はいくらにするのか、いつまでに手続きを完了させるのかなどを明確にします。この段階で、できれば書面で合意内容を残しておくと安心です。特に家族間であっても、後々のトラブル防止のために、「持分移転契約書」のような形で合意内容を文書化することをおすすめします。
手順2:必要書類の準備
次に、移転手続きに必要な書類を準備します。主な必要書類は以下の通りです。
- 登記識別情報(旧権利証)
- ]印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 住民票(同じく3ヶ月以内)
- 固定資産評価証明書 ・実印
- (売買の場合)売買契約書
- (贈与の場合)贈与契約書
これらの書類は、移転の方法や不動産の状況によって異なる場合がありますので、事前に司法書士に確認するとよいでしょう。
手順3:契約の締結
書類が揃ったら、正式に契約を締結します。売買であれば売買契約書、贈与であれば贈与契約書を作成し、関係者全員が署名・押印します。契約書には、対象となる不動産の表示、移転する持分の割合、対価(売買の場合)、契約日、引き渡し日などを明記します。
手順4:登記申請の準備と申請
契約が締結されたら、登記申請の準備に入ります。登記申請書の作成は専門的な知識が必要なため、通常は司法書士に依頼します。司法書士に依頼する場合は、前述の必要書類一式を提出し、委任状に署名・押印することになります。
登記申請書が作成されたら、管轄の法務局に申請します。申請の際には登録免許税を納付する必要があります。登録免許税は不動産の評価額に対して一定の税率(現在は0.4%)がかかります。
手順5:登記完了と確認
申請から約1〜2週間程度で登記が完了します。完了後は登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、正しく登記されているかを確認しましょう。特に名義や持分割合が正確に記載されているかのチェックが重要です。
手順6:税務申告(必要な場合)
取引内容によっては、税務申告が必要になる場合があります。贈与の場合は贈与税の申告(翌年2月1日〜3月15日)、売買で利益が出た場合は譲渡所得税の申告(翌年2月16日〜3月15日)が必要です。申告期限を過ぎると加算税などのペナルティが発生する可能性がありますので、注意しましょう。
共有持分の全部移転にかかる費用の詳細

共有持分の全部移転には、いくつかの費用がかかります。ここでは、主な費用項目とその目安について解説します。
登録免許税
登記を行う際に必要な税金です。持分を移転する不動産の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。持分移転の場合の税率は不動産の種類によって異なりますが、土地・建物の所有権移転登記では通常0.4%(特例が適用される場合は0.1〜0.3%)です。
例えば、固定資産税評価額2,000万円の不動産の持分2分の1を移転する場合、2,000万円×1/2×0.4%=4万円が登録免許税の額になります。
印紙税
契約書に貼る収入印紙の費用です。売買契約書の場合、取引金額に応じて税額が決まります。例えば、500万円以下の売買なら1,000円、5,000万円以下なら1万円といった具合です。贈与契約書の場合は、原則として一律200円となっています。
司法書士報酬
登記手続きを司法書士に依頼する場合の報酬です。司法書士によって料金体系は異なりますが、一般的には不動産の評価額や取引の複雑さに応じて決まります。持分全部移転の場合、5〜15万円程度が相場となっています。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
不動産取得税
不動産を取得した際にかかる税金です。取得した不動産の固定資産税評価額に税率(現在は住宅用地・住宅は3%、その他は4%)をかけて計算します。ただし、取得する持分が小さい場合や、一定の条件を満たす場合には非課税になることもあります。
その他の費用
上記以外にも、以下のような費用がかかることがあります。
・書類取得費用(住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書など):1通あたり300〜500円程度 ・銀行振込手数料(売買代金を振り込む場合) ・交通費(法務局や司法書士事務所への往復交通費) ・相談料(税理士や弁護士に相談する場合)
共有持分の全部移転にかかる総費用は、不動産の価値や取引条件によって大きく異なりますが、おおよそ10〜30万円程度(登録免許税や不動産取得税を除く)と考えておくとよいでしょう。高額な不動産の場合はさらに費用が増えることもあります。
費用を抑えるコツとしては、複数の司法書士から見積もりを取る、特例や控除の適用可能性を確認する、まとめて手続きを行うなどが挙げられます。特に税金面では専門家のアドバイスを受けることで、合法的に節税できる可能性があります。
共有持分の全部移転と税金対策

共有持分の全部移転を考える際、税金面での対策は非常に重要です。ここでは、主に関係する税金と節税のポイントについて解説します。
贈与税について
共有持分を無償または著しく低い価格で移転する場合、贈与税の対象となります。贈与税は基礎控除(年間110万円)を超える部分に対して課税され、税率は10〜55%(特例を除く)と高めに設定されています。
例えば、市場価値2,000万円の不動産の持分2分の1(1,000万円相当)を贈与した場合、基礎控除110万円を差し引いた890万円に対して税率がかかります。この場合、約170万円の贈与税が発生する計算になります。
ただし、配偶者や親族への贈与には特例があります。例えば、「配偶者控除」を使えば、居住用不動産の贈与について最大2,000万円まで非課税になります。また、「相続時精算課税制度」を選択すれば、親から子への贈与について2,500万円まで非課税となり、超過分も一律20%の税率で済みます(ただし相続時に精算)。
相続対策としての共有持分移転
共有持分の移転は相続対策としても有効です。例えば、親が生前に子に少しずつ共有持分を贈与することで、相続時の遺産総額を減らし、相続税の負担を軽減できます。贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用すれば、10年間で1,100万円までは非課税で移転可能です。
また、共有持分を配偶者に移転することで、配偶者控除や配偶者の税額軽減を最大限に活用できるケースもあります。相続税の配偶者控除は法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい額まで非課税となります。
相続と売買の使い分け
共有持分の全部移転の方法として、「贈与」と「売買」があります。贈与税の負担が大きい場合は、適正価格での売買を検討する価値があります。売買であれば贈与税はかかりませんが、売り手側には譲渡所得税(所得税・住民税)が発生する可能性があります。
例えば、相続で取得した不動産の共有持分を他の相続人から買い取る場合、売り手側は「取得費加算の特例」を使えることがあります。これは、相続税のうち不動産に対応する部分を取得費に加算できる制度で、譲渡所得税の軽減につながります。
不動産の評価方法の選択
共有持分の価値評価には複数の方法があり、選択によって税負担が変わることがあります。例えば、相続税評価では「路線価」が用いられますが、実際の市場価値より低いケースが多いです。一方、譲渡所得の計算では「実勢価格」が基準となります。
また、収益物件の場合は「収益還元法」による評価も可能です。この方法では物件の収益力に基づいて価値を算出するため、利回りの低い物件では評価額が下がり、税負担が軽減される可能性があります。
税金対策は非常に専門的で、法改正も頻繁にあるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。特に高額な不動産や複雑な持分関係の場合は、専門家のアドバイスが税負担を大きく軽減する可能性があります。
共有持分の全部移転で揉めないためのポイント
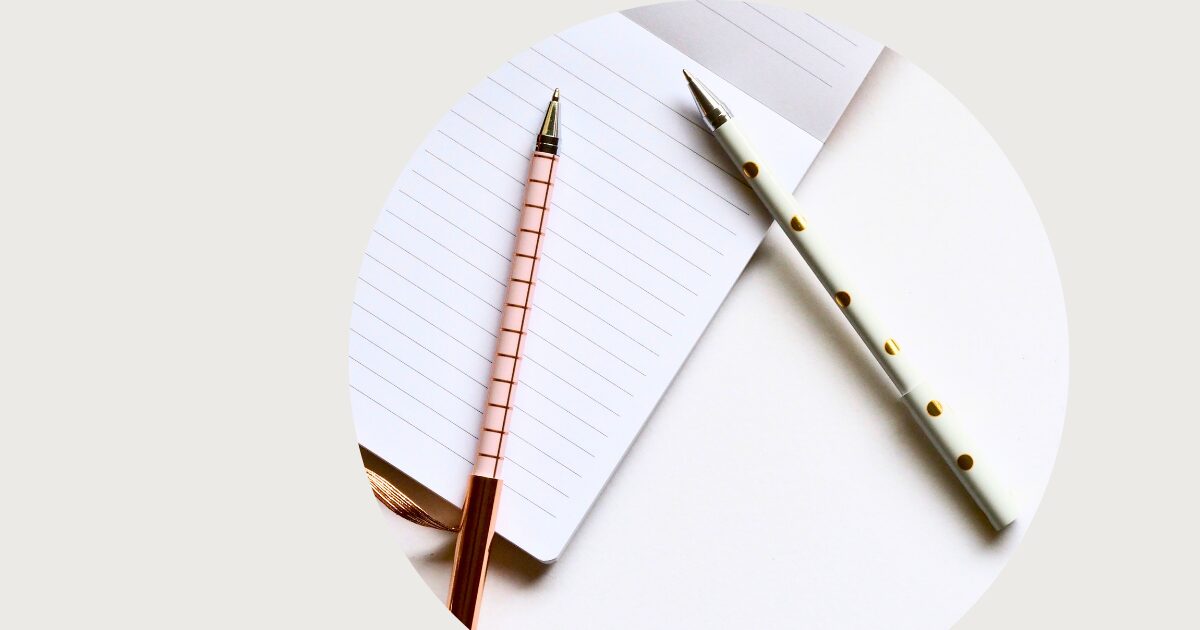
共有持分の全部移転は、家族間や共有者間での感情的なもつれや誤解から揉め事に発展することがあります。ここでは、スムーズに進めるためのポイントを解説します。
早い段階からの丁寧な説明と対話
共有持分の全部移転を考え始めたら、まず関係者全員に対して、なぜ移転が必要なのか、どのようなメリットがあるのかを丁寧に説明しましょう。一方的な通知ではなく、相手の意見や懸念事項も聞き入れる姿勢が大切です。
例えば、親から子への持分移転を考える場合、「将来の相続を円滑にするため」「固定資産税などの負担を整理するため」といった目的を明確に伝え、他の家族にも理解を求めることが重要です。
公平性への配慮
特に家族間での持分移転では、不公平感が揉め事の原因になりやすいです。一人の子どもだけが不動産の持分を集めるような場合、他の子どもたちに対して適切な補償や説明が必要です。
例えば、兄弟の一人が親の家に住み続けるために他の兄弟の持分を集める場合、その対価として他の資産を分配したり、将来の売却益の一部を約束したりするなど、全体としてのバランスを取ることを検討しましょう。
書面による合意の徹底
口頭での合意だけでなく、必ず書面で内容を残すことが重要です。「いつ」「誰の」「どの持分を」「いくらで」「どのように」移転するかを明記した契約書や覚書を作成しましょう。
特に重要なのは以下の点です。
・移転する持分の正確な記載(例:持分2分の1全部) ・対価がある場合はその金額と支払い方法、時期 ・登記費用や税金の負担者 ・引き渡し条件や期限 ・特約事項(例:売却時の優先交渉権など)
これらの内容を書面化しておくことで、後々の「言った言わない」というトラブルを防ぐことができます。
専門家の活用
共有持分の移転は法律や税務の専門知識が必要な手続きです。一般の方が自力で進めようとすると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。信頼できる専門家(司法書士、税理士、場合によっては弁護士)のサポートを受けることをおすすめします。
特に複雑なケースでは、中立的な立場の専門家に入ってもらうことで、感情的な対立を避け、客観的な判断に基づいた手続きが可能になります。
将来を見据えた取り決め
共有持分の全部移転を行った後のことも考えておくことが重要です。例えば、不動産を取得した人が将来売却する場合の他の元共有者への通知義務や優先交渉権、賃貸している場合の収益分配方法などについても、可能な範囲で取り決めておくと安心です。
特に家族間での移転の場合、「いずれは売却して分配する」というような暗黙の了解があることもありますが、そのような内容も覚書などの形で残しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
共有持分の全部移転の具体的な事例紹介
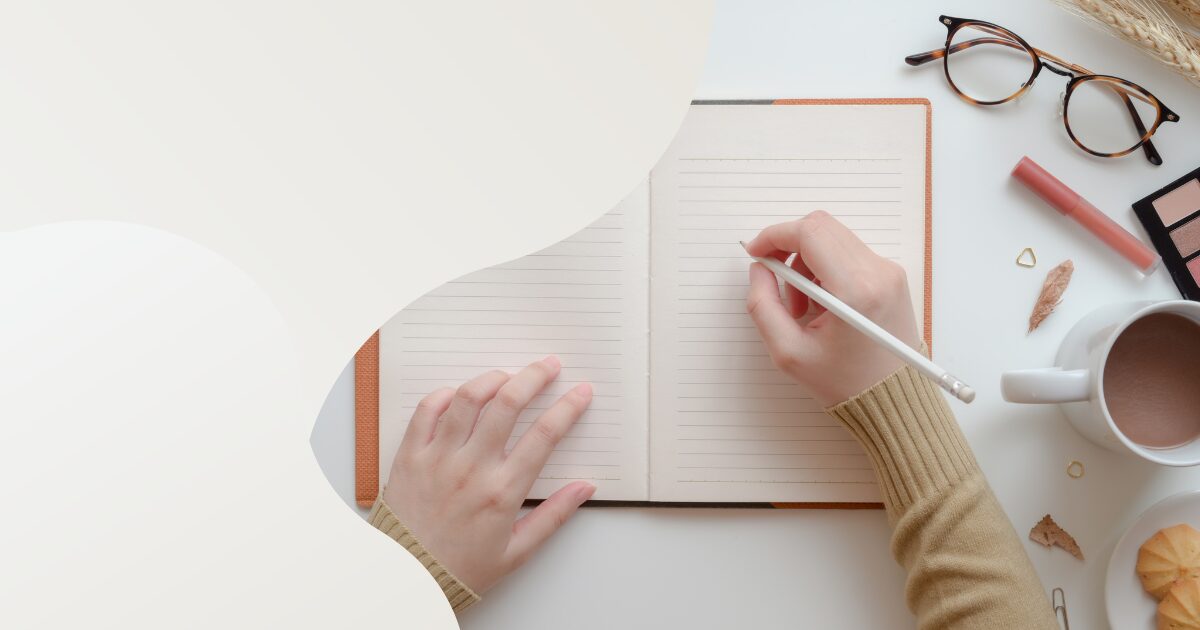
ここでは、実際にあった共有持分の全部移転の事例とその教訓を紹介します。
事例1:親から子への持分移転で成功したケース
70代の両親が所有する実家について、長男家族が同居していたケースです。両親は将来の相続時のトラブルを避けるため、生前に持分を整理することにしました。
まず、両親と3人の子ども全員で家族会議を開き、「長男家族が実家に住み続ける」という方針を共有しました。次に、不動産の適正価格を不動産鑑定士に依頼して算出。両親はそれぞれの持分2分の1ずつを、長男に対して贈与と売買を組み合わせて移転しました。
具体的には、父親の持分2分の1のうち、基礎控除内の部分(評価額110万円分)を贈与し、残りを10年間の分割払いで売買。母親も同様の方法を取りました。また、次男と三男には、別の金融資産を生前贈与することで、バランスを取りました。
この事例の成功ポイントは、
- 早い段階での家族会議による方針共有
- 専門家による適正な評価額の算出
- 税金対策(基礎控除の活用と分割払いの組み合わせ)
- 他の相続人への配慮(別資産での生前贈与)
- すべての取り決めを公正証書で残したこと
事例2:共有持分の集約に失敗したケース
兄弟3人で相続した賃貸アパートの事例です。当初は共有のまま運営していましたが、修繕方針で意見が分かれるようになりました。長男が他の兄弟から持分を買い取って一元管理しようと提案しましたが、うまくいきませんでした。
失敗の原因は以下の点にありました。
- 提案が突然で、他の兄弟に十分な説明がなかった
- 買取価格が市場価値より低く設定されていた
- 将来の売却益の分配についての取り決めがなかった
- 感情的な対立が生じた際の仲介者がいなかった
結局、不動産は売却され、売却益を3等分することになりましたが、売却までに2年以上の時間を要し、その間の管理も滞るという結果になりました。
事例3:離婚時の共有持分移転で円滑に進んだケース
夫婦で購入したマンションの持分を、離婚に伴い整理したケースです。当初は夫婦で各2分の1ずつの持分でしたが、離婚協議の中で、妻が夫の持分を買い取ることになりました。
円滑に進んだポイントは以下の通りです。
- 弁護士と不動産鑑定士を交えた話し合いを行った
- 住宅ローンの借り換えを含めた総合的な解決策を検討した
- 子どもの養育費と絡めて、分割払いの仕組みを構築した
- すべての合意内容を離婚協議書に明記した
この事例では、専門家のサポートと詳細な取り決めが功を奏し、感情的な対立を最小限に抑えながら持分移転を実現することができました。
これらの事例から学べる共通の教訓は、「早い段階での丁寧な説明」「適正な価格設定」「専門家の活用」「将来を見据えた取り決め」「書面化の徹底」の重要性です。特に家族間での持分移転では、金銭面だけでなく感情面にも配慮した対応が成功の鍵となります。
Q&A:共有持分の全部移転についてよくある質問
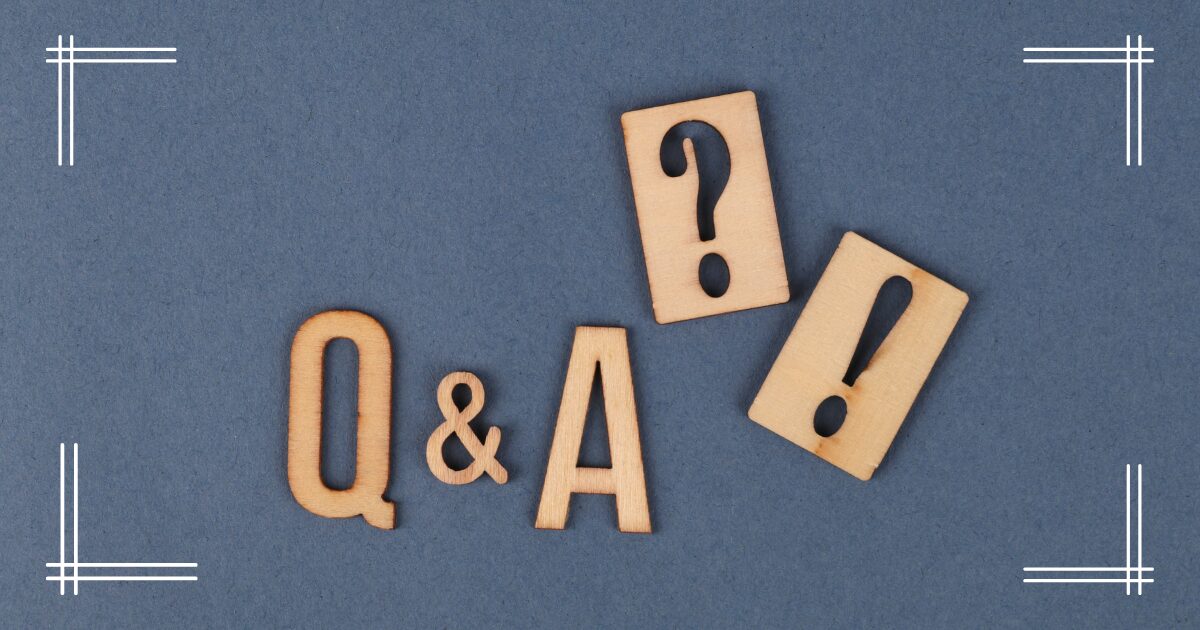
ここでは、共有持分の全部移転に関して多く寄せられる質問と回答をまとめました。
- 共有者全員の同意がない場合でも、持分移転はできますか?
基本的に自分の持分は自分の財産ですので、他の共有者の同意がなくても第三者に売却や贈与することは可能です。ただし、家族間などで後々トラブルになることを避けるためには、事前に十分な説明と話し合いを行うことをおすすめします。なお、共有物全体の処分(売却など)には共有者全員の同意が必要です。
- 相続で共有状態になった不動産を一人に集約するには、どのような方法がありますか?
主な方法としては、(1)他の相続人から買い取る方法、(2)代償分割として他の相続人に金銭などの代償を渡す方法、(3)遺産分割協議で当該不動産を取得する代わりに他の遺産を放棄する方法などがあります。どの方法が適しているかは、相続財産の内容や相続人の事情によって異なりますので、専門家に相談することをおすすめします。
- 登記手続きは自分でもできますか?専門家に依頼するメリットは?
理論上は本人でも登記申請は可能ですが、専門的な知識が必要なため、一般的には司法書士に依頼することが多いです。専門家に依頼するメリットとしては、(1)書類作成の正確性が担保される、(2)手続きの漏れや不備を防げる、(3)トラブルが発生した際の相談先になる、(4)関連する税務アドバイスも受けられる可能性がある、などが挙げられます。特に複数の共有者間での持分移転では、中立的な専門家が入ることで円滑に進むケースが多いです。
- 共有持分を移転する際の税金対策で、特に注意すべき点は?
税金面で特に注意すべき点は、(1)贈与税の基礎控除(年間110万円)を有効活用する、(2)配偶者控除や相続時精算課税制度などの特例を検討する、(3)売買と贈与を適切に組み合わせる、(4)不動産の適正な評価方法を選択する、などです。また、将来の譲渡所得税(キャピタルゲイン税)も視野に入れた長期的な税金対策を考えることが重要です。不動産の価値が高い場合や、税務関係が複雑な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
- 共有持分の移転に必要な費用の相場はどれくらいですか?
費用は不動産の価値や取引の複雑さによって異なりますが、一般的には登録免許税(不動産評価額の0.4%程度)、印紙税(1,000円〜数万円)、司法書士報酬(5〜15万円程度)などがかかります。合計すると、小規模な物件で10万円前後、大きな物件では数十万円になることもあります。なお、贈与の場合は贈与税、売買の場合は譲渡所得税がさらに加わる可能性があります。正確な費用は専門家に相談して見積もりを取ることをおすすめします。
- 共有持分を買い取る際の「適正価格」はどう決めればよいですか?
適正価格の決定方法としては、(1)不動産鑑定士による評価、(2)公示価格や路線価からの算出、(3)近隣の類似物件の取引価格参考、(4)収益物件の場合は収益還元法による算出、などがあります。特に家族間での取引では、後々のトラブルを避けるために、第三者の専門家による評価を取り入れることが望ましいでしょう。また、税務上は「著しく低い価額」での取引が贈与とみなされる可能性もありますので、適正価格での取引を心がけることが大切です。
まとめ:共有持分の全部移転を円滑に進めるためのチェックリスト
共有持分の全部移転を無事に成功させるためのポイントを、チェックリスト形式でまとめました。
移転前の準備
・共有者全員との十分な話し合いと説明を行う ・不動産の適正価値を把握する(専門家の評価を取り入れる) ・移転方法(贈与・売買・その他)を決定する ・税金面での影響を確認し、必要に応じて対策を講じる ・書類や費用の準備をする
手続き時の確認事項
・契約内容を書面化し、関係者全員が確認する ・必要書類をすべて揃える(登記識別情報、印鑑証明書、住民票など) ・司法書士など専門家への依頼内容を明確にする ・登記申請の内容に誤りがないか確認する ・関連する税金の申告期限を確認する
移転後のフォローアップ
・登記が正しく完了したか確認する(登記事項証明書を取得) ・必要な税務申告を期限内に行う ・他の共有者への報告を行う ・将来の売却や相続に備えた資料を整理保管する
共有持分の全部移転は、将来の不動産管理や家族間のトラブル防止のために有効な手段です。しかし、手続きの複雑さや税金面での影響もあるため、十分な準備と専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
特に重要なのは、「早い段階からの丁寧な説明と対話」「公平性への配慮」「書面による合意の徹底」「専門家の活用」「将来を見据えた取り決め」です。これらのポイントを押さえることで、共有持分の全部移転を揉めることなく円滑に進めることができるでしょう。
今すぐ実行できる3つのアクション
- 共有者間での話し合いの場を設ける: カレンダーに具体的な日時を設定し、関係者全員が参加できる家族会議や話し合いの場を作りましょう。オンライン会議でもかまいません。目的と議題を事前に共有しておくことがポイントです。
- 不動産の価値を把握する: 固定資産税評価証明書を取得したり、不動産鑑定士に相談したりして、対象不動産の適正な価値を把握しましょう。これは話し合いの基礎資料になります。相続や贈与を検討している場合は、税理士にも相談することをおすすめします。
- 専門家への相談予約を入れる: 司法書士や税理士など、共有持分の移転に詳しい専門家への相談予約を入れましょう。初回相談は無料の場合も多いので、複数の専門家の意見を聞いて比較検討することも有効です。相談の際は、不動産の概要や共有状況、希望する移転方法などの情報を整理しておくと効率的です。
共有持分の全部移転は、事前の準備と適切な進め方によって、スムーズに実現できます。この記事が皆様の不動産管理や家族間の資産整理のお役に立てば幸いです。



コメント