不動産の共有持分をお持ちの方、売却を考えていませんか?親から相続した実家を兄弟で共有している、離婚後に元配偶者と共有名義のままになっている、投資用に他の人と共同購入した不動産を手放したい…。様々な理由で共有持分の売却を検討されている方は多いでしょう。
しかし、共有持分の売却は通常の不動産売却と比べて、多くのトラブルが起こりやすい傾向があります。「他の共有者との関係が悪化した」「想像以上に安い金額で買いたたかれた」「売却後に思わぬトラブルに巻き込まれた」など、多くの失敗事例が報告されています。
そもそも共有持分とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有している状態で、それぞれが持っている所有権の割合のことを指します。例えば、あなたと兄弟2人で実家を相続した場合、3人がそれぞれ3分の1ずつの持分を持つことになります。この持分は、原則として自分の意思だけで自由に売却することができます。
しかし、自由に売却できるからこそ、様々なトラブルが発生するリスクもあるのです。この記事では、共有持分の売却で実際に起きている危険なトラブル事例と、それらを回避するための具体的な対処法を初心者にもわかりやすく解説します。共有持分を安全に、そして後悔なく売却するための知識を身につけましょう。
共有持分の不動産を高く売るために一番重要なのは、複数の会社に相談することです。一つの会社だけだと、不動産の相場だけではなく、相性や強みもわかりません。以下の記事で共有持分が得意な不動産会社を厳選しましたのでご参考ください。
共有持分の買取でおすすめの不動産会社TOP5
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応業者 |  |  |  |  | |
| スピード | 最短30分 即日対応OK | 最短30分 即日対応OK | 当日・翌日 対応OK | 応相談 | 当日・翌日 対応OK |
| 対応地域 | 全国 ※一部非対応 | 関東/東海/関西/中国/九州 ※一部非対応 | 関東/関西 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
共有持分を売却する方法と選択肢

共有持分を売却する方法には、大きく分けて3つの選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
他の共有者に売却する方法
最もスムーズに進みやすいのが、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう方法です。例えば、兄弟3人で共有している実家を、そこに住んでいる兄に自分の持分を売却するケースなどが考えられます。
この方法のメリットは、すでに面識のある相手なので信頼関係がある程度構築されていること、また不動産を実際に使用している人にとっては単独所有になるというメリットがあるため、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高いことです。実際、他の共有者への売却では、市場価格の80〜90%程度で売却できるケースが多いとされています。
しかし、他の共有者に資金力がない場合や、そもそも買取の意思がない場合は実現が難しいというデメリットがあります。また、金額の交渉で揉めるケースも少なくありません。
第三者(買取業者など)に売却する方法
他の共有者に売却できない場合、共有持分専門の買取業者に売却する方法があります。共有持分買取業者は、複雑な権利関係がある不動産でも買い取ってくれるため、早く現金化したい場合には便利です。
ただし、市場価格よりもかなり安い金額になることが多く、一般的に市場価格の50〜70%程度、悪質な業者だと30%以下で買いたたかれるケースもあります。また、買取業者が新たな共有者となることで、残された共有者とのトラブルが発生するリスクもあります。
参考)共有持分の売却方法
共有物分割請求による解決方法
上記の方法が難しい場合、最終手段として「共有物分割請求」という法的手続きがあります。これは、裁判所に共有状態の解消を求める手続きで、現物分割(不動産を物理的に分ける)、換価分割(競売にかけて売却代金を分ける)、価格賠償(一人が不動産を取得し、他の共有者に金銭を支払う)のいずれかの方法で解決が図られます。
この方法は、他の共有者との話し合いが難航した場合の最終手段ですが、弁護士費用がかかること(50〜150万円程度)、時間がかかること(半年〜数年)、関係が悪化する可能性が高いことなどから、できれば避けたい選択肢だと言えるでしょう。
どの方法を選ぶにしても、事前に十分な情報収集と準備が必要です。次に、共有持分売却で起こりやすい具体的なトラブル事例を見ていきましょう。
共有持分売却で起こりやすいトラブル事例①:他の共有者とのトラブル

共有持分売却で最も多いトラブルは、他の共有者との関係悪化です。法律上は自分の持分を自由に売却できますが、事前に相談なく売却すると、信頼関係が崩れて様々な問題に発展することがあります。
事前通知なしで売却したことによる人間関係の悪化
Aさんの事例:実家を弟3人で共有していたAさんは、急な資金需要があり、弟たちに相談せずに自分の持分を不動産業者に売却しました。売却後、弟たちから「なぜ相談してくれなかったのか」と強い不満を持たれ、家族関係が悪化。その後の冠婚葬祭にも呼ばれなくなってしまいました。
共有持分は法的には自由に売却できますが、特に親族間での共有の場合、事前の相談なしでの売却は人間関係に大きなダメージを与えることがあります。たとえ急ぎの事情があったとしても、一言連絡を入れるだけでも印象が大きく変わります。
共有者間の信頼関係の崩壊事例
Bさんの事例:離婚後も元妻と共有名義のままだった不動産について、Bさんは自分の持分を売却しました。しかし、買取業者が元妻に対して強引な買取営業をしたため、元妻からBさんが意図的に嫌がらせをしたと誤解され、その後の子どもの親権問題にも影響が出てしまいました。
共有者間に過去のいざこざがある場合、持分売却がさらなる関係悪化のきっかけになることがあります。特に離婚後の財産や相続不動産などは、感情的な側面も絡むため慎重な対応が必要です。
共有者が売却に反対するケースの対処法
共有者があなたの持分売却に反対する場合、以下のような対処法が考えられます。
- 丁寧に事情を説明する: 売却しなければならない理由を誠実に説明し、理解を求めましょう。
- 売却先について相談する: 「誰に売るか」について相談すれば、共有者の懸念を和らげられる可能性があります。
- 優先的に買取の機会を与える: 他の共有者に「まず買取の意思があるか」を確認することで、信頼関係を保ったまま進められます。
- 専門家に間に入ってもらう: 弁護士や不動産会社に間に入ってもらうことで、感情的なもつれを避けられます。
共有者との関係を大切にしたい場合は、時間をかけてでも丁寧に対応することが重要です。一方で、どうしても折り合いがつかない場合は、法的手続きも視野に入れる必要があるでしょう。
共有持分売却で起こりやすいトラブル事例②:新しい共有者とのトラブル

あなたが持分を売却した後、新しい共有者(買取業者や第三者)が加わることで、残された共有者に様々なトラブルが発生する可能性があります。そのことを知らずに売却すると、後々罪悪感を感じたり、思わぬ責任追及を受けたりすることもあります。
買取業者が共有者になった場合の問題点
Cさんの事例:相続した実家の持分をCさんが買取業者に売却したところ、その業者は残りの共有者(Cさんの兄)に対して、「このままでは競売にかけるしかない」と脅し、市場価格の半額程度で持分を買い取ろうとしました。兄はCさんに「こんな業者に売るなんて」と激怒し、兄弟関係が修復不能なほど悪化してしまいました。
買取業者の中には、残りの持分も安く買い取るために強引な交渉をする業者も存在します。場合によっては、共有物分割請求訴訟を起こして競売にかけることをちらつかせるなど、残された共有者に大きなプレッシャーをかけることもあります。
見知らぬ第三者が敷地内に出入りするようになる問題
Dさんの事例:マンションの一室を友人と共有していたDさんが、自分の持分を第三者に売却した後、その第三者が度々物件に訪れるようになりました。「共有者として物件の状態を確認する権利がある」と主張され、友人は不審者が出入りすることに強い不安を感じるようになりました。
共有持分の売却後、新しい共有者には法的に不動産への立ち入り権が発生します。そのため、これまで実質的に単独で使用していた共有者にとっては、突然見知らぬ人が出入りするようになり、大きな精神的ストレスになることがあります。
賃料請求されるリスクと対応策
Eさんの事例:両親から相続した実家に住んでいたEさんの兄。Eさんは自分の持分を業者に売却しましたが、その後、業者から兄に対して「共有持分に応じた賃料を支払うよう」要求がありました。兄は突然の出費に困り、Eさんを責めることになりました。
共有物の単独使用者(例:実家に住み続けている兄弟の一人)は、法的には他の共有者に対して持分割合に応じた賃料を支払う義務があるとされる場合があります。買取業者はこの権利を行使して賃料請求をすることがあるのです。
これらのトラブルを防ぐには、以下の対策が有効です。
- 信頼できる買取業者を選ぶ: 評判の良い業者を選び、売却後のトラブル可能性について事前に確認する。
- 契約書に特約を入れる: 「残された共有者に不当な要求をしない」などの特約を契約書に盛り込む。
- 他の共有者に事前に説明する: 売却先や売却後に起こり得る状況について、誠実に説明しておく。
売却はあなたの自由ですが、残される共有者への配慮も忘れないようにしましょう。
共有持分売却で起こりやすいトラブル事例③:売却条件・金額のトラブル

共有持分は通常の不動産と違い、市場価値を正確に把握することが難しく、適正価格での売却が難しいという特徴があります。そのため、売却条件や金額に関するトラブルが非常に多く発生しています。
市場価格より大幅に安く売却してしまう危険性
Fさんの事例:資金繰りに困っていたFさんは、マンションの共有持分(50%)を持っていましたが、急いでいたため最初に声をかけた業者にすぐ売却。後から知ったのですが、市場価格の3割程度という非常に安い金額で売却してしまったことがわかりました。同じ条件の持分でも、業者によって2倍以上の差があったのです。
共有持分の適正価格は、通常の不動産とは違う計算方法で算出されます。一般的に、不動産全体の市場価格に持分割合をかけた金額の50〜70%程度が相場と言われていますが、買取業者によっては30%以下という低い金額を提示してくる場合もあります。
不利な契約条件に合意してしまうリスク
Gさんの事例:Gさんは共有持分を売却する際、契約書の細かい条件をよく確認せずに契約してしまいました。後になって、「残された共有者が売却を希望した場合は協力する義務がある」という条項があり、Gさんは買主の代理人として残りの共有者と交渉する必要が生じ、大きな精神的負担を負うことになりました。
共有持分の売買契約には、通常の不動産売買には見られない特殊な条項が含まれていることがあります。特に、残された共有者との関係に関する条項や、将来の共有物分割請求に関する条項などは注意が必要です。
売却金額の相場と適正価格の見極め方
共有持分の適正価格を見極めるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 複数の業者から見積もりを取る: 最低でも3社以上の見積もりを比較することで、相場観を掴むことができます。
- 適正な計算方法を確認する: 一般的な計算式は「不動産の市場価格×持分割合×(50%〜70%)」ですが、実際に居住している共有者に売る場合は80%〜90%程度になることもあります。
- 物件の状態や権利関係を正確に伝える: 物件の状態や共有者間の関係性などを正確に伝えることで、より適切な査定額を出してもらえます。
- 急いで売らない: 資金需要が急でなければ、時間をかけて良い条件の買い手を探すことが重要です。
共有持分は「売りにくい」という性質上、買取業者に有利な価格設定になりがちです。しかし、適切な知識と準備があれば、不当に安い金額での売却は避けられます。
共有持分売却で起こりやすいトラブル事例④:法的問題とトラブル
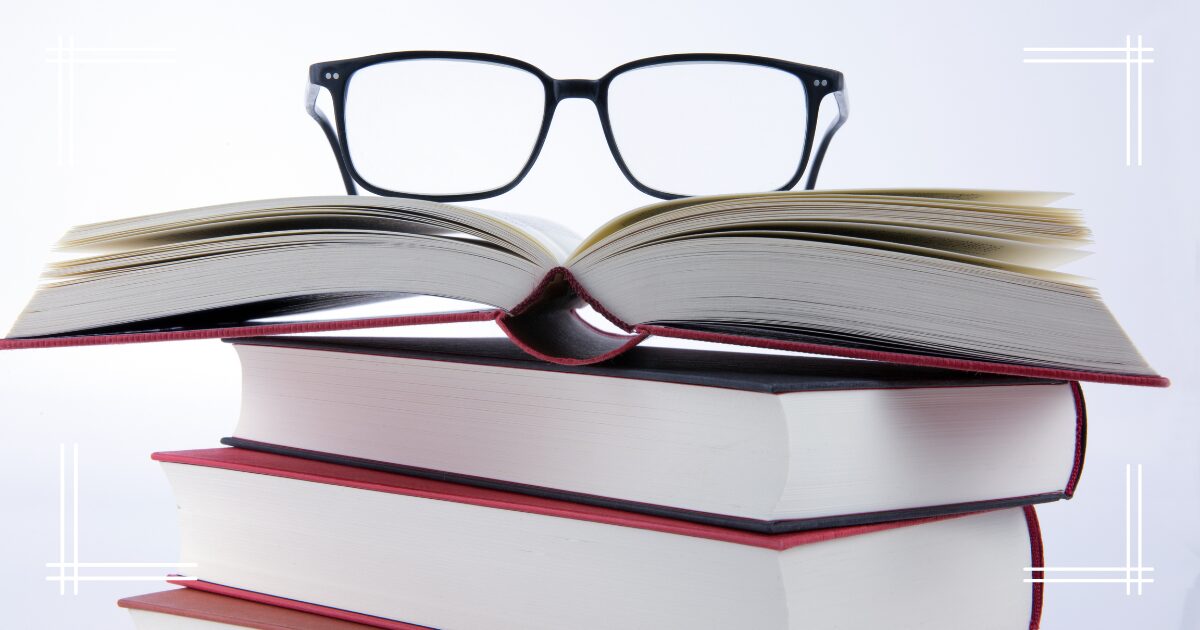
共有持分の売却は、その後に法的な問題が発生するケースも少なくありません。特に、売却後に思わぬ請求や訴訟に発展することもあり、注意が必要です。
売却後に発生する可能性のある法的トラブル
Hさんの事例:Hさんは相続した実家の持分を売却しましたが、売却後に固定資産税の未払い分について市役所から連絡がありました。売却前の未払い分も含めて請求され、すでに売却していたにもかかわらず、支払い義務があることが判明したのです。
共有持分を売却しても、売却前に発生した税金や費用の支払い義務が消えるわけではありません。特に固定資産税などは、1月1日時点の所有者に課税される仕組みになっているため、年の途中で売却すると思わぬ請求が来ることがあります。
共有物分割請求を受けるリスク
Iさんの事例:Iさんは共有マンションの持分を売却しましたが、半年後、買主から「共有物分割請求訴訟を提起した」と連絡がありました。残された共有者(Iさんの姉)が困っているため対応してほしいと言われましたが、すでに売却済みで法的な責任はないものの、道義的な責任を感じて苦しむことになりました。
共有持分を買取業者に売却した場合、その後に業者が残りの共有者に対して共有物分割請求訴訟を起こすことがあります。これは法的には問題ありませんが、残された共有者にとっては大きな負担になります。
税金や費用負担のトラブル事例
Jさんの事例:Jさんは共有アパートの持分(30%)を売却しましたが、売却後もアパートの大規模修繕が必要になり、残された共有者から「売却前に決まっていた修繕だから費用を負担すべき」と請求されました。契約書に特約がなかったため、トラブルに発展しました。
共有不動産の修繕費や管理費についても、売却前に発生した費用や、売却前に決定していた費用について、後から請求されるケースがあります。これらのトラブルを防ぐためには、以下の対策が有効です。
- 売買契約書に詳細な特約を盛り込む: 売却前後の費用負担について明確に定めておく。
- 固定資産税等の清算を正確に行う: 日割り計算で清算するなど、後々トラブルにならないよう配慮する。
- 売却時点での修繕計画や決定事項を確認する: 将来発生する可能性のある費用について把握しておく。
- 残された共有者への配慮を忘れない: 法的責任がなくても、道義的な責任を果たす姿勢が大切。
共有持分売却後の法的トラブルは、事前の準備と適切な契約内容によって多くが防げます。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることをおすすめします。
共有持分を安全に売却するための準備と心構え
ここまで様々なトラブル事例を見てきましたが、適切な準備と心構えがあれば、多くのトラブルは回避できます。共有持分を安全に売却するための重要なポイントを見ていきましょう。
売却前に確認すべき重要書類と情報
共有持分の売却を考える前に、以下の書類や情報を確認しておくことが重要です。
- 登記簿謄本(登記事項証明書): 正確な権利関係や共有者、持分割合を確認できます。
- 固定資産税評価証明書: 固定資産税の額や、評価額の参考になります。
- 実測図や境界確認書: 土地の正確な範囲や境界を示す書類です。
- 共有者間の取り決め書: 共有者間で使用方法や費用負担について取り決めがあれば、それを確認します。
- 物件の状態: 建物の老朽度や修繕履歴なども把握しておきましょう。
これらの情報を事前に整理しておくことで、売却時の説明がスムーズになり、買主との信頼関係も構築しやすくなります。
共有者への事前相談の重要性と進め方
法律上は自分の持分を自由に売却できますが、他の共有者への事前相談は非常に重要です。特に家族や親族間での共有の場合、事前相談なしでの売却は人間関係の悪化につながります。
事前相談の際のポイントは以下の通りです。
- 早めに伝える: 売却の意向は決まったらすぐに伝えましょう。直前になって告げると不信感を持たれます。
- 理由を誠実に説明する: なぜ売却したいのかを誠実に説明し、理解を求めましょう。
- 買取の意思を確認する: 他の共有者に買取の意思があるかを確認することも大切です。
- 売却先や価格について相談する: 誰にいくらで売るかについても、可能な範囲で相談すると良いでしょう。
- 将来的な不動産の活用について話し合う: 売却後にどうなるのかについても、共有者全員で考える機会を持ちましょう。
これらの配慮により、売却後のトラブルを大きく減らすことができます。
専門家(弁護士・不動産会社)への相談タイミング
共有持分の売却は通常の不動産売却より複雑なため、専門家への相談が重要です。特に以下のタイミングでの相談をおすすめします。
- 売却を検討し始めた段階: 売却の方法や選択肢について知識を得るため。
- 他の共有者との話し合いが難しい場合: 第三者の客観的な視点が必要な場合。
- 買主候補が現れた段階: 契約内容や条件の適正さを確認するため。
- 契約書を作成する段階: 特約条項など、重要な契約内容を確認するため。
専門家への相談費用は5,000円〜30,000円程度(初回相談)ですが、この費用を惜しんでトラブルに発展すると、何倍もの損失や精神的苦痛を味わうことになりかねません。売却金額が大きい場合は特に、専門家への相談は必須と考えましょう。
信頼できる買取業者の選び方と見極めポイント

共有持分を第三者に売却する場合、信頼できる買取業者を選ぶことが非常に重要です。悪質な業者に売却すると、安値で買いたたかれるだけでなく、残された共有者とのトラブルに発展するリスクも高まります。
悪質な買取業者の特徴と見分け方
悪質な買取業者には、以下のような特徴があります。
- 極端に安い買取価格を提示する: 市場相場の30%以下など、著しく安い金額を提示する業者は注意が必要です。
- 急かして契約を迫る: 「今日中に決めないと金額が下がる」などと急かす業者は避けるべきです。
- 説明が不十分: 売却後に起こり得るトラブルや、契約内容について詳しく説明しない業者は危険です。
- 書面を残さない: 口頭だけでの取引を進めようとする業者は避けましょう。
- 会社情報が不透明: 会社の実態や実績が不明確な業者は信頼性に欠けます。
こうした業者に売却すると、安値での売却だけでなく、残された共有者への強引な営業や、共有物分割請求訴訟の濫用などにつながる可能性があります。
優良業者の選定基準と確認すべき項目
信頼できる買取業者を選ぶためのチェックポイントは以下の通りです。
- 宅地建物取引業の免許を持っている: 免許番号を確認し、国土交通省の「宅地建物取引業者検索システム」で確認できます。
- 実績と評判: 共有持分の買取実績が豊富で、口コミや評判が良いかをチェックします。
- 丁寧な説明: 売却後に起こり得るリスクや契約内容について、わかりやすく説明してくれるかを確認します。
- 適正な価格提示: 極端に安い金額ではなく、市場相場に近い金額を提示しているかをチェックします。
- アフターフォロー: 売却後のサポートや、残された共有者への配慮がある業者かを確認します。
これらのポイントを確認することで、悪質な業者を避け、信頼できる業者を見つけることができます。
複数の業者から見積もりを取る重要性
共有持分の買取価格は業者によって大きく異なります。同じ条件でも、業者によって2倍以上の価格差があることも珍しくありません。そのため、必ず複数の業者(最低3社以上が理想)から見積もりを取ることが重要です。
見積もり比較のポイントは以下の通りです。
- 買取価格: 単純な金額の高さだけでなく、算出根拠もチェックしましょう。
- 手数料や諸費用: 買取価格とは別に、手数料や諸費用がかかるかも確認しましょう。
- 支払い条件: 一括払いか分割払いか、支払いのタイミングはいつかを確認します。
- 契約条件: 特約条項の内容や、売却後の責任範囲について比較します。
- 対応の丁寧さ: 質問への回答や説明の丁寧さも、業者選びの重要な判断材料です。
複数の見積もりを比較することで、より有利な条件で売却することができます。また、業者同士を競わせることで、買取価格がアップする可能性もあります。
共有持分売却後のトラブルへの適切な対処法

万全の準備をしていても、売却後にトラブルが発生する可能性はゼロではありません。そんなときのために、トラブルへの適切な対処法も知っておきましょう。
他の共有者からクレームを受けた場合の対応策
売却後に他の共有者から「なぜ相談なく売却したのか」「問題のある買主に売ってしまった」などのクレームを受ける可能性があります。その場合の対応策は以下の通りです。
- 誠意をもって説明する: 売却の理由や経緯を誠実に説明し、理解を求めましょう。
- 謝罪すべき点は謝罪する: 事前相談が不十分だった場合など、謝罪すべき点があれば素直に謝罪しましょう。
- 解決策を一緒に考える: 発生したトラブルに対して、一緒に解決策を考える姿勢を示しましょう。
- 専門家に間に入ってもらう: 感情的な対立になっている場合は、弁護士など第三者に間に入ってもらうことも検討しましょう。
不動産の共有関係は、売却後も何らかの形で関係が続くことがあります。特に家族や親族間の場合は、将来的な関係修復の可能性も考慮して対応することが大切です。
売却後に法的問題が発生した場合の解決方法
売却後に法的な問題(例:税金の未払い請求、修繕費の負担要求、共有物分割請求訴訟など)が発生した場合の解決方法は以下の通りです。
- 契約書を再確認する: まず売買契約書の内容を確認し、該当する事項に関する取り決めがあるかをチェックします。
- 弁護士に相談する: 法的な問題は素人判断せず、早めに弁護士に相談しましょう。初回相談は5,000〜30,000円程度ですが、早期解決のための投資と考えるべきです。
- 売却先の業者に確認する: 買取業者に売却した場合、契約違反や説明不足があれば、業者に責任を問うことも可能です。
- 話し合いによる解決を試みる: 裁判などの法的手続きは時間とコストがかかるため、可能であれば話し合いでの解決を目指しましょう。
- 証拠を保全する: メールや書面のやり取り、録音などの証拠は大切に保管しておきましょう。
法的問題は早期発見・早期対応が重要です。「様子を見よう」と放置すると、問題が複雑化して解決が難しくなることがあります。
共有持分トラブルを根本的に解決する方法

共有持分の売却トラブルは事後対応より予防が重要です。共有状態そのものを避けるか、早期に解消することが根本的な解決方法となります。
共有状態を避けるための相続・購入時の対策
共有状態は様々なトラブルの原因になりやすいため、可能であれば最初から避けることが賢明です。
- 相続時の対策:
- 遺言書で不動産の帰属を明確にする
- 生前贈与で所有権を整理する
- 相続時に「代償分割」(一人が不動産を相続し、他の相続人に金銭で代償する方法)を活用する
- 購入時の対策:
- 共同購入する場合は、共有者間で詳細な契約書を作成する
- 可能であれば、共有ではなく「区分所有」の形で購入する
- 将来的な共有関係解消の方法についても事前に取り決めておく
これらの対策により、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
共有状態を解消するための具体的な手順
すでに共有状態にある場合は、以下の方法で共有状態を解消することが根本的な解決策となります。
- 他の共有者への売却:
- 最もスムーズな方法で、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高い
- 共有者に資金力がない場合は、分割払いなどの提案も検討する
- 他の共有者の持分を買い取る:
- あなた自身が不動産を使用したい場合は、他の共有者の持分を買い取る
- 単独所有になれば、自由に活用や売却ができるようになる
- 共有物分割協議:
- 共有者全員で話し合い、分割方法を決める
- 「現物分割」「換価分割」「価格賠償」などの方法がある
- 共有物分割請求訴訟:
- 協議が難航した場合の最終手段
- 弁護士費用(50〜150万円程度)と時間(半年〜数年)がかかる
- 不動産全体の売却:
- 共有者全員の合意のもと、不動産全体を第三者に売却する
- 売却代金を持分割合に応じて分配する
どの方法を選ぶにしても、共有者間の十分な話し合いと、専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。
将来のトラブル防止のための予防策
共有状態が継続する場合の将来的なトラブル防止のための対策も重要です。
- 共有者間の取り決め書を作成する:
- 不動産の使用方法
- 修繕費や税金の負担方法
- 将来的な売却に関するルール
- 共有者が死亡した場合の取り扱い これらを含む詳細な取り決め書を作成し、共有者全員が署名しておきましょう。
- 定期的な話し合いの場を持つ:
- 年に1回程度は集まり、不動産の状況や今後の方針について話し合う機会を持ちましょう。
- 共有者の変更に備える:
- 共有者が高齢の場合、相続が発生した際の対応についても事前に話し合っておくことが大切です。
- 専門家のサポートを継続的に受ける:
- 税理士や弁護士など、専門家とのつながりを維持しておくことで、問題の早期発見・解決がしやすくなります。
これらの予防策によって、将来的なトラブルのリスクを大きく減らすことができます。
よくある質問(Q&A)

共有持分の売却に関して、多くの方が疑問に思う点を質問形式でまとめました。
共有持分はどうやって価値を算出するの?
共有持分の価値は一般的に以下の式で算出されます。
共有持分の価値 = 不動産の市場価格 × 持分割合 × 減価率
ここでの「減価率」は、共有物件の流動性の低さや制約の多さを反映したもので、通常0.5〜0.7(50%〜70%)程度とされています。例えば、市場価格1億円の不動産の30%の持分であれば、1億円×0.3×0.6=1,800万円が一つの目安となります。
ただし、売却先によって価格は大きく変わります。
- 他の共有者への売却:市場価格の80〜90%程度
- 専門業者への売却:市場価格の50〜70%程度
- 悪質な業者への売却:市場価格の30%以下になることも
適正価格を知るためには、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。
他の共有者に無断で売却しても法的に問題ないの?
法律上、自分の持分は他の共有者の同意なく自由に売却することが可能です(民法206条)。したがって、無断で売却しても法的な問題はありません。
しかし、法的に問題がなくても、人間関係や道義的な観点からは事前に相談することが望ましいです。特に家族や親族間での共有の場合、無断での売却は関係悪化の原因になりやすいため注意が必要です。
売却時にかかる税金や費用はどれくらい?
共有持分売却時にかかる主な税金・費用は以下の通りです。
- 譲渡所得税・住民税:
- 売却益(売却価格-取得費-諸経費)に対して課税
- 所有期間5年以下:39.63%
- 所有期間5年超:20.315%
- 印紙税:
- 売買契約書に貼付する印紙代
- 売却金額により異なる(1万円〜6万円程度)
- 登記費用:
- 所有権移転登記費用(司法書士報酬含む)
- 5〜10万円程度
- 仲介手数料(仲介業者を利用する場合):
- 売却価格の3〜3.6%+6万円程度(税込)
このほか、測量費用や不動産会社への広告費用などが発生する場合もあります。
共有者が行方不明の場合はどうすればいい?
共有者が行方不明の場合、以下の方法で対応が可能です。
- 調査する:
- 住民票や戸籍の附票を取得して最後の住所を確認
- 親族や知人を通じて連絡を取る
- 弁護士や探偵事務所に依頼して調査する
- 不在者財産管理人の選任:
- 家庭裁判所に申し立て、行方不明者の財産を管理する人(不在者財産管理人)を選任してもらう
- 管理人を通じて持分の売買交渉や共有物分割協議を行う
- 失踪宣告:
- 普通失踪(7年間生死不明)または、危難失踪(危険な状況下で1年間生死不明)の場合
- 家庭裁判所に申し立て、失踪宣告を受けると死亡したものとみなされる
- 相続が発生し、相続人と協議できるようになる
行方不明の共有者がいる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。手続きは複雑で時間もかかりますが、適切に対応することで解決の道が開けます。
まとめ:共有持分売却の重要ポイントと注意点

この記事では、共有持分売却にまつわる様々なトラブル事例と対処法を紹介してきました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。
重要ポイントのおさらい
- 共有持分売却は自由だが、トラブルリスクが高い:
- 法律上は自由に売却できるが、様々なトラブルが起こりやすい
- 特に他の共有者とのトラブルや、売却後の法的問題に注意が必要
- 売却先によって金額に大きな差がある:
- 他の共有者への売却:市場価格の80〜90%程度
- 専門業者への売却:市場価格の50〜70%程度
- 悪質な業者への売却:市場価格の30%以下になることも
- 事前準備と専門家相談が重要:
- 必要書類の準備
- 共有者への事前相談
- 専門家(弁護士・不動産会社)への相談
- 複数業者からの見積もり取得
- 共有状態そのものを解消することが根本的解決:
- 他の共有者への売却
- 他の共有者の持分買取
- 共有物分割(協議または訴訟)
- 不動産全体の売却
安全な共有持分売却のための最終チェックリスト
共有持分を売却する前に、以下のチェックリストを確認しましょう。
- [ ] 登記簿謄本で正確な権利関係を確認した
- [ ] 他の共有者に売却の意向を伝えた
- [ ] 複数の業者から見積もりを取得した
- [ ] 買取業者の信頼性を確認した
- [ ] 契約書の内容を詳細に確認した
- [ ] 売却後に起こり得るトラブルについて理解した
- [ ] 売却に関わる税金や費用を把握した
- [ ] 必要に応じて専門家(弁護士・税理士等)に相談した
このチェックリストをクリアすることで、安全な共有持分売却が可能になります。
読者が次にとるべき具体的なアクション3つ
共有持分売却を検討している方が、この記事を読んだ後にすぐに実行できる具体的なアクションは以下の通りです。
- 共有持分の正確な情報を収集する
- 法務局で登記簿謄本を取得する(1通数百円)
- 固定資産税評価証明書を市区町村役場で取得する
- 不動産の実測図や境界確認書があれば準備する これらの書類は売却の基本となる重要資料です。まずはこれらを揃えましょう。
- 他の共有者と話し合いの場を設ける
- 売却の意向と理由を説明する
- 買取の意思があるか確認する
- 将来的な不動産の活用についても話し合う 事前相談により、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
- 複数の専門業者に査定依頼をする
- インターネットで「共有持分 買取」で検索する
- 少なくとも3社以上から見積もりを取る
- 業者の信頼性(免許番号、実績、口コミなど)も合わせて確認する 見積もり比較により、適正価格での売却が可能になります。
共有持分の売却は一般的な不動産売却より複雑ですが、正しい知識と準備があれば、後悔のない形で売却することができます。この記事が、あなたの共有持分売却のお役に立てれば幸いです。

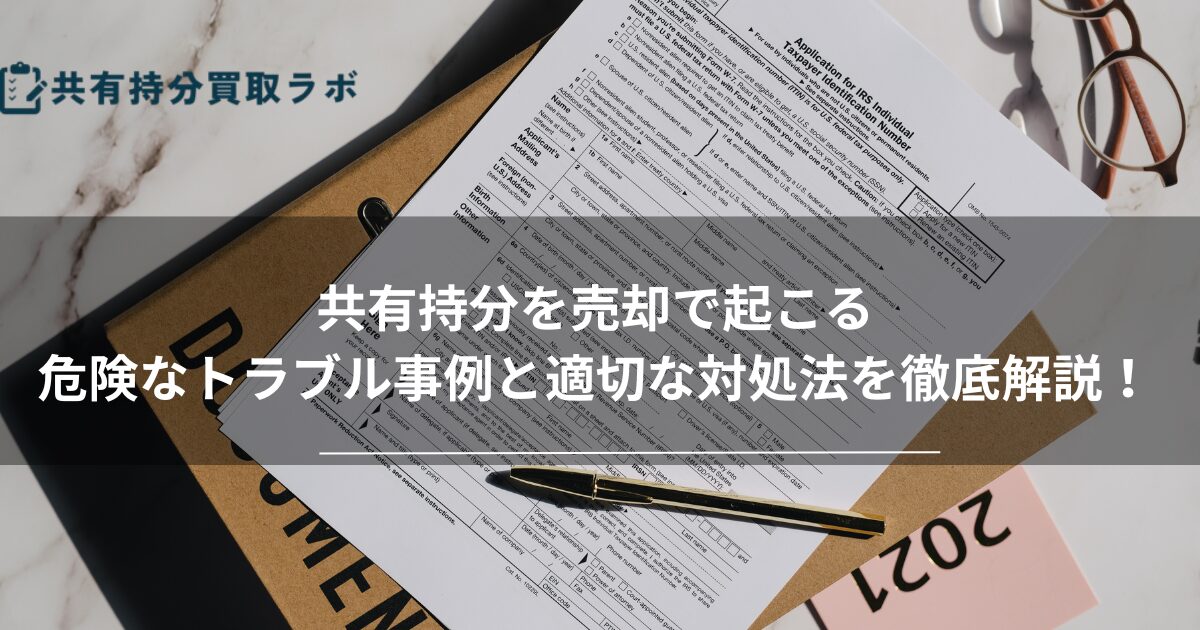

コメント