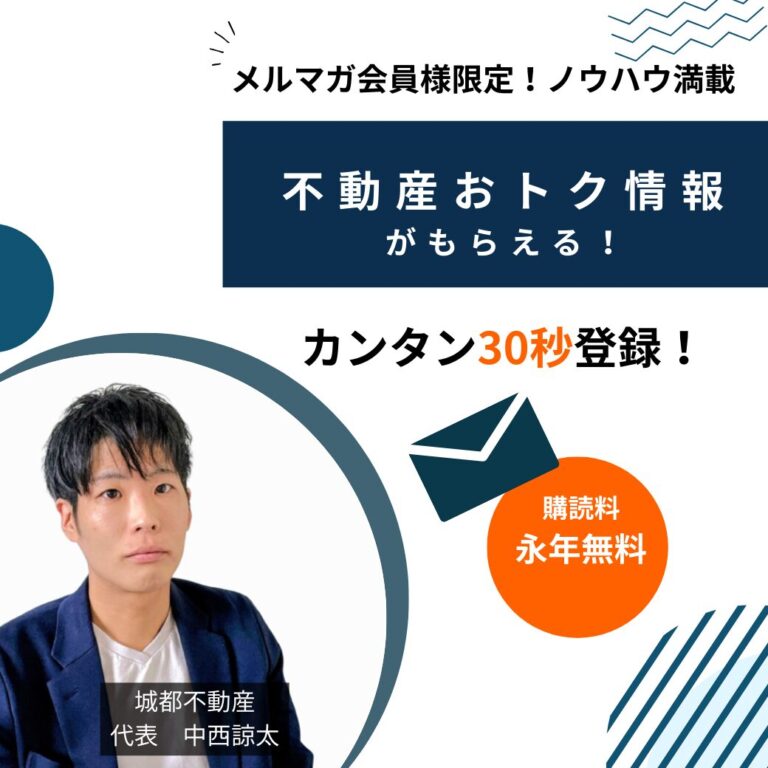こんにちは中西です。今回は「遅刻をする人は仕事ができないのか」をテーマにお話ししていきます。
お笑いコンビEXITの兼近大樹さんが、テレビ番組で「遅刻を責める人は能力が低い」という発言をし、大きな議論を呼びました。
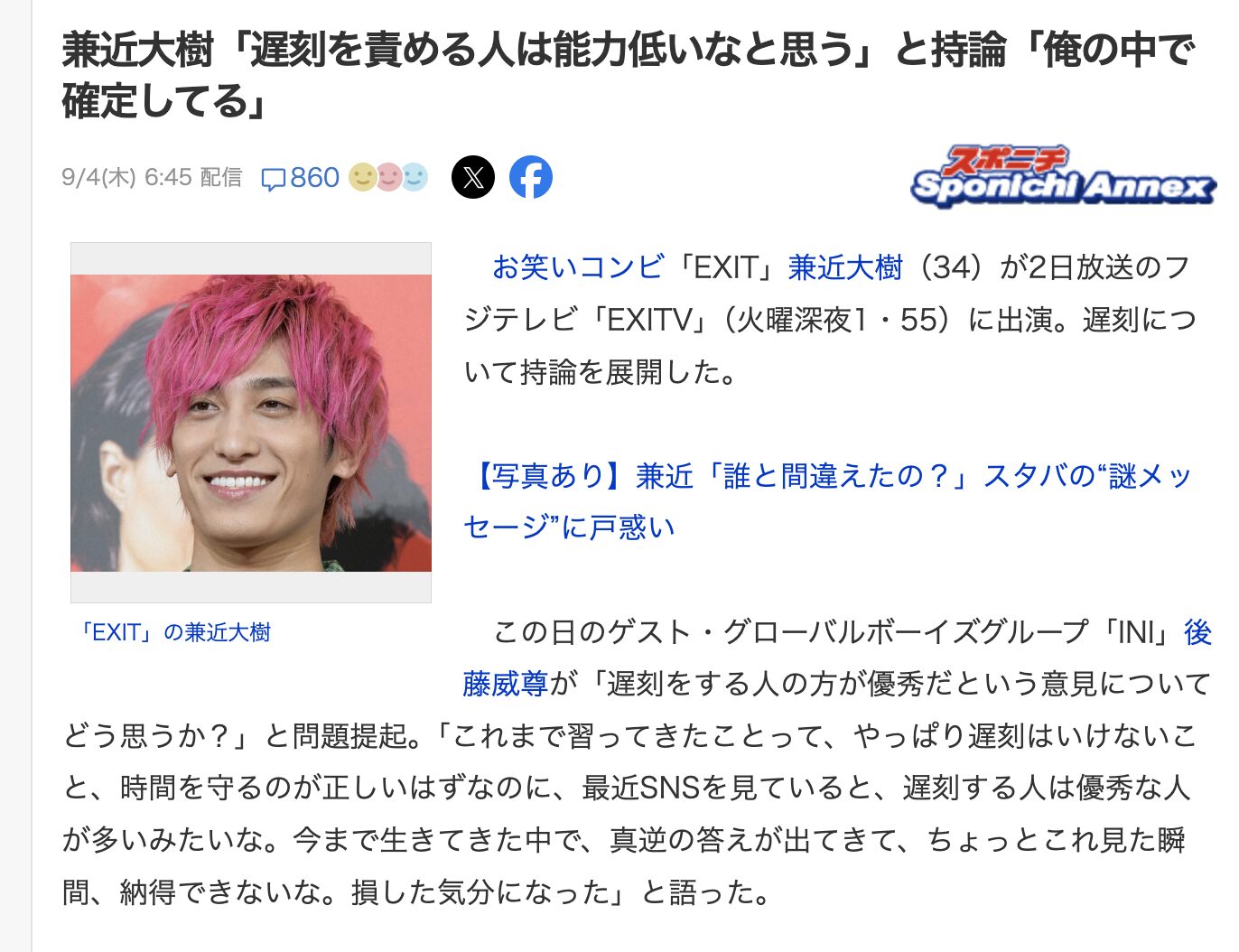
SNSでは「非常識だ!」と批判する声と「合理的な考え方だ」と賛同する声が真っ二つに分かれ、いわゆる“炎上”状態になったんですよね。
一見すると芸能ニュースのゴシップに見えますが、実はこの遅刻については、私たちが社会で働く上で非常に重要な「時間の扱い方」や「立場ごとの視点」に直結します。
今回は、炎上の経緯を整理し、遅刻をする人は仕事ができないのかについて考えながら、「社会で成果を出すために時間をどう捉えるべきか」を掘り下げていきます。
- 炎上ニュースを「学び」に変えられる
- 働き方を見直すきっかけになる
- 客観的な視点を得られる
遅刻する人は仕事ができない

一般的には遅刻する人は仕事ができないとみなされるのは間違いありません。理由はどうあれ、常識はずれで信用をなくす行為です。
信頼を失う
約束の時間を守らないことは、顧客や同僚から「責任感がない」と見られやすい。特に新人や若手社員の場合、時間厳守は信用を得る最低条件です。これからいろいろなことを任せるのに、時間さえ守れないような人は不安でしかありません。特に関係ができていない初対面などでは遅刻は完全に信頼を失う行為です。仕事ができるできない以前の問題だとみなされてしまいます。
チーム全体に影響する
一人が会議や現場作業に遅れると、他のメンバーの時間を奪い、効率を下げます。当然チームの中にはスケジュールが詰まっている人もいるでしょうし、それぞれ決められた時間の中で仕事を進めています。もし、一人の遅刻のせいで他の人の仕事に影響が出て、万一失敗したとしても、遅刻をした人が責任を取るわけでもありません。そういった部分でもチームの輪を乱すのは仕事ができない認定をされてしまいます。
社会的マナーの問題
日本のビジネス文化では「時間を守る=相手を尊重する」という意味が強いため、遅刻は評価を落としやすいです。たとえば就職の面接で遅刻をしたら理由を聞かれることが多いですし、印象はよくないですよね。「遅刻する=仕事ができる」というのであれば、遅刻をした方が企業に採用されるはずです。そうなっていないということは遅刻をすることが非常識と思われている証拠。遅刻に対して個人がどう思うかは自由ですが、社会的には仕事ができない以前の問題と思われてしまいます。
「仕事ができる」人でも遅刻して許されるケース

一般的には遅刻は許されないですが、中には例外もあります。
成果を出している
多少遅れても、大きな成果を残す人は評価されやすい。経営者やトップ営業マンなどは「結果でカバーする」という考え方が浸透しています。
たとえば、「多少の遅刻よりも、この人がいれば契約が取れる」「売上が上がる」という確信があるため、周囲も柔軟に対応します。
例)毎回数字で結果を出す営業マンは、多少の遅刻があっても顧客や上司から「この人だから仕方ない」と許容されることもあります。極論、毎回時間を守る売り上げゼロの営業マンか、たまに遅刻するトップ営業マンなら後者を選ぶ経営者も少なくありません。
遅刻の理由が“納得感”を持てる場合
突発的なトラブル対応
→ 緊急案件で対応していた場合、むしろ「責任感がある」と評価されることも。
前の会議や仕事が長引いたケース
→ 多忙な経営者やコンサルタントはスケジュールが重なりやすく、多少の遅れは「仕方ない」と受け止められることがある。他の部下や上司のフォローに入っていたなど、他人のために動いていたことで遅刻したケースも許されることがある。
創造的・クリエイティブな業界
成果物やアウトプットが重視される分野では、時間より「どんな価値を生み出せるか」が重視されやすい。時間ではなく、成果主義なので、そこまで重視する人はいない業界もある
信頼関係がすでにできている場合
長年の取引や上司・部下との関係で「この人は遅刻しても必ず結果を出す」と信頼されているケース。
信頼が厚ければ、遅刻が「その人の個性」として受け止められることもあり、あらかじめ遅刻したときのフォロー体制が整っているケースです。
遅刻を責める人は仕事できないのか?

遅刻した相手を責める時間は生産性ゼロ。
遅刻は肯定できるものではありませんが、たとえば遅刻したことで何時間も説教したりする人がいますが、こういったことは価値を生みません。責める時間があれば次の議題を進める、顧客対応を整える、再発防止策を決める…などは前進につながる行動をした方がはるかに生産的です。責めている間はそれらが止まる=成果が生まれないので「生産性ゼロ」と言えるわけです。
次の行動に移れる人のほうが結果を出しやすい。
遅刻を責めるのは多くの場合「苛立ち」「不満」などストレスの発散です。
感情のはけ口にはなっても、組織の効率や売上にプラスにはなりません。ストレスは生産性を著しく下げる行為です。
逆に責められた側が萎縮したり不満を持つことで、次の仕事のパフォーマンス低下を招く可能性すらあります。両者にとってプラスにならない行動をすること自体が「仕事ができない」ということにつながるということになります。
立場によって変わる「時間の価値」

ただし、この考えをすべての人・場面に当てはめるのは危険です。
社会では立場や状況によって「時間の意味」が大きく変わるからです。
1. 経営者・マネジメントの立場
- 遅刻よりも成果を重視
- 「5分遅れても数百万円の契約を取ってくるなら問題ない」という感覚
- 成果で評価されるため、時間に多少ルーズでも許容されることがある
2. 現場社員・新人の立場
- 信頼を積み上げる段階では、遅刻は信用を失う大きなリスク
- 「あの人は約束を守れない」というレッテルが貼られると、成果を出す前にチャンスが失われる
- 特に新人や若手は「まず時間を守る」ことが最優先
3. 顧客対応の立場
- クライアントとの約束に遅れることは信頼の喪失に直結
- たった1回の遅刻で契約を失う可能性もある
- BtoB、BtoC問わず、顧客対応では「時間厳守」が絶対条件
社会で活かすためのヒント
今回の炎上から得られる学びは「状況に応じた時間の使い方」です。
- 個人として働くとき
信用を築くために、まずは時間を守ること。 - チームを率いるとき
遅刻を責めるのではなく、立て直しや成果につなげる判断を重視する。 - 顧客と向き合うとき
信頼を守るために時間厳守。ここでは一切の妥協が許されない。
つまり、「全員が同じルール」ではなく、立場や目的によって時間の基準を切り替える柔軟性が求められるのです。
まとめ
「遅刻を責める人は能力が低い」という発言は、一見非常識に聞こえるかもしれません。
しかしそこには、「過去より未来に目を向ける」「生産性を最大化する」という重要な視点も含まれています。
私たちが学ぶべきポイントは次の3つです。
- 遅刻そのものより、その後どう行動するかが大切
- 時間の価値は立場や状況によって変わる
- 成果を出すには「信頼」と「生産性」の両方を意識すること
炎上ニュースは一瞬で消費されがちですが、捉え方次第で「働き方を見直すヒント」に変わります。