賃貸物件を探す際、「普通借家」と「定期借家」という言葉を見聞きすることがあると思います。どちらも賃貸契約の種類ですが、具体的にどう違うのでしょうか?
実はどちらを選択するのかによって、契約期間や家賃、さらには引っ越しのタイミングにも影響する重要なポイントです。
普通借家は長期間住むことを前提とした契約で、更新が可能なため、安定した生活を求める方に適しています。一方、定期借家は契約期間が限定されており、短期間の居住や割安な家賃を求める方に向いています。
この記事では、普通借家と定期借家の基本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、さらに契約時に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。自分に合った住まいを選ぶための知識を身につけましょう!
 中西諒太
中西諒太私は現在都内で不動産会社を経営しています。もちろん宅建士資格も保有しているため、プロの視点で解説していきます。
部屋探しで失敗しないためには正しい知識を身につけることが重要です。お部屋探しで失敗しないための無料メルマガ講座を提供しています。いまなら特典もプレゼントしているので、ぜひ登録してみてください。▶︎詳細はこちら
普通借家と定期借家とは?基礎知識

まずはじめに、普通借家と定期借家の基本的な意味について解説します。
普通借家とは
普通借家は、日本で最も一般的な賃貸契約の形式です。この契約形式は借地借家法によって定められており、主に長期間住むことを目的としています。通常、契約期間は2年以上が基本とされます。
普通借家の特徴
- 契約期間
最低2年間とされるのが一般的です。契約満了時には自動更新が可能で、借主が住み続ける意志を持っている限り、契約を更新することができます。 - 借主保護の強さ
貸主が契約終了を希望する場合、正当な理由が必要です。例えば、貸主自身が住む必要がある場合など、具体的な事情が求められます。 - 更新料
多くの場合、契約更新の際には更新料が発生します。更新料の金額は、通常家賃の1~2か月分程度が相場です。
普通借家の利用場面
普通借家は、長期的な居住を目的としている人に最適です。家族で住む場合や、特定の地域に腰を据えて生活したい場合に選ばれることが多いです。また、更新が可能なため、ライフステージに合わせて柔軟に住まいを維持できるのも利点です。
定期借家とは
定期借家は、2000年に導入された新しい賃貸契約形式です。契約期間があらかじめ定められており、その期間が終了すると契約も終了します。原則として更新はなく、再契約が必要になります。
定期借家の特徴
- 契約期間の自由度
契約期間は数ヶ月から数年まで柔軟に設定できます。例えば、短期間だけ住む必要がある場合には3ヶ月契約、比較的長期間であれば5年契約など、自由に決められます。 - 契約更新の不可
契約期間が終了すると契約が終了します。ただし、貸主と借主が合意すれば再契約が可能です。 - 家賃の安さ
定期借家物件は普通借家物件と比べて家賃が安い傾向があります。これは契約期間が限られているため、貸主が条件を緩和するケースが多いためです。 - 中途解約の制限
原則として契約期間内に解約することはできません。ただし、転勤や介護といった特別な事情がある場合は例外が認められることがあります。
定期借家の利用場面
定期借家は、短期間の居住を目的としている人に向いています。例えば、転勤中の仮住まい、ウィークリーマンションやマンスリーマンション、リロケーション物件などでよく利用されています。
両者の違いを比較
普通借家と定期借家には、以下のような大きな違いがあります。
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 2年以上が基本 | 数ヶ月から数年まで自由に設定 |
| 更新の有無 | 更新可能 | 更新不可(再契約が必要) |
| 中途解約の可否 | 条件次第で可能 | 原則不可(例外あり) |
| 家賃の傾向 | やや高め | 割安な場合が多い |
普通借家と定期借家のメリット・デメリットを比較

次に、普通借家と定期借家のメリット・デメリットを比較します。
普通借家のメリット
普通借家には以下の3つのメリットがあります。
1. 長期間住む安心感
普通借家では、契約期間が終了しても借主の希望があれば更新が可能です。この点が最大の魅力であり、長期間同じ場所に住むことを考えている人には非常に安心感があります。
例えば、子どもが学校に通っている家庭の場合、学区を変更せずに住み続けられるメリットがあります。また、引っ越しの頻度を減らすことができるため、引っ越し費用や新しい住環境への適応コストも抑えられます。
2. 借主保護が強い
普通借家は借地借家法によって借主の権利が強く保護されています。具体的には、以下のような点で借主に有利な条件が設定されています。
退去に対する補償
貸主が退去を求める場合、正当事由に加えて、借主に対して一定の補償が必要となるケースがあります。これにより、借主の立場がより保護されます。
契約終了の制限
貸主が契約を終了させるためには、「正当事由」が必要です。正当事由には、貸主自身が物件を使用する必要がある場合や、借主が家賃を長期間滞納している場合など、限られた条件が含まれます。そのため、借主は不安なく長期間住むことができます。
3. 家族向けの選択肢
普通借家は、人生の様々なステージにおいて適応しやすい契約形式です。以下のようなシチュエーションに適しています。
高齢者の住居
高齢者にとっても、引っ越しを繰り返さずに済む普通借家は安心感があります。地域コミュニティとのつながりを維持しやすく、暮らしやすさが向上します。
家族の拡大
結婚や子どもの誕生など、家族構成の変化に合わせて住み続けることができます。長期間同じ場所に住むことで、家族の生活リズムが安定します。
普通借家のデメリット
1. 家賃が高め
普通借家は、長期間の契約を前提としているため、家賃が相場より高めに設定されるケースが多いです。これは、借主が契約期間中に安定的に住む権利を持つため、貸主がそのリスクを家賃に上乗せする傾向があるからです。
例えば、都心部や人気のエリアでは、同条件の定期借家物件と比べると数万円程度家賃が高くなることもあります。長期契約での利便性と安心感を求める代償として、住居費の負担が増える可能性があります。
2. 更新料の発生
普通借家では、契約期間が終了すると更新料が発生するのが一般的です。この更新料は、家賃1か月分から2か月分程度が相場とされ、借主にとっては大きな出費になります。
更新料が必要な理由としては、契約を継続する際に新たな契約手続きが発生することや、貸主が長期間のリスクを補うためとされています。しかし、更新料は日本特有の制度であり、実際には貸主にとっての利益に過ぎないとの指摘もあります。この点に納得できない借主にとっては、普通借家のデメリットといえるでしょう。
3. 退去交渉が難航する可能性がある
普通借家では、貸主が借主に退去を求める際に「正当事由」が必要です。このため、貸主が契約終了を望んでも、借主が納得しない場合はトラブルに発展することがあります。
例えば、貸主が物件を売却したいと考えていても、借主が退去に応じなければ、売却がスムーズに進まない可能性があります。また、逆に借主が退去を希望しても、契約内容によっては退去条件を満たす必要があるため、交渉が必要になるケースもあります。
定期借家のメリット
1. 家賃が割安
定期借家の最大のメリットは、家賃が相場よりも割安になる可能性が高い点です。契約期間が限定されているため、貸主にとって空室リスクが高くなることから、その分家賃を低めに設定する傾向があります。
例えば、同じ条件の普通借家物件と比較すると、家賃が1~3割程度安くなるケースもあります。特に大都市圏や高級住宅地では、定期借家物件が予算内で借りやすくなるため、家賃を抑えたい人にとっては大きな魅力です。
2. 短期契約が可能
定期借家は、契約期間を自由に設定できるため、短期間だけ住む場合に最適です。例えば、以下のような状況で役立ちます。
- 転勤や単身赴任:3ヶ月や半年など、短期間の住まいが必要な場合。
- 仮住まい:自宅のリフォームや建て替え期間中の一時的な居住。
- 試し住み:特定の地域に引っ越す前に、そのエリアでの生活を試してみたい場合。
短期契約が可能なため、普通借家のように契約期間の縛りがなく、利用目的に合わせて柔軟に対応できるのが大きな利点です。
3. 高品質な物件の選択肢
定期借家では、分譲マンションや一戸建てなど、通常は賃貸に出されないような良質な物件を借りられるケースが多いです。これは、貸主が一時的に自宅や高品質な物件を貸し出すために定期借家契約を選ぶことがあるためです。
具体的には以下のような物件が対象となります。
- 分譲マンション:高級住宅街にある分譲タイプの物件。
- 一戸建て住宅:貸主が転勤や留学で一時的に住まなくなるケース。
- リゾート物件:別荘やセカンドハウスの空き期間を有効活用した賃貸。
このため、短期間でも質の高い住環境を手に入れることができるのは、定期借家の大きな魅力です。
定期借家のデメリット
以下に「定期借家のデメリット」を詳しく掘り下げて解説します。
1. 契約期間終了時に退去が必須
定期借家の最大の特徴である「契約期間が明確に決まっている」という点は、デメリットにもなり得ます。契約期間が終了すると原則として借主は退去しなければならず、住み続けたい場合でも貸主の同意が得られなければ再契約はできません。
例えば、居住期間が短いことを理由に引っ越し費用や新居探しの負担が増えることがあります。また、住まいに愛着が湧いた場合でも退去を余儀なくされるため、長期的な住居を求める人には不向きです。
2. 中途解約が原則として不可
定期借家契約では、原則として契約期間内に解約することができません。これは普通借家と異なり、借主にとっての大きな制約となります。
ただし、以下のようなやむを得ない事情がある場合には中途解約が認められるケースもあります。
- 転勤:遠方への転勤が決まった場合
- 健康問題:療養や介護が必要な場合
- 家族の事情:親族の介護や家庭の急な変化があった場合
これらの例外が認められる場合でも、事前に貸主に通知し、一定の手続きを踏む必要があります。もし貸主が中途解約に応じない場合、裁判などの法的手段を取る必要が生じることもあります。
3. 家賃交渉が難しい
定期借家では、契約期間が限定されているため、家賃交渉が難しい場合があります。貸主が「短期間しか貸さないからこの家賃で提供する」というスタンスを取ることが多いため、借主が家賃の引き下げを希望しても応じてもらえないことがあります。
特に、契約期間中の家賃変更や減額請求はほぼ不可能であり、普通借家のように更新時に交渉する余地もありません。そのため、契約時の家賃がそのまま固定されることになります。
契約時に気をつけるポイント

ここからは普通借家契約と定期借家契約をする際に気をつけるポイントを解説します。
普通借家契約での注意点
- 更新料や礼金の確認
更新料が発生する場合、その金額や条件を明確にしておくことが重要です。更新時に更新料が発生する場合、その金額と支払いのタイミングを契約書で確認してください。更新料は家賃1~2か月分が相場です。また、初期費用としての礼金があるかも確認してください。 - 契約内容の詳細確認
家賃の改定条件や、敷金の返還ポリシーについても事前に確認しておきましょう。契約期間は通常2年間が基本ですが、特別な事情でそれ以上の期間が設定される場合があります。この期間がライフプランに合っているか確認しましょう。 - 交渉の余地
家賃交渉が可能な場合があるため、地域の相場を調べてから交渉を行うと良いでしょう。
定期借家契約での注意点
- 契約期間と再契約条件の確認
契約期間がどの程度設定されているかを確認し、再契約の可能性についても事前に貸主に相談しておきましょう。 - 中途解約の条件
中途解約が可能なケース(転勤や介護などの特例)について契約書に明記されているかを確認してください。 - 退去時の対応
契約終了時に必要な手続きや、敷金の返還条件について事前に確認しましょう。
まとめ
普通借家と定期借家は、それぞれの目的やライフスタイルに応じたメリットとデメリットがあります。長期的な安定を求めるなら普通借家、短期間の柔軟性やコスト削減を重視するなら定期借家を選ぶと良いでしょう。
契約前にしっかりと条件を確認し、自分のニーズに合った契約を選択することが重要です。この記事を参考に、賃貸契約をよりスムーズに進めてください。特に再契約の可能性について明確にしておきましょう。
部屋探しで失敗しないためには正しい知識を身につけることが重要です。お部屋探しで失敗しないための無料メルマガ講座を提供しています。いまなら特典もプレゼントしているので、ぜひ登録してみてください。▶︎詳細はこちら

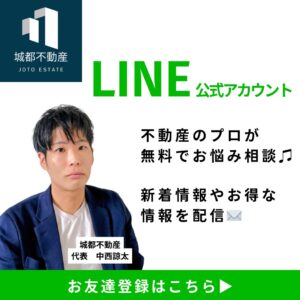
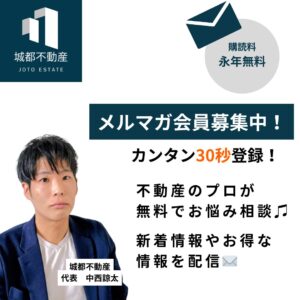
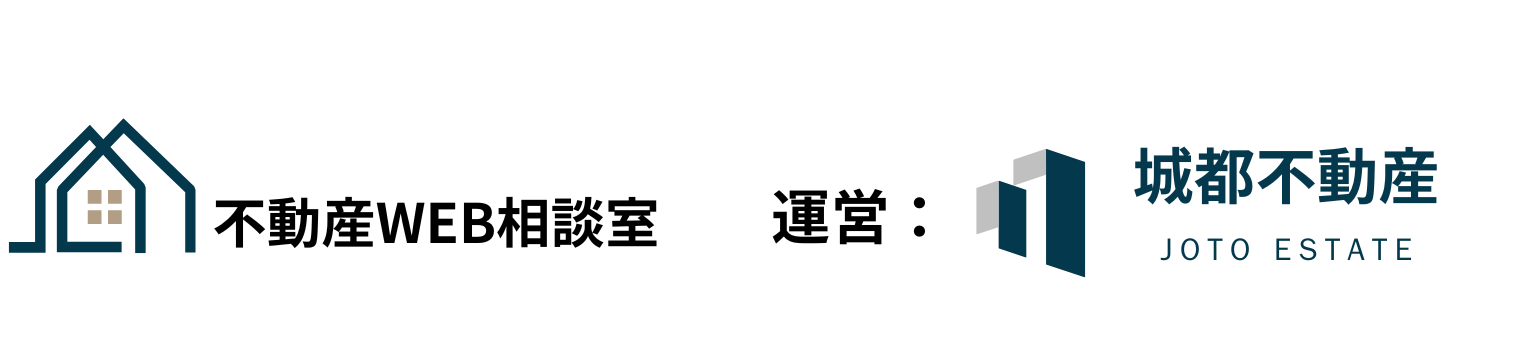
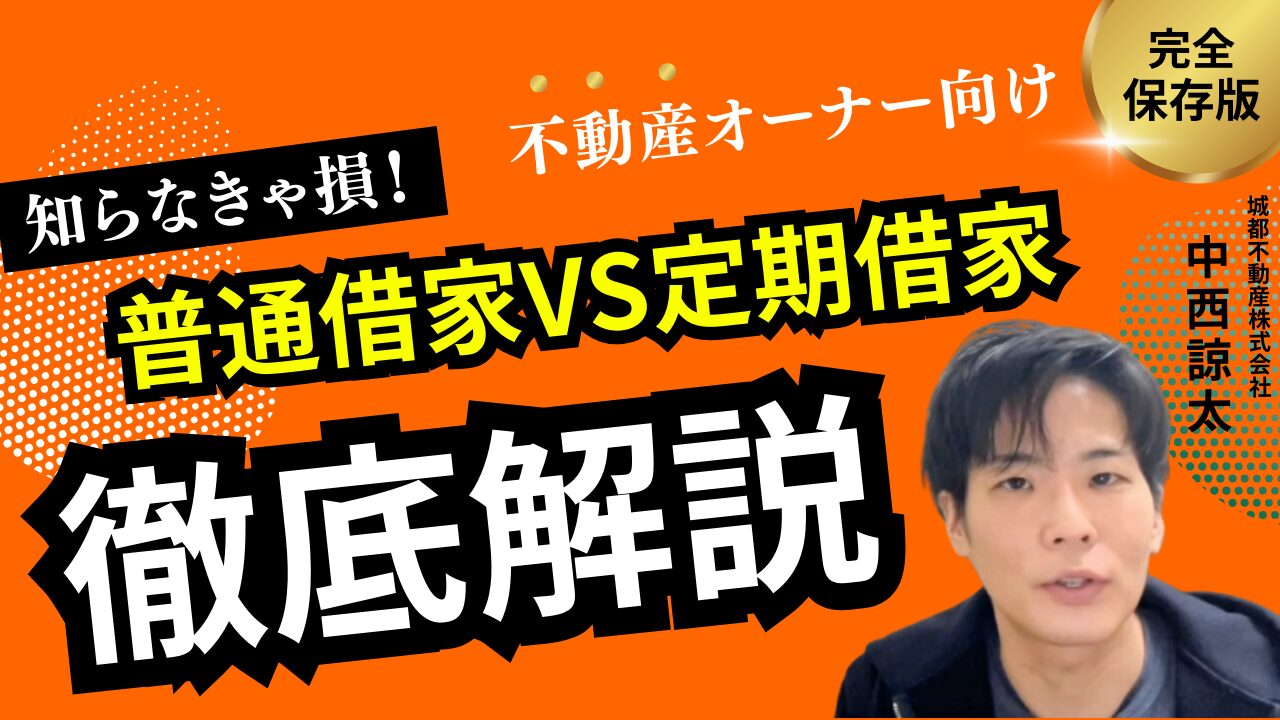

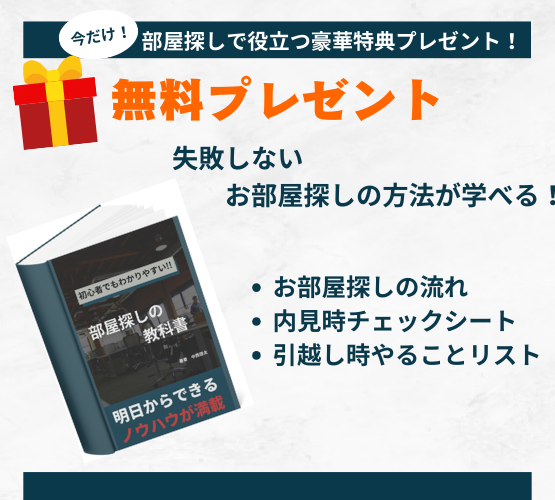
コメント