先日、不動産クラウドファンディングのヤマワケエステートのファンドが償還延期されたというニュースを見かけました。
不動産のクラウドファンディングは資産形成の一つとして最近人気が急上昇している投資商品です。少額から投資でき、意外と利回りが高いので投資初心者にも取り組みやすいですが、きちんと内容を理解していないと思わぬところで大きく損してしまう可能性があります。
特にデメリットやリスクについてきちんと理解しておくことは重要です。
そこで今回のヤマワケエステートのニュースから、不動産クラウドファンディングについてのリスクやデメリットについても解説していきます。
これから不動産クラウドファンディングを始める方はもちろん、投資の知識として知っておきたい人にとっても役立つ内容となっていますのでぜひ最後までお付き合いください。
 中西諒太
中西諒太私自身、現在不動産会社を経営しています。本記事では専門家や実体験に基づいた解説をしていきます。
ちなみに私が経営する城都不動産では、一都三県を中心に不動産事業をしています。お気軽にご相談くださいませ。
ヤマワケエステートとは
ヤマワケエステートとは、不動産クラウドファンディングの一つで、個人投資家から資金を集め、不動産を購入・運用して収益を分配するサービスです。
2023年9月に開始された新しいサービスで、元サッカー日本代表の本田圭佑氏が公式アンバサダーを務めることでも注目されています。商品によっては1万円から投資可能で、気軽に投資を始められることから投資初心者にも人気です。
2025年1月時点で登録会員数は3万人以上、募集金額390億円に対し応募総額は1,091億円と非常に人気の高いサービスとなっています。毎月10件以上のファンドが募集されており、中には倍率10倍を超える人気商品も存在しています。
関連記事:ヤマワケの評判・口コミは?メリットとデメリットもあわせて解説!
ニュースの概要
今回のニュースはヤマワケエステートのファンドの一つが償還延期というトラブルが発生したというものです。
問題となったのは、建築家・隈研吾氏が設計を手掛けた札幌市の集合住宅を対象としたファンドで、総額23億900万円、想定利回り13~18.4%の商品でした。
通常、クラウドファンディングは一定期間運用後に元本と利益を投資家に返還しますが、今回のファンドは償還日の前日に延期が発表されました。その理由としては、物件の売却契約が直前で破談になり、メゾネットタイプの構造が購入者に受け入れられなかったため、包括的に販売し直すことになったという説明がされています。
ただ、この説明だけでは正直納得がいかない部分も多く、他に何らかの問題が隠れている可能性も否定できません。特に償還直前になって急な変更が起こるのは異例であり、投資家の間では不安や不満が広がっています。
貸していたお金が返済日前日に「やっぱりお金返せなくなった」といわれたと思えばわかりやすいと思います。
問題点やリスク
ヤマワケエステートに限らず、不動産投資クラウドファンディングにはさまざまな問題点やリスクがあります。これらを把握しておくことで、自分に向いている投資なのかを知ることができます。
元本割れのリスクがある
不動産クラウドファンディングには元本割れのリスクが常に存在します。特に「優先劣後出資方式」を採用しているファンドでは、事業者が一定割合まで損失を負担しますが、それを超える損失は投資家が負担しなければなりません。
一定の割合までは事業者が負担、それ以上は出資者が負担する方式のことです。
たとえば1億の物件で事業者負担20%のファンドで、2,000万円損があった場合は20%なので事業者が負担。しかし、5,000万円の既存があった場合は差額の3,000万円は元本の中から補填することになります。
今回のヤマワケエステートのファンドでは、事業者の劣後出資割合がわずか0.1712%しかなく、実質的には投資家がほぼ全てのリスクを背負っている形になります。
一般的に、劣後出資の割合が高いファンドほど利回りは低く、安全性が高くなる傾向がありますが、ヤマワケエステートの今回のケースは非常に高い利回りに対して事業者側のリスクが低すぎるという点で問題があります。
リターンが期待できない
さらに、今後は経済全体の物価高や建設業界での資材や人件費の高騰が進み、ますますリターンが期待できなくなる恐れがあります。また、有名人を広告に使うなどの高額な宣伝費用も利回りを下げる要因になりかねません。広告費が増加すれば当然、投資家が受け取るリターンに悪影響を及ぼす可能性があります。
プロジェクトが破綻するリスク
ま過去には「みんなの大家さん」のように、プロジェクトの開発が遅延したり建築会社が倒産したりして、計画そのものが破綻した事例もあります。
さらに運営会社自体が資金繰りに失敗して倒産するリスクも常に存在します。このような事態が発生すると、投資家が資金を回収することは非常に困難になります。過去の失敗例を知ることで、同じようなリスクを回避するための判断材料とすることが重要です。
対策
業者を信用しない
これらのリスクに対する対策として、まず業者を過度に信用しないことが重要です。契約や売却先、プロジェクトの条件などは徹底的に調査し、不透明な部分が多い場合は投資を避けるべきでしょう。
別の投資もあわせる
プロジェクト破綻に備え、株式や実物不動産など別の投資手段も併用し、リスクを分散することも大切です。不動産クラウドファンディング一本に絞らず、多角的に資産を運用することで、万が一のリスクに備えることができます。
まとめ
かつてスルガ銀行の「かぼちゃの馬車事件」のような投資トラブルもありましたが、結局は他人のせいにするのではなく、自分でリスクを認識して投資判断することが重要です。
不動産クラウドファンディングを利用する場合は、プロジェクト破綻や事業者の倒産リスクを覚悟の上で投資する必要があります。常に周囲の情報に振り回されず、自ら調査し慎重に判断する姿勢が求められます。投資はあくまで自己責任であり、自らのリスク許容度を明確にし、無理のない範囲で行うことが何より大切です。

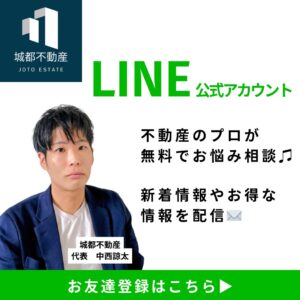
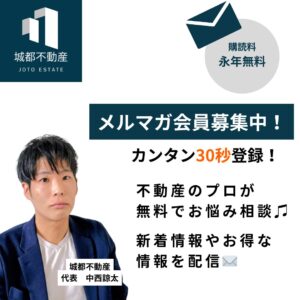
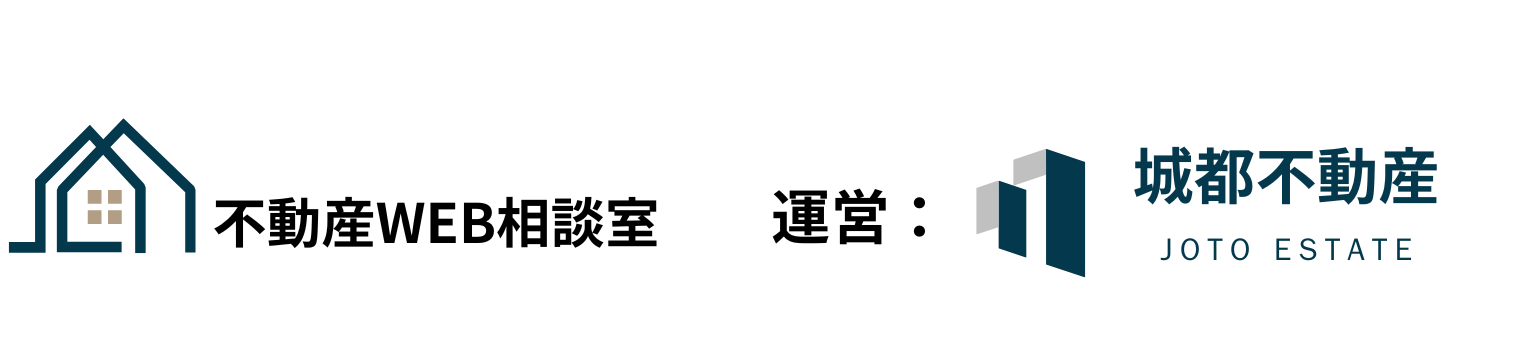


コメント