国土交通省から全国の地価動向は全用途平均で4年連続上昇と発表されました。
そこで今回は、不動産業界で働いている立場から、公示価格について徹底解説していきます。
単なる「公示地価が上がった」という表面上だけのニュースを伝えるだけではつまらないので、今回はなぜ地価が上昇しているのか、その背景や今後の不動産市場の動向について詳しく解説します。
TVやネットニュースなどのメディアでは、限られた時間内で情報を伝えるため、表面的な情報にとどまりがちです。しかし、私のブログやYouTubeチャンネルでは、より詳細な情報と分析を提供し、深掘りした視点でお届けできるのが強みです。
今回は、私自身の見解も交えながら、市場の変化を読み解いていきます。
 中西諒太
中西諒太私自身、現在不動産会社を経営しています。本記事では専門家や実体験に基づいた解説をしていきます。
ちなみに私が経営する城都不動産では、一都三県を中心に不動産事業をしています。お気軽にご相談くださいませ。
ニュースの概要

全国の地価動向は全用途平均で4年連続上昇したと国土交通省より発表されました。
全国の地価は、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇傾向が継続するなど、全体として上昇基調が続いている。
国土交通省:報道発表資料より作成
今回の地価上昇においては以下のポイントを把握しておきましょう。
- 全国平均 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇し、上昇幅が拡大した。
- 三大都市 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇し、上昇幅が拡大した。
- 地方都市 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇した。
東京圏の場合
◆住宅地(平均+4.2%)
広い範囲で住宅需要が堅調で、都心部では10%を上回る高い上昇率の地点も多くありました。ただ、郊外の一部では、建設費の上昇などに伴って戸建て住宅の売れ行きが鈍っているということで、去年と比べて上昇率が縮小した地点もありました。
◆商業地 (平均+8.2%)
オフィスの賃料の引き上げが進んでいることや、渋谷駅近くでは+32.7%となるなど街の再開発による期待が地価の上昇にもあらわれる形となっています。
◆最高価格(住宅地)
○東京・港区赤坂1丁目(8年連続)
○1平方メートルあたり590万円
○大使館が多く立地し、マンション用地の需要が引き続き堅調となっていることから去年に比べて10.3%上昇しました。
◆最高価格(商業地)
○東京・中央区銀座4丁目の山野楽器銀座本店(19年連続)
○1平方メートルあたり6050万円
○富裕層や外国人によるブランド品の消費が盛んなため、高級品店の出店需要が非常に強く、去年に比べて8.6%上昇しました。
全国で大きく上昇したエリア
◆住宅地(上昇率 高い順)
1位 北海道富良野市北の峰町(+31.3%)
2位 長野県白馬村北城(+29.6%)
3位 沖縄県宮古島市上野(+23.1%)
◆商業地(上昇率 高い順)
1位~3位 北海道千歳市が占める
5位 東京都渋谷区桜丘町(+32.7%)
7位 東京都台東区浅草1丁目(+29.0%)
地価が上昇した背景

今回、地価が上昇した背景としては主に2つあります。
「投資マネーの流入・高所得世帯の購入」と「ホテルや工場の建設」です。
都市部の場合は都市部を中心に投資マネーの流入や高所得世帯の購入
今回の地価は、東京だけではなく、名古屋や大阪のタワマンも値上がりしました。
特に東京都心部はいまだに大きく値上がりしています。
以前までは一般世帯向けに盛んに供給されていましたが、原価を販売価格に転嫁せざるを得ない中で、各社、高値でも買ってくれる高所得世帯にターゲットを絞っている状況です。世帯年収2000万円以上に標準をあわせていると公言する会社もあるくらいなので、よりマンション価格は上がっています。
人口が減少し、住宅や土地が余っている中で、安価な住宅を大量供給する時代から、良質なストックを形成する時代にシフトしているとも言えます。
地方ではホテルや工場の建設
都内のマンションだけではなく、地方にも海外資本による不動産の買い漁りが目立ってきています。
たとえば山梨の石和温泉やにせこが有名です。中国の企業が旅館やホテルを購入し、中国人のためにサービスを提供しています。
宿泊業だけではなく、工場も増えてきています。
北海道では先端半導体の国産化を目指す「RAPIDUS」の工場の建設で賃貸マンションや事務所、ホテルの需要が高まり、上位3地点を北海道千歳市が占めました。
熊本で工業地で最も高かったのはTSMCの近くの「熊本県大津町杉水」で+33.3%となりました。隣接する菊陽町に台湾の半導体大手TSMCが進出したことが地価の上昇につながっています。
これからは製造業だけではなく、さまざまな業態の企業が進出してくる可能性があります、円安で日本円の価値が下がっているいま、昔の東南アジアのようになってきています。
今後はどうなる?

今回のニュースでは全国的に4年連続で地価が上昇したと発表されましたが、今後も地価が上がるのでしょうか。現在の不動産市場や世界的な経済情勢を踏まえて考えていきたいと思います。
結論からいうと、今後も全国的に上昇傾向。特に都心や地方で局所的に値上がりしていくと予想しています。
具体的な理由を解説していきます。
今後も都心を中心に値上がり
賃金の上昇を上回るペースで住宅価格の上昇が続いていますが、その一因は、建設費における人件費の値上がりであります。もちろん、海外資本の流入も今後も急激に下がることはないでしょうし、神戸市のタマワン空室税のような規制が全国的に導入されなければ住宅価格が大きく下がることは見込めません。大幅に安くなることはなかなか望めない状況だといえます。
地方では観光地や大規模工場があるエリアなど局所的に値上がり。
中国企業が北海道や山梨で中国人のためにホテルや旅館を買っているように、他の県でもこういった施設が増えていき、中国人以外の他の外国人が中心の街が出てくる可能性もあります。
実際のところ、東京都心ではベトナムやフィリピンなどの富裕層がマンションを購入するケースも増えているので、こういった層も今後、地方でホテルや旅館を買う可能性があります。
日本は世界的にみても治安がよく自然が多い国のため、富裕層にとってはそれだけでも魅力的です。マンションや別荘、ホテルや旅館を買っておけば、有事の際の避難場所にもなります。
こういったメリットに気づいた外国人が増えていけば、当然地価も底堅く維持していくでしょう。
一般層は家を買うのが難しい時代に!?
今後はいままでのように一般層が居住のために家を買うのが難しくなっていくでしょう。実際のところ、東京の場合は23区を中心とする都心ではマンション価格が高すぎてパワーカップル以外は手が出せなくなり始めています。
事実、都心の新築・中古マンションともにマンションの平均価格は1億以上します。パワーカップルでもない限り1億以上を出すのは厳しく、郊外で探す層が増えています。また、住宅ローンで50年返済がはじまったのも、返済期間を長くしないと資金計画が立てられない人が増えた証拠です。
そして、手が出しづらくなるのは東京だけではありません。地方でも、北海道のにせこや熊本のように部分的に値上がりするエリアができれば、当然そのエリアは買いにくくなります。
いまは金利も上がっているのでますます今後はマイホームを購入する層は減る可能性が高いというわけです。
となると、今後マイホームの代わりとなるのが首都圏郊外や地方都市近辺の賃貸になるかもしれないという考えも生まれてきます。
不動産投資家にとって家賃収入を期待する場合は首都圏郊外や地方都市近辺が穴場かもしれません。
これはあくまでも予測です。
まとめ
マイホームの購入や不動産投資を検討している場合は、公示価格などの統計をみるだけではなく、そのデータから今後どうなるか仮説を立てて、どういったメリットやデメリットがあるのかシミュレーションしていくことが重要です。
今後、私のブログやYouTubeでは不動産のニュースから今後の市場予測もしていくので、情報収集をサポートすることができれば幸いです。

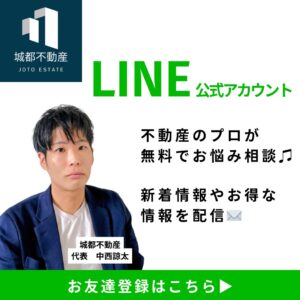
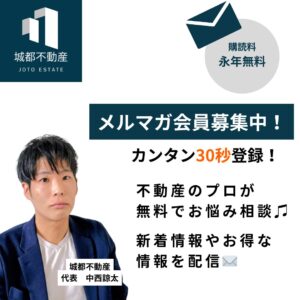
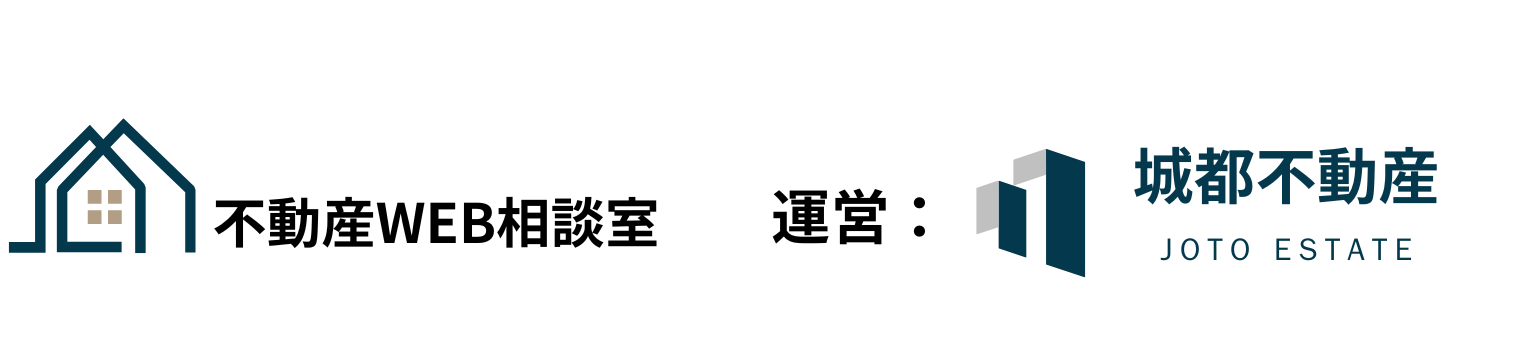


コメント