借地借家法は家や土地を借りるときに関わってくる重要な法律ですが、きちんと理解せずに契約手続きをしている方は意外と多いです。
一般的な賃貸借契約はもちろん、不動産投資やマイホームで物件を購入する際にも借地借家法を知らずに契約してしまうと思わぬトラブルを招く恐れがあります。
この記事では、借地借家法の基本的な仕組みや契約の種類、トラブルを防ぐ方法についてわかりやすく解説します。これから賃貸契約をする方はもちろん、マイホームや収益物件の購入を検討している場合でも役立つ内容となっていますのでぜひ最後までお付き合いください。
 中西諒太
中西諒太私自身、宅建資格を保有しており、現在不動産会社を経営しています。賃貸・売買どちらも経験があるため、プロの立場から解説していきます。
不動産でトラブルになりたくないと思っている人もいるのではないでしょうか?メルマガでは不動産はもちろん、ビジネスやお金についても無料で情報を配信しています。いまだけ登録料は無料です。合わないと思ったらすぐに登録解除できますので、ぜひ覗いてみてください😊→詳細はこちら
借地借家法とは?基本をわかりやすく解説
借地借家法は、土地や建物を借りるときに適用される法律です。
借地借家法の歴史
借地借家法の歴史は意外と古く、前身となる法律は100年以上も前の1921年に制定されました。さらに起源となった「建物保護ニ関スル法律制定」に関してはさらに前に制定されています。
今の借地借家法になるまで、次のような歴史を辿っています。
借地権保護の起源となった法律です。民法上は地上権も不動産賃借権も登記していないと第三者に対抗できないこととされていますが、建物の登記があれば借地権を主張し認めさせることができると定めました。
1921年には、「建物保護ニ関スル法律」を補足する特別法として、借地法と借家法が制定されます。現在の借地制度の基本にもなっています。建物所有を目的とする土地利用を保護するため、借地権の長期の存続期間を保障し、存続期間満了時における借地人の建物買取請求権などを定めました。
借地人の借地上の建物における生活や事業を安定させることを目的に、借地法が改正されます。借地人の借地上の建物における居住や事業を安定させるため貸主は自己使用が必要であるなど「正当事由」がなければ、更新を拒絶することができないとされました。現在では借地権が強い権利ですが、この改正が基本となっています。
貸主の承諾が得られない場合は、承諾に変わる裁判所の許可を得て、借地人は借地権の譲渡・転貸ができることとなりました。
以前の法律を一本化し、新しく制定されたのが借地借家法です。施行時に、建物保護法、借地法、借家法は廃止されました。ただし、旧法で契約された借地契約については、更新される限り、旧法が適用されます。
戦前は土地の値段が安く、土地を所有したいというニーズや権利意識が薄かったので、日本の都市部では借地、借家の利用が一般的でした。
昭和16年に導入された「正当事由」制度は借地契約の更新を拒絶することをほとんど不可能とした改正でした。これは軍国主義の時代に賃借人が多いであろう出征兵士の銃後の暮らしを守るためというのが大きな理由でした。また「国家総動員法」によって日用品や食料品などあらゆるものの価格を国が決めていたこともあり、賃料も公定価格でした。一度土地を貸してしまえば、他の用途に変更することはもちろん、賃料を上げることもできませんでした。
戦時中は多くの成人男性を徴兵し戦地に送り出すため、、一家の大黒柱が留守の間に借家に住む家族が家を追い出されることのないため、国策として権利を保護したというわけです。
戦争が終わっても正当事由の制度は残されたため、一度土地を貸したら返ってこないのが当たり前でした。しかし、バブル崩壊後は土地の活用を阻害している借地制度が改正されました。土地を保有するよりも活用することに軸を置くために1992年に借地借家法が一本化されたという経緯があります。
そして現在は新しい借地は新法でが適用される一方で、既存の借地については旧法が適用されているという状況です。旧法と新法かどうかも踏まえて不動産取引をしていく必要があります。
借地借家法の基本的なポイント
借地借家法の基本的なポイントは以下の3つです。
- 借主(借りる側)を守るための法律:賃貸契約をしている人が、不当に立ち退きを求められたり、不利な契約を結ばされたりしないようにするものです。
- 民法よりも借主に有利:普通の契約では「契約書の内容がすべて」となりますが、借地借家法があるおかげで、借主が一方的に不利になる契約を防ぐことができます。
- 借地契約と借家契約の2種類がある:土地を借りる「借地契約」と、建物を借りる「借家契約」に分かれています。それぞれに異なるルールがあるため、契約内容をしっかり確認することが重要です。
借地借家法は、一般的な賃貸契約だけでなく、店舗や事務所の賃貸にも適用されることがあります。たとえば、オフィスビルや商業施設の賃貸契約においても、この法律のルールが適用されることがあり、特に契約期間や更新に関する取り決めが重要になります。
また、借地借家法が適用されるかどうかは、契約の内容によって決まるため、貸主・借主の双方がしっかりと理解しておく必要があります。賃貸契約を結ぶ際には、借地借家法に基づいた契約内容になっているかどうかを確認しましょう。
借地契約の種類と特徴
借地契約は、土地を借りて家や建物を建てるときに結ぶ契約です。主に次の2種類があります。
普通借地権
普通借地権のポイントは以下の3つです。
- 契約期間:30年以上(更新可能)
- 更新の仕組み:借主が希望すれば、基本的に更新できる。
- 貸主が契約終了を求める条件:正当な理由(例:建物の老朽化、借主の重大な契約違反)がない限り、契約を終了させられない。
普通借地権は、借主にとって有利な契約です。基本的に長期間使うことができ、貸主(地主)は契約の更新を拒否することが難しくなっています。
長期間にわたって土地を使用できるので、自宅を建てるために土地を借りる場合、30年以上の契約期間があるため、長期的な計画を立てやすくなります。
もし更新拒否で正当事由が認められ、契約終了となった場合には借地人は地主に建物を時価で買い取ってもらえる建物買取請求を行うことができます。借地人からの建物買取請求があった場合は、地主は購入を拒否できず、建物の売買契約が成立します。
定期借地権
定期借地権のポイントは以下の3つです。
- 契約期間:住宅用は50年以上、事業用は10年以上。
- 更新の仕組み:契約満了時に土地を返還しなければならない。
- メリット:貸主側は契約終了後に確実に土地を取り戻せる。
定期借地権は、普通借地権とは異なり、契約が満了すると更新できません。定期借地権は、土地を持っている貸主にとってはメリットの大きい契約形態です。例えば、大型商業施設やマンション開発などでは、この契約がよく利用されます。
借地権の更新について
借地権は旧法か新法か、普通か定期かによって更新できるかどうか変わってきます。
借地権の種類と契約更新の可否は以下の通りです。
| 借地権の種類 | 契約の更新 |
|---|---|
| 旧法の借地権 | できる |
| 普通借地権 | できる |
| 定期借地権 | できない |
普通借地は更新が前提のため期間が短め、定期借地は更新ができないため期間が長めに設定されています。
旧法と普通借地権を更新する際には以下の3つの方法があります。
- 合意更新
- 更新請求
- 法定更新
基本的に更新できるものの、地主が納得した上で更新した方がトラブルも防ぎやすいです。土地を借りる場合にはあらかじめ地主の意見を聞いておくのも重要です。
建物賃貸借契約(借家契約)の種類と特徴
建物を借りる場合の契約には、次の2種類があります。
普通借家契約
普通借家契約は、借主が長く住めるように守られた契約です。
- 契約期間:1年以上(更新可能)
- 更新の仕組み:借主が希望すれば、基本的に契約を更新できる。
- 家主が退去を求める条件:正当な理由がない限り、契約の更新を拒否できない。
定期借家契約
定期借家契約は、契約期間が決まっていて、更新ができない契約です。
- 契約期間:自由に設定可能(1年や3年など)
- 更新の仕組み:契約満了後は再契約しない限り退去しなければならない。
- メリット:貸主は計画的に物件を管理できるが、借主は契約期間満了後に引っ越しが必要になる。
定期借家契約は、短期間だけ賃貸物件を利用したい場合や、企業が社員寮として物件を借りる場合などに活用されることが多いです。
普通借家と定期借家についてさらに詳しくは以下の記事で解説していますのでご参考ください。
関連記事:【保存版】普通借家VS定期借家!契約の違いとお得な選び方を解説!
借地借家法についてよくある質問
ここからは借地借家法についてよくある質問について回答します。
- 借地権や借家権の譲渡・転貸はできる?
借地借家法では、借地人や借家人は借地権や借家権を第三者に譲渡したり、転貸したりすることができます。
ただし、借地権については、地上権の場合は地主の承諾なしでも譲渡・転貸が可能ですが、賃借権の場合は地主の承諾が必要です。もし承諾なく譲渡・転貸すると契約解除の対象となります。
ただし、もし地主が承諾しない場合でも、借地人は裁判所に地主の承諾に代わる許可を請求可能です。譲渡・転貸によって地主に不利益が生じないと認められれば、裁判所は許可を出すことができます。
借家権についても、賃貸人の承諾を得れば譲渡・転貸が可能です。賃貸人が正当な理由なく承諾を拒んだ場合、借家人は裁判所の許可を得て譲渡・転貸を行うことができます。
- 地代や家賃の増減額請求はできる?
可能です。借地借家法では、地代等増減額請求権を定めており、当事者は将来に向かって地代や家賃の増減を請求できるとあります。社会経済情勢の変化や土地の価格変動などにより、一度取り決めた地代や家賃が不相当になることがあるため、状況に応じて請求は可能です。
ただし、増額するためには、物価の上昇や経済情勢の変化など、客観的なに地代・家賃を上げる必要があると認められる必要があります。
増額に関して当事者間で協議が調わない場合は、最終的には裁判所の判断に委ねることになります。家賃の増減はトラブルのもとになるため、詳しくは以下の記事をご参考ください。
まとめ
借地借家法は、土地や建物を借りるときの重要なルールを定めた法律です。
契約の内容をしっかり理解し、トラブルを避けるためにも、契約時には細かい条件を確認することが大切です。賃貸契約を結ぶ前に、借地借家法の基本を押さえておけば、安心して不動産取引することができます。とはいえ、物件によっては権利関係がややこしいケースもあります。
少しでも不安をなくし安心したい取引をしたい場合は信頼できる不動産会社に依頼しましょう。

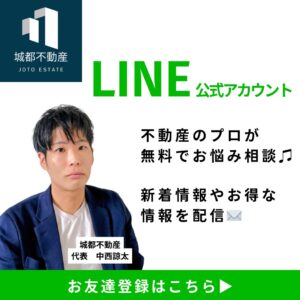
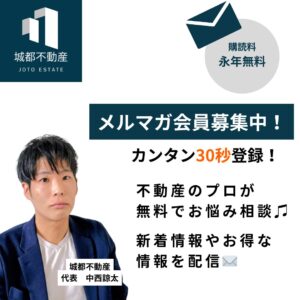
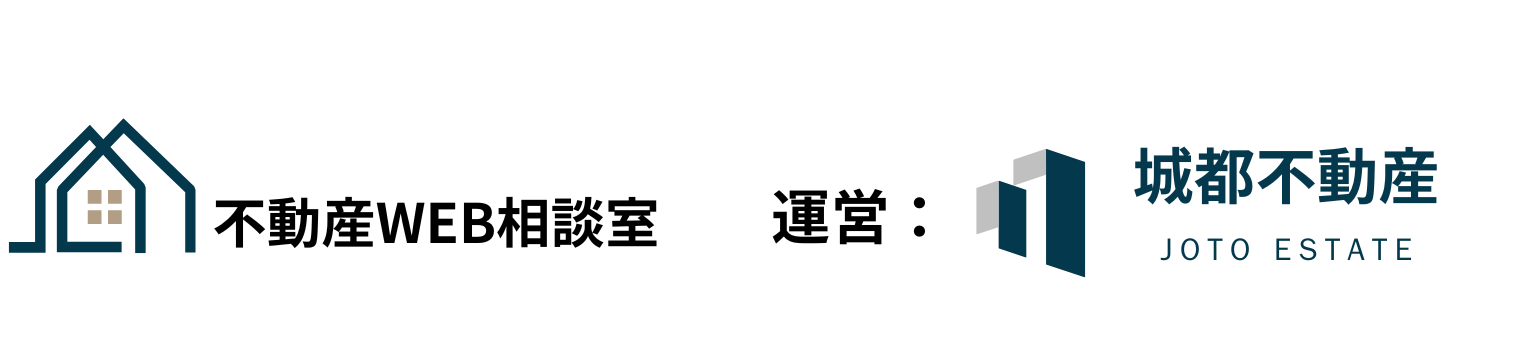


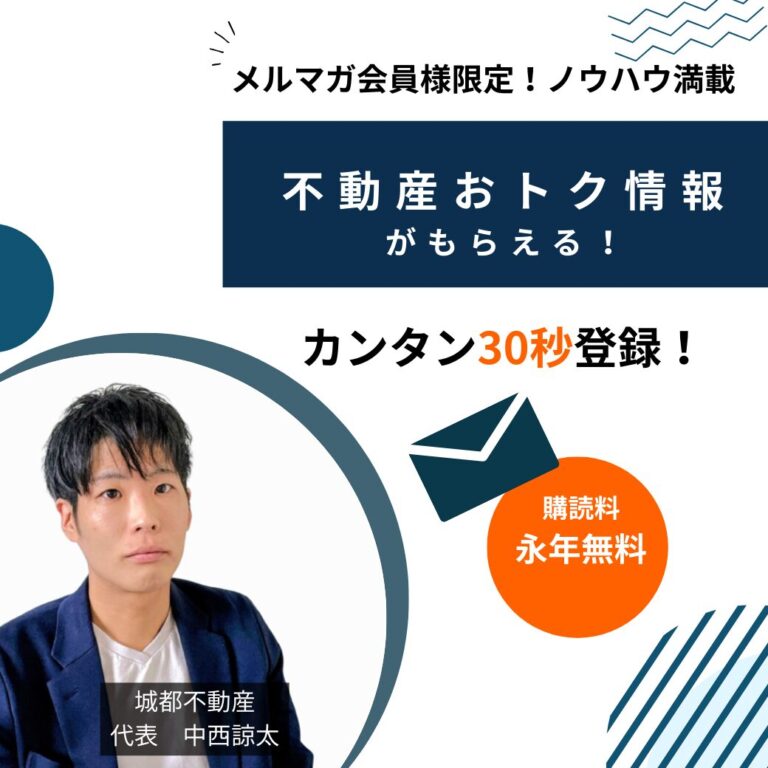
コメント