老後は今の家に住み続けるべきかそれとも賃貸に移るべきか悩まれている人もいるのではないでしょうか?
階段の上り下りがつらい、病院やスーパーが遠い、家の修繕費が思った以上に負担になる…。こうした悩みは、多くのシニア世代が直面する「住宅問題」が原因です。
この判断を誤ると、資金不足や生活不便など老後の安心が崩れる可能性もあるので要注意です。そこで今回は、老後の住み替えで「賃貸か持ち家か」で悩む方へそれぞれのメリット・デメリットに加えて、賃貸に向いている人・持ち家に向いている人の特徴をわかりやすく解説します。
今回最後まで読んでいただくことで以下のメリットがあります。
- 賃貸・持ち家それぞれの利点とリスクが整理できる
- 「自分はどちらに向いているか」が明確になる
- 安心して老後の住み替えを考えるための具体的な判断基準が得られる
少し内容にボリュームはありますが、記事を読むことで賃貸か持ち家かの基準がわかり、より安心な老後を過ごせることにもつながりますので、ぜひ最後までご覧ください。
 城都不動産株式会社 代表取締役 中西諒太
城都不動産株式会社 代表取締役 中西諒太私自身、現在都内で不動産会社を経営しており、こういった相談をよくもらうようになりました。そのため、今回は専門家としての立場から発信していきます。
結論|「賃貸か持ち家か」はライフスタイルで変わる

結論から言うと、「賃貸か持ち家か」は、個人のライフスタイルや価値観、そして経済状況によって決めるべきです。どちらが正解というわけではありません。
- 持ち家は「安定した資産を持ちたい」「家族に資産を残したい」と考える人向きです。
- 賃貸は「柔軟性」「身軽さ」「生活の利便性」を重視する人向きです。
重要なのは、資金、生活環境、家族構成をしっかり見て判断することです。とはいえ、自分がどちらを選べばいいかわからない場合はそれぞれのメリット・デメリットを把握しておくことが非常に重要です。具体的に解説します。
持ち家を選ぶメリット・デメリット

老後の住まいとして持ち家を選択することは、人生の後半をどのように過ごすかという、重要な決断です。それぞれのメリットとデメリットを深く理解し、自分にとって最適な選択を見極めましょう。
メリット
家賃を払い続ける必要がない
最大のメリットは、住宅ローンを完済すれば、その後は家賃の支払いがなくなることです。年金収入が主な生活費となる老後において、毎月かかる家賃の負担がないことは、経済的な安心感を大きく高めます。この安定感は、賃貸では得られない持ち家ならではの強みです。
資産として子どもに残せる
家は大切な資産であり、子どもや孫に相続することができます。家族にとっての思い出の場所を、形として次世代に引き継げるのは、持ち家ならではの魅力です。ただし、相続には専門的な知識が必要であり、お子さんが複数いる場合は、事前に家族でしっかりと話し合い、相続方法を決めておくことが大切です。
自由にリフォーム・改修できる
持ち家であれば、ライフスタイルの変化に合わせて自由にリフォームや改修が可能です。例えば、足腰が弱くなってきたら手すりを設置したり、段差をなくすバリアフリー化を行ったりすることができます。また、子どもが独立して使わなくなった部屋を趣味のスペースに変えるなど、自分らしい快適な空間をつくり出すことができます。
デメリット
修繕費・固定資産税など維持費がかかる
持ち家は、購入して終わりではありません。毎年支払う固定資産税や都市計画税に加え、建物の老朽化に伴う修繕費用が避けられません。外壁の塗り替えや屋根の葺き替え、水回りのリフォームなど、高額な費用が一度に必要になることもあります。これらの費用を計画的に準備しておかなければ、いざという時に困る可能性があります。
立地不便が将来的なリスクに
年月が経つにつれて、建物は確実に老朽化していきます。また、今便利だと思っていても、将来的にスーパーや病院がなくなったり、バス路線が廃止されたりするリスクもゼロではありません。特に、車を手放した後に生活に不便を感じることがないか、将来を見据えた立地の検討が必要です。
売却や相続でトラブルになる可能性
持ち家は資産になる一方で、将来的に住む人がいなくなった場合、売却するか、誰かが相続するかを決めなければなりません。しかし、築年数が古い家はなかなか買い手がつかなかったり、相続する人がいない場合、空き家として管理費用だけがかかる、といった問題が生じることがあります。また、相続人が複数いる場合は、家の価値や分割方法を巡ってトラブルになる可能性も考慮しておく必要があります。
賃貸を選ぶメリット・デメリット

老後の住まいとして賃貸を選択することは、自由で身軽な生活を望む人にとって、非常に魅力的な選択肢です。そのメリットとデメリットを深く理解し、自分にとって最適な選択を見極めましょう。
メリット
ライフスタイルに合わせた住み替えが可能
賃貸の最大の強みは、その柔軟性にあります。持ち家と違い、ライフステージの変化に合わせて、住む場所を自由に選び直すことができます。例えば、退職後には郊外の静かな場所に住み、健康に不安が出てきたら病院やスーパーが近くにある都心部の物件へ引っ越す、といったことが可能です。この身軽さは、老後の変化に柔軟に対応できる大きな安心感につながります。
修繕・管理の手間が少ない
持ち家と違い、賃貸では建物の修繕や設備の交換は大家さんや管理会社が対応してくれます。高額なリフォーム費用を準備する必要もなく、急な故障などにも煩わされることがありません。日々の管理も、持ち家の一軒家と比べて格段に楽なため、精神的な負担が少ないのも大きなメリットです。
利便性の高い場所を選べる
賃貸物件は、駅やバス停に近い、病院やスーパー、公共施設などが充実した都市部にも多く存在します。車を運転しなくなったり、足腰が弱くなったりしても、生活に不便を感じることがありません。利便性の高い場所を選ぶことで、外出の機会が増え、生き生きとした老後を送ることができるでしょう。
デメリット
家賃を払い続ける必要がある
賃貸は、住み続ける限り家賃の支払いが続きます。高齢になってからの収入は年金が中心となることが多いため、老後の生活費として家賃が大きな負担になり、資金計画に影響を与える可能性があります。寿命が延びた場合、何十年分もの家賃を払い続ける必要があることも考慮しなければなりません。
高齢者は入居審査が厳しいケースあり
高齢者が賃貸物件を探す際、入居審査が厳しくなることがあります。単身者や保証人がいない場合、家賃滞納のリスクや孤独死のリスクを懸念され、契約を断られるケースも少なくありません。高齢者向けの賃貸住宅や、家賃保証会社を利用することで解決できる場合もありますが、物件の選択肢が限られる可能性も考慮しておく必要があります。
資産として残らない
賃貸は、どれだけ長く住んで家賃を払い続けても、自分の資産にはなりません。将来的に子どもに家を残したいと考えている方にとっては、デメリットとなるでしょう。また、家を売却して老後資金に充てる、といった選択肢も持てません。
持ち家に向いている人の特徴

子どもや家族に資産を残したい
「住まい」は、単なる生活の場ではなく、大切な資産です。老後に持ち家を選べば、家を子どもや孫に引き継ぐことができます。これは、子どもたちにとって大きな財産となり、家族の歴史を刻む場所にもなります。特に、家を大切な家族のシンボルとして考えている人にとって、持ち家はかけがえのない選択肢となります。
ただし、相続にはトラブルがつきものです。複数のお子さんがいる場合は、事前に話し合い、誰もが納得できる形で進めておくことが大切です。
定年後も安定した収入や十分な貯蓄がある
住宅ローンを完済していれば、老後の生活で大きな出費となる家賃の心配はありません。しかし、持ち家には維持費がかかります。毎年支払う固定資産税や都市計画税に加え、築年数が経てば、外壁の塗り替えや水回り設備の交換など、高額な修繕費用が必要になります。
したがって、持ち家を選ぶには、これらの維持費を賄えるだけの安定した年金収入や十分な貯蓄が必要です。経済的に余裕があり、将来のメンテナンス費用を計画的に準備できる人は、持ち家で安心して暮らすことができるでしょう。
今の住まいをリフォームすれば快適に暮らせる
今すでに持ち家を持っていて、その家でこれからも暮らしたいと考えている人も多いでしょう。老後のライフスタイルに合わせて家をリフォームすれば、新しく住み替える必要はありません。
たとえば、バリアフリー化を進めたり、使っていない部屋を趣味のスペースに変えたりと、自分らしい快適な空間をつくり出すことができます。長年住み慣れた家には、思い出がたくさん詰まっています。住み慣れた場所を離れることなく、自分にとってより暮らしやすい形に変えていくことができるのは、持ち家ならではの大きなメリットです。
長年住み慣れた地域で安心して過ごしたい
人生のほとんどを過ごしてきた地域には、かかりつけ医や顔なじみの店、友人や近所付き合いなど、かけがえのないつながりがあります。持ち家を選択すれば、こうしたコミュニティを維持したまま、老後を過ごすことができます。
高齢になってから新しい場所で人間関係を築くのは簡単ではありません。住み慣れた地域で、安心して気兼ねなく暮らしたいと考える人にとって、持ち家は精神的な安定をもたらしてくれるでしょう。
賃貸に向いている人の特徴

住み替えや引っ越しの自由度を重視する
老後の生活は、健康状態や家族構成の変化によって大きく変わる可能性があります。持ち家の場合、一度購入すると簡単に住む場所を変えることはできません。しかし賃貸であれば、その時々の状況に応じて柔軟に住み替えることが可能です。たとえば、夫婦二人になったので今の家よりコンパクトな間取りのマンションに引っ越したり、足腰が悪くなってきたので病院の近くやエレベーター付きの物件に移り住んだり、といった選択が簡単にできます。自由な住み替えは、老後の生活をより快適に保つための大きなメリットになります。
修繕費や税金などの維持費を負担したくない
持ち家は、築年数が経つにつれて修繕費用がかさんできます。屋根や外壁の塗り替え、水回りのリフォームなど、一度に数十万円から数百万円といった大きな出費が必要になることも珍しくありません。また、毎年かかる固定資産税や都市計画税も無視できない負担です。
一方、賃貸はこれらの維持費を自分で支払う必要がありません。建物の修繕や管理はすべて大家さんや管理会社が担ってくれるため、急な出費に悩まされる心配がなく、費用面でも精神面でも安心できます。
病院やスーパーなど、生活の利便性を最優先にしたい
年齢を重ねるにつれて、買い物や通院がより重要になります。持ち家の場合、今の家が駅から遠かったり、周辺にスーパーや病院が少ないと、将来的に不便を感じるかもしれません。
賃貸であれば、生活の利便性を最優先にして物件を選べます。公共交通機関や生活施設が充実した場所に住むことで、車を手放した後の生活もスムーズになります。都市部で利便性の高い暮らしを望む方にとって、賃貸は最適な選択肢と言えるでしょう。
子どもに資産を残す必要がない、または相続トラブルを避けたい
「子どもに家を残す」という考え方も素敵ですが、一方でそれが負担になることもあります。子どもが遠方に住んでいたり、すでに家を持っていたりする場合、親の家を相続しても管理や売却に困るかもしれません。
賃貸は資産として残らないため、子どもに家の管理や売却といった負担をかけることがなく、相続でのトラブルを避けることができます。家族に「住まい」以外の形で資産を残したい方や、子どもの負担を減らしたいと考えている方にも、賃貸は賢い選択肢です。
判断基準|自分に合う選択を見極めるチェックリスト

後悔のない選択をするために、以下の項目をチェックしてみましょう。持ち家か賃貸にするか考える重要な判断基準になりますのでぜひご参考ください。
老後資金に余裕があるか
持ち家の場合は修繕費、賃貸の場合は継続的な家賃負担を考慮して、資金計画に無理がないか確認する。持ち家、賃貸どちらを選んでも、まとまったお金は必要です。退職金や年金で賄えるか、具体的にシミュレーションしてみましょう。
車がなくても生活できる立地を確保できるか
免許返納後を考え、公共交通機関や買い物に便利な場所を選べるかは、重要なポイントです。持ち家の場合は気軽に引っ越すことはできないので、いまのうちから確認しておきましょう。
家族に資産を残す必要があるか
家は資産として子どもに残すことができます。しかし、こどもが複数いる場合は、相続で揉める原因になることも少なくありません。事前に家族とよく話し合い、相続について納得してもらうことが大切です。
一人暮らしや夫婦のみになった場合の生活イメージが描けるか
持ち家の場合は家族が減った後、広すぎる家で生活していくことに不便や不安を感じることはないでしょうか。家の管理や掃除、防犯面で不安が残る可能性もあります。今の広すぎる家で二人きり、あるいは一人で生活していくことが本当に快適か、もう一度考えてみましょう。
まとめ
老後の住み替えは「賃貸か持ち家か」で悩むのが普通です。
大切なのは、「自分はどちらのライフスタイルを望むか」を考えることです。
- 持ち家は資産や安定志向
- 賃貸は柔軟性や利便性重視
というように、それぞれにメリット・デメリットがあります。
今回紹介した判断基準をもとに、資金、生活環境、家族の3つの視点から自分に合った選択肢を見つけましょう。
正しい知識を持って、あなたの老後がより安心で豊かなものになるよう、納得のいく住まいの選択をしてください。

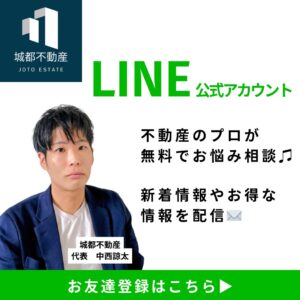
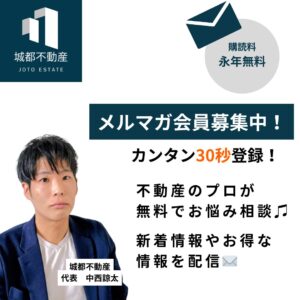
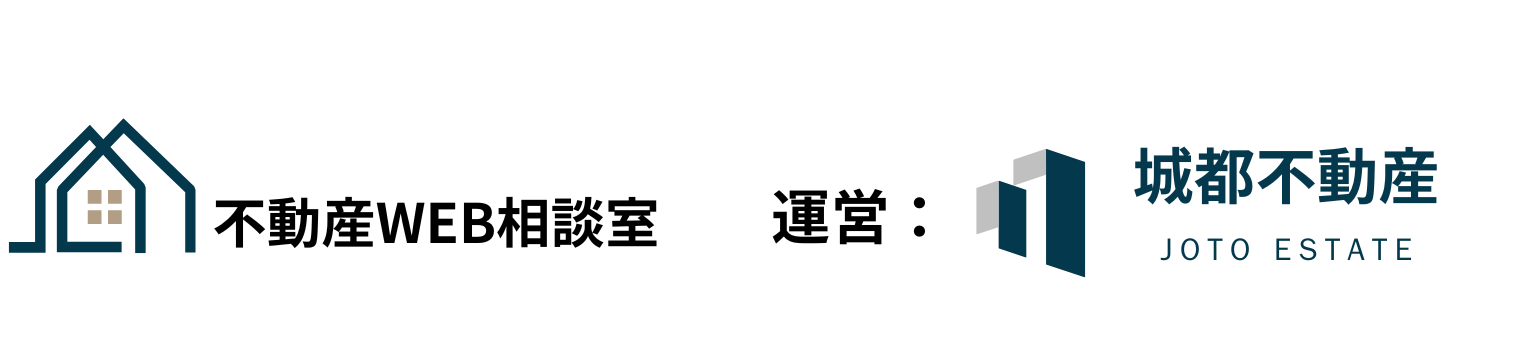
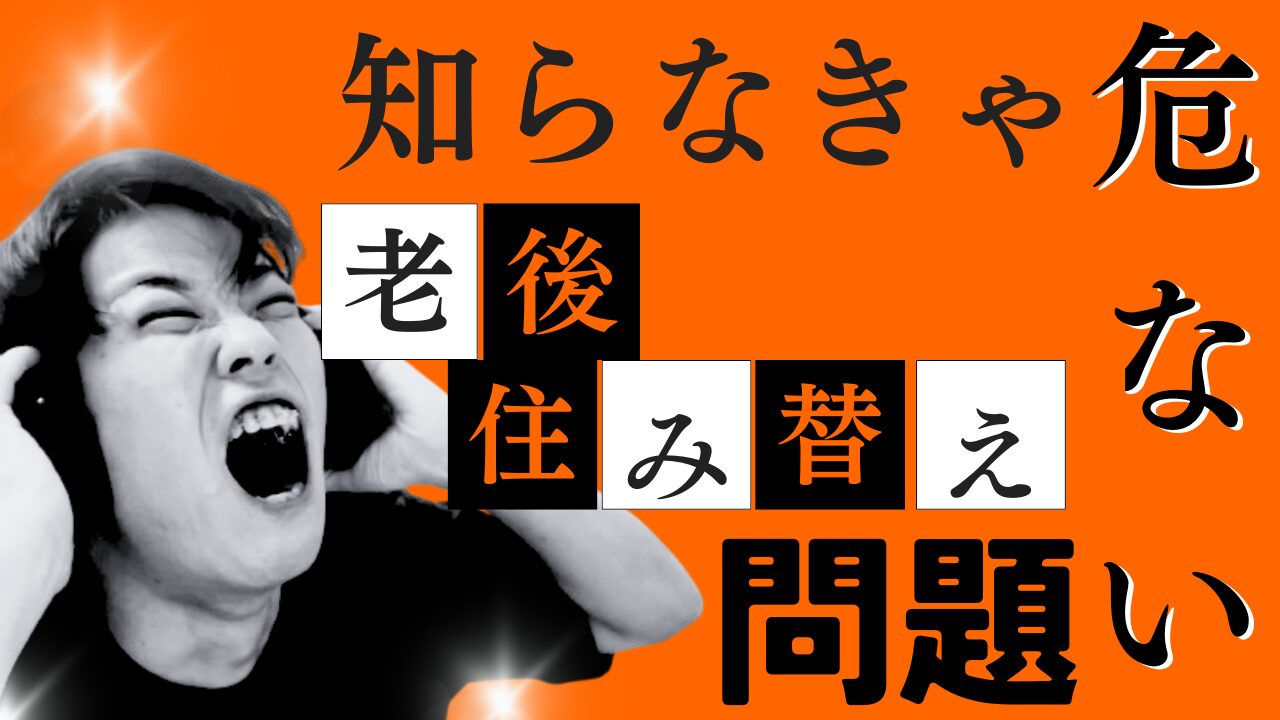

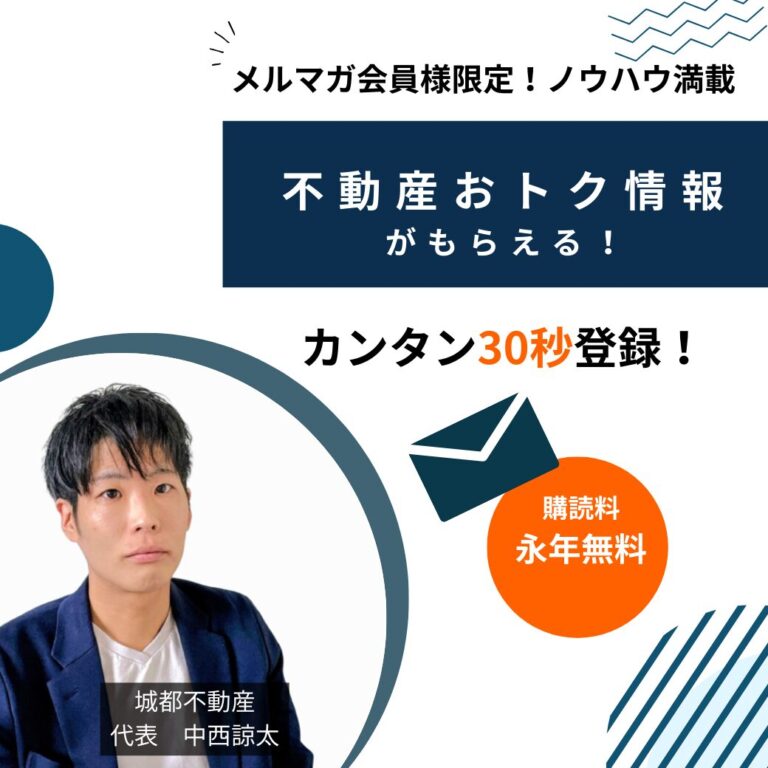
コメント